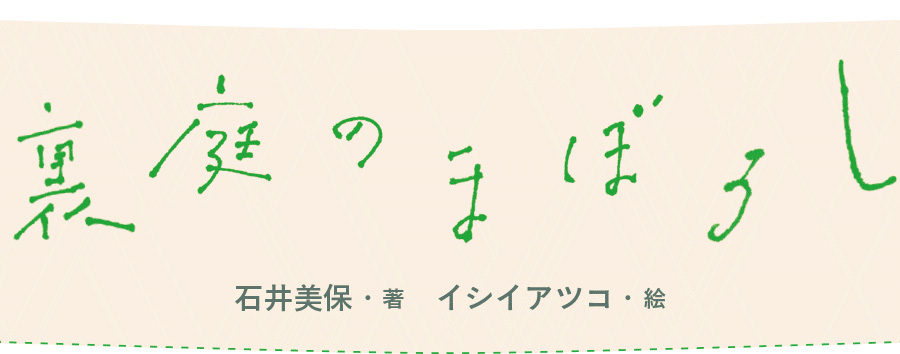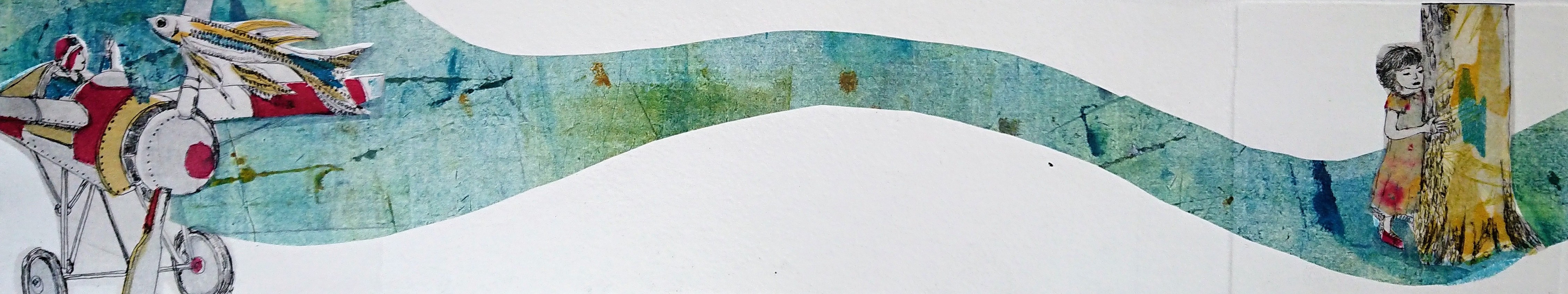behind the sun
柿の木、枇杷の木、かりんの木。金柑、あんず、ゆすらうめ。南天、あじさい、夾竹桃。椿につつじ、金木犀。
大阪府の北端にある実家の裏には、畑と雑木林がある。私たちが「山」と呼んでいる雑木林のシンボルは、大きな栴檀(せんだん)の木だ。樹齢何年ほどになるのか、周囲のどの木よりも立派な幹をもつ栴檀は空に樹冠を広げて細かな葉をさらさらと揺らし、秋にはたくさんの実を落とす。
畑や山の端に植えられたさまざまな果樹や花の名前を私が覚えはじめたのは、ここ数年のことだ。畑も山も、自分が世話をしなくても、ずっとそこにあるものだと思っていた。
長いあいだ、畑と山の世話をしていたのは母方の祖父母だ。まだ元気だった頃、祖母は畑で幾種類もの花や野菜を育てていた。茄子に大根、トマトに胡瓜、時にはヘチマや西瓜まで。畑でとれた茄子や胡瓜を、祖母は糠味噌に漬け込んでいた。夕飯の前、畑に紫蘇や葱や山椒の葉をとりに行くのは子どもたちの役目だ。草叢にすだく虫の声、顔にかかる蜘蛛の巣、ひらひらと飛んでいくコウモリ。夜の畑は広くて、空には小さく星が光っていた。
裏山で遊ぶのが好きだった私のために、祖父はあるとき、山の入り口の斜面に石段を作ってくれた。石段を登って、落ち葉を踏んで、山の中に分け入る。その頃、我が家の近隣の山々はすでに切り崩されて、新しい宅地が造られていた。それでも小さな裏山はいまよりも鬱蒼として、いろんな生きものの気配に満ちていた。下生えの間を急ぐもぐらの行列、目の端をかすめるイタチ、家のすぐそばまでやってくるタヌキ。中には危険な生きものもいる。姿の見えないマムシ、不意に現れる大きな蜘蛛にアシナガバチ。
ずっと昔、この裏山がもっと奥深くて、ほんとうの山だった頃。曾祖母だったか高祖母だったか、家の誰かが狐に化かされたことがあったという。山一面にちらちらと光る赤い炎を見て、山火事だと思ったと。その話を祖母から聞いて、いつか私も狐火を見たいものだと思っていた。
広葉樹の雑木林は、孟宗竹の竹林につながっている。竹林の中は一面に青くて、清明で静かだ。竹の稈(かん)が風でふれあってカタカタと鳴り、はるか上のほうで梢がざわざわと揺れている。それなのに竹林の中がしんとしているように感じるのは、生えている竹の同質性と、伝わってくる振動の単調さのせいなのかもしれない。子どもの頃は竹林の中に入ると、ひんやりした竹の稈に耳をつけて、コロコロと流れているはずの水音を聴こうとしていた。
いま、その家には誰も住んでいない。長年にわたって畑と山の世話をしてきた祖父母はとうに亡くなり、その後を継いだ父母も、数年前に別の場所に引っ越した。ふだんは外国に住んでいる姉が、年に数回帰ってきては家の管理や修繕を受け持っている。姉のいない時には私と夫がときどき行って、雨戸を開けて風を通したり、庭の草を刈ったり、畑の片隅を耕して芋を育てたりしている。
でも、そんな気まぐれで散発的な世話では、迫りくる自然の猛威にはとてもかなわない。人間の領分を侵食してくる自然の猛威、それは草と笹と竹、それに蔓植物だ。春先から雑草が伸びはじめ、あっという間に丈高く伸び拡がり、あじさいや雪柳の茂みから細い竹の束が突き出してくる。蔓植物が南天に絡まり、ヤツデに絡まり、柿の枝に絡まる。植栽と笹と蔓植物が絡まりあって、何がどうなっているのかわからない。
私は虫除け網を垂らした帽子をかぶり、庭仕事用の長靴を履き、両手に軍手をはめて剪定鋏を構える。完全武装だ。あじさいの茂みに潜って竹の根元をばっさりと伐る。樹上まで伸びた長い蔓をつかんで引っ張って切り離し、南天やヤツデを救出する。山の斜面を覆っている笹の群生を刈り込む。どんどん切って、引っ張って、ざくざく切って。
虫除け網で視界が狭いのと暑さのせいでちょっとハイになってくるのか、作業の手が止まらなくなってくる。そろそろ休憩して、水を飲まないと危険。鋏を持つ手が震えて、腱鞘炎になりそうだ。でも止まらない。どんどん切って、引っ張って、ざくざく切って。
少しずつ、畑が元の姿を取り戻していく。山と畑の境界が消失し、植栽と笹と蔓植物が渾然一体となったカオスから、それぞれの植物があるべき場所に収まり、自分の領分に安らいでいる秩序ある空間へ。でももちろん、それは束の間の秩序にすぎない。笹も竹も太い地下茎で横へ横へとつながっていて、切っても切ってもまた生えてくる。雑草も、刈っても刈ってもまた伸びてくる。リゾーム。本などで目にする分には魅力的な言葉だけれど、畑に潜む実物は、手強くて憎たらしい。まさに人間的秩序にとっての脅威だ。それなのに、除草剤を使って根絶やしにする勇気はない。だから刈って刈って、刈りつづける。終わりなき闘いだ。
少し休もう。山の斜面に腰を下ろして、顔の前に垂れた虫除け網をまくって水筒の水を飲む。枝を低く伸ばした樫の葉叢の向こうに、黄昏の日にあかるむ畑と黒い屋根瓦が見える。祖父母たちはこの山や畑を、どうやって美しく維持していたんだろう。こんな場当たり的で適当なやり方ではなく、それは毎日の気配りと、一年の見通しをもった世話だっただろう。
春先から晩秋にかけての朝まだき、私が部屋で寝ていると、祖父や祖母が裏口から出て畑に向かう、ざっざっという足音がいつも聞こえてきた。祖母の爪は、土と植物をさわるので黒ずんでいた。むくげ、ろうばい、くさかげろう。俳句をたしなむ祖母は、植物や虫の名前にも詳しかった。
その時々の季節の、大気と植物と水と土の醸しだす匂い。畑に足を踏み入れるとき、草木の茂みにホースで水を撒くとき、子どもの頃の感覚がふっとよみがえる。祖父母のいた頃の畑の光景が、幻のように浮かんでくる。
十歳の私が、山の入り口の段々に座って祖父を見ている。祖父は草焼き用のバーナーで、畑の草をごうごうと燃やしている。雑草の殲滅。アリもバッタもダンゴムシも巻き添えだ。私は作業中の祖父に近づいて、「燃やさんといて」と言ってみる。
「ええ? みよちゃん何て」と、祖父は作業の手を止めて言う。そういえば祖父も祖母も、私のことを「みよちゃん」と呼んでいた。
「みよちゃんは雑草が可哀想やと思てるんか」
そう言って笑われただけで、案の定とりあってもらえなかった。
私が遡ることのできる記憶は、そのあたりまでだ。でももちろん、この山も畑も、もっとずっと昔からあったのだ。
裏山のふもとに お祖父さんの丹精になる南天の実が赤く美しくたれています
朝毎に百舌鳥(もず)が来てついばみます
一葉取って送りますから 何卒山里の晩秋を御想像下さいませ
この文章は、私の祖母である美智子が、彼女の夫(つまり私の祖父)の弟の婚約者に宛てた手紙の結びに書かれていたものだ。手紙の日付は、一九四一年十一月十五日。便箋の最後のページには、洋装のおしゃれな母娘のイラストとともに、色褪せた南天の押葉が挟まれている。祖父の弟はその頃、歳若い陸軍士官として海外の任地を転々としており、婚約者の文子さん1は東京に住む女学生だった。祖母の同じ手紙には、その年の春に生まれたばかりの長女についての記述もある。
容子もおとなしく元気に 皆んなの愛情を一身にうけて育っていきます〔…〕温いお縁がわでスクスク出来るように成りました もうセルロイドのおもちゃより絵本だの紐だの お祖父さんのお目ガネが好む様で御座いますの 大きな声で時々アプアプを云ってみんなを笑わせてくれます
でも今年は初めての冬でしょう ですから容子ちゃんの防寒着を作るのに忙しいです 縫物はお姑さんにお願いして私は編物ばかりやっておりますの 小さいジャケツやらレギングスやら 今ハーフコートを編んでいます
この手紙に出てくる赤ちゃんは母の二つ違いの姉で、私にとっては伯母にあたる人だ。日の当たる縁側で、婦人雑誌の見本を見ながら小さな娘の上着を編んでいる、若い祖母の姿が眼に浮かぶ。その翌年、一九四二年十月三十日付の祖母の手紙には、次のように書かれている。
もう朝夕はほんとうにお寒くなりましたのネ
田舎は只今茸がりで毎日賑(にぎわ)っています
お父さんも毎日栗拾いに行っておられます
お母さんは容子のお守りで大変です 此の頃はよく歩く様になりまして すぐお祖母チャンをさそって遊びに出かけます
いまから八十年以上も前に書かれた、祖母の書簡。どの手紙にも、家族の近況とともに畑の実りや田舎の風物のことがこまごまと記されている。茸狩り、栗拾い、雪景色、梅や桜の開花……。祖母の手紙を読んで初めて、私は裏山のふもとに生えている南天の木々が、曾祖父の植えたものだと知った。祖母は畑でとれた栗や芋を、ときどき東京の文子さんの家に送っていたようだ。一九四〇年代の初めから半ばにかけて、都会ではしだいに食料が不足していく時代だった。
曾祖父母や祖父母たちの暮らしとともにあって、一家の生活を支えていた山と畑。戦時中には、まさに彼らの命を支え、守るものでもあっただろう。
裏山には、防空壕の跡がある。私が子どもの頃、それはすでに落ち葉や枯れ木に覆われた横穴にすぎないものだった。それでも、「ここ」と指差すことのできる、それは確かな痕跡だった。近所に住む同級生たちが、連れだって見に来たこともある。
いまではそれと知らなければ見つけることも難しい、ただの窪みになっているけれど。
文頭にアクセントのくる独特の発音で、祖父母たちが「やしき」と呼んでいた家。その家はいま、季節の移ろいの中に長々と横たわって、静かに時を吸いこんで古びている。
曾祖父と曾祖母、祖父母とその娘たち。家の縁側に、庭に、裏口に、山や畑に。手を休めることなく日々のしごとをしながら、あれこれと喋りあい、家の内や外を歩きまわっていた懐かしい人たちの声や気配が、いまもそこここに漂っているような気がする。畑仕事のあいまにふと目を上げれば、その姿にもう一度出会えるような。
それは私の想像なのか、それともこの場所のもつ記憶なのか。
この連載は月2回の更新です。
次回は2023年6月15日(木)に掲載予定です。
バナーデザイン:山田和寛+佐々木英子(nipponia)