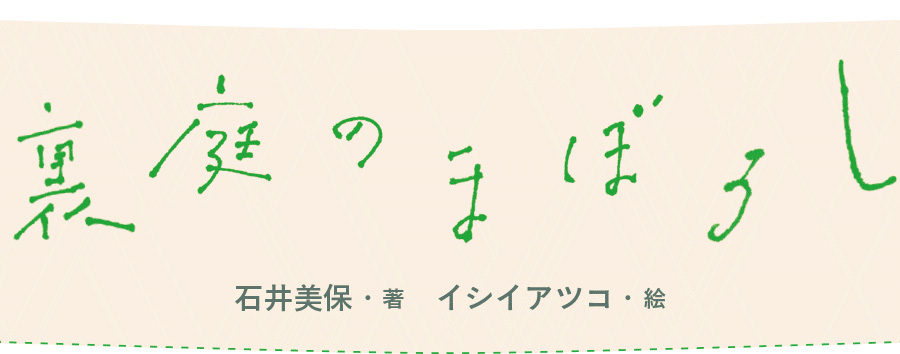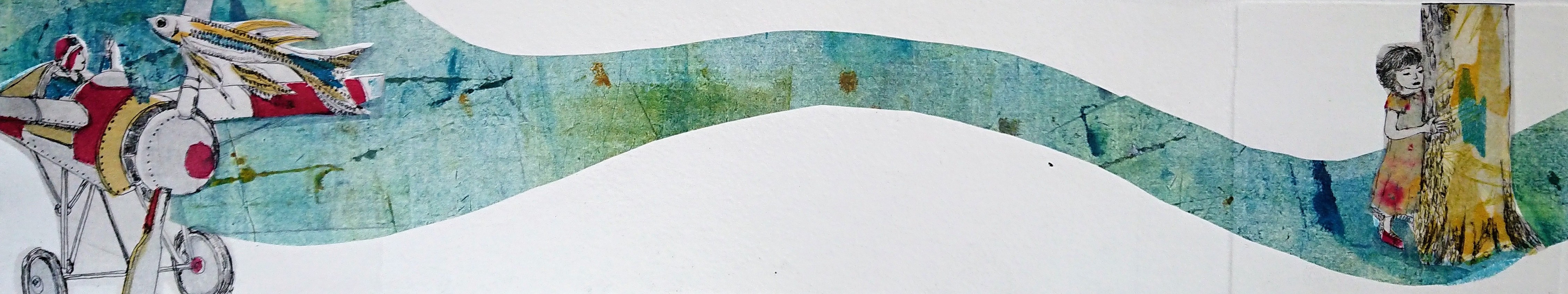until next time
until next time
実家の裏山にある栴檀(せんだん)の大木は、いつも変わらず細かな葉をさらさらと揺らしている。葉叢の間をよぎる鳥たちの影。樹冠の上に、白い雲が浮かんでいる。
普段はしんと閉ざされて眠っているような古い家が、活気を取り戻すひとときがある。たとえばそれは、外国に暮らしている姉がたまに日本に帰ってきた折に、家族が久しぶりにこの家に集まるようなときだ。縁側の硝子戸を開け放って風を通し、廊下や畳も拭き清めて。座敷の床の間に掛け軸をかけ、庭に咲いている花を飾って。
手元にある写真には、二組の姉妹が写っている。それは何十年も前のモノクロ写真ではなくて、ついこの間撮影されたものだ。伯母と母、姉と私。床の間を背景に、畳の上に正座して、喪服姿で晴れやかに笑っている。喪服を着ているのは、その日が父の一周忌の法要だったからで、それはでも、久々に二世代の姉妹たちがこの家に集まる懐かしい機会になったので、私たちはくつろいだ笑顔をみせている。
けれどもその日、数珠を手にした母や姉と並んで客用の分厚い座布団の上に座り、仏壇に向かって読経している僧侶の背中を見ながら、私は不思議な気分にとらわれていた。
子どもの頃、いまと同じように私は座布団の上に座って、僧侶の読経を聞いていた。でも、その頃私が座っていた場所は座敷のずっと下座の方で、前の列には何人もの大人たちがいた。祖父と祖母、父と母、伯母たち一家。普段は滅多に会うことのない、親戚のおじさんやおばさんたち。
この辺りでは「おおっさん」と呼ばれているお坊さんが家にやって来る日、大人たちはあれやこれやの支度に気をとられて、朝からずっと慌ただしい。玄関の引き戸ががらがらと開いては人が出入りし、客用の食器やお盆が蔵から運び出される。座敷と居間の間の襖が取り払われて、広々とした空間に紺色の座布団が整然と並べられる。そんなとき、私は大人の目には見えない侏儒(しゅじゅ)になったかのように、座敷と隣り合った台所や縁側を気ままに行き来しながら、大人たちの様子を観察していた。
座敷も縁側も庭の木々も、あの頃と変わらないようにみえるのに。
畳の上に並んだ座布団はこんなにも少なく、あの頃ここにいた人たちの多くは、写真の中だけの存在になってしまった。
それでも、だからこそ、私たちはこうして晴れやかに笑っている。
昔はどこか厳かな雰囲気が漂い、足を踏み入れることも憚られた座敷の、仏壇の前に据えられた大きな座卓にご馳走を並べて、にぎやかに喋りながら箸を動かす。話の合間にふと目を上げると、鴨居の上に祖父と祖母の写真が並んで、微笑を浮かべてこちらをみている。仏壇の前には、大叔父と父の顔写真。
もうこの世にいない人たちと見つめあうその瞬間、いまこうして集まって、笑いさざめきながらご飯を食べている私たちもまた、夢まぼろしのような気がしてくる。
というよりも、たぶん本当にまぼろしなのだ。ほんのいっとき、奇跡のように現れた、うたかたのようなこの時空間。私たちの存在も、いつの間にかすうっと消えてなくなる陽炎(かげろう)のようなものに過ぎないのかもしれない。
食事と片付けを終えた後、しばらくの間縁側に佇んで、前庭を眺めるともなく眺めている。庭の隅や敷石の上、植え込みの陰に、子どもの頃の私が佇んだり、飛び跳ねたり、しゃがみこんだりしているのが見えるような気がする。その子の影につられて前庭に出て、離れの傍の小道を通って裏の畑へ歩いていく。
柿の木、枇杷の木、かりんの木。金柑、あんず、ゆすらうめ。南天、あじさい、夾竹桃。椿につつじ、金木犀。
いつの季節も、花々はひとりでに咲いては散る。果樹は実をつけ、鳥たちがそれをついばむ——遠い日の祖母の手紙にあったように。初夏になるといつも、細い枝にたわわに実をつけるスモモの木は、かつて大叔父が祖母のためにその実をもいできたというスモモだろうか。
祖父の作った石段を上って、笹藪をかきわけて、栴檀の幹に近づく。昔はもっと自由自在に、山の中を歩きまわっていたものだったのに。あちこちに張りめぐらされた巨大な蜘蛛の巣の下をくぐって、色とりどりの木の実や、動物たちの気配を探して。山はいまよりずっと奥深くて、いつか明かされるはずの秘密に満ちていた。
それでも見上げれば、あの頃と変わらない青空に大きな樹冠が蒼々と広がっている。
この大木はどのくらい昔から、この家の甍(いらか)を見下ろしてきたのだろう。曾祖父と曾祖母、祖父と祖母、大叔父と文子さん、父と母。かつてここにいた、いまはもういない、何世代にもわたる人たちの暮らしの傍らで。
幼い頃にも、こうして栴檀の木に寄り添って空を見上げていると、どこか懐かしいような、切ないような、それでいて茫然とするような気分にとらわれることがあった。理由もわからずに。
いまそれは、私の知らないうちにこの場所に生きて去っていった人たちの、いまここにいていつかはいなくなる人たちの、いまここに存在しているものたちすべての、まぼろしのような儚さのせいかもしれないと思う。
年月というもの。生死ということ。
そろそろ夕刻だ。幼い頃の自分の影を雑木林の中に残して、私は一人で石段を下りる。
いつものように畑を横切って、家の裏手にある納屋の傍を通って勝手口へ。
その昔、ここには水を湛えた井戸があり、蔵と土間と台所に面した裏庭は、祖母や曾祖母たちの日々のしごとの場所だった。
家に入ろうとして、聞き覚えのある物音に、ふっと後ろを振り返る。
誰かが砂利を踏んで歩く、ざっざっという足音。畑につづく裏の木戸がギイーときしみ、ついでバタンと閉まる音。
裏山の木々の間に、納屋のそばに、井戸のほとりに。
いまはもういない、会ったこともないかもしれない、でも懐かしい人たちの姿が目に浮かぶ。いま、ここにある景色の向こうに、あの頃の風景と人びとの面影が映しだされる。
その面影に向かって、かすかに頷いて踵を返し、私は家の中に入る。
いつかまぼろしのように消えてしまう、日々の記憶を降り積もらせた家に。
(おわり)
本連載は2024年夏頃に書籍となって発売予定です。
楽しみにお待ちください。
バナーデザイン:山田和寛+佐々木英子(nipponia)