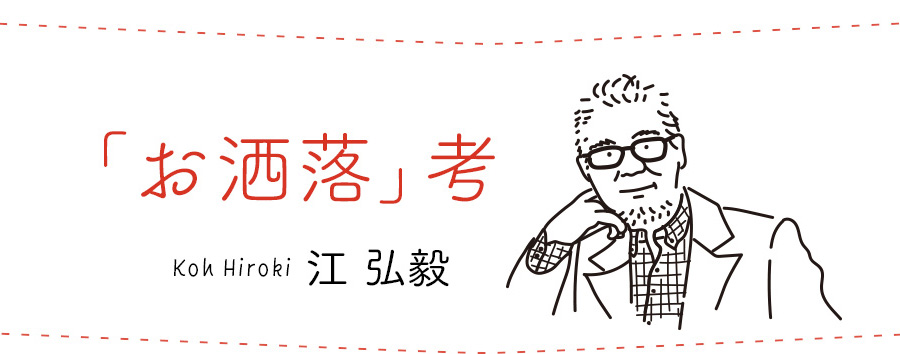うちの実家は「洋装店」で1階の店が生地屋だったが、70年代半ばまでは店の3階が「仕事場」で、40代の男性の「仕立て職人」と2〜3名の30前後の女性の「縫い子」さんがいた。
工業用ミシンが2台とベビーロック、天井からぶら下げられた水タンクにつながったプロ用のアイロンがあった。裁ち鋏や竹製の1メートルのものさしといった道具、チャコや糸巻きなど小物のデザイン。
それらは小学生のわたしに、独特の「服をつくる世界」を感じさせていた。
ちょうど背中合わせの1本向こうの商店街の同級生の家は「テーラー」で、父親が近辺のオシャレ客のためにスーツやジャケットをつくっていた。
ドーメルとかスキャバルの生地をほんの数種類置いたショーケースは「高そうな生地やなあ」だったし、小学生にも一目でそれと分かる度胸千両系男稼業の客は、よくサングラスをかけていた。

スーツもジャケットも、シャツもオーダーというのを一時、目指したがいろいろあってヤンピした。

よく行くBrowne Browne Kobeでは、ネクタイもこういうふうに生地見本がある。そんなのを見せられると「おお、ええな」とクラッとくる。
90年代になって雑誌業界で「ビスポーク・テーラー」という言葉を耳にするようになったとき、「ああ、仕立屋のことやねんな」と理解したが、なんだか「ん?」と思ったのは、あの時代の縫い子の「よっちゃん」やテーラーのオヤジのカッコよさの種類みたいなものが違うからだった。
「3つボタンのナロー・ラペル」「胸ポケットはアイビーなパッチ・ポケットで」「パンツには尾錠を付けてほしい」とか、そういうのがビスポークなんだと思っているが、なんかそういったディテールの知識的なこだわりばかりで、「おぬしデキる」「おぬし分かる」みたいなことばかりやりとりするのは、あんまりカッコいいなとは思えへんかった。
「やっぱりオーダーのスーツは違う」と思ったのは、『ミーツ』誌が軌道に乗り始めた90年代後半。
小西マサヒトくんが大阪の南船場に「ビスポーク・テーラーDMG」という店を出して、わたしは取材して記事を書いた。
小西くんのお母さんは北摂で「洋装店」をやっていて、かれはそこで育ったとのことだ。「オレとこと一緒やんけ」と思って、以後プライベートでよく遊びに行くようになった。
雑誌の編集者という仕事では、目上の偉い人に取材するときや、クライアントに挨拶に行ったりする以外はスーツは必須ではなかったので、はっきりいって「どういうスーツが本物だ」的な知識はなかった(今もないだろうが)。
ネクタイもプレーンノットしか締めたことなかった30代後半だった。
ある日、岸和田の実家の生地屋に帰ったら、淡いベージュのコードレーンの生地を発見した。綿100%のカリっとした結構ぶ厚い生地で、うちの店では珍しいメイドインUSAもの。
そのころ水色のコードレーンのジャケットがビームスとかで流行っていたのだが、「このベージュはないやろ。それもスーツや」という「ええカッコ心」が沸いて、ダブル幅のその生地3メートルほど切ってもらってDMGへ持っていった。
確か仕立代6万円ぐらいだった(現在は6万8千円+税とのこと)と記憶する。
ジャケットは3つボタン段返りで貼りポケ、パンツはタック無しの「小西くんのいつもの」ちょっとだけテーパー細身のパンツの両サイド尾錠を、と注文付けてあとはお任せ。
採寸しながらわたしの肩が極端ななで肩なのを小西くんは見抜いて、「肩パッドちょっとだけ入れさせて」と言って、「ほなそうやっといて」と任せた。

今でも着ているDMGに仕立ててもらったスーツ。三つボタンの段返り、サイドベンツ(アイビーなセンターのフック・ベントと迷った)。ジャケットの腰ポケットはフラップ付き貼りポケ(パッチ・ポケット)。パンツのサイドの尾錠(調子に乗りすぎている)。尻ポケットは両玉縁のかけボタン。

しかし、こういうところはオーダーがダントツに良い。で、ラペル裏のこんなところにネーム刺繍を入れた(お調子者である)。
「仮縫いは要らんわ」と言って、1カ月ほどして上がってきた夏物のスーツは完璧だった。
「ええスーツやなあ」「そらそやオーダーや」「ワシもつくろかなあ」みたいな感じで好評。
それから10年以上。スーツを以前よりよく着るようになって気づいた重要なことがある。
どうも肩のあたりが「合いすぎ」というか、なで肩をカバーして「隙がない」というか……。
しいて言ってみればまるで昭和天皇とかのスーツ姿なのだ。あるいはありし日の横山やすし師匠。
これがほかの「自分が似合ってると思っている」ジャケットと比べて気にくわないのである。
「なで肩」はもちろん「腹が出ている」「脚が短い」「胸が薄い」……。それぞれあるよなあ。
それを悩むあまり、そんな欠点を補ったり隠すこと目的でオーダーするのはダサい。そう思うのだ。
究極はきっとシークレットブーツとかズラなんだから。
「やっぱり着こなしや」みたいなことはおっきな声で言わないが、あたり前の「吊しの服」で自分に合うのはどういう感じのもんかとか、ほかの人にない「なで肩」そのままのカッコよさというのは、自分が一番よく知っている。
そういう立ち位置で服と関わっていきたい。そう思うのだ。
なにかといろいろオーダーのことを書いていたが、実は一番の落とし穴は、「試着出来ない」ということにつきる。
それはテーラーの「腕」ではなく、多分に「感性」という例のヤツだ。鼻をふくらませて、襟の感じやポケットのフラップを「これで」とオーダーしたのは良いけれど、仕立てが出来上がってきてフィッティングルームに入る。テンションも上がってるで。着る。で、鏡の前に立つ。「あれ、なんじゃこれ」(または「あわわ」)それで「違うやん」。
これは誰のせいだろう、オレが悪かったんか。
というか、ここまで来ると後戻りできない。言っておくが、それが「試着ではない」からだ。客側がそういうふうな顔をしても、もうテーラーの側はレジを打つしかないのだから。
(第2回・了)
次回2020年1月22日(水)掲載