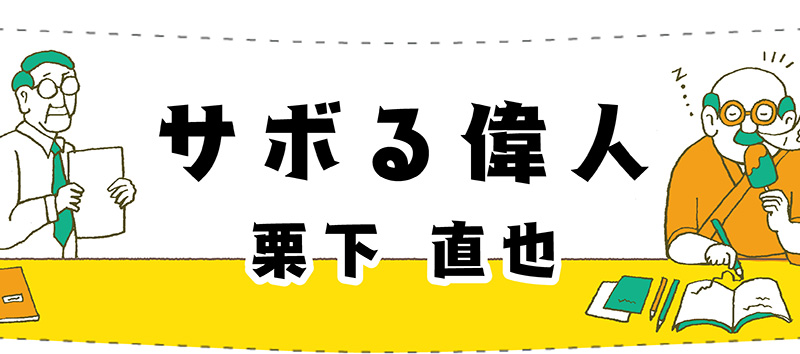10年以上前の話になるが、僕は仕事をサボっては昼間から酒を飲んでいた。特に何か絶望したわけでも、夢に敗れたわけでもなく、ただただ飲みたかったのだ。
とはいえ、21世紀の企業社会に昼酒に付き合ってくれる人はほとんどいない。僕も勤め人だったので、「じゃあ、明日、11時に!」などと前もって約束して飲むわけにもいかない。業界紙記者という仕事の性質上、なぜか超暇な日がありというか、今日は店じまいだと勝手に暇にしてしまい、酒でも飲もうとなるわけだが、そんなに急に飲んでくれる人はいないのだ。
そんな時によく飲んでくれたのが「部長」だ。部長といってももちろん、自分の会社の部長ではない。取材で知り合ったベンチャー企業の部長で急に誘ってもイチローの打率以上の確率で付き合ってくれた。「あんた、本当に会社員かよ」と心の中で突っ込みながら感嘆していたのだが、今となっては「おまえも会社員だろ」という話である。
部長は突然の誘いに付き合ってくれるだけでなく、僕が「金がない」というと奢ってくれた。当時は本当に金がなく、クレジットカードのポイントで交換した商品券を換金してまで飲んでいたくらいなので、結局、毎回、奢ってもらっていた。「うーん、現人神ってこんな顔しているのか」とあまりの人格者ぶりに後光がさして見えたときもあったが、そもそも、人に会うという名目で外に出られるから急な誘いに付き合ってくれていただけで部長も仕事をサボりたかっただけなのだ。そして、会社のカネで飲みたかっただけなのだ。
部長と何を話したかはほとんど覚えていないのだが、よく上野で飲んでいた。そして、「上野は落ち着くなー、地元にかえった感じがする」と部長は繰り返していた。「北の玄関口っていいますもんね」というと「そうそう」とノリノリだったが、部長のふるさとは兵庫県だった。全くもって北でない。そもそも、部長といっても30歳そこそこでふるさとを思う年でもない。お互い適当だったのだ。
ただ、僕も部長も適当だったとはいえ、上野で故郷を思うのはおかしくはない。
「ふるさとの 訛なつかし 停車場の 人ごみの中にそを 聴きにゆく」
上野駅の15番線ホーム近くには直径70センチほどの円形の歌碑に石川啄木の有名な歌が記されている。
石川啄木と聞くと朴訥な印象を抱くかもしれないが、歌の内容と人格は一致しない。「よくわからないけど貧乏そうでかわいそう」と同情されがちな宮澤賢治も雨にも風にも負けないどころか台風が来てもびくともしないくらい実家が資産家だったのは有名だ。
石川も貧しそうなイメージが強いが、貧しかったというよりも、働かないのに浪費家だっただけなのだ。
1909年8月に出された週刊誌「サンデー」(サンデー社)で2号にわたって「東京朝日新聞社編輯局の内幕」という記事が展開されている。
そこでは朝日新聞の内情や言論界をリードする社員についてあれこれと書かれているのだが、二葉亭四迷や夏目漱石と並び、ひとりの社員について触れられている。「旧新詩社中の天才と謳われた青年詩人、今の昴同人たる啄木石川一も校正にいる」。半年前に入社した校正係に対しては異例の言及である。
啄木が朝日に入社するのは1909年3月。給料は30円。月額25円に一夜1円の夜勤料が加わって30円だった。ちなみに、当時在籍していた夏目漱石は200円、二葉亭四迷は100円である。
この頃の朝日の入社試験にはまだ筆記試験はなかった。同年12月に初めて入社希望者に筆記試験を課し、東京帝大卒と早稲田大卒 を採用している。新聞が面白おかしく、まるで、見てきたように書かれる時代から取材力や論証力が求められるようになった時代の端境期であった。
啄木はぎりぎり滑り込んだわけだが、実際、入社の面談もかなり適当だ。
応接室で待っていると男が現れ、「やあ」というので啄木もつい「やあ」という。相手が「私が佐藤!」といったので、啄木は「私が石川!」と答えた。双方アハハハと笑い、「じゃ、追ってさたします。さようなら!」「さようなら!」。「やあ」の応酬で採用は2分で決まった。
面接で「佐藤」と名乗った相手は、編集長の佐藤北江(本名・真一)だった。編集長というのは現代では整理部長や編集局長に相当する幹部だ。
死後、啄木の名声が高まるにつれて「俺は啄木をよく世話したんだよ」と社内で自慢する者が続出したが、実際は佐藤と社会部長の渋川玄耳くらいだったという。特に佐藤は葬式でも親族のように弔問客に対応した。
さて、肝心の働きぶりだが、入社以降は他の社員と同じく週一の休みで出勤していたが、初任給を貰った頃から怪しくなる。
給料日翌日の3月26日に無断欠勤すると、30日、4月3日と休みが目立つようになる。そして、4月13日から5日連続で会社に行かない。
啄木は校正が仕事だ。記者ではないので会社に行かなければ校正も出来ない。
体調が悪かったわけでもない。まず、13日は「電車の切符が一枚しかない」と日記に書いているが、一枚あるのならば、とりあえず行けよと思うのだが。その後は仮病を使って2日休み、創作するからとまた2日休むのだが「今日こそ必ず書こうと思って社を休んだ―否、休みたかったから書くことにしたのだ」とあるので、どこまで創作する気があったのかわからない。
ようやく出社する日も別に上司に怒られたわけでも心を改めたわけでもない。11時まで床の中で会社に行こうか行くまいか悩んでいたら、下宿の女中に声をかけられ、「今日も休んでいる」と思われたくなかったからに過ぎない。5日休んで言う台詞ではない。
日記を追うと、その後はしばらく出勤するが、4月29、30日と休む。「今日は社に行っても煙草代が払えぬ。前借は明日にやらなくてはダメだ―どうしようかと迷った末、やはり休むことにした」と、おまえは何のために会社に行くのだとつっこみたくなる記述もある。実際、翌日に給与の前借りに出社すると、5月はほとんど出社しない。
啄木はこんな感じでのらりくらりと会社員生活を送るが、1911年2月に腹膜炎で入院するや、足が社に全く向かなくなる。闘病生活を経て、1912年4月に亡くなるが、その間も朝日新聞が啄木に給与を払い続けた。ただでさえ働いているかどうか怪しい啄木を雇っていただけでなく、全く働けない啄木に給与を払い続け、賞与まで与えていた。
懐が深すぎるではないかと感涙して朝日新聞を購読しかねない勢いだが、実際は社の方針というよりは面接の相手でもあった編集長の佐藤の温情によるものが大きかったようだ。佐藤は遅刻や欠勤の多い啄木に対する社内の苦情からも守ってくれていた。朝日新聞社が自由すぎる社風だったわけではない。
そもそも、朝日入社前から、啄木はサボりの帝王だった。朝日入社前に釧路新聞社(北海道新聞社の前身のひとつ)に1908年1月下旬から勤めていたが、わずか76日で退職している。それまで、ほとんど記者経験がなかったが三面の主任、実質は編集長待遇で迎えられた。短い在職中に「紅筆便り」(芸者たちの私生活などに関する連載)や「雲間寸観」(政治評論)など企画を立ち上げる。文章もうまかったが現代のジャーナリズムの感覚からすると決して褒められたものではなかった。というのも、記者は100行分の取材をして10行を書くが、啄木は10行分しか取材しないのに100行書いた。新聞の記事を小説のように書き、事実を度外視して盛りすぎる傾向にあった。実際、気象に関する記事も、他の文献や気象データと見比べると、「盛ってる」面が否めないという。
人間関係から嫌気が差し、3月23日から無断欠勤を始め、4月5日には釧路を離れている。会社では啄木の欠勤を快く思わない者も少なくなく、啄木の愛人の芸者が紙面上で攻撃される。そもそもは啄木自身が芸者との関係を吹聴するような記事を書いていたのだから身から出たさびなのだが、私怨で紙面を使うなど学級新聞でもあるまいしと思うのは私だけではあるまい。それだけで驚いてはいけない。待てど暮らせど出社しない啄木に業を煮やした釧路新聞社は4月25日に「石川一 退社を命ず」と社告を掲載する。紙面で退社を命ずるなどあまり聞いたこともないが、本人はその前日に北海道を離れ、上京していた。
啄木は創作で身を立てる夢を抱いていたが、19歳で結婚する前に義父に将来の生計の手段を問われた際に「新聞記者」と答えている。ある意味、理想通りの人生だったともいえるがその道のりは苦難の連続だ。
結婚の翌年の1906年に故郷である盛岡郊外の渋民の小学校の代用教員に採用されたが、ストライキ騒ぎを起こして1年余りで職を追われる。「三つ子の魂百まで」ではないが、問題を起こす奴は職場を変えても問題を起こすのは変わらない。
教員をクビになり、出身地の岩手を離れ北海道に渡ると、前述した釧路新聞に入社する前には小樽新聞社に勤務していた。ここでは上司からの暴力で職を離れる。確かに殴られてまで仕事に執着する必要はないが、殴られた原因は啄木の無断欠勤だった。
なんでそんなに仕事をサボるのかと思わざるをえないが、サボるのは仕事だけではない。それどころか、自身の結婚式すらサボっている。
(後編につづく)
この連載は次回より月1回、月末に更新予定です。
次回は2023年1月31日(火)に掲載予定です。