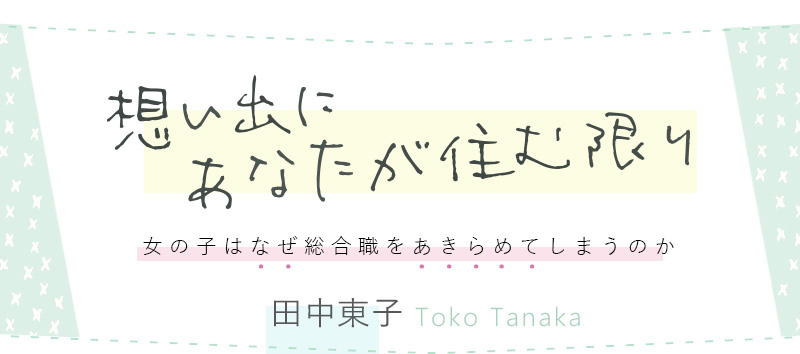これまで20年以上にわたって、数多くの大学で授業を行ってきました。
授業が終わると多くの女子学生が話しかけてくれたり、相談を持ちかけてきたりします。大学には女性の先生が少ないから、東子先生は話しかけやすそうだからという理由で、彼女たちは勉強についてや、女子大学生としての生きづらさ、日常の悩みなどを打ち明けてくれます。
そうやってたくさんの会話をして、学期が終わっても連絡をくれる彼女たちのなかには、エネルギッシュで自分自身の道を切り開いていくタイプの女の子もいれば、自己肯定感が低くて、ここぞという時に委縮してしまうタイプの女の子もいました。
彼女たちに自信とパワーを与えているものは何なのか、その反対に、彼女たちから自信やエネルギーを奪い、足を竦ませ金縛りのような状態にしてしまうものは何なのだろうか?
その疑問を解いていくために、彼女たちとの話を改めて思い起こしてみることにしました。
想い出にあなたが住む限り――女の子はなぜ総合職をあきらめてしまうのか 田中東子
2021.11.22
01前略 はづき様
はづきさん、お久しぶりです。お元気にしていますか? ジェンダー関係の授業の後、足早に教室を出ていった私の後を廊下まであなたが追いかけ、すごく緊張した面持ちで話しかけてくれた日のことを今でもはっきりと覚えています。まだ19歳でしたよね。
あなたはすごく不安そうな顔をしていて、でも、しっかりとした口調で「先生に相談したいことがあります」と切り出してくれました。あなたは北陸の出身であること、小さいころからお兄さんの影響で野球をやっていて、中学3年の終わりに肘を壊してしまうまで地元ではかなり有力な選手であったことを話してくれました。
「将来、野球やスポーツにかかわる仕事をしたいんです」
あなたはそう言い、私がスポーツとフェミニズムについて論文を書いていることを知って、相談してみようと考えたのだと教えてくれました。
「女の子が野球を続けるのは、大変だったんじゃないの?」と私が聞くと、あなたは男の子たちに混ざって野球を続けるのはすごく楽しかったけど、徐々に家族や周りの人たちには、女の子なのに野球なんていつまで続けるの? と聞かれる頻度が上がっていったと答えました。それでもあなたは野球が好きだったから、できなくなるその日まで男の子たちに混ざって一生懸命頑張っていたのでしょう。
その授業が終わってからも、あなたは時々連絡をくれましたよね。大学3年生の頃には、スポーツの業界に進みたいからインターンに参加して積極的に就活の準備をするのだと、話してくれました。あなたは何度も、「私はバカだから、早めに頑張らないと」と言いました。それを聞いて、私は少し不思議に思いました。きちんと将来の夢を持っていて、そのために準備をしようとしているあなたが、どうして自分のことを「バカ」だと思うのだろうと。それは決して、女の子たちが自虐的にふざけあって言うときの「ばか」ではなく、あなたのなかでなにか呪いのような言葉として響いているのではないかと思わせるものでした。
一方で私は、フェミニズムを教える立場として、就活を頑張ろうとする女子学生を目の前にすると、いつもある葛藤に囚われます。職を得る、というのはいまの日本社会の中で女の子が自活して自力で生きていくためには非常に重要なものであることは間違いないのだけれども、いまの日本の会社文化というのは女の子にとって不平等な条件のもとに編成されていることから、無邪気に「就活頑張ってね!」なんて言えない、そんな複雑な気持ちになってしまうのです。
でもあなたは、広告代理店に勤めている知り合いの方に、ESの書き方などを教わっていて、すでにインターン先もいくつか決まっていると教えてくれました。スポーツにかかわる仕事をしたい人は今すごく多いけど、女性社員をこれから増やそうと考えているはずだからしっかり頑張ってね、と私は告げて、それからしばらくあなたと会いうことはほとんどなくなってしまいました。
次にあなたから連絡をもらったのは、卒業間近の頃だったでしょうか。卒論はどうしたの? 就職先はどこに決まったの? 矢継ぎ早に尋ねる私に、あなたはやっぱりちょっと自信のなさそうなオーラをまとって、卒論は日本のスポーツと人種差別の問題について書いたこと、就職活動はうまくいかなかったのだということを、ぽつぽつと話してくれました。就活はどんな感じで進んでいったのかと尋ねる私に、あなたは1年半くらいの時期に経験したことを話してくれました。
代理店勤務の知り合いの指導を受けて、いくつかの大手スポーツ企業の書類審査は通ったこと。面接も頑張って、先に進んだり、途中でお祈りメールをもらったり、いくつもトライできたということ。その途中で、代理店勤務のその人に就活セクハラを受けるようになり関係を断ったということ。最終面接に呼ばれた時、男性の最終候補者のなかにたったひとりの女性候補者として残っていると分かり、急に自信がなくなってしまったということ。男子学生たちは理工系や芸術系の有名大学の学生で、自分だけバカなんだと思ってしまい、ここっていう時に頑張る力が出てこなくなってしまったということ。
「それ、前からすごく気になってたんだけど――どうして自分のことバカだって思うの? 女の子でひとりだけ最終面接まで残るなんて、すごいことじゃない?」――最初に声をかけてくれたときの、あなたの自信のなさそうな顔つきがふっと頭を過ぎり、私は思わず聞いてしまいました。
「だって、わたしバカだし、ブスだし」
「どこが? すごく頑張ってたし、ぜんぜんブスじゃない」
「でも、ブスだって、女の子らしくないってずっと言われてたから……」
「誰に? いつ? なんでそんなこと言う人がいたの?」
あなたに、そんな言葉を投げつけた人がいたということに、ものすごい怒りが沸いてきて、その時、質問した私の声は震えていたと思います。
私の問いかけに、あなたは高校時代のことを話してくれました。中三で野球ができなくなり、それでも好きな野球の近くにいたくて、進学した県立高校では野球部のマネージャーになったこと。その野球部は毎年、県大会でベスト8くらいにまで進む地元では有名な強豪校であり、その野球部の部員たちはスクールカーストの最上位に居て、他の女子マネージャーたちとあなたのことを比較して、ブスだの女らしくないだの3年間ひどいハラスメントを加え続けてきたということ。
「ずっとスポーツやってたから、実際、肌は真っ黒で髪の毛も短かったし」――と話す、その時のあなたは、ちっとも日焼けをしてなくて、髪もサラサラのロングヘアでしたよね。肌をこんがり焼いてショートヘアのあなたの姿を想像してみると、すごく似合うのにもったいない、と私には感じられました。
「他の女子マネは、みんな色白で髪も長くてスカートはいてて女の子っぽくて、部員の言うことを素直に聞いて……だけどわたしには、すごく意地悪でした」――詳しく聞くと、男子部員の口撃に乗っかって、女子マネ―ジャーたちからも意地悪をされていたということでした。
「頑張らなきゃっていう時になると、あの時の、野球部員たちの声が聞こえるんです」
「最終面接の時にも聞こえたの?」
「そうです。お前なんかにできるはずないって……」
「はづきさん、それは呪いだよ。あなた大学でも頑張ったじゃない。」
「そうなんですけど……うち、地元ではあんまり上位の高校じゃなくて。大学は東京に行きたい、って言ったらそれもバカにされました。うちの高校に来るようなバカが、東京に行けるわけないだろ、って」
「マネージャー、辞めちゃおうとは思わなかったの?」
「野球の近くに居たかったんです」
「そうか……そうだよね。野球が本当に好きなんだもんね。それで、どうしたの?」
「勉強、めちゃめちゃ頑張りました。それで、高三の3月の懇親会の時にひとりずつ進路を発表するんですけど、私が進学先の大学の名前を言ったら、保護者席がざわついて。野球部の男子たちは全然分かってなかったんだけど、保護者はちゃんと分かったみたいで。それはちょっとだけ……いや、かなり気分が良かったです」
「そしたらさ、そっちのことを思い出そうよ。これからまた、仕事を続けていろんなプレッシャーに直面すると思うけど、その気分良かった時のことを思い出して、呪いを解いてしまおうよ!」
食い気味に話す私を見て、あなたは、先生っていつも楽観的ですよね、と言ってちょっとだけ笑顔を見せて。
「そうですね。次にチャンスが来た時には、必ずそっちを思い出すようにします」
「約束だからね!」
「はい、絶対に守ります!」
最後は笑顔で手を振って別れました。あなたはきっと、卒業してからも元気で頑張っていることでしょう。
10代の頃、男の子たちにブスだとか女らしくないだとか言われるのは、実はそんなに珍しい話ではないんです。その他愛もないように見えてしまう言葉が、どれだけ言われた女の子たちから自信と自尊心を奪い、前に進もうとする足を竦ませ、体を委縮させてしまうのかも知らず、彼らは気軽に侮辱的な言葉を口にするのです。
あなたとの会話は、私の記憶の奥底に潜んでいる呪いの声を呼び起こしたのだけれど、あなたにかけられた呪いが解けたら、いつかその話を聞いてもらえるかしら。
草々
*社会調査法に準ずるインタビュー調査と直接行われた会話の内容から、個人が特定されないように情報を再構成して書いた、フィクションとノンフィクションのあわいのようなエッセイになります。