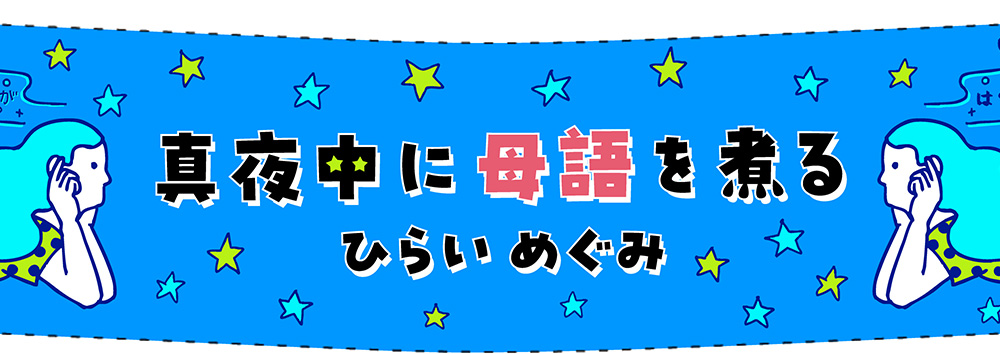送られてきたメール。SNSの投稿。乗った電車の車内に吊るされた広告。ただ生活しているだけで、わたしたちは毎日たくさんの言葉を浴びる。そして、目にする言葉のほとんどは、手書きの文字ではなく活字だ。活字のふしぎなところは、ぱっと見、それなりに整った文章に読める点にある。活字で書かれていると、整然とした日本語が並んでいるように感じてしまう。しかし、まじまじと読んでみると、不可解な内容になっていたり、意味を理解するのに時間がかかる説明になっていることが意外と多い。
たとえばある日、Instagramでレシピを紹介する動画を観ていたら、「鬼リピが止まらない!」「ケチャップがペーストになるまで炒めて」というテロップが流れてきた。言いたいことはわかるが、どこか違和感がある。「鬼リピ」は「鬼のように繰り返すこと」で「止まらない!」とほぼ同義のような気がするし、ケチャップはそもそもペーストだ。これらは、決してめずらしい例ではない。普段の日常会話の中や、街中で見かける広告など、ありとあらゆるところにふしぎな日本語は潜んでいる。
英語を習いはじめたときは、明快でたのしかった。「a」と「the」の違いや「in」「to」「out」などの前置詞をイラストで説明してもらったり、時制が変わると「am/is/are」が「was/were」になるなど、ひとつひとつの法則を理解することができたので、納得して言葉を覚えられた。国語はどうだろう。文法のテストでは満点をとれても、「てにをは」の間違いがなくならない。「ナップザック」と「リュック」の違いはうっすら感じるけれど、自分の言葉では説明できない。日本語を当たり前に使いこなせているようで、根っこから理解できているような気がしない。他言語を理解すればするほど、かえって日本語への疑問は膨らんでいった。このもやっとした感覚は、大人になった今も変わらずある。いまいち違いがわからないまま「は」と「が」を無意識に使い分け、「どんぶらこどんぶらこ」と聞けば、頼まれてもないのに脳内の川で桃を流している。
国語嫌いだった身としては、今から日本語の文法を一からやり直すことだけはぜったいに避けたい。だけど、文法の鎧で覆われたカチカチの母語を、鍋の中でコトコト煮込むように、捉え直してみるのはどうだろう。一旦専門的な知識は脇に置いて、実際に見聞きした言葉を自分なりの解釈でほぐしていくのだ。「鬼リピが止まらない!」の違和感の正体はなんだろう?「ケチャップをペーストにして」が理解できるのはどうしてだろう? 教師でも研究者でもない、野良の日本語話者が身近な母語と向き合うことで、英語を習ったばかりのときのような、言葉を学ぶたのしさに触れることができるかもしれない。
あらためて向き合ってみたい、気になる言葉のテーマはたくさんある。母語をおいしく煮込むために、まずなにからはじめようか。