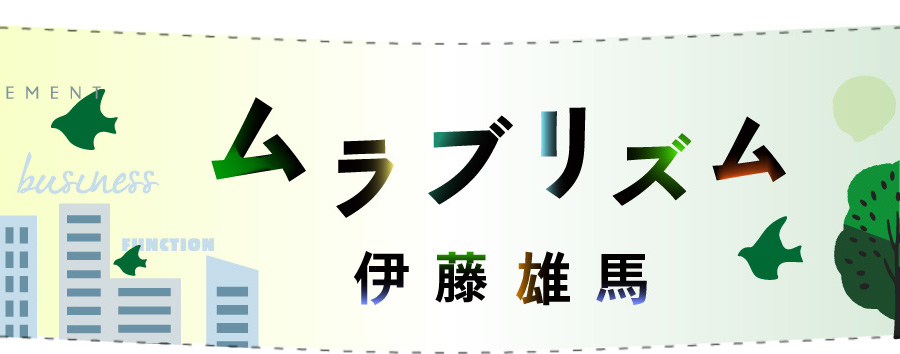ムラブリズムのコンセプトについて、もう少し深掘りしてみたいと思います。まず、ちょっと学術的にお話ししてみますね。そういうのはいいやって人は、次の章まで飛ばしてください。次の章で、ほとんど同じことを、日常的な言い方で言い換えています。
では、学術的に説明します。ムラブリズムは「トランス・ランゲージング超越性(translanguaging supremacy)」によってデザインされています。あ、検索しないでください。これはぼくの造語です。ヒットしません。
トランス・ランゲージング超越性とは、「複数の言語を深く学習することで、母語のみの習得よりも、ある感性へ導かれやすい」というぼくの体験に基づく仮説であり造語です。個別の言語を超えた言語資源があるとする「トランス・ランゲージング(translanguaging)」と、古典コンピュータよりも量子コンピュータが課題を簡単に解決する量子超越性(quantum supremacy)から着想をえています。どういうこっちゃ? 少しずつ説明してみます。
まず「トランス・ランゲージング」です。「トランス」は「超える」、「ランゲージング」は「考えを言語化する」なので、直訳すれば「言語を超えて考えを言語化する」みたいな感じです。これは、複数の言語を話す人はどうやって話しているかの研究で登場した概念です。
例えば、ふたつの言語を使う人を、バイリンガルと言います。日本語とムラブリ語を使うぼくも、バイリンガルです。では、ぼくがこうして日本語で考えを書いているとき、ムラブリ語はどう影響しているでしょうか?
古典的な考え方では、ムラブリ語は影響しません。日本語とムラブリ語は、使っている辞書や文法が違うからです。この辞書や文法を言語資源(language resource)と言います。生成AIだとデータセット(データの集合体)にあたるでしょうか。バイリンガルの人は、異なるふたつの言語資源を独立して持ち、使うときも独立したままだと考えてきたわけです。
しかし、その考え方はバイリンガルの実感や実情と合わないことが指摘されてきました。ぼくの経験でもそうです。ポッドキャスト「ムラブリとしてみる。」の収録などで、ムラブリ語と日本語を使い分けます。そこでの自分を振り返ると、日本語とかムラブリ語とか、どちらともいえない何かから言語化が起きているように感じられます。つまり、言語資源は特定の言語を超えた、未指定のものとして捉えられるのです。これが「トランス・ランゲージング」、つまり「言語を超えて言語化する」の意味することです。
次に量子超越性です。これは量子コンピュータの登場によって生まれた言葉です。古典的なコンピュータは「電源のオンかオフか(0か1か)」の組み合わせで情報を処理します。それに対して、量子コンピュータは「0であり1でもある」という量子の性質である重ね合わせ状態(superposition)を利用して処理します。これまでは「0、1」と「1、0」は別々に処理しなければならなかったのが、量子コンピュータでは「0かつ1、0かつ1」の1回で処理できます。「Aでない、かつAである」重ね合わせ状態をどのように実現するかが、量子コンピュータの技術的な課題だと言います。
この「トランス・ランゲージング」と「量子超越性」の概念から、トランス・ランゲージング超越性が着想されました。つまり、特定の言語を超えた未指定の言語資源に、複数言語の重ね合わせ状態によって気づきやすくなると考えたのです。なぜ未指定の言語資源に気づこうとするかと言えば、言語の虚構性を看破するためです。言語化が未指定の言語資源から起きていることに気づけば、特定の言語による言語化がいかに限定的であるかも必然的に自覚するようになります。
言語資源が特定の言語を超えた未指定のものならば、単一の言語だけを使っていては気づきにくいでしょう。ではどうするか。複数の言語を使うこと、いえ、ただ使うだけでなく、同時に複数の言語を生きることが有効だと考えます。言い換えると、as研究です。「as(として)」とは、「そうではないけれど、それとして振る舞う」という意味です。より抽象的に言えば、「Aでない、かつAである」ことを目指す試みです。つまり、ぼくのムラブリ語のas研究とは、日本語とムラブリ語の重ね合わせ状態をぼくの内に達成しようとする試みだったのです。
日本語とムラブリ語の重ね合わせ状態をどれだけ達成できているのかは分かりませんが、未指定の言語資源に気づいたのが、as研究の一番の成果だと現時点では思います。未指定の言語資源は、どこまでも言語に自由なところで、誰もがすぐにでも思い出せるはずのものでした。それをみなさんと共有しようとするのがムラブリズムです。
ここまでがちょっと学術的な説明でした。今度は、もっと日常的な言い方で説明してみようと思います。
ムラブリズムはメガネの重ねがけ?
「ムラブリ語を学んで、世界を変えるって、日本語とは全然違う言語を学んで、世界の見方を豊かにするってことですか?」
確かに、日本語とは全く違う言語を学ぶと、世界の見方にバリエーションが増えて、楽しいですよね。例えば、ムラブリ語には「食べる」が3つあります。詳しくは後ほどまた描くとして、そんなムラブリ語で見るときの食卓は、日本語で見る様子と少し変化します。ムラブリ語のメガネでみると、食卓が異なる彩りを見せる。世界の見方が増え、解像度が上がること。これが言語学習の魅力であるのは間違いありません。
しかし、世界の解像度が上がることだけが、言語学習のアドバンテージだとは思いません。むしろ、ムラブリズムにおいては、その「効用」はミスリードです。そもそも、世界の解像度は高い方がいいのでしょうか。分かることは分けること。より細かく世界を分けるのを良いとする前提には、世界は細かく見た方がいい、という信念があります。その信念をもってムラブリ語を見た場合、がっかりすることが多い。
ムラブリ語は「ないない尽くし」で、解像度が上がらないことがほとんどです。文字はなく、暦はなく、数字は10までしかない。色も味も少なければ、身体部位の区分もシンプル。ムラブリ語の世界は「粗く」、解像度を上げません。「世界は細かく見た方がいい」という信念のもとでは、価値の少ない言語と見なされるかもしれない。
これを逆手にとって、「粗い」ことがいいんだと言うこともできます。例えば、ムラブリ語には「健康」を意味する語がありません。普段は胃がどこにあるのか気にしません。しかし、胃痛になると、胃の存在を強く感じます。不健康な人だけが、健康を強く意識する。つまり、健康を気にしない人が、最も健康といえます。その意味で、「健康」という語を持たないムラブリ語は、構造的に話す人を最も健康にします。このような効用をもって、「世界は粗く見た方がいい」と主張することも可能です。
しかし、この主張は経験上、ウケがあんまりよくありません。「それはそうだけどさ〜、もう健康って知っちゃてるし、忘れるのは難しいよ」という反応が多い。ぼくも同感です。そもそも、ムラブリも「健康」という語がないだけで、その概念は理解しています。ちなみに、ムラブリ語では「体調が悪い」ことを「小さめの何かが痛い(グレット チャドゥー)」と言います。身体部位ですらないのに驚きますが、よく考えると、日本語の「体調」もかなり漠然としたものですね。ともかく、同じ人間である以上、ムラブリも日本語話者も「小さめの何かが痛い」ことは生じます。
世界は「細かく」みるべきなのか、「粗く」みるべきなのか? そこに明確な答えはありません。好き嫌いであり、程度問題です。細かいメガネがあり、粗いメガネがある。色々な種類のメガネをたくさんもって、取り換えたり、重ねがけすることは楽しいです。しかし、視力が良くなっているわけではありません。むしろ、メガネをかけることで目が悪くなっているかもしれません。また、「他にもっと理想的なメガネがあるのではないか」とメガネを探して回るハメになるかもしれません。残念ながら、その旅に終わりはありません。理想のメガネに出会った!と思った次の瞬間に、そのメガネに飽き始めるからです。人は変わり、好みは変わります。それは誰にも止められません。
ムラブリズムの狙いは、その理想のメガネを探して回る不毛の旅を終えて、自分の目を思い出すことです。どんなメガネをかけていようと、目は共通です。しかし、ぼくたちは見えている色を世界の色だと勘違いするのが日常です。目が見えない方に向けて書けば、聞こえている音が世界です。目も見えず、耳も聞こえない方に向けて書けば、皮膚に触れる感触が世界です。目も耳も皮膚も働かない人に向けて書けば……いえ、きっとぼくが書かずとも、世界が何か、知っておられるんじゃないでしょうか。ともかく、ぼくらが「これが世界だ」と感じているものは、感覚です。でも、感覚には「メガネ」がかかっている。
ガッチャマンっていますよね。知らないですか。異なる色のマスクをかぶっている5人組のヒーローです。それだけ分かればいいです。そのガッチャマンが、ある車を見て、「あの青い車を追うんですね?」「バカ、あれば紺だ。」「黄色よ。」「緑だぜ。」「お前ら1回マスク取れ。」という二次創作のネタがあります。何度も見ているのに、見かけるたびに笑ってしまいます。悔しい。
もっと古典的なものだと、目が見えない人が象を触って、「これは大木だ」「いや蛇だ」「何を言う、うちわじゃないか」「壁だろう」「ロープだ」「槍だ」などと言い合うが、それぞれ脚、鼻、耳、胴体、しっぽ、牙だった、のような「6人の目の不自由な人と象」というインドのお話もあります。
これらは笑い話ですが、ひとしきり笑ったのちに、冷静になって考えると、彼らはまさにぼくらのことだと気づきます。ぼくらは「感覚=世界」だと勘違いしています。しかし、その感覚は「メガネ」、つまり言語によって影響を受けています。極論、ぼくらは言語を世界だと思い過ぎているのです。「言語=世界」。そんなはずはありませんよね。世界は言語を超えて、もっともっと分からないに満ち満ちています。分からないは分けていない。ぜーんぶ一緒。それに思い至るのが、ムラブリズムの狙いです。
メガネをかけているのを思い出すためには、日本語だけでも可能です。ムラブリ語だけでも可能です。けれど、日本語とムラブリ語という組み合わせは、なかなか有利かもしれません。日本語とムラブリ語のメガネの取り換えには、大きなギャップがあるからです。日本語とムラブリ語の話されている環境のギャップと言い換えてもいいです。このギャップによって、メガネを取り換える時間が長くなります。その滞空時間に、自分の目を思い出す可能性が拓かれているのです。
また、メガネを重ねがけすることも有効かもしれません。なぜなら、メガネ同士が矛盾することがあるからです。ムラブリ語には「心が上がる」と「心が下がる」という表現があります。日本語のメガネで考えれば、「心が上がる」はポジティブな気分で、「心が下がる」はネガティブな気分だと予想できます。「それって、当たり前では?」しかし、ムラブリ語は、「心が上がる」がネガティブで、「心が下がる」がポジティブです。逆なんですね。
もし、日本語とムラブリ語のメガネを重ねがけすることができたら、「気分アゲアゲ」がポジティブとネガティブの両方に感じられるはずです。矛盾しているのが分かる。矛盾してると、噓っぽく感じませんか? そう、結局は「気分アゲアゲ」がポジティブかネガティブかなんて、メガネによって違う、言ってしまえば噓っぱちなのです。ムラブリズムは、メガネの重ねがけによる違和感で、メガネの存在を際立たせます。それが「あ、メガネかけてるんだった」と思い出すきっかけになる。それが狙いです。
ガッチャマンに泣く
日々、ガッチャマンを目にします。色々な人が色々なメガネをかけながら、「世界は赤だ!」「いや青だ!」と罵り合っている。メガネのことを忘れちゃってたら、そりゃ、自分が赤に見えるものを、誰かが青だと言っていたら、「バカじゃねーの」と思いますよね。一時期までは、それを笑えなくて、腹を立てていました。「赤でも青でもねーよ、メガネ取れって!」と叫んでいました。でも、それって、ブーメランですよね。「罵り合いはよくない」というメガネを、ぼくもかけていたわけですから。あらゆる信念、良い悪い、べき論は、メガネです。
生きている限り、メガネを取ることはきっとできません。メガネって、平たく言えば、肉体ってことです。肉体というメガネを外すのは、死ぬときでしょう。生きることは、メガネをつけること。つまり、生きている限り、メガネ越しの不完全な状態でしか世界を生きられない。それに気づいてから、そんな自分が嫌で、やることなすこと全てが愚かで、何もしたくない、死んだ方がマシじゃ〜と思っていました。そんな風に考えていたから、他の人たちが不完全であることを忘れて罵り合っているのが、我慢できなかったんだと思います。「おまえらも自分が不完全だって気づいて、俺と一緒に黙るか死にたくなるかなれよーっ!」って言いたかったのかもしれません。おー怖い怖い。
でも、メガネを取ることができないことと、メガネから自由になることは、別なんですね。「これもメガネを通じて見てるんだな〜」って忘れないこと。ぼくは、日本語のメガネと、ムラブリ語のメガネを付け替えたり、重ねがけすることで、世の中のデタラメさが分かりました。それってメガネのデタラメさだったんですけどね。そのおかげで、メガネをかけていることに自覚的になったのだと思います。
いまは、ガッチャマンがとてもおかしく、そして美しく見えます。不意に泣きそうになるくらいまであります。罵り合おうが、殺し合おうが、笑い合おうが、抱きしめ合おうが、ぼくたちがやっているのは、とどのつまり、「メガネ違うな!」だけなんです。ガッチャマンは、不完全でしか生きられないぼくが、不完全でしか生きられないあなたと、そのままの姿で愛し合う無限の表現の、ひとつなんです。それが許されていることの、完全無欠さといったら! これが、ムラブリズムの告知文で、芸術という言葉でぼくが意味しようとしたことです。「あなたの世界に、あなたによって、あなたであること」。何を言うかも、何をするかも関係ない、芸術の定義です。もしくは、生活のあらゆる側面を芸術にする試みです。
日本語のリズム、ムラブリ語のリズム。それは量子の重ね合わせ状態のように、ぼくの中に同時に存在しています。そうとしか言いようがありません。それは矛盾で、かつ自然です。それが、日本に生まれ、日本語を話すようになり、ムラブリと出会い、ムラブリ語を学び、日本でムラブリとして生きてみた、ぼくの素朴な感想です。そして、いかなる名付けをも抱擁し拒否する未指定の言語資源をみなさんと踊ろうとする無謀な遊びが、ムラブリズムなのでした。
なんのこっちゃかもですね。でも、スッと分かってくださる方もいると思います。連載を読み進めていただくことで、「あ~ね~」ってなれば嬉しいです。
次回からは、ムラブリ語のメガネがどんなものか、それをどうやって重ねがけしていけるのか、実際におこなわれた「座る語学」の様子とともに紹介していきたいと思います。
(続く)