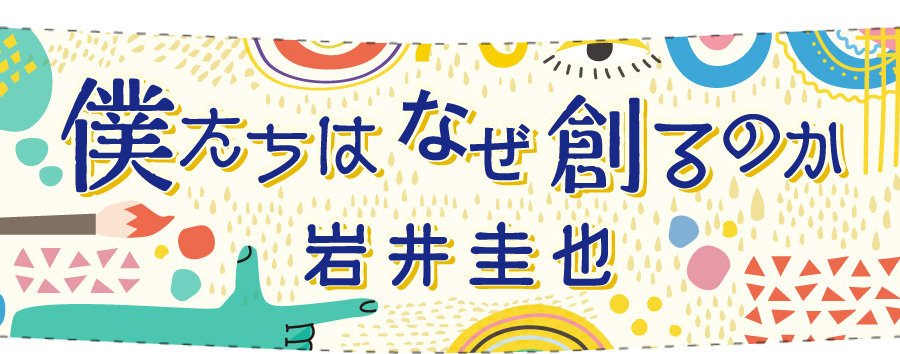「自給自足」と「意思表示」
朝夕めっきり冷え込むようになった、十月下旬。僕は編集者NさんとJR中野駅前で待ち合わせた。
Nさんは、以前、『アール・ブリュット 湧き上がる衝動の芸術』(大和書房)を担当したことがある。中野に来たのは、その本の著者である小林瑞恵さんにお話を伺うためだった。
中野駅から歩くこと数分、取材場所である社会福祉法人愛成会に到着した。予定よりも少し早く着いてしまったため建物の前で待っていると、リュックサックを背負った女性が現れ、にこやかに挨拶してくださった。
「おはようございます!」
彼女こそ、愛成会で副理事長を務める傍ら、アートディレクターとしても活躍されている小林瑞恵さんであった。
小林さんは美術展の企画や講演活動等を通じて、アール・ブリュットの魅力を発信している。国内外の作家を発掘するほか、作家の権利保護にも尽力されるなど、その活動範囲はきわめて広い。
たとえば、中野区内では商店街と愛成会が連携して、二〇一〇年からアートイベント「NAKANO街中まるごと美術館!」を開催している。街中にアール・ブリュット作品を展示したり、商店街のアーケードなどにポスターを掲示したりといった取り組みで、作品と市民との接点を拡大しているが、そのディレクションの中心人物こそが小林さんだ。
応接スペースで対面した小林さんに、まずアール・ブリュットとの出会いについて尋ねてみた。いわく、スイスのローザンヌにあるアール・ブリュット・コレクション(一九七六年、ジャン・デュビュッフェが集めた作品を展示する美術館として設立された。三万五〇〇〇点に上る作品を収蔵する)への訪問が、本格的な邂逅のきっかけだったという。
「枠におさまらない、原始的なエネルギーを感じました。両親の影響で小さいころから美術館にはよく足を運んでいたのですが、作品の技法に関する議論などを高尚に感じてしまい、心に響くものがなくて……けれどローザンヌでアール・ブリュットを観た時に、すっごいな、と。一つ一つの作品にその人の生きざまを感じるというか、個々の作品に同じものがない、ということが衝撃でした」
二十六歳の時にアール・ブリュットと出会った小林さんは、その魅力にのめりこんでいく。二〇一〇年にパリで開催された「Art Brut Japonais」展にも携わり、約十二万人もの観客が来場した。二〇一八年には再びパリで「Art Brut Japonais Ⅱ」展の日本側のキュレーターを担当し、こちらも約十万人の来場者を集めた。
国内外のアール・ブリュット作品に精通している小林さんであれば、作り手の「創作の源泉」についても何かご存じなのではないか。そう考えて、取材の時間を取っていただいた。さっそく、アール・ブリュットの作り手たちがどういった経緯で作品制作に向かうのか尋ねてみた。
「動機やきっかけは本当に人それぞれなので、あくまでも個々人についてお話しする形にはなりますが」
そう断ったうえで、小林さんは幾人かの作り手について話してくださった。
「勝部翔太さんは、これまでに何百体もの『戦士』を作られています」
勝部さんの作品は、ビニールタイで作られた戦士たちだ。ラッピングやお菓子の袋を閉じる時に使う、あのビニールタイである。
勝部さんは光沢のある素材を使って、見事な戦士たちを生み出す。ハサミやニッパーを駆使し、数ミリメートル幅のビニールタイを切ったりねじったりすることで、腕や足、武器や衣装などを精巧に作り上げている。たくさんの作品が一堂に会した光景は、圧巻というほかない。
「勝部さんはもともと、市販されているキャラクターのおもちゃが欲しかったそうです。でも、市販のおもちゃをコレクションするのはお小遣いだけでは難しいじゃないですか。それならば自分で作ろう、というのがきっかけだったみたいですね」
勝部さんの創作衝動は、僕とよく似ているようだ。勝部さんは「自給自足」から創作活動を開始したわけだが、「自給自足」という意味では、愛読していた連載が終わったため小説を書きはじめた僕と同じだ。
暮らしのなかにある素材で作る、という点では、「はじめに」で紹介した萩尾俊雄さんも同様である。
萩尾さんは、広告紙とセロハンテープから怪獣を作り出す。角や背びれ、尻尾や爪などが、固く巻きつけられた紙とテープによって表現されている。これらの怪獣は、萩尾さんにとって「作品」ではなく「おもちゃ」として作られているという。やはり動機は「自給自足」なのだ。
僕個人も、幼い頃はチラシとセロハンテープを使った工作に没頭した経験がある。母いわく、紙をくるくると巻いてテープで固めた「剣」を作ることに熱中していたそうだ。家中の広告紙を使い尽くしてしまい、知り合いに頼んで分けてもらうほどだったらしい。こうした経験があるせいか、萩尾さんの作品には心惹かれるものがある。まるで自分の少年時代を見ているかのような気持ちになるのだ。
「萩尾さんは作家になろうと思って作っているわけではないので、いい画材をそろえたり、粘着力の強いテープを選んだりはしないんですよね。日常のなかにある素材を使って作る。だからこそ親近感が生まれる面もあります」
彼らは「いい道具を使わなければ」といった固定観念にとらわれていないし、身近だから価値が低いとも思っていない。手の届く範囲にある素材で制作した結果として、鑑賞者の心に訴えかける力が生まれたということだ。
萩尾さんに限らず、セロハンテープを使って制作する人は一定数いると小林さんは言う。
「セロハンテープというのは劣化する素材なんです。時間が経って変色したり、パリパリになったりする。でも作り手たちは、そもそも作品を美術館で見せたり、収蔵して長く保管しようとは思っていないんですよね」
プロの作家であれば、よい状態を長く保てるように、劣化が少ない素材を選ぶかもしれない。だが、彼らはそういう視点で制作を行っていない。テープの劣化を気にしているのは、本人ではなく周囲の人間に過ぎないのだ。
「朽ちていく芸術じゃないけど、制作した直後、その一瞬しか見られない作品があるということも自然なんじゃないかと思います」
作品を長く保管してほしいと望むのは、誰かに見せることが前提になっているからだろう。しかし「自給自足」が目的なのであれば、長期保管の必要はない。自分が楽しめればよいのだから。
続いて、藤岡祐機(ゆうき)さんについて伺ってみた。藤岡さんは、チラシなどの紙類に一ミリメートル未満の間隔でびっしりと切れ込みを入れていく「切り紙」で知られる。ハサミに角度をつけることで、切った部分はクルクルとした螺旋状になっている。一つ一つの切れ込みの細さと正確さは、とても人間業とは思えない。
「これも私の推測ですが」
小林さんはそう前置きしたうえで語ってくれた。
「藤岡さんにとって、『自在に紙を切る』ことはとても気持ちがいいのかもしれないですね。ご自身の思いや考えを自由に表現できる手段として、切り紙を捉えているのかもしれません。ご家族から聞いた話ですが、寝る間際まで紙を切っていて、布団のなかが切った紙で一杯になっていたこともあるそうです」
この洞察に基づくなら、藤岡さんは「意思表示」が創作活動の動機なのかもしれない。ハサミを動かせば、藤岡さんの意思のままに紙が切られ、造形される。その世界では、作り手はまさに創造主である。切り紙そのものにメッセージがこめられているというよりも、切り紙を作り続けること、それ自体が意思表示であるとも言えそうだ。
完成と未完成のあいだ
小林さんは言葉を選びながら、作り手たちについて慎重に話をされていた。その姿勢からは、作り手たちを「アール・ブリュット作家」という総称ではなく、あくまでも個々人として尊重しようとする意志を感じた。
制作ペースも人によってまちまちだという。数分のうちに制作してしまう作り手も、一つの作品に長い時間をかける作り手もいる。
「なかには、永遠に終わらない方もいます」
永遠に終わらない、とはどういうことだろう。
「たとえば、二十メートル近い絵巻物を描かれる戸谷誠(とやまこと)さんは、何年も経ってから作品に手を加えたりするんです。長大な絵巻物が六十本近くあるにもかかわらず、『あの作品のあの部分に色を足さなきゃ』ということをはっきり覚えている。自分の作品の模写もされているようです。まったく同じではないですけど、構図や展開が同じものを複数作られたりしています」
完成がない、というのは商業作家としては考えにくいことである。たとえかりそめであっても、完成させなければ作品を市場に流通させることはできないからだ。しかしどうやら、一部の作り手は完成そのものを目指しているわけではないらしい。それは商業ベースの発想ではないからこそ、できることにも思える。
「人って答えを求めがちじゃないですか」
小林さんのつぶやきは、僕の胸にぐっと突き刺さる。
「すぐにパターン分けしたり、表現する時はこういうものだって経験則に当てはめたりするでしょう。作品は完成しているように見えるのに、どうして完成していないんだろう、と疑問を抱くのも、そういう基準で見ているせいじゃないですか。私たちは答えを求めてしまいがちですけど、作り手は答えのない問いをずっと抱え続けている。そこにアール・ブリュットの面白さがあるのかなと思います」
答えのない問いを抱える。それは、非常に苦しいことだ。
難題にぶつかった時、答えを求めたくなる気持ちには心当たりがある。心が弱っている時ほど、誰かが差し伸べてくれる解にすがりつきたくなる。そこで急いで助けの手をつかまず、悩みのなかに留まることは簡単ではない。
世間的に「タイパ」という語が流行して久しい。『三省堂現代新国語辞典』の編者である小野正弘先生によれば、「タイパ」は「タイム パフォーマンス」の略称であり、〈あることにかけた時間から得られる見返りや利益。時間効率。時間対効果。〉を意味するという。(1)
できるだけ速く、効率的に正解を知りたい。「タイパ」の流行からは、そうした欲求が透けて見える(もちろん僕にとっても他人事ではない)。そして「答えのない問いを抱える」ことは、タイパを追求する姿勢の真逆と言える。
フランスのマーガレット・シルヴィンスという女性は、入院していた精神科病院のシーツを紡いでウェディングドレスを作ったという。シルヴィンスは「いつか結婚したい」という夢を抱きつつ、晩年までドレスの制作を続けた。彼女にとっては、制作そのものが生きることと一体化していたのだ。完成を必要としない作り手たちにとっては、むしろ「未完」であり続けることが創作の意義なのかもしれない。
戸谷誠やシルヴィンスの制作姿勢を知るにつれて、作品の「完成」と「未完成」は、くっきりと判別できるものではないような気がしてきた。これはアール・ブリュットという分野にだけ見られる事象なのだろうか。私にはそうも思えない。宮沢賢治は「農民芸術概論綱要」という評論で「永久の未完成これ完成である」と述べているが(2)、シューベルトなど多くの芸術家が未完の作品を遺している。「完成」をどのように定義するかということは、普遍的な問題であるように思える。
そもそも「はじめに」で示したように、アール・ブリュットという言葉の意味自体、非常に曖昧なものだ。小林さんは、アール・ブリュットという定義に当てはまるか否かは、比較的些末な問題だと考えている。
「ジャン・デュビュッフェが提唱したアール・ブリュットの概念は、あくまでも概念であってジャンルではないんですよね。特定の作家や作品がアール・ブリュットの枠組みに入るか入らないか、というのはあまり重要ではないかなと」
デュビュッフェがこの概念を提唱した背景には、見られていない存在を可視化する、という目的があった。すでにアール・ブリュットという言葉が一定の知名度を得た現代において、定義そのものが変容するのは自然ななりゆきなのだろう。
「人っていろいろな幅のなかで生きているものですよね。高度な専門教育を受けてきた作家だからといって、いわゆる専門家向けの作品だけを相手にしているわけではなく、衝動的な表現活動や無垢な発想から生まれる作品に衝撃を受けることがあります。日本の著名な作家でも、日比野克彦や坂本龍一のように、アール・ブリュットに目を向けている人は少なからずいますよね」
人は生まれ持った性質だけで創作するわけでも、後天的に身につけた知見だけで創作するわけでもない。その両輪を回しつつ、全人的に前進することが、創作活動であると言えそうだ。人生に解がないように、創作にも解はない。
海外でのキュレーション経験について伺っている時、小林さんはこう話していた。
「海外で関心や注目が集まると、それだけで国内の評価が変わることもあるんですよね。作品自体は変わっていないんですけどね……」
似たようなことは文芸の世界でも、その他のアート、エンタテインメントの領域でも起こっている。わかりやすいのは、文学賞だろう。著名な文学賞を受賞したことで、作品の売り上げが急増することがある。そのこと自体は悪いことだとは思わない。すばらしい書き手が顕彰され、評価されることに異論はない。一方で、「作品自体は変わっていない」という事実を忘れてはならないとも思う。賞を授けられる前から、その作品は人々の目につく場所にあったはずなのだ。
受け止め切れないほどの情報で溢れる現代、評価軸をある程度他人に委ねるのは致し方ないことなのかもしれない。だが少なくとも、「アール・ブリュットだからこうだ」という粗雑な議論には陥らないよう、気をつけねばならないと自戒した。
ネガティブ・ケイパビリティと創作活動
小林さんへの取材をしながら、僕は「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を思い出していた。最近はビジネスの場でも使われる言葉であり、聞いたことがある人もいるかもしれない。作家で精神科医の帚木蓬生は、この言葉について次のように説明している。(3)
ネガティブ・ケイパビリティ(negative capability 負の能力もしくは陰性能力)とは、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」をさします。
あるいは、「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」を意味します。
小林さんの言う「答えのない問いを抱える」ということは、まさにネガティブ・ケイパビリティそのものではないだろうか。戸谷誠やシルヴィンスといった作り手は、創作活動を通じて、「人生」という答えのない問いとじっくり向き合っているのかもしれない。
この言葉を作ったのは、一七九五年生まれのイギリスの詩人ジョン・キーツである。しかしキーツの手紙に書き残された「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉は、およそ百七十年もの間、歴史のなかに埋もれていた。
再発見したのは、精神分析の大家ウィルフレッド・R・ビオンである。ビオンは〈ネガティブ・ケイパビリティが保持するのは、形のない、無限の、言葉ではいい表わしようのない、非存在の存在です。この状態は、記憶も欲望も理解も捨てて、初めて行き着ける〉のだと考えた。(4)
記憶も欲望も理解も捨てて――。
この一節は、美術教育を受けず、名誉欲に乏しく、衝動的に創作に向かう作家たちを想起させる。勝部翔太や萩尾俊雄、藤岡祐機といった作り手たちには、「自給自足」や「意思表示」という目的があるかもしれないが、それらの目的はネガティブ・ケイパビリティを保持することと矛盾しない。作品単位での完成はあっても、創作活動そのものは未完だと言える。
そう考えると、もはやアール・ブリュット云々は関係なく、あらゆる創作活動を続けている人は、皆ネガティブ・ケイパビリティを備えていると言えるのかもしれない。私自身、一人の実作者として命が続く限り書き続けたいと願っている。終着点があるとすれば、それは息を引き取る瞬間だろう。
帚木氏は小説を書くこともネガティブ・ケイパビリティを要する行為だと語り、一例として池波正太郎の談話を引いている。(5)
私自身、もう三十五年以上も前、『鬼平犯科帳』の作者である池波正太郎氏が、ある月刊誌で編集者と対談したときの記事を読んだことがあります。
池波氏が週刊誌に時代小説を連載していた頃です。ある回の最後のところで、夜道を歩いていた主人公の侍が、背後から一太刀を浴びせられます。瞬時に身をかわした場面で、その回は擱筆したのです。
担当の編集者が、「この切りつけた男は、いったい何者ですか」と訊いた返事が、「いや私も実は分からんのだよ。来週になれば大方の見当はつくと思うが」でした。
このやりとりを読んだ私は、何と無責任な作家だろうと、腹が立ちました。
しかし、創作とはそういうものだと、今では池波氏が到達していた境地に敬意を払うばかりです。
僭越だが、この感覚には心当たりがある。
僕はプロット(小説の設計図のようなもの)を立ててから原稿を書きはじめるタイプだが、書いているうちにプロットを逸れていくのはいつものことだ。登場人物のほうから、台詞やアクションを提案してくるのである。いわゆる「キャラクターが動く」状態に近い。その結果、時にはあらかじめ考えていた結末が大きく変わることもある。だが、それでいいのだと思う。
言い方を変えれば、執筆は常に先行きがわからない状況で行われる。帚木氏は〈小説を書くのは、まさに暗闇を懐中電灯を持って歩くのと似ています〉と語っている。少し先しか見えない状況で、周囲に目配りしながらじりじりと歩を進めるには、ネガティブ・ケイパビリティを発揮する必要がある。
僕はむしろ、作者がコントロールしきれない部分にこそ、小説の面白さが滲み出るとすら思っている。プロットは「その通りに書かなければならない道」ではなく、「執筆の見通しをよくするための道しるべ」に過ぎない。実際の路上では道を外れることは許されないが、執筆ではいくら道を外れても怪我はしない。行き止まりに突き当たれば、引き返して走り直せばいいだけだ。
少し話が逸れてしまった。ともかく小説の執筆は、わずかな光を頼りに暗闇を進んでいくような作業であり、ネガティブ・ケイパビリティが求められるということだ。
同じようなことは小説に限らず、創作活動全般に当てはまりそうだ。
以前、『完全なる白銀』(小学館)という小説を雑誌で連載していた時、写真家の山内悠(ゆう)さんの作品を挿画として使わせてもらった。その縁でお会いした際、山内さんは「シャッターを切る瞬間は、何が写っているのかわからない」と話していた。
「持ち帰って現像して、初めて何が写っているかがわかる。そこには意図していなかったもの、撮影する時には気がつかなかったものが写り込んでいることもある。そこが、写真の面白いところだと思うんです」
この一言には目を開かれた。今思えば未熟きわまりないが、当時の僕は、写真を撮ることを「目に見えているものを記録する」行為であるかのように思っていた。その理解はまったく違っていたわけで、むしろ「目に見えないものをも記録してしまう」ことが、写真撮影の面白さなのだと思い知った。
創作活動はどこかワクワクする感覚をはらんでいる。それは、創作活動の根源的な不確かさによるものではないだろうか。先行きが見通せない冒険だからこそ、人はワクワク感を覚える。
イベントとしての創作、エピソードとしての創作
哲学や公共政策学を専門とする、若手研究者たちによる鼎談本『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』では、「イベント」と「エピソード」という言葉が象徴的に用いられている。(6)
彼らは、SNSの普及した現代社会が〈イベントをフックにしないと集まれない、関心を喚起できない社会になっている〉可能性を提示しつつ、〈そこでしかありえない関係性が表現されている〉「エピソード」を対比させている。誰が相手でも成立する祝祭的な「イベント」と、特定の関係だからこそ作られていく日常的な「エピソード」。よりネガティブ・ケイパビリティが発揮されるのは、後者であろう。
同書には次のような一節がある。
杉谷 〔前略〕私たちは「型にはまるな」という教訓を知っているのに、よく似た語りをして、原則通りの関係を作って、型通りのイベントを楽しんでしまう。そういう社会からのメッセージをはねのけて、自分の身の回りに注意深くなれるかどうか、プライベートな関係をしっかり作っていけるかということが試されているんですね。
谷川 なるほどな。そうやって自分を振り返る視線に、「ネガティヴ・ケイパビリティ」って名前がついていると。〔後略〕
この会話も、先の小林さんの言葉を思い起こさせる。人はパターン分けや、経験則への当てはめをしたがるものだ。それは型通りのイベントを楽しむことと似ている。
その点、先に紹介した作り手たちの創作活動には型がない。作家たちは端(はな)から型など無視して、自らやり方を模索してきた。具体的には、セロハンテープやビニールタイ、ハサミやシーツなど、暮らしのなかにあるものを使って創作をしてきた。それは、身の回りに立脚した「エピソード」的な態度に他ならない。
「イベント」と「エピソード」の対比は、創作活動にも当てはまるように思える。不特定多数の人の目に触れる商業出版や、コンクールへの出展を目的にした創作は祝祭的な「イベント」であり、他者に見せることを目的としない、プライベートな創作は「エピソード」であると言えそうだ。
もっとも、創作においては「イベント」と「エピソード」が入り交じった状態というのも往々にしてあるだろう。たとえば、文芸の分野では私小説がそうかもしれない。私小説とは、作者自身をモデルにした小説分野のことである。商品としてパブリックに流通しているという意味では「イベント」であり、同時に、作者自身のプライベートに材を取るという意味では「エピソード」なのだ。
僕は両者を区別すべきだと言いたいのではない。創作活動には「イベント」的な面と「エピソード」的な面があり、その濃度は場合によってさまざまだということである。ただ、アール・ブリュットと呼ばれる作品の作り手たちは、比較的「エピソード」の濃度が高いように見受けられる。
小林さんが全国を巡って出会ったアーティストの多くは、工房や施設で人知れず創作していた方々である。彼ら彼女らにとって、創作することは日常そのものだ。全員がそうだとは言わないが、傑作をものにしてやろうという気負いや、美術界で名を上げようという功名心とは無縁の人が大半だろう。そういう人たちにとって、創作はどこまでも個人的な「エピソード」だ。
そういえば、小林さんはこうも語っていた。
「作品がアール・ブリュットの展覧会に出たり、雑誌で紹介されたりする人って、氷山の一角じゃないですか。多くの人は亡くなるまで無名のままですよね」
僕たちが目にしているアール・ブリュット作品は、パッケージングされ、鑑賞に供されたものであり、その裏には数えきれないほどの無名の作り手の作品がある。それらの作品は「イベント」的側面を獲得しなかったかもしれない。だが、「エピソード」としての役目は果たしているはずだ。ネガティブ・ケイパビリティを発揮し、身の回りに目を向け、ものを創ること。そこにはきっとワクワクする感覚が潜んでいる。
今日もこの世界には、人知れず「エピソード」としての創作を行っている人たちがいる。
(1) 三省堂 辞書を編む人が選ぶ「今年の新語2022」(https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/shingo/2022/best10/Preferenceall.html)二〇二三年十月二十四日閲覧
(2) 宮沢賢治『新 校本 宮澤賢治全集〈第十三巻 上〉覚書・手帳 本文篇』筑摩書房、一九九七年