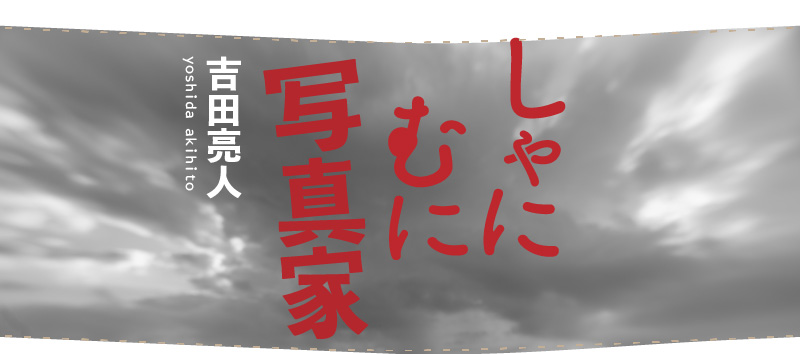2019年8月から2020年7月まで「あき地」で連載をしていた、写真家の吉田亮人さんの「しゃにむに写真家」がこのたび書籍になりました!
 本体価格 1,600円、2月17日(水)全国発売!
本体価格 1,600円、2月17日(水)全国発売!
〈いしいしんじ さん、推薦!!〉
タイトルは『しゃにむに写真家』。
妻の一言から教員という仕事を捨て、無謀にも写真家の道を選んだ。専門的に学んだことのない男が、右も左もわかないまま踏み出し、挫折し、傷つき、そして国際的に評価を受けるようになるまでの10年を振り返る。
——「働くとは何か」「生きるとは何か」について考えた渾身の一冊にできあがりました。
そこで、2月17日(水)の発売に先駆け、収録原稿の試し読みを4回に渡って公開します!
試し読み第1回目は書籍の冒頭に収録した「プロローグ」です。吉田さんが写真家になって5年目のときに起きた衝撃的な出来事から、物語は始まります。
「プロローグ」
二〇一五年三月一四日、早朝六時。枕元に置いてあったスマホが「ブーンブーン」と不快な音を立てて鳴り続けている。寝ぼけ眼でまさぐりながらスマホを手にし、画面を見ると母からの着信だった。
「こんな朝早く……」
舌打ちをしながら、スマホを耳に当て、「はい」とぶっきら棒な声で出た。
「おはよう。寝ちょったや? ごめんね、朝早くに」
遠慮がちな母の声が向こうから聞こえる。いったいこんな時間に電話をかけてくるなんてどんな用件なんだ。布団にくるまりながら「うん。なんや」と短く答えた。
「大輝が見つかったとよ」
母が一呼吸置いて静かに放った言葉に僕は仰天した
「え!?」
一気に眠気が吹っ飛び、布団から飛び起きて、横で妻と子どもが寝ているのも構わず受話器に向かって大声で叫んだ。
「どこおったとや!」
母は口ごもりながら、残念そうな声で言った。
「ダメやったとよ……」
その言葉の意味が分からず、「ダメやった?」と聞き返した。
「山ん中で死んじょったとよ」
震える母の声。
「え? え? え?」
頭の中がパニックの洪水に流されて言葉が出てこない。なんだ、これは悪い夢か。冗談なのか。歯がガタガタと震え、しばらく呆然と布団の上で突っ立っていた。
そこまでは鮮明に覚えているのに、その後母と何を話したのか、どんなふうに電話を切ったのかまるで思い出せない。ただ、ズシリと重くて寂しい何かが僕の心の中をいっぱいにしたことだけは確かだった。
どうやら大輝は「自死」したらしかった。
僕は九州は宮崎市の新興住宅地に建つ中華料理屋の長男として生まれた。若くして結婚した両親は子どもを切望していたが、なかなか授かることができなかった。夫婦生活も五年目に入ろうとしていた頃、ようやく身ごもったのが僕だった。父は妊娠の報を聞いた時、「バンザーイ、バンザーイ」とその喜びを目一杯表して外を走り回ったらしい。それくらい待望の子どもとして誕生を期待されていたが、へその緒を首にぐるぐるに巻きつけ、顔は窒息状態で紫色に変色し、産声も上げず、ぐったりして生まれてきた。仮死状態だった。
「車に轢かれたカエルみたいやった」と母が後年笑いながら教えてくれたことがあるが、その時は笑いごとではなかったろう。産婦人科医がへその緒を首から外し、顔やお尻を叩き続けて数分後、突如として息を吹き返し、この世に高らかに産声を上げたのだった。
虚弱な体質に生まれついたのか、病気ばかり繰り返す息子を連れて両親はあらゆる病院を巡る日々が続いたという。
一方でミルク代と病院代を稼ぐために、商売も頑張らなければならない。宮崎市郊外の借家を改造したカウンター席だけのボロっちい店を畳んだ両親は、銀行から融資を受けて、宮崎市街からほど近い当時造成中だった新興住宅地に新たに店を構えた。立地の良さが功を奏したことと、一九八〇年代前半という日本全体が好景気に沸いていた時代も追い風だったのだろう、いつしかお客さんが絶えない店へと成長し、両親は朝から晩まで働いた。母は病弱な息子をいつもおんぶ紐で背負って店の中を忙しく走り回り、出前にも出かけた。だから僕の一番古い記憶をたどると、両親の働く姿と油の匂いと炎と店内の騒々しさに行き着く。
そんな忙しない環境に生まれ育った僕にはもう一つの故郷があった。それは実家から車で二〇分ほどのところにある母方の祖父母の家だ。「国富町」という田畑に囲まれたのどかな田舎町にある祖父母の家に僕はしょっちゅう預けられ、幼少期のほとんどをそこで過ごした。つねにうるさくて慌ただしい雰囲気の実家とは違って、静かでゆったりした時間が流れる祖父母の家はオアシスのような場所だった。また祖父母にとって初孫ということもあったのだろう、目一杯の愛情を注いでくれた。今でも祖父母が僕の半分を作ってくれたと思っているし、親代わりをしてくれたことに感謝している。
そんな祖父母と母の弟、つまり叔父の家族が同居し始めたのはいつ頃だっただろうか。二世帯家族となった祖父母の家に行くと年の近いいとこ二人がいて、よく一緒に遊んだ。そして僕が一〇歳になった頃、もう一人のいとこが誕生した。それが大輝である。
「また男が生まれたとか!?」
僕を含めてすべて男の孫に囲まれて一〇年。祖母は五人目の孫は女の子がいいと密かに切望していたのだろう。大輝が誕生した時、うっかり口を滑らせてしまった。
その言葉を聞いた産婦人科の婦長さんが、「何を言うとね。この子が一番ばあちゃんのためになるとよ」と言ってなだめた。
その言葉を祖母はずっと覚えていたようで、ことあるごとに僕に「何であん時婦長さんはあんなこと言ったっちゃろうかね。あの婦長さんの言うとおりになったわい」と言った。
そして「言うとおりになった」というその言葉は真実だった。一、二歳くらいから祖父母の部屋で寝るようになった大輝は、小中高生になってからも寝起きも勉強も一日の大半をそこで過ごすようになっていた。実際、僕が祖父母の部屋を訪ねると、六畳一間の部屋に大輝の勉強机が鎮座し、祖父母と大輝がそこで共に生活していることはいつもの光景だった。祖父が亡くなってからも、祖母と大輝はそのまま同じ部屋で生活を送る日々が続いた。
やがて看護大学生になった大輝。それでも相変わらず二人の小さな日常は続いており、前にも増して祖母と大輝の結びつきは深くなった。もうこの頃には祖母にとって大輝は孫という存在を超えて、この世で最も大切な宝物だったに違いない。そして自分の存在価値そのものだったかもしれない。大輝も祖母の深い愛情に応える形で祖母を誰よりも大切に思い、手取り足取り助けた。
そんな折、三〇歳で写真家の道を志した僕は、誰に頼まれたわけでもないのに二人の日常を撮るようになった。そしてそれは祖母の死をもって終わりを迎えるはずだった。しかし、誰も予想だにしなかった展開で突如終わりを迎えた。
それは僕が写真家になって五年目のことだった。
ここから書くことは、思いもかけず写真という道に迷い込んでしまい、いつ溺れてもおかしくない状態で今ももがき続けている僕の一〇年間の出来事だ。
(プロローグ・了)
『しゃにむに写真家』刊行記念
オンラインイベントを開催!(全3回)
第1回目のゲストは、推薦文をお寄せくださった作家のいしいしんじさんです。
テーマは「撮ること・書くこと・生きること」。表現することを職業とするお二人に「写真家に〝なる〟・写真家に〝なる〟ってどういうこと?」を語っていただきます。

開催日時は2月18日(木)20:00~21:00です。
イベントの詳細、チケットの購入は「Peatix・亜紀書房ページ」まで。ぜひご参加ください!
試し読み 第2回「始まり」は2月10日(水)更新です。お楽しみに。