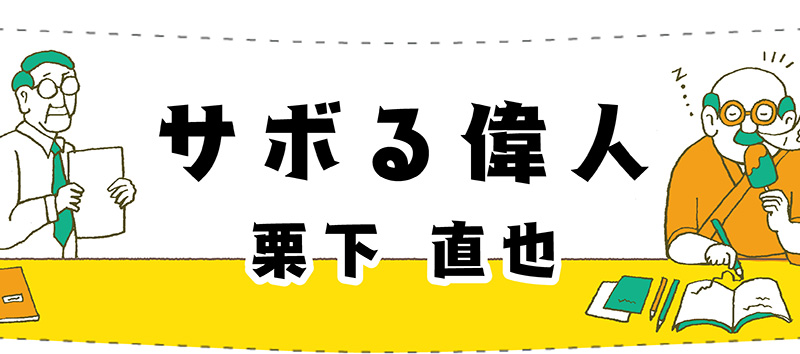「人間は中庸が肝心だ」とはよく聞く。確かに何事においてもやりすぎるのも、全くやらないのもよくない。だが、「中庸」とは何だろうか。
坂口安吾に「中庸」という短編小説がある。戦後日本の小さな村を舞台に、元海軍大佐で現村長が語り手となって展開する物語だ。
新任の女性小学校教師マリ子は、その現代的な考え方により村民から敵視される。村長は儒教的な「中庸」の精神で両者の調停をいくども試みるが、村民の嫌がらせは次第にエスカレートし、マリ子は下宿を追い出され、学校の宿直室での生活を余儀なくされる。
嫌がらせは止まらず、村民たちはマリ子の部屋の畳まで剝がす暴挙にまで及ぶ。しかし、マリ子は屈することなく、「畳に甘えるぐらいなら、恥辱に生きられやしない」と宣言し、藁に包まって土の上に直接寝ることを選ぶ。
村長は、マリ子の揺るぎない精神的強さと絶対的な誠実さを目の当たりにし、自らの「中庸」の哲学の限界を悟る。妥協と調和を重んじる自分のアプローチが、マリ子の価値感の前では無力であることを認識し、物語は「中庸に敗る」という村長の深い自覚で締めくくられる。
1953年に発表されたこの作品は、表面的には農村社会の閉鎖性を風刺しているが、より深層ではすべての状況において中立や妥協が最善とは限らないことを物語っている。形式的な中立は時として悪への加担となることを示し、本当の意味での均衡は、均衡を破る時を知ることであると教えてくれる。人間性は時として極端な状況でこそ輝きを放つのだ。
そもそも、「中庸」とは、「ほどほど」にということであるが、「ほどほど」を実現するには極端を知らなければいけない。極端を知ることでバランスが初めてとれるのである。
安吾は実際にこうしたメッセージを体現するような働き方をしていた。「サボる」とは対照的な生活を送っていた。
1946年に『堕落論』で注目を集めると、馬車馬のように働いた。戦前に売れない時期を味わっているだけに、「来るものは拒まず」の姿勢で依頼された原稿は媒体を問わず、書きまくった。1947年の1年間だけで、小説集8冊、評論集2冊、雑誌・新聞・座談会など長短70近い作品を発表している。1947年、48年の2年間では著書は30を数える。これは月に1冊以上であり尋常ではない。近年も、月に1、2冊出す著者がいるが、あれはすべてを自分で書いているわけではなく、ライターやら編集者やらがかなり手伝っており、安吾の異常さがわかる。
なぜ、安吾はそれほどまで書けたのか。
寝なかったのだ。3日いやときに5日は寝ずに書きまくって、一気に仕上げてしまっていた。「いやいやいや、3日寝ないなんて無理でしょ。5日なんてありえない」という声も聞こえてきそうだが、とにかく寝なかったのだ。むちゃくちゃ体力があれば可能かもと思う人もいるかもしれないが、安吾は1906年生まれで当時、アラフォー。徹夜が難しくなる年齢だ。それなのに完徹を4連続。まさに極端すぎる働き方だが、それを可能にしたのはヒロポンだ。覚せい剤だ。
安吾といえばヒロポンの代名詞にもなりつつあるが、安吾が何も法から外れていたわけではない。覚せい剤取締法が施行されたのは1951年。それまで規制はなく、薬局などで売られていた。戦前・戦中の雑誌には「ヒロポン錠 除倦覚醒剤」と広告が掲載され、「頭脳の明晰化 体力の亢進 疲労除去」など効能もうたわれていた。家事がはかどるからと一家そろってヒロポンを使用するなんて家もあったほどだ。
安吾はもともと体力には自信があったが、思考を集中持続させるために覚せい剤(最初はヒロポン、後にゼドリン)を常用した。不眠不休で仕事を続けるのだが、原稿を書き終えてもクスリが効きすぎて、気持ちが昂って眠れない。そこで、酒をぐでんぐでんになるまで飲み、そのまま眠っていた。実際、戦後の一時期は自宅の床の間にカストリのドラム缶を置いていた。当時は素人の密造酒として、どぶろくが流行った。ただ素人がつくって吞める代物ではない。これらを鍋にぶっ込んで沸騰させ、蒸発した液体をあつめてつくったのがカストリだ。
来客たちは、これを水で薄めて、勝手に吞んでいた。安吾はその隣の部屋で仕事をしていたが、集中するときには閉め切っていたため、執筆する姿を見た者はいなかった。写真家の林忠彦は、安吾に頼み込み、その姿をカメラにおさめた。安吾がシャツ姿で原稿用紙を広げ、カメラを見上げる有名な写真が記憶にある人は多いだろう。
ただ、クスリの量が増えると、酒を飲んでも寝付けなくなった。催眠剤のアドルムをつかうようになった。そして、通常ならば2、3錠も飲めば十分なアドルムを一日数十錠も飲む状態に陥るまで時間はかからなかった。
アドルム中毒の根っこにあるのは覚せい剤中毒だったが、覚せい剤を止めないのでアドルムも止められない。覚せい剤の量も増え、アドルムの量も増える。負の循環は止まらなくなる。
超人的な仕事量をこなすためにクスリを始めたのに、いつのまにか仕事に支障をきたすようになる。家から全裸で飛び出して丸太をもって暴れる。夜中に「今すぐに酒を買ってこい」とストップウオッチ片手に家人を恫喝する。2階から家財道具を階下に投げ飛ばす。そして、自分も2階の窓から飛び降りる。仕事どころではない。それでもクスリをやめられず、幻覚や幻聴が止まらなくなり、1949年2月、東大病院の神経科に入院する。
なぜ、そこまでひどくなったか。安吾はいつでもクスリをやめられると考えていたようだ。中毒になる人はいつの時代も変わらない。「俺だけは大丈夫」と思うのだ。安吾の場合、「注射ではなく錠剤だから大丈夫」「ウイスキーを飲めばヒロポン中毒にならない」と現代の我々からすると、「トンデモ科学ですか」「誰に教えてもらったんですか」など突っ込みどころが満載なのだが、突っ込みどころが満載の認識だからか、東大病院を退院して半年も経たずに、再び発作に襲われている。
安吾は名作も多いが、よくわからない作品も少なくない。登場人物が全く関わらないまま、突如、作中にあらわれなくなり、そのまま終わる謎の作品(「逃げたい心」)もある。こうした破綻は書きすぎたためか、クスリが原因かわからないが、クスリを乱用してまで量産したから、迷作も名作もうまれたといえるかもしれない。だが、やはり、周囲に迷惑をかけ(発狂して警察に保護されたこともある)、仕事もままならなくなれば、元も子もない。
安吾の軌跡は、現代の私たちに重要な示唆を与えてくれる。
確かに極端を知れば真のバランスは見えてくるかもしれない。しかし、安吾が身をもって証明したのは、極端に振れすぎる危険性でもあった。彼の超人的な仕事量は一時的には驚異的な成果を生んだが、仕事そのものを続けることすら困難にした。極端に振り切ったところから、うまく戻ってこられなくなった感もある。我々が学ぶべきは、安吾の創作への情熱ではなく、その破綻から得られる教訓だろう。
多くの社会人が求められるのは、安吾のような一瞬の輝きではない。継続的な価値であり、それを生み出し続けるためには持続可能な働き方が必要になる。適度に手を抜き、適度に休み、適度に挑戦する。この「適度」を見極める姿勢こそが、現代を生き抜く極意なのだ。
自分の限界を理解し、持続可能なペースを見つけ、長期的な視点で成果を積み重ねる。短期的な成功に目を奪われて健康や人間関係を犠牲にしない。そうした当たり前だが実は難しい行為の積み重ねの先に「中庸」は初めて見えてくる。そうなのだ。「中庸」を安吾は批判していたが、「中庸」の実践は現代ではかなり難しいことなのかもしれない。
今回の教え:「適度」を探して良き人生を。
バナーデザイン:藤田 泰実(SABOTENS)