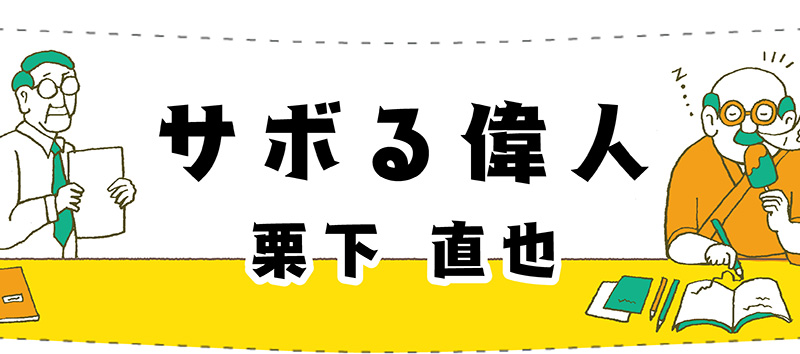娘が保育園のころ、「出家したい」といいだした。この子は出家の意味を果たしてわかっているのかと思いつつ、話していると、とにかく保育園が嫌なので、「保育園を中退して出家したい」と強く訴える。保育園児が自主的に保育園を中退できるのだろうか、なぜ、ひらがなも書けない子供が「中退」やら「出家」やら穏やかでないワードを放っているのだろうか。どこから突っ込んでいいかわからなかったのだが、当時、会社員だった私は「まあ、確かに、俺も会社辞めて、どこかに姿をくらましたくなるしな。せいぜい会社サボって夕方から飲むくらいしかできないけれども」と変に共感してしまったのだ。血は争えないのか。いや、親子でなくても多くの社会人は満員電車に揺られながら、会議に追われながら、「ああ、古の世捨て人みたいに、のんびり暮らせたらなあ」と一度は思ったことがあるはずだ。そんな願望があるからこそ、『徒然草』のような古典はいまなお輝くのだろう。出家して、徒然なるままに筆を走らす。かっこいいではないか。
『徒然草』の著者である兼好法師は鎌倉時代末期の生まれで本名は卜部兼好(うらべかねよし)。卜部家は京都の吉田神社の神官を代々司っていた官僚だ。官僚といっても今も当時もピンキリだが、卜部家は中流官僚だった。ただ、中流といっても兼好は天皇の秘書のような仕事を務めており、学問にも芸能にも詳しかった。インテリだ。収入もそこそこあり、一説によると、兼好が出家した30歳ごろに年収1400万円くらいはもらっていたというから、そこらの超大手企業のエリートサラリーマンではかなわない。
それなのに、そんな好待遇を投げ捨ててまで、世捨て人になってしまう。なんで?と誰もが思うだろうが、理由はあまり定かではない。何となく嫌になってしまったのだ。「なんだか、家柄的にも先が見えてるしな……」と出家してしまう。ちなみに、出家といっても僧侶になったわけではなく、自由出家だ。別に仏門に正式に入る必要もない。極端な話、家にいても問題ない場合もある。それだと、家を出ていないのだが当時はそんな出家が一部で流行っていた。
出家した兼好は肩書に縛られなくなったので、より多くの身分の高い人たちと親交を結ぶようになる。学問や芸事には詳しかったので、重宝されたのだ。教養人としてのポジションを築く。
ただ、一方で問題があった。職についていなければ学問や芸能で食える時代ではない。学問や芸能に詳しい無職でしかない。でも、仕事は辞めてしまっている。いまでいうならば、やたら教養のあるフリーターである。
兼好は生年は定かではないが70歳くらいまで生きたとされている。出家したのが30歳ころなので40年間、何かしらの手段で生計を立てていたことになる。
官僚をやめて、まず、手を出したのが不動産投資だ。出家後まもなく、京都の山科に田地を購入し、そこで取れる年貢米を金に換えて貯蓄し、10年後に売却した。現代の「土地転がし」顔負けの手法である。こう聞くと、何だかかなり儲かっていそうだが、最初に投じた額は現代の貨幣価値で450万円程度だ。そして、毎年の年貢米は金に換えると約50万円の収入だった。50×9=450なので、9年で初期投資のもとをとり、10年目に売却したというわけだ。売却額は140万円で、この140万円が、「土地ころがし」の儲けになる。かなり、こじんまりした土地転がしである。
もちろん、これだけでは食えない。食えない兼好は有力者のラブレター代筆まで手掛けていた。この代筆の仕事は、確かにお金を稼ぐためでもあったが、それ以上に重要な意味があった。有力者のために働くことで、彼らとのつながりをつくる狙いがあった。一度信頼関係ができると、その有力者たちから文書作成や教養に関する様々な知的な仕事を任されるようになり、これらの仕事が安定した収入源となった。
何だか徒然草の印象が変わってくるのは私だけだろうか。硯に向かって書いていたのは他人のラブレターかよ、そんなもん徒然なるままに書いたらダメだろと突っ込みたくもなるが、生活はそれほどまでに楽でなかった。
兼好は友人に経済援助を求める歌まで詠んだこともある。
しかも、ただ「お金ください」と言うのではなく、歌の技巧を凝らして隠語で訴えた。
「よもすずし ねざめのかりほ たまくらも まそでもあきに へだてなきかぜ」
この歌は各句の最初の文字を縦に読むと「よねたまへ(米給へ)」、終わりの文字を下から読むと「ぜにもほし(銭も欲し)」になる。現代で言えばクラウドファンディングのようなものである。遊び心たっぷりとはいえ、米も銭も欲しいって、困窮し過ぎだろ。
何だか官僚をやめなくてもよかったのではと思えてくるが、いつの時代も自由であることは大変なのだ。特に昔はセーフティネットも皆無だ。現代なら、会社を辞めても失業保険があり、フリーランスになってもクラウドワークスで仕事を探せる。ミニマリストになりたければ、YouTubeで「断捨離チャンネル」でも開設すれば広告収入も期待できる。だが、昔は全て自分の才覚と人脈に頼るしかなかった。元祖「サボりスト」たちの苦労は現代の比ではない。全く持って悠々自適ではない。彼らはサボりたかったのに、むしろ現代以上にハードに働かざるをえない皮肉な状態に陥っていたのだ。
だからだろう。苦労を重ねた兼好だからこそ、『徒然草』で語る言葉には重みがある。「一時の懈怠は一生の懈怠」という戒めも、安易にサボった結果を身をもって知っているからこそ説得力がある。
また「財多ければ身を守るにまどし」「金は山に捨て、宝は淵に投ぐべし」と金銭への執着を戒めているが、これは自分が一番お金に苦労したからこその言葉だろう。
「人の嘲りをも恥づべからず。万事にかへずしては、一の大事成るべからず」(人に笑われることを恥じてはいけない。全てを捨てなければ、本当に大切なことは成し遂げられない)という言葉も、実際に安定を捨てた体験談そのものである。
そんな厳しい環境で生き抜いた兼好だからこそ、兼好は後世に残る名作を生み出すことができたのかもしれない。
兼好が現代の私たちをみたら、きっとこう言うだろう。
「君たち、失業保険に健康保険、クラウドワークスにメルカリまであるじゃないか。こんな恵まれた環境で『リスクが』なんて言ってちゃダメだよ。でもね、覚悟だけはしっかり持って。サボって自由に生きるって、本当に大変なんだから」
***
『徒然草』と並び称される随筆といえば『方丈記』である。著者の鴨長明は現代人なら一度は憧れる隠遁生活を実践した先駆者でもある。生きた時代は兼好の百数十年前。「ゆく河の流れは絶えずして」の名文を残し、「究極のミニマリストとして悠々自適に暮らしていた」というイメージが強いかもしれないが、実際の彼の生活を詳しく見てみると兼好同様に自由に生きたはずなのにけっこうハードなのだ。
鴨長明は京都の下鴨神社という超名門の神職の家に生まれた。現代で言えば、老舗企業の御曹司として生まれたようなものだ。7歳で五位という高い位を授けられ、将来は父の跡を継いで神社の責任者になることが約束されていた。だが、長明は知らなかった。社会的地位ではこのときがピークだったとは。
20歳のころ、父が亡くなると事態は急変する。長明の出世の目を親族につぶされてしまったのだ。現代で言えば、同族会社の跡継ぎ争いに敗れて、何代か先の社長の座を奪われたようなものだ。しかも、その後も嫌がらせは続く。
長明が歌合わせで鴨川を「蟬の小川」と表現した革新的な歌を詠むと、親族がこれに激怒。「うちの川を蟬呼ばわりするとは何事か!」と難癖をつけられる。この歌は後に『千載和歌集』に選ばれるほどの名作だったのだが、当時は完全に無視されてしまった。
決定的だったのは、就職を潰されたことだ。歌の才能があった長明は後鳥羽院のおぼえがめでたかった。フラフラとしている長明にそれなりのポジションを与えようとしたが、これをまたもや親族が全力でブロックする。後鳥羽院が与えようとしたのは下鴨神社と関係が深い河合社の神職。このポジションに就くと自動的に将来、下鴨神社の神職に就くことが約束されていたからだ。自分の直系で牛耳りたい一派にしてみれば、いまさら長明がノコノコ割り込んでくるなんて到底受け入れることはできない。「それだけは勘弁してください。あいつ、マジで働いていませんから、神職なんて務まりません」と直訴し、後鳥羽院も確かに、あいつ、和歌ばっか詠んでるよなと思ったかどうかは知らないが、長明の河合社への推挙を諦める。で、それを聞いた長明は「やってられるか!」とブチ切れる。確かに後鳥羽院のプッシュがあって、成立しない人事ってなんだよって話だろう。後鳥羽院は長明に他のポジションを用意したが、世俗に見切りをつけ、出家する。
ちなみに、このころ長明は50歳前後だ。当時としてはかなりの年寄りだ。もう破れかぶれになってもおかしくない。
長明は30歳くらいまでは妻子がいるのにもかかわらず祖母の大豪邸でニートのような生活を送っていたが、妻子と別れ、祖母の家を追い出される。鴨川のほとりに家を建てて暮らし、自分の好きな和歌と琵琶に没頭する。結局、ボンボンのニートだからあまり危機感がない。ただ、才能はあったのだろう。宮中で認められ、和歌所の専門職として採用される。といっても、そのころ、すでに40代半ばだ。40代半ばにして初めての就職だ。実家太すぎだろ。
役職は低かったが、よく働いた。新古今和歌集の編纂にも携わった。その上、一度はあきらめた、幼いころから希望していたポスト(河合社の神職)に就けるかもしれない。後鳥羽院も推してくれている。なんだか運が向いてきたぞとウキウキしていたら、またもや一族の邪魔が入ったのだ。そりゃ、「もう、やってられない」となるのもわかる。
ただ、出家したものの、もともと出家していたような人生である。その上、出家から5年は大原あたりにいたが、人の往来も少ないわけでなく、あまり出家感がない。やっていることもあまりかわらない。大原で、何をしていたかはわかっていないが、とりあえず5年経って日野という山奥への移住を決意する。
有名なのがそこでの住まいだ。祖母の豪邸の1000分の1、祖母の家を出た後に住んだ鴨川のほとりの家と比べても100分の1の大きさだ。それもそのはずだ。現代の感覚で言えば、4畳半よりも狭い。一丈四方、つまり約2.7メートル四方の小屋である。これが有名な方丈庵であり、長明がミニマリストの元祖といわれる所以である。
長明は世俗の欲望に執着しないために山にこもったのだが、別にこもりきっていたわけではない。交流は続いていた。山奥に引っ込んでも、山を下るどころか鎌倉にまで足を運び、時の将軍、源実朝にも会っている。和歌の職を得ようとしたのである。めちゃくちゃ世俗的だ。そもそも山にこもって『方丈記』をはじめとして執筆活動もしている。
山にこもっても俗世間と関係を断つこともできない上に、新たな執着も見つけてしまう。自分の庵に愛着を感じてしまったのだ。
『方丈記』の最後で、長明は正直に告白している。「草庵を愛するのは、また執着ではないか」「私は聖ではなく、遁世者でもない。むしろ隠者、つまり俗っぽい美学者に過ぎない」
持ち物を整理したら、今度は「何も持たない自分」に執着してしまったのだ。不便な生活を続けておいて、「実は俺、修行のふりしてただけかも」という自己分析に至ったのだ。現代でも「会社辞めて田舎暮らし」や「ミニマリスト生活」に憧れる人は多いが、長明の体験は重要な教訓を与えてくれる。どこに行っても結局は自分であり、環境を変えても内面の問題は解決しない。むしろ、新しい環境が新しい問題を生むことも多い。サボるために環境を変えても、そこには何か違った悩みが生まれるかもしれない。
今回の教え:いつの時代も「鴨の水かき」
バナーデザイン:藤田 泰実(SABOTENS)