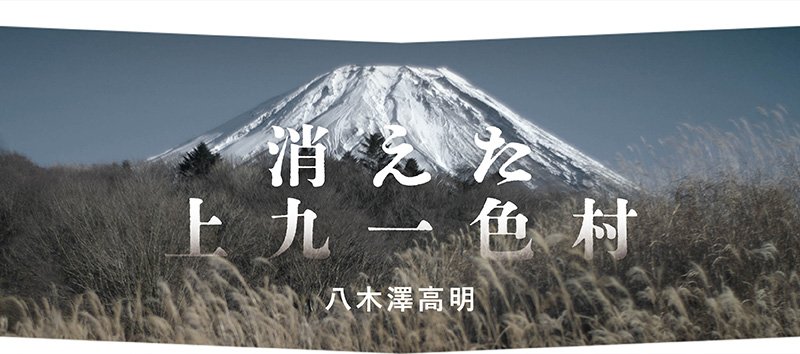オウム真理教が一大拠点を築いた上九一色村。北は山梨県甲府市、南は静岡県富士宮市に接する、縦に長い村だ。面積は86・59平方キロメートルあり、現在の千葉県船橋市や奈良県天理市よりも若干広い。
しかし平成18(2006)年、同村北部の古関(ふるせき)と梯(かけはし)の区域が甲府市へ、それより南側に位置する精進、本栖、富士ヶ嶺の区域は南都留郡富士河口湖町にそれぞれ編入された。したがって、上九一色という村はもうこの世に存在していない。
御坂(みさか)山地が事実上の境界線となり、行政面においても長らく南北で公的機関が別々に置かれてきた歴史がある。また、住民たちの経済活動も北部は甲府寄り、南部は富士宮寄りだったことなどが編入の主な理由とされている。
上九一色村は、古くからの歴史を有する村だ。富士山の北側(河口湖から本栖湖にかけて)に広がる御坂山地。その峰々に囲まれた谷には、遠く駿河湾へ注ぐ富士川の支流である清流、芦川(あしがわ)が流れている。その川筋に沿ってできた集落は、かつて「工一色村」と呼ばれた。
山深いこの集落には、農耕具づくりや木材加工などを生業とする人々が多く暮らした。そこで職人を意味する「工(たくみ)」が「一色(ひといろ)」に見えるほど集まって暮らしている、という意味合いから工一色と名づいたとも、手工芸品を年貢として納めていたからともいわれる。
農民ではなく職人が多かったという事実が、この村の歴史を端的に決定づけることになった。夏でも冷涼な山間部に位置するため、農業には不向きな土地だったのだ。さらには、甲府と駿河を南北に結ぶ中道往還(なかみちおうかん)のおかげで古来より人の行き来が絶えることなく、旅人を相手にした商売はもちろん、駿河湾で上がった海産物を村人自身が海のない甲州へ運ぶなど、商いに積極的に関わることになった。もしこの街道が通っていなかったら、村の歴史はまたちがったものとなっただろう。
中道往還は古代から連綿と使いならされてきた街道だ。それが証拠に、山梨の古代文化発祥の地といわれ、弥生時代後期から古墳時代にかけての遺跡が多く分布する甲府盆地南部の曽根丘陵から、中道往還を通じて東海地方から文化がもたらされたことを示す埋葬物などが見つかっている。甲府盆地と東海地方を結ぶ大動脈の役割を果たしていたのだ。
近代になるまで街道としての重要性は変わらず、中世から戦国時代になると、甲斐国を支配した武田氏はここに関所を設けた。今も地名に残る古関がそれだ。すなわち中道往還は軍用道路としての役割を担ったのだ。
工一色一帯は、武田氏の治世に「九一色郷」とされた。工一色に九つの集落が存在したのが由来という説もある。武田氏はこの地域に九一色衆という武士団を置き、街道の警護や甲府盆地への敵侵入の防御に当たらせた。当地の土豪や百姓などが主な構成員だった。街道筋には、城や狼煙台なども築かれた。
織田信長による甲州攻めのために徳川家康が街道を整備したのち、天正10(1582)年に武田氏を討伐した信長は駿河を経て安土へ帰る際、中道往還から富士山を眺めたという。
その後、戦(いくさ)のない時代が訪れると、軍用道路としてではなく、生活物資を運ぶ道として利用されるようになる。駿河で水揚げされた海産物や塩などの輸送に活用されたのだ。甲州名物に「鮑(あわび)の煮貝」があるが、醬油漬けされた鮑が甲府へと運ばれたのが、まさにこの中道往還だった。
武田氏の時代から、山間部のため耕地が少ないこと、また交通の要衝であったことを理由に、九一色郷の村人たちは「諸商売役免許」の朱印状を下付されていたが、のちに甲斐を治めた徳川家康氏もそれを踏襲した。おかげで諸国の関所を無税で通過できるようになり、隣国ばかりでなく関東各地まで出向き、商売する者も少なくなかった。
武田氏や徳川氏がそれほどに重要視したのがこの地域だったのだ。
しかし明治時代に入ると、生活物資の輸送を担う役割は身延線などの鉄道に取って代わり、長いあいだ南北を結ぶ唯一の街道だった中道往還は廃れてゆく。
明治7(1874)年、九一色郷は「九一色村」となり、明治22(1889)年の町村制施行で「上九一色村」と「下九一色村」の二村に分割された。下九一色村は、上九一色村から見て北西部に付帯した地域(現・市川三郷町および南巨摩郡身延町)で、芦川溪谷に沿った山間部だった(1954年に廃村)。その上九一色村の最南部にある地域こそ、オウム真理教が拠点を置いた富士ヶ嶺地区であった。
*
富士ヶ嶺地区は、古代からの連綿たる歴史を経た上九一色村の中にあって、もっとも歴史の浅い地区だ。富士ヶ嶺という名前がつけられたのは昭和32(1957)年のこと。原野に覆われていた富士ヶ嶺にまとまった数の人々が暮らしはじめたのは、終戦直後の昭和20(1945)年に満州から帰国してきた開拓団が入植してからのことであった。
富士ヶ嶺はその歴史の希薄さゆえに、古来から地縁血縁で結ばれた上九一色村の他の地区とはちがい、よそ者であるオウム真理教が付け入る隙が多分にあったのかもしれない。
既述のとおり上九一色村には、古代より駿河から中道往還を伝って人や物の伝播・交流があった。奇しくも、駿河の富士宮市に本部を置いたオウム真理教も北進して甲斐・上九一色村へとやってきたわけだが、その意味合いの大きな落差には歴史の無常を思うほかない。
上九一色村が分割・編入となり、歴史ある古関などの地区は甲府市へ、富士ヶ嶺や本栖など南部の地区は富士河口湖町となったのは冒頭で触れたとおりだ。村名が消えてしまったこと、村が分かれてしまったことには、経済圏の分断なども影響しただろうが、1990年代のオウム事件の影響も、また少なくなかったのではないかと思う。
戦後、国策開拓で開かれた新興地域である富士ヶ嶺が、上九一色村を代表するような存在となってしまったのだ。上九一色村といえば古来より、古関などがその名を代表する土地だったはず。しかし、おそらくあの事件以降、大多数の人にとって上九一色村のイメージは、オウムのサティアンがいくつも建てられた富士ヶ嶺地区の景色に変わってしまった。
満州開拓義勇軍として戦時中を満州で過ごし、戦後シベリアに抑留され、帰国後に富士ヶ嶺の開拓に携わった竹内精一さんに、私はもう一度、上九一色村での当時の話をうかがった。
「シベリアから帰ってきて、最初ここを見たときにはびっくりしたよね。小さな掘っ立て小屋があるだけだったから。それこそシベリアや満州より大変なとこに来ちゃったなと。前にも言ったけど、まず水がないんだから風呂にも入れない。遠くから汲んできた水は、飲み水や料理のためにしか使えないから。風呂に入れるのは雨が降ったときだけ」
風雨が容赦なく吹き込んでくる家に住み、一日何往復も川での水汲みを続けて荒地を畑に変える作業。聞いているだけで過酷さが身に迫る。
では、竹内さんが富士ヶ嶺の開拓に加わるきっかけは何だったのか。
「鳴沢に帰ってくると、ひと足先に父親が開拓に応募していたんですよ。鳴沢で父親は土建屋をやっていたけど、土地は一坪も持っていなかった。開拓をすれば自分の土地が持てるし、可能性を感じたんでしょうね。私もほかに仕事があったわけじゃないから開拓に応募したんです」
それと同時に、所帯を持ったほうがいいという周囲の勧めもあり、竹内さんは同じ鳴沢村出身で8歳年下の勝子さんと結婚した。勝子さんの実家でも貧しい暮らしを強いられていたという。
「今は観光が盛んな土地になりましたけど、鳴沢は米が採れない村でしたからね。あのころ山梨で貧しいのは道志、秋山、丹波、小菅といわれましたけど、鳴沢も同じです。蕎麦、粟、モロコシ、麦を育てて、あとは養蚕ですね。米は結婚式、正月、お葬式のときに食べられたらいいぐらいで」
そんな勝子さんだったが、嫁いだ先の富士ヶ嶺での生活はさらにひどいものだったという。
「あばら家でしたからね。風が抜けるのも驚きましたけど、冬のひどく寒い日に、朝起きたら布団の上に雪が積もっていたのにはびっくりしました」
 竹内さんが開拓時に建て改築を経た母屋(現在は写真奥の住居に暮らす)
竹内さんが開拓時に建て改築を経た母屋(現在は写真奥の住居に暮らす)
開拓の苦労話は今でこそ笑い話だが、当時は日々を生き抜くのに精一杯だったと竹内さんは言う。雑穀で食料を自給することはできたが、現金収入を得るためには、屋根にも葺(ふ)いていた萱(かや)に頼った。
「萱を使って、炭を束ねる炭俵を編むんですよ。日中は開墾をしなければならないので、夜になると子どもや女性が炭俵を編んだ。それを翌日、本栖にあった配給所に子どもたちが持っていって現金に換えるんです」
苦しい開墾の日々を癒してくれた存在のひとつが、地区の名前にもなっている富士山だったという。
「大陸もスケールの大きな土地だったですけど、やっぱり富士山のあの形というのは優美ですよね。子どものころは毎日のように見ていて何とも思いませんでしたけど、一度外に出てからあらためて見ると、故郷の山であり、美しい山ですよ。ここから見える富士山は本当に綺麗で、心が落ち着くんです」
昭和22(1947)年からはじまった原野の開拓は、ゆっくりとではあったが着実に、富士ヶ嶺を人が暮らせる土地へと変えはじめたのだった。

(第3回・了)
本連載は、基本的に隔週更新です。
次回:2025年4月14日(月)予定