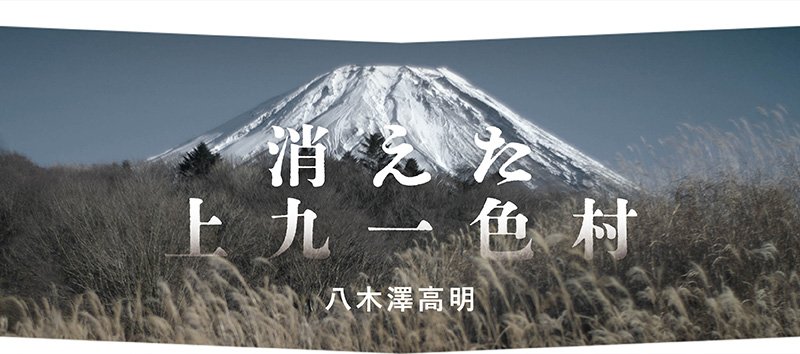上九一色村には古代から連綿と続いてきた人々の営みがあった。
しかし、その南部一帯に当たる富士ヶ嶺地区は、人間の営みという点でいえば非常に濃度の希薄な土地だった。開拓以前、地区の大部分は原野であり、人煙はまれで、わずかに暮らしていたのは山仕事を生業としている人々ぐらいのものだったからだ。
その後、昭和11(1936)年に富士ヶ嶺から東へ十数キロメートルほどの山麓一帯が日本陸軍の軍用地となった。敷地面積は2000へクタール(東京ドーム400個分以上)におよび、現在の富士吉田市と南都留郡山中湖村にまたがっていた。終戦まで、この北富士演習場は各部隊の訓練や戦車の演習などのために利用され、戦後すぐ米軍により接収されキャンプ・マックネアと改称した。
今も富士山の周辺にはこの北富士演習場や東富士演習場(静岡県)などがあり、日米地位協定に基づいて米軍と自衛隊が実弾射撃などの演習を行なっている。広大な富士山麓は、軍事演習にはうってつけの土地なのだ。もし、あのとき国策で開拓地として利用されなければ、富士ヶ嶺地区も拡大演習場となっていた可能性は高いだろう。
昭和20(1945)年に決まった上九一色村富士ヶ嶺地区における開拓事業は、昭和21(1946)年にGHQの許可が降りたことで、ついに正式に動き出した。
しかし、のちに詳しく触れるが、じつは開拓が始動してから5年後には、富士ヶ嶺地区から立ち退くように、という要請が米軍側から出されている。米軍は現在の東富士、北富士両演習場だけでなく、青木ヶ原を含めた一帯を基地として利用しようとしていたのだ。
その思惑は、地区の人々の総反対によって退けられた。彼らが土地から立ち退かなかった背景には、荒地を一から耕してきたという思いの強さがあったはずだ。
開拓団の人々がこの土地との繋がりを深めた時代について、竹内さんに話を聞いた。
入植した当時、地区は一面葦(よし)の原っぱだったという。
「葦を刈って、石をどけるところからがはじまりですよ。それからアワ、ヒエ、トウモロコシ、大根などを植えましたね」
山間部の土地では蕎麦というイメージがあるが、富士ヶ嶺地区では蕎麦すら育てることができなかったという。
「蕎麦ができる土地というのは、褒められた土壌じゃないからね。ここでも当然、最初は植えたんですよ。でもね、できなかったんです。ここらは、大きな木もあんまりないでしょう。風が強い土地なんです。植えてもね、せっかく成った実が風で持っていかれちゃう。蕎麦には、春蕎麦と秋蕎麦というのがあって、春蕎麦は少しばかりできた。その時季は風があんまり強く吹かないから。だけど春蕎麦は、美味しくないんだ。本当は秋蕎麦を育てたいんだけど、そのころは風が強い。台風も来ますからね。さえぎるものがないから風が半端じゃないんです。蕎麦は二作できて、50日で収穫できるから、昔から飢饉にも強い作物ですよ。採れたらよかったんだけど、ここには向かなかった」
その代わりにトウモロコシ、大根などが盛んに育てられるようになった。
「トウモロコシは4カ月ぐらいかかって、秋が深まる前に収穫できますし、大根はそもそも土の中ですから風の影響もないしね。ここではいい大根ができたんですよ」
竹内さんが大根の話題を出したこともあって、「そんなら、たいしたものではないですけど」と謙遜しながら奥さんの勝子さんが台所に向かい、大根の煮付けを出してくれた。醬油と砂糖でしっかりと煮付けられた大根は、箸をすっと通した。口に運ぶと、しっかりと染み込んだ味が口に広がり、肉身はほろほろ溶けてなくなった。
大根を食べる私を眺めながら、竹内さんがしみじみと言った。
「この大根がまずは有名になったんですよ。富士ヶ嶺だけじゃなくて、鳴沢村だって、本栖湖の周辺だって、米が採れないから貧しい土地だった。富士ヶ嶺は大根のおかげで、まずは現金収入が得られるようになったんです。東京や名古屋で味が認められて、出荷できるようになりました」
富士ヶ嶺地区の大根は豊茂(とよしげ)大根と呼ばれ、味の良さだけでなく、他の産地より少し早く出荷できたこともあり、一大ブランドとなった。昭和27(1952)年には地区内にたくわん工場を建て、大阪や東京方面に出荷した。そのたくわんは全国たくわん品評会で最優秀賞を受賞し、農林大臣表彰を受けるほどだった。
野菜が少しずつ都会の人々から注目されるようになった一方で、富士ヶ嶺地区での生活は相変わらず都会とは隔絶されたものだった。
「いちばん苦労したのは、水ですよね。その問題を解決する必要がありました。水がある場所まで一時間半歩かないといけなかったんです。背負子にのせた18リットルの醬油樽を背負ってね。汲んできた水は天水槽(てんすいおけ)に溜めておくんです。冬は、雪上げをするんですけど、その雪を溶かして飲み水にしました。屋根から雪を下ろすことを雪下ろし、家のまわりに積もった雪をかき上げてどかすのを雪上げというんです。天水槽の水は、暖かい季節になるとボウフラが湧いたりするんですけど、そんなのを気にしてたら飲み水がないわけですから、ポカンと水面を叩いてボウフラを沈めてから、すくった水を飲むんです。飲み水には苦労する土地だったけど、大雨が降ろうものならこんどは道が川になっちゃうしね。水がないところなのに水害があるんだ。昭和24(1949)年のキティ台風のときには、50戸の家が潰れて牛が流された。とにかく、水に困らされた土地だったね」
竹内さんは開拓団の一員として、水に難儀しながらも畑を作り、少しずつ生活を安定させていった。その後、生活の基盤となったのは酪農だった。
富士ヶ嶺地区だけでなく、全国で酪農が広まったのは戦後のことだ。日本における酪農の歴史はじつは古く、起源をたどれば奈良時代に遡るといわれるが、生業として多くの農家が関わっていたわけではない。
一般的な酪農が盛んになったきっかけは、戦後学校給食で牛乳などの乳製品が出されるようになり、日本人の食卓が欧米化したことにあった。
昭和29(1954)年、政府は酪農振興法を公布し、集約酪農地域の制定を行うなど酪農の発展を後押しした。富士ヶ嶺地区はその7年後に、政府から酪農主産地の指定を受けた。
世の中の流れや国からの援助もあり、富士ヶ嶺地区における酪農はスタートした。牛を飼うのに適した冷涼な気候だけでなく、広大な原野を牧草地に転換できたことも奏功した。標高900~1255メートルと高低差があり、夏は35度、冬はマイナス15度に達することもある土地だが、冬の寒さは厳しいものの、夏は高原らしく湿度も低いため、牛たちにとっても過ごしやすいのだろう。
乳牛を飼育する者は生乳を売ることにより、現金収入を得る道を切り開くことができた。竹内さんも肉牛の飼育を始め、大根づくりだけではまかなえない安定した現金収入を得ることができるようになった。
昭和32(1957)年になって富士ヶ嶺地区にようやく電気が通ったことはすでに述べたが、その立役者のひとりが竹内さんだった。当時農協の組合長だった竹内さんは、何度も東京へ足を運び、東京電力などと交渉を重ねた。その甲斐あって、晴れて村に電気が通るようになった。
「電気がはじめて来た日、灯りの眩しかったことは忘れられないね」と竹内さんは言う。
次に地区での生活で必要だったのは、水道を通すことだった。
地区では、地下水脈を探るボーリング調査を何度か行なっていたが、芳しい結果は得られなかった。最後の手段は、本栖湖から水を汲み上げることだった。竹内さんは、十数回にわたって資料などを携え農林省に陳情を重ねた。その結果、本栖湖からの揚水が認められることになり、紆余曲折の末、昭和39(1964)年に水道が開通したのだった。
日本が高度成長期に突入し、経済白書に「もはや戦後ではない」という言葉が綴られてから8年が経っていた。遅まきながら富士ヶ嶺地区でも公共のインフラが少しずつ整備されはじめ、人々の暮らしは開拓時代から確実に変化してきた。
上九一色村にこの変化をもたらしたものは何だったのか。
国としての経済発展だけが唯一の理由だとは、私にはどうしても思えない。文字どおり裸一貫で満州から引き揚げてきた地縁もない人々が、葦や茅の群生地を切り払い、硬質な溶岩地帯をみずからの手で切り拓いてきた。そこで手に入れたわずかな畑を耕し、牧草地を拓き、牛を育て、県内随一の酪農地を築き上げた。
これこそ、開拓団の一人ひとりがくじけず、真摯に土地と向かい合い、たゆまず積み重ねてきた成果に他ならないのではないだろうか。
*
そしてオウム真理教が村に入り込む前、上九一色村には、じつはもうひとつの大きな危機が迫っていた。それは、米軍による大規模な土地接収計画だった。
(第4回・了)
本連載は、基本的に隔週更新です。