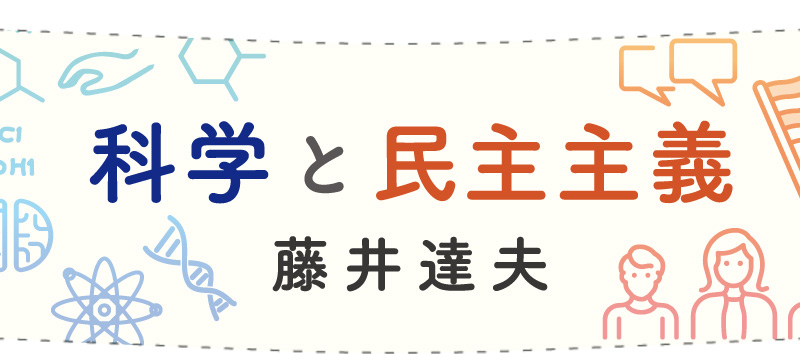民主主義からのエリートと大衆の離反
ようやく、代表制民主主義の現状にたどり着いた。現代の観察者たちが指摘するところでは、民主主義は二方向から発する危機に直面している。一つは社会の上層、すなわち、エリートに由来する危機だ。その危機は、リンドの言葉を借りれば、現代のエリート層を構成するインサイダーのマネージャーたち、すなわち、「国内の大手企業や多国籍企業、政府機関、非営利団体運営する民間と公的機関の官僚である」[1]、高学歴の専門技術者たちが民主主義から撤退しつつあるという危機である。もう一つは、社会の下層から発せられる危機だ。工業化社会からポスト工業会社会へ転換する中で、政治・経済・文化の領域から締め出され、アウトサイダーとなった労働者を支持基盤とするポピュリスト政治家が民主主義を横領しつつあるという危機である。
おそらく、民主主義の現状に対するこの指摘は、正しいといえるだろう。冷戦期の二〇世紀中葉から現代まで民主主義を標榜してきた多くの国々において、程度の差こそあれ、この危機を確認することができる[2]。
民主主義諸国でこの危機が生じた背景については、すでに論じた。工業化社会からポスト工業化への転換を通して、代表制民主主義が機能するために不可欠な社会的・経済的・文化的な条件が消失したというのがその背景だ。この下で、例えば、代表制度のエリート主義的な性格を薄める際に決定的な役割を果たした大衆政党は弱体化していった。これが意味するのは、代表制度を民主主義に縛り付けておくための重要な足枷の一つがなくなってしまったということだ。しかし、この二方向からの危機を十全に理解するには、さらに別の視点からの説明が必要だ。それは、新自由主義の秩序の時代に進んだグローバル化という視点である。
代表制民主主義からのエリートの離脱を推し進めたのはグローバル化であり、その出発点となったのは冷戦の終結である。ボーダーレスでグローバルな自由市場の構築は、新自由主義のかねてからの夢であった[3]。それを実現可能にした歴史的な事件が一九九一年のソ連の崩壊による冷戦の終焉であった。当時のエリートたちにとって、この終焉が意味したことの一つは、一九四五年以来、自分たちの権力の行使に制約を課し、社会の多数派に対する譲歩を強いてきたライバルが退場したということであった。すでに指摘したように、第二次世界大戦後の西側諸国において、多数派の労働者の政治的あるいは経済的要求に対して当時のエリートたちを譲歩させたのは、ソ連を中心とする東側の社会主義諸国ならびに共産主義というイデオロギーの存在であった。こうした存在のおかげで、資本主義を守るための労使和解体制が確立され、ケインズ主義の秩序の安定がもたらされた。
冷戦の終結によるいわゆる「歴史の終焉」は、エリートたちを共産主義の亡霊から解放した。その結果、エリートたちの自制は弱められることになった。もはや新自由主義の秩序を担うエリートたちにとっての懸念は、不安定な雇用によって自国の労働者が強いられている苦境にはない。また、民主主義的な意思決定手続きの順守による統治の正統性にもない。主権国家による規制を逃れた超国家的機関の設立とそこでの民主主義的な手続きなしでの世界秩序の構築こそ、彼らの関心となった。民主主義からのエリートの撤退はこのようにして進んでいった。
エリートが民主主義から離反していく一方で、かつて大衆と呼ばれた普通の労働者たちの間で広がっていったのが、民主主義に対する失望や不信であった。
そもそも、民主主義を嫌悪し「根絶やし」にしようとしてきたのは、それがいつの時代であろうと、エリートたちだ[4]。その始まりは、プラトンにある。『国家』におけるプラトンの古代の民主主義批判は、現代のエリートたちの民主主義批判におけるプロトタイプといえる。それもそのはずだ。いつの時代であろうと、西洋のエリートたちはプラトンの私怨に満ちた民主主義批判を読んで「エリート」となってきたからだ。この意味で、現代のエリートが民主主義を憎悪し、離反しようとすることに何ら驚きはない。
驚くべきは、二〇世紀に代表制民主主義という制度の内部で政治権力を獲得することができるようになった大衆が、民主主義に見切りをつけようとする情勢であろう。この情勢は政府や政治家、政党に対する不信として表出されてきた。アメリカをはじめ、ヨーロッパの民主主義諸国、そして日本において、政治不信が増大している傾向を明示する指標については事欠かない。民主主義からの疎外が深刻化しているわけだ。これまで述べてきたように、この傾向は、ポスト工業化の時代において選挙を基盤にした代表制度が機能不全を来たしている点から理解されねばならない[5]。しかし、そうした理解に加えて、エリートたちが民主主義から離反し始めたのと同じ要因がそこにあることを押さえておく必要もある。それが、グローバル化という要因なのである。
国際機関やグリーバル企業による新しい秩序
冷戦の終結後、急速に進んだグローバル化によって、世界貿易機関(WTO)や東南アジア諸国連合(ASEAN)といった国際機関、あるいはヨーロッパ連合(EU)などの超国家機関が誕生した。これらは、当初、新しい時代における国際秩序の新たな枠組みになると期待された。しかし、よくよく考えるなら、主権国家にとっては、この新たな枠組みは必ずしも、手放しで歓迎されるものではなかった。というのは、それは国家の主権を制約し、その自立性を侵害する可能性があったからだ。この事態は、主権国家の内部で作動し、その国民を構成員とする現代の代表制民主主義に対して少なからぬ影響を及ぼすことになった。その影響の一つは、国民が政治からいっそう疎外されるという形で現れる。
グローバル化によって引き起こされる疎外は、特に政府と国民との関係において確認することができる。一般に現代の民主主義諸国において、民主的な選挙によって設立された政府の権威は、国民に由来すると考えられており、また、その権力は国民の利益のために行使されると想定されている。しかしながら、冷戦後のグローバル化の中で、国際機関を媒介にした多国家間関係への依存が高まると、こうした想定には疑念が向けられやすくなる。一国家の政府の自立性がこの依存関係の高まりの中で制限される結果、国家内部の代表制度の下で行われた民主的な意思決定は、他国との交渉において妥協を強いられ、変更を余儀なくされる場合が出てくるからだ。国内の有権者の多数の目には、この状況が政府の政治エリートたちが国民の利益よりも、他国やグローバル企業の利益を優先している光景として映りうる。こうして、民主主義からの疎外が進み、不信はますます募ることになる。
すでに言及したように、二〇世紀の代表制民主主義の黄金期の要は大衆政党であった。それは、経営者団体や労働組合などの諸組織を媒介にして社会に根を張ることで有権者を政治に結び付けるという、極めて重要な役割を果たしてきた。しかし、ポスト工業化への転換の中で、そうした大衆政党は党名を変えることがなくても、その内実を大きく変えることになった。政党が社会との結びつきを弱め、有権者から疎遠になるに伴い、有権者は自分の利益を代表してくる政党がどれなのかもはや見当がつかなくなっていく。つまり、議会の中に自分たちの代表者を見出すことができなくなっていくのだ。こうした中、有権者にとっての投票の手掛かりは、政党ではなく、政権を担うリーダーとしての政治家へと移り変わっていった。有権者は、政党が掲げる綱領でも公約でもなく、政権を目指す各党のリーダーのイメージや個性を手掛かりに投票するようになる。選挙戦の勝敗は、政策ではなく、党の顔となった政治家のイメージ次第となるわけだ。そうなれば、政党が、選挙に勝利した暁に政府の首長となる自党のリーダーに従属するようになるのも、程度の差こそあれ、必然だ。こうして、マナンが指摘したように、代表制民主主義は「政党民主主義」から「観衆民主主義」へと移行していった[6]。
民主主義の観衆化は、業界団体などの一部の利益集団との結びつきを強める既成政党から選挙時以外は見向きもされない一般の有権者が、代表制度の下で民主主義を何とか維持しようとする試みの帰結とも解釈できる。かつて「大衆政党」と呼ばれた政党は、今では一般の有権者に背を向け、社会を構成する多数派の利害関心や意思を政治に伝達する役割を放棄しつつある。そうであるから、見放された有権者は、政党ではなく、政治家一個人に主権者としての意思を託そうとする。こうして、投票所に足を運ぶ有権者は、政治リーダーのイメージや個性を頼りに、投票するようになるのだ[7]。
しかしながら、グローバル化は「観衆」となった有権者までも翻弄する。というのは、この観衆からしても、政治家という俳優は、明らかに、自分たちに向けてその役回りを演じていないように見えるからだ。有権者たちによって選挙で指名されたリーダーが向き合っているのは、有権者とは別の相手、すなわち、国内の巨大な利益団体や多国籍企業、さらには諸外国や国際機関である。選挙時に有権者になされた約束が果たされるどうかは、そうした相手との交渉次第なのだ。そうなれば、有権者はもはや観衆でさえない。観衆でさえないということは、観衆という極めて受動的な形で代表者をコントロールすることさえできなくなっていることを示唆する[8]。こうした状況がつづくなら、代表制度は、民主主義の制度であることをやめ、エリートによるエリートのための統治制度という本来の姿へと立ち返ることになったと判断するのが妥当であろう。
現在、アメリカやヨーロッパの民主主義諸国で観察されているポピュリズムの勃興は、代表制民主主義が病的な状態にあることを示しているといわれる。ポピュリズムについては、拙著でも詳しく議論したので、ここで立ち入って論じることはしない。とはいえ、これまでの議論から、次のことは指摘しておかねばならない。すなわち、病的状態というのが、代表制度の脱民主主義化、すなわちエリート主義化に直接関係しているということ。また、この脱民主主義化は、エリートたちの民主主義からの離脱と、かつて大衆と呼ばれた非エリートたちの民主主義からの離反とに由来しているということだ。これらを理解するには、工業化社会からポスト工業化社会への転換や、その転換をとおして漸進的に進んだ新自由主義の統治の確立、そしてこの秩序のグローバル化について押さえておく必要がある。いずれにせよ、ポピュリズムは二方向からの危機に直面した現代の民主主義の苦境を物語っている。
アメリカのトランプ政権やブラジルのボルソナーロ政権は近年を代表するポピュリズム政権であった。両政権は、支持者による議会の襲撃によって終焉を迎えたが、その光景によって示されたのは何であったか。それは、民主主義を破滅へと追いやる可能性が最も高いのは、現代の中国やロシアの権威主義であるよりも、代表制民主主義それ自体であるという皮肉な事実だ。この事実以上に、代表制民主主義の置かれた苦境を雄弁に物語るものはないように思われる。
[1] M.リンド(二〇二二年)『新しい階級闘争――大都市エリートから民主主義を守る』、施光恒監訳、東洋経済新報社、四六頁。
[2] ちなみに、リンドによれば、日本や韓国などの極東の民主主義国家は、現在の民主主義の危機を生み出した「テクノクラート新自由主義」に汚染されずにいるとされる。リンド(二〇二二年)、二四九頁を参照。とはいえ、この評価には議論の余地がある。仮に汚染されていないとしても、日本の民主主義が健全に機能しているということにはならないように思われる。例えば、藤井達夫(二〇一九年)『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』、集英社新書、第一章を参照。
[3] Slobodian, Q.(2020). Globalist: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, Harvard University Press, pp.7-13.
[4] D.グレーバー(二〇二〇年)『民主主義の非西洋起源について――「あいだ」の空間の民主主義』、片岡大右訳、以文社、八八頁。
[5] この点については、藤井達夫(二〇二一年)、第五章を参照。
[6] Manin B.(1997). The Principles of Representative Government, Cambridge University Press, ch.6.
[7] 機能不全に陥った政党によって代表されないと感じ、議会に自分たちの代表者を見出すことのできない有権者が政治家個人によって、しかも政府の首長によって代表されようとするようになる現象は、すでに第二共和制末期のフランスにおいて観察されている。K.マルクス(二〇〇八年)『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』、植村邦彦訳、平凡社ライブラリー、第七章における「分割地農民」に関するマルクスの分析を参照。
[8] 選挙が民主的なコントロールという役割を果たしていないことを明らかにした研究として、以下を参照。Achen, C.H. and Bartels, L. M.(2017). Democracy for Realist: Why Elections Do Not Produce Responsive Government, Princeton University Press.