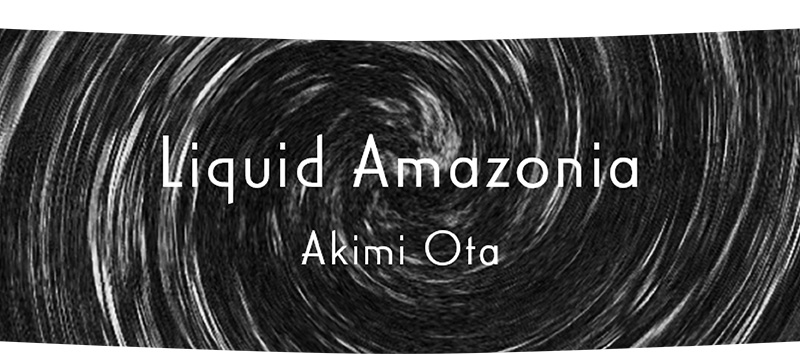「アロ?」2週間も経っていないのに、すでにこの声が懐かしく聞こえる。電話越しに、建物の外で行われている工事の音がわずかに漏れてくる。サンマルタン運河とパリ10区の光景が瑞々しく脳裏に浮かんだ。こちらは夕方だから、時差の関係で向こうは今早朝のはずだ。プーヨのアパートでMacBookの画面の奥に目をやると、窓越しにスコールが降り注いでいるのが見える。
「アキミがいなくてすごく寂しい。エネルギーがすっかりなくなっちゃったみたいで、体調も最近よくないの。でも、アマゾンにいるのにWhatsAppが使えるなんて、信じられない世界になったものね」。回線状態の悪さによって途切れ途切れでしか聞こえないエミリーの声には、あまり生気がなかった。
修士号を取得したあと、次に進む道に迷っていた彼女は、俺と同棲していたマンチェスターからパリの実家に戻り、ひとまず1月にエクアドルに来ることだけを決めていた。だが、たとえ今回のフィールドワークが博士号取得のために必要なことであり、1年後に帰って来るということがわかっていても、それまで一緒に過ごしていた俺が彼女を置いてアマゾン熱帯雨林という途方もなく遠い土地へ行ってしまったことによる喪失感は、想像以上だったようだ。彼女が感じている距離は、物理的なだけではない。ここに来るまでの俺がそうだったように、それはあらゆるメディアが作り出すイメージや言説がもたらす、アマゾンに対する絶対的な触れ合えなさの感覚の産物だった。
今拠点を置いているプーヨは、アマゾン地域で最後にネットが届く街だが、実際に現地にたどり着くまではそれすらも不確かだった。もしプーヨにネットが存在しなかったら? ここに来る前はむしろその可能性の方が高いと思っていたし、ネットの有無などどうでもよかった。しかし、今のエミリーの状態を考えると、恐ろしい。
エクアドルに着いてからというもの、俺の時間感覚は濃縮に濃縮を重ねていた。新たな冒険に対する高揚感、研究遂行のための義務感とプレッシャー、未知の現実に分け入っていく際の危機感や好奇心や緊張感。土地を探索し、人に出会い、言語を学び、情報を精査し、価値観や固定観念をズタズタにされ、吟味し、悩み、そして何より思考するために費やす日々の時間と、そこに注ぎ込む集中力。人類学者であり、同時に一人の揺れ動く感情を伴う青年でもある俺という人間が、自らを取り巻くあらゆる社会的、物理的、精神的要素によって知覚しているエクアドルでの環境の総体は、俺の時間感覚を例外状態に置いていた。
それは、決して「濃密すぎて一瞬のように感じる」のでも、「退屈すぎて永遠のように感じる」のでもなかった。強いて言うなら、それは「濃密すぎて永遠に感じる」時間の体験だった。いいとこ取りでもあり、最悪の組み合わせでもある、名伏し難く、世界の別の次元に連れ去られてしまったような感覚でもあった。
他方、エミリーの立場に立つと、彼女の生活は俺がいなくなったことを除いて大きくは変わらない。ちょうど学業も終えたばかりのタイミングで、生まれ育ったパリに留まっていても、日々目新しい何かが立ち現れる環境ではない。そこには明確に、待つ側と待たせる側の残酷な不平等が存在していた。その関係性についての俺の見立ては、甘かったのかもしれない。
最後にエミリーと話したのは、キトからプーヨに移る直前だった。その後、あまりにもたくさんのことが起きた。その中には、身の危険を感じるようなことも、目から鱗が落ちて心底衝撃を受け、涙腺が緩みそうになることもあった。自分が信じてやってきたことやこれから進もうと思う方向性について、あらためて思索の深まりを感じる瞬間もあった。しかし、どうしても電話越しに彼女にうまく伝えることができない。
これまでの複雑な体験を言語化することが難しいだけではない。心身ともに弱っている彼女に、無用な心配をかけたくないという気持ちもある。逆に、万事快調で素晴らしい体験の連続であるかのように話すのも、ヨーロッパに残っている彼女の精神を搔き乱すことになるかもしれない。結局、詳細にはそこまで踏み込めず、浮き沈みがありつつも研究が前に進んでいることを淡々と伝えることに終始してしまう。彼女は、最近お兄さんが始めたフードトラックをよく手伝っているらしい。2区のグラン・ブールヴァール沿いにあるRex Clubなどで回した経験があり、イビサ島のイベントにもよく出演していた名の知れたDJであるエミリーのお兄さんは、プロモーション面で彼に付いていたパートナーと決裂し仕事が減ってしまっていたこともあり、何か新しい事業に挑戦しようと思い立ち、自身のルーツであるバルカン半島の料理を振る舞うフードトラックを始めたのだった。
お互いの近況報告が一段落すると、「あのね、実は聞いてほしいことがあるの」と唐突気味にエミリーは言った。「どうしたの?」と聞くと、彼女は少し取り繕ったような明るいトーンの声で切り出した。「求人に応募してみたの!」少し驚いたが、「そうなんだ、いいじゃん! どんな求人だったの?」とポジティブなトーンで反応した。
「日本大使館関係の文化活動のPRで、日本語の能力が必須条件なの。もちろん、日本文化に関わる学歴があったら、有利ね。募集枠は1人で、大学の先輩たちも含めてきっとものすごい数の応募が来るだろうから、正直受かる自信はないんだけど。私さ、お父さんとの関係があまりよくないじゃない? ていうか、正直嫌いだし。だからあの人にお金の面でこれ以上頼りたくないの。早く経済的に自立したい。だからとりあえず応募してみようと思って、締め切り直前だったけどギリギリで書類を送ったんだ」。
「そっか、良いタイミングでそんな募集を見つけられてよかったね。確かに、エミリーの学科を出た人たちにとっては理想の進路の一つだろうから、すごい数の人が来そうだな……。でもエミリーは性格も明るくて面白いし、PRにはすごく向いてると思うから、チャンスはかなり大きいよ。日本語のレベルも高いしね」。
「本当にそんなこと思ってる? フフフ。なんかね、入学したばかりのときに私をバカにしてきた1学年上のシャルロットとか、同期のポーリーヌとか、みんな応募するらしいの。正直、せっかく応募するならあの人たちには負けたくないな。留学してからは私の方が絶対日本語上手くなったし」。お調子者で少し意地悪なエミリーの歯切れの良さが戻ってきた。それだけで嬉しかった。
「でもね、もしこの仕事に受かっちゃったら、1月にエクアドルに行くためにヴァカンスがあるか、わからないの。でも、心配しないで。この旅のことは、面接のときに隠さずに伝えるから。エクアドルにいる間にアキミに絶対会いに行きたいし、結婚もしたい。子供が欲しいって話も、前に一緒にしたよね。本当に思ってる。大好きだから」。
「俺も大好きだよ。1月には本当に来てほしかったから、仕事が決まったらエミリーがエクアドルに来られなくなるかもしれないのは確かに少し心配だな……。正直、このことは予想してなかったから少しビックリしてる。でも、エミリーが選んだなら、俺は応援するよ」。
すぐに会える予定もないまま遠く離れた環境で電話する場合、お互いの気分を害す可能性が少しでもあるような率直な会話はしにくい。次にいつネットが繋がる環境にいられるかわからないアマゾン熱帯雨林では、なおさらだ。だが、俺は自分が身勝手であることを理解しつつも、エミリーの決断を聞いて少し寂しさを感じた。
エクアドルに発つ前に、彼女とは将来について様々な想像を一緒に膨らませていた。例えば、一緒にモバイルハウスを作り、廃油などを上手く処理してガソリンの代わりに使いながらヨーロッパ中を転々とするノマド生活を構想し、実際にそのようなライフスタイルを可能にする技術革新の動向などについてもリサーチをしたりしていた。モバイルハウスの作り方を探究し、脱資本主義的ライフスタイルを構築しつつ、究極的にはそれをある種のアート実践として成立させるため、エミリーはオランダの大学が提供する先鋭的なアート学科の修士課程に入学することを目指して研究計画を書くまでに至っていた。
結局、その研究計画は「あまりに具体的過ぎる」としてオランダの大学には受け入れられず、エミリーはギャップイヤーを過ごすことになった。しかし、エミリーが既存の価値観を根っこから疑い、オルタナティヴな可能性を探究し、それを具現化するための斬新で創造的な発想を捻り出す力を持っているのは明らかだった。それに加え、彼女には独特な審美眼があり、絵画のみならず、インスタレーション作品を制作するある程度の能力もあった。
日本大使館関係のPRの仕事が決まれば、パリで不自由のない生活を送るだけの十分な収入を確かに得られる。経済的に自立したい気持ちも理解できる。だが、彼女が持っている感性を最大限に活かす道はもっと他にあるという率直な思いを拭うことはできなかった。それに、この種の仕事が新入りに対してイレギュラーな時期にヴァカンスを認めてくれるとは到底思えなかった。「1月まで頑張れば、エミリーに会える」。今揺るがされつつあるこの希望が、自分にとって大きなモチベーションのひとつになっていたことに気づかされた。
数日後、俺はプーヨ郊外にある「シェル」と呼ばれる飛行場に来ていた。ペルーとの国境にほど近いエクアドル東端にある、ロロカチという場所へ小型機で飛ぶためだ。ロロカチの着陸場はクラライ川に面していて、そこからカヌーで40分くらいのところにあるキチュア族の村に、全ての荷物を持って訪ねに行くことになっていた。
クラライ川は、ヤスニ国立公園自然保護区の最南端に位置する川で、それ自体が保護区域の境界線になっている。その川に面した村々に住む先住民たちは、保護区域内に出入りしつつ、生活の糧の一部を得ているという。また、エクアドルのアマゾン熱帯雨林に存在する最後の未接触民族であるタガエリ族とタロメナニ族は、この自然保護区の中で生活している。観光客としてヤスニ国立公園を訪れる場合は、オレジャナ州にあるコカという街を出発し、ガイドツアーに参加して西側から入るのが一般的だ。しかし、今回のように森の奥深くの南東部から入り、先住民たちの助けを借りることができれば、通常のルートでは足を踏み入れることができない区域に入ることができるかもしれない。
約1万平方キロメートルに及ぶエクアドル最大の自然保護区であるヤスニ国立公園は、「地上で最も生物多様性に溢れる場所」という評価を受ける。2010年にバス、ファイナー、ジェンキンスらが発表した論文によれば、区域内には爬虫類だけで最低でも121種、両生類では150種、魚類では382種、哺乳類では169〜204種、さらに鳥類に至っては596種が確認されている。また、植物種としては2700〜4000種が存在するとされる1。もちろん、いまだ科学が発見していない夥しい数の生物種も生息している。
この数値の凄まじさを理解するには、ヤスニ国立公園の面積が「アマゾン全体」の中で占める割合と、そこに生息する生物種の数がアマゾン全体に生息する生物種の数に比してどれほどの値かを見るといい。まず、ヤスニ国立公園はエクアドルはもちろん、ペルーやブラジル、コロンビア、ベネズエラ、ボリビアなど周辺国にも広がる「アマゾン熱帯雨林」と認識されるエリア全体の中で、 わずか0・15%しか面積を占めていない。しかし、そのヤスニ国立公園が養う両生類種の数は、アマゾン全体の中でなんと28%、爬虫類は33%、鳥類に至っては34%に達すると、同論文は結論づけている。その中には、オオカワウソやケナガクモザルなど、絶滅危惧種も多く含まれる。「アマゾン」と曖昧に定義される緩やかなモザイク状の熱帯雨林地帯の中でも、桁違いの生物多様性を内包しているのが、この保護区域なのだ。
区域内に眠る豊富な石油資源の採掘容認を巡ってエクアドルが国際的批判にさらされるなど、ヤスニ国立公園を巡る議論や未来への展望は激しく揺れ動いている。今ここで俺がそれについて論じ切ることはできないが、確実に言えるのは、アマゾンの奥深くにひっそりと存在する、地上で最も複雑な生命の迷路に、自分は今から行くということだ。
なぜこのような場所に行こうと思ったのか。セバスティアンとパストーラが住むケンクイム村は確かに素晴らしい場所だった。セバスティアンの薬草の知識にも非常に興味を惹かれた。しかし、ケンクイム村しか知らない状態では、この村やここの住民たちがどのような意味で、どのような文脈上で特異なのか、1年間の長期にわたって向き合い続けるべきなのか、自分の中で納得ができない。また、それを他者に説明することもできない。だからこそ、俺は大きな決断をする前にシュアールとは異なる民族の生活を垣間見たいと思い、自分ができる限界までアマゾン熱帯雨林の「奥地」に行ってみたかった。もしかしたら奥地では人々はまだTシャツやデニムを着ていないかもしれない。もしかしたらそこにはセバスティアン以上の薬草の知恵や想像を絶する発想を持ったメディシンマンやシャーマンがいるかもしれない。そこまで行った上で、人々に出会い、何が起きているのか観察し、分析することで、アマゾンを複眼的に眺める視点を持ちたいと思った。誤解を恐れず言えば、俺はヤスニ国立公園まで訪ねることで、自分がまだ捨てきれていないアマゾン先住民へのロマンティシズムが首の皮一枚繫がることで現実と接続するのか、それとも死を迎えるのか、ハッキリさせたかったのだ。
今回の旅がどのように実現したかというと、まず知人の紹介をたどってJICAの海外協力隊としてプーヨに滞在していたヒロシという日本人に出会った。彼は市の観光局で働いていて、同僚の多くは先住民系のエクアドル人だった。彼の手引で何度か業務に同行させてもらう機会があり、そのときに仲良くなったキチュア族のマヌエルに、仕事で行く機会があったという奥地の村に一緒に行ってもらえることになった、という流れだ。しかし、仕事の関係もあり、小型飛行機でロロカチに着いたあと、彼は友人に俺を紹介したらすぐにプーヨに帰ることになっていた。
村はあまりにプーヨから遠く、ボートでは到着まで3日間かかってしまうため、定期的に飛んでいるわけではない小型飛行機を手配してもらう今回の機会は非常に貴重だった。もしこの村に滞在しながらフィールドワークを行うことに決めた場合、荷物をプーヨに取りに行くために往復する余裕はない。賭けではあったが、思い切って旅の前に借りていたアパートを引き払い、全ての荷物を持って俺は飛行場に向かった。もし長期滞在が決まった場合、村では住民たちに英語を教えるという役割で受け入れてもらうことになっていた。確かにセバスティアンたちの住むケンクイム村は魅力的だったが、ヤスニ国立公園に接する村に滞在するチャンスは、そのときの俺にとっては千載一遇であり、文化的にも他の村とは比べ物にならないくらい「本物」のものが存在するのではないかという期待に溢れていた。
小型機のパイロットが俺とマヌエルに合図を送ってきた。そろそろ出発するようだ。バックパック、カメラバッグ、そしてキャスター付きの大型ソフトケースを持って他の乗客数人とともに機体に乗り込む。乗っているのは全員で7、8人だろうか。
上空に向けて機体が離陸を始める。ゆっくりと上昇する視界を味わう。やがて、辺りは全て真緑の広大な熱帯雨林だけになった。NetflixやBBCのドキュメンタリーで観る、あの景色である。初めて上空から眺める森に、圧倒された。高地アマゾンの緩やかな山々をすり抜けるようにたくさんの川がうねりながら流れている。この巨大な森は、それ自体がまるで別の惑星のようだ。この世界には複数の「世界」が存在している。それが今までの文化主義的理解ではなく、マテリアルな、宇宙論的意味において腑に落ちつつあった。
45分くらい経っただろうか。機体が下降を始めた。もともとジェット機のように最高度では飛んでいなかったため、すぐに地上に近づいていく。機体の軽さゆえ、下降に伴うフワフワとした揺れが身体に直接伝わってくる。着陸用に整えられた原っぱのようなところに無事着陸した。降りると、乗客の中に家族などがいるのだろう、待っている人々が10人くらいいて、そこかしこで呼びかけ合ったりしていた。男が1人俺たちに近づいてくる。今回世話になる村の住民のオスカルだ。先住民の男性としても少し小柄で細身の彼は、森で何かしてきたばかりなのだろうか、泥の跡がたくさんついた赤茶色のTシャツに、それよりもう少し赤い色のキャップを被っていた。洋服ではない衣服を身に纏っている者は男女ともにいなかった。
「よく来たね。君を歓迎するよ。ここでは一緒に過ごしながら、私たちのコスモロジーを体験してもらえるだろう。さあ、カヌーがあるからこっちに来てくれ」。ここで俺は、一言目で「コスモロジー」という言葉を使った彼の二重意識を感じた。先住民の人間でも、コスモロジーという語句で自分たちの世界の見方に言及するのは極稀だ。それは、ほんの一部の外部との折衝経験を持つ者たちだけが内面化する、外の世界に対して自分たちのことを言語的に説明しなければならない必要性に基づいた言い回しなのだ。
自分を受け入れてくれることへの感謝の気持ちを俺も述べると、カヌーの方に一緒に向かう。流れの緩やかな川に着いた。そうか、ここは低地アマゾンなのだ、と気付いた。ケンクイム村はアンデス山脈により近い高地アマゾンに位置するため、川の流れは急で、底や岸にはゴツゴツした大きな石がひしめいている。それに対し、ここにあるのは石ではなく砂で、川は動いているのはわかるが渦ができたり水しぶきが上がるほどではない流れの強度だった。
カヌーはもちろん木製で、漕ぐための櫂(かい)も木を削って作られていた。しかし、カヌーの後部にはホンダ製の小型エンジンによる船外機が取り付けられていた。どうやら、ガソリンで動くらしい。この状態のカヌーのことを、彼らは「ペケペケ」と呼んでいた。オスカルがエンジンを起動すると、けたたましい音を上げてボートが進み始めた。船外機には手動で方向を変えることができる長い棒のようなものが取り付けられていて、その棒の先端にプロペラが付いている。それが高速で回転し、棒を自在に動かすことでボートが進む方向を調整することができるようだ。
カヌーに乗りながら横を眺めていると、明らかに今までアマゾン熱帯雨林地域で訪れたどんな場所とも異なることがわかる。森の知識がなくとも、単純な種のヴァラエティの豊富さは形質や色彩の個性や匂いのとらえどころのなさを通して知覚され、それぞれの木々が発する野太いエネルギーが途轍もないパワーで迫ってくる。セバスティアンとパストーラを訪ねてケンクイム村に滞在したのは1か月くらい前のこと。初めて足を踏み入れたアマゾンの森が放つ荒々しい生命力に俺は圧倒されたばかりだ。だが、その衝撃をさらに上回る複雑なエコシステムと巨大な生物多様性をここの森が擁しているのは、ディテールに触れる前にひしひしと感じられた。
40分くらい進むと、オスカルの村に着いた。彼の家は岸辺近くにあり、村の中心は小川を挟んだ向こう側にある。木製で茅葺き屋根の家に入ると、床は土ではなく高床式になっていて、家の外側に焚き火があった。オスカルには3歳と5歳の子供が2人いて、妻の女性もいた。シュアール族と同じように、着いた客人はまずチチャをいただく。シュアールの人々からは、「キチュア族とチチャを飲むときは、もらったお椀を完全に飲み干さないと無礼になるから気をつけろ」と言われていた。お椀の半分弱ほどの量を飲んだあと、オスカルに正直に「これは全部飲んだ方がいいのかな?」と聞いた。一杯丸ごとを飲み干すと、それだけで酔ってしまいそうだった。オスカルは「大丈夫さ、自分が必要な分だけチチャを飲めばいいんだ。お腹が空いたんじゃないか? これでも食べてくれ」と言うと、大きな鍋の蓋を開けた。そこには、黒黒としたイノシシ肉の燻製の大きな塊がいくつも入っていた。中には、イノシシの頭部から肉付きのいい部分を引き剝がしてスモークにまぶしたと思われるものもあった。
「こいつは何日か前に僕が自分で仕留めたんだ。この辺りにはイノシシがたくさんいるからね。少し森に入ると見つかるよ」とオスカルは言う。部屋の角に、猟銃が立て掛けてあった。ケンクイム村では、4日間の滞在中に狩猟肉にありつくことはなかった。セバスティアンや他の村人たちからは、野生のイノシシなどを狩るには何日も森にこもらなければならず、いつでも食べられるものではないと聞いていた。ここロロカチでは、明らかに状況は異なるようだ。
いただいた肉片に、早速かぶりついてみる。すると、爽やかな炭火の薫香が鼻を通り抜ける。すごい歯ごたえだ。決して柔らかい肉ではない。力を入れて嚙みちぎり、咀嚼する。ひと嚙みごとに図太い繊維と、それが纏う森の匂いが舌と鼻を滑っていく。特に日本で気にされることが多い狩猟肉の「臭み」なるものは、微塵も感じなかった。元々、俺は肉や魚が持つ特有の「臭み」なるものを忌避するよりはむしろそれが持つ強烈な個性を愛で、深く味わうことに価値を見出す人間ではあるが、このとき食べたイノシシ肉が実際に「臭み」を帯びていないかどうかはわからない。なぜならアマゾン熱帯雨林で日々を過ごすうちに嗅覚が変わってきているからだ。都市部のプーヨにいたとしても、そこで没入する「スメルスケープ」(David Howes)によって全身の感覚が影響を受ける。それによって、イノシシを食べたときに脳内で変換される匂いの意味も異なるものになる。
だが、次の瞬間、気になる情景を見た。オスカルの妻のオリビアがお湯を沸かそうとして火を焚こうとするとき、薪にガソリンを注いでいたのだ。驚いたものの、最初はガソリンかどうか確信が持てなかったため、オスカルに何を注いでいるのか聞いた。「ガソリンだよ。この方が早く火が点くからね」と彼は答えた。この言葉を聞いたとき、自分の中で何か大きな軸が揺らぐような感覚があった。それはまるでX軸とY軸による比例関係の図が、無軌道に捻じれ上がり、全く参考にならない状態のようだった。つまり、アマゾン熱帯雨林の中でも、「より奥地の、より手つかずの自然が残っている場所に住む人々の方が、より昔ながらの生活様式を保っている」という、無垢な比例関係のことだ。
オスカルが村人に俺のことを紹介してくれるというので、小川の上に掛けられた小さな橋をわたり、村の中心にあるコミュニティホールのような場所に一緒に向かった。民家の3倍くらいはある広さだったが、全て木製で茅葺き屋根の美しい建物だった。
建物の壁に沿って取り付けられた長いベンチに、20〜30人くらいの村人たちが座っていた。真ん中を境に男女がパッキリと分かれて座っている。ケンクイム村と同じように、皆洋服を着て、長靴を履いている。「みんな、ここにいるのはアキミという人で、イギリスからやってきたそうだ。今回、1年間くらいここに住み込んで村の希望者に英語を教えてくれると言っている。彼を歓迎しよう」とオスカルは語りかけた。「日本人だけどイギリスに住んでいて、しかも中国人ではない」という説明を毎回するのに疲弊していた俺は、英語を教える役としてこの村を訪ねることもあり、シンプルに「イギリスから来た」と伝えていたし、その説明に対して彼らが違和感を抱いている様子でもなかった。
難しいのは、俺がまだこの村に長期滞在するかどうかは確定させたくないものの、村人たちには長期滞在を前提に紹介されてしまっていることだ。オスカルには、ぜひとも村を訪ねたい、もし住むことになったら村への貢献として英語を教えることもできる、ということまでは説明した。「視察のために3日間だけ滞在したい」という言い方をしていたら、今回受け入れてもらえたかはわからない。村に貢献する気がない外部の人間を受け入れる道理は彼らにはないからだ。アマゾン熱帯雨林の村々や人々全体から感じるのは、彼らの領域に立ち入ろうとする人間たちが、果たして彼らに貢献しようとしているのか、野次馬的興味しかないのか、あるいは害を与えようとしているのか、鋭く観察しているということだ。それは至極正当なことである。その中で人類学者たちが森に潜水し人々の懐に入っていくためには、絶妙なニュアンスを使い分け、限りなく虚実の境目が曖昧な表現をも駆使しながら道を切り開かなければならない瞬間が必ずある。
村人たちへの俺の紹介が終わったあと、オスカルが他の数人と川へ漁に行くというので、同行させてもらうことにした。川岸に停めてある2艘のカヌーに参加メンバーが分かれて乗り込む。オスカルと俺の他に、男性と女性が2人ずついた。女性のうちの1人は、妊娠8ヶ月くらいだろうか。お腹がかなり大きく膨らんでいる。網漁を行うらしく、束になった網がカヌーに積んであった。さらに、マチェーテはもちろん、銛(もり)のようなものやチチャの入ったポリタンクも持ち込まれている。船外機を起動すると、カヌーがまるで猛禽類の群れが威嚇しているような耳をつんざく音を立て始めた。クラライ川を上流に向かって進んでいき、徐々に支流の小川に入っていく。すると、運転していたオスカルが船外機のエンジンを切った。速いスピードでこの先を進んでしまうと、障害物を避けられない可能性が出てくるからだ。倒れた木々が10メートルくらいの川幅の中に沈み、川面から飛び出している枝葉が視界を曖昧にしている。目視できない水中にある木の幹に衝突したら大事故に繋がる。ときに枝を首の動きで避けながら、櫂を使って緩やかに注意深く進んでいく。
漁の地点に着いたようだ。広大な森と川が支配する空間ではあるが、彼らは定期的に立ち寄るスポットをいくつか決めていて、ランダムに目的地を選んでいるわけではない。川岸といっても、細い支流に入ると砂はなく、倒木や枝や大きな葉っぱが川の縁に沿って何重にも折り重なることでクッションのようになっている部分に、足を乗せてデッキのように利用する。言語化すると簡単だが、俺にとっては全く安定した足場ではない。足を踏み外したら、胸のあたりまで泥水に吞まれるだろう。しかも、その下には底なし沼が広がっている可能性がある。すると水底を蹴る反発によって身体を持ち上げることができず、非常に危険だ。
だが、オスカルはカヌーから降りると、足元に目を配ることすらせず、悠々と木や枝の束の上を伝っていく。近くに落ちている手頃なサイズの木の枝を水底の安定した部分に突き刺し、そこにロープを巻き付けることでカヌーを停めた。次々に同行している村人たちが降りていく。まるで幽霊が進むかのように、身体の軸が全くブレない。彼らに付いていくべく、俺も水に浮かぶカヌーの中で立ち上がると、足元がグラついてバランスを保つのに一苦労で、視線は限りなく真下に向かう。ここからカヌーをまたいで川岸に移るが、その川岸もまた、木や枝の集積によってできた一時的なマットのようなものに過ぎず、川に落ちるリスクは全く軽減されない。背筋がピンと伸びて身体中の微細な筋肉が「おっと、これはさすがに出番かな」と言わんばかりにアクティベートされるのを感じる。エクストリームな自然環境に否応なく放り込まれたとき、自分の肉体が保持していることをとっくに忘れていたような能力が突然表れる。それは必ずしも日頃のトレーニングなどによって維持されうる何かではなく、「死」の淵に接地していると肉体が感知することによって初めて呼び覚まされるゾーン状態のようなものだ。
なんとか川岸に飛び移り、転倒せずに耐えていると、村人たちはマチェーテで森を切り分け、奥へ入っていく。全員で一つのことをやるというよりは、それぞれが森から得られる何かを探しているようだ。近くに生えている食べられる葉っぱや木の実、果実などを採集したり、村に持ち帰って植えるための苗木を手に入れたりしていた。森の奥深くへは入らず、カヌーの近辺に留まっている。あくまで今日の目的は漁であり、今行っているのはそのついでに川岸近くでできる活動だ。
ひとしきり皆の活動が終わると、カヌーにもう一度乗り込み、いよいよ漁をする地点に向かった。すでに何度もここで漁をしているのだろう。杭のように打たれた木の枝が何本か水面から飛び出している。そこに持ってきた網を掛け、魚が逃げられないようにし、櫂でカヌーを漕ぐのを止めて静寂を作る。網を掛けたのは、妊娠中の女性だった。臨月に差し掛かろうとする女性が安静にしていないどころか、俺の目からすれば危険を伴うこのような漁に非妊娠者と同じ条件で参加している。
すると、オスカルが銛を持って立ち上がり、かがんで待ち構えるような体勢になった。一瞬の間のあと、「パシャン」と音を立てて銛が水面を突いた。先端には、体長15センチくらいの魚が突き刺さり、ブルブルと震えていた。揺れを伴い、フラットではない足場の上で、水中の魚を目視しながら単純に銛で突くことで、一撃で仕留める。その一連の美技にわけもわからず目を奪われた。カヌーに乗る他の男性たちも銛を手に握り、集中力を高め、身体の動きをピタリと止めて水面に目をやる。俺も川面に視線を移し、中にどんな魚がいるのか見ようとした。ところが、川の水は薄茶色に濁っていて、魚が動いている様子など全く見えない。「オスカル、魚が全然見えないよ」と言うと、「見えるさ。ほら、そこで動いているのがわかるだろ?」とオスカルは答えた。水の濁りに加え、太陽光の反射や、木々が作る影、葉っぱの断片や泡、川の流れによるうねりが水面に生む襞などが、裸眼での視力が1・0はある俺にとっても水中を覗くことを困難にしている。どうやって、こんな水の中にいる魚の存在を認識できるのだろうか?
「パシャ!」オスカルが目の前で銛を再び突いた。その先端には、再び魚が刺さっていた。彼は、俺には見ることすらできない魚をいとも簡単に捉えることができた。「ほら、いただろ?」オスカルが穏やかに笑う。
その直後、もう片方のカヌーから声が聞こえた。「気を付けろ! あいつだ!」どうやら不穏な事態が起こりつつあるようだ。オスカルがもう一方のカヌーの方に向かって櫂を漕ぐと、数メートル先の水面に、2メートル近くはありそうな細長い魚の背面がゆらりと見えた。感覚毛が口周りにあるように見え、光に反射すると黒が強めのグレースケールの肌が青っぽくきらめく。得体の知らない化け物に出会ったような感覚だ。「アキミ、いいか。こいつは強力な電気で攻撃してくるんだ。絶対に直接触るなよ。触ったら死ぬぞ!」村人たちが口々に叫びながら警戒する様子を見せる。見たこともないような怪物に突然出会ったと思ったら、さらにそいつはまるでポケモンのような電気攻撃を仕掛けてくるらしい。理解が現実に追いつかないが、時折水面に顔を出し、飛び跳ねるような動きを見せる巨大魚に対して、とにかく身を守ろうと必死にカヌーの側面に張り付く。オスカルによれば、この魚は「アギーラ」と呼ぶようだ。以前、彼が殺そうとしたところ、反撃にあい電流を食らってしまい、死にかけたことがあるという。
こちらを警戒しながら遠ざかっていく電気巨大魚を仕留めようとカヌーの上で立ち上がった村人たちには、あの妊婦の女性も混じっていた。いや、むしろ積極的に前のめりになっていた。彼らの警告が本当ならば、あの魚に誤って触れれば、彼女にとっても、お腹の中の胎児にとっても大きなダメージを受けるリスクがあるはずだ。しかし、そんなことには微塵も関心を抱いていない様子で、女性自身も、周りの村人たちも、厳しい形相で銛を持ちながら電気巨大魚を睨む。
結局、仕留めるタイミングを逃し、電気巨大魚は水中深くに消えていった。なるほど、この視認が困難な川の水は、ただ転落することや、水底に広がっているかもしれない底なし沼が恐ろしいだけではない。水中に潜む生物たちによる攻撃を受ける可能性もまた、この土地の川と人間の関係を形作る要素なのだ。
漁から戻ると、すでに日差しは傾き、日没が近くなっていた。オスカルの家の前の川辺で身体を洗い、その日捕れた魚を焚き火で焼いたものをいただく。今日の体験だけでも、ヤスニ国立公園に面するここクラライ川やその支流の環境が、アマゾン熱帯雨林の中でも別次元のスケールを擁していることや、銛による漁の技術をはじめ、村人たちの途轍もない身体知の広がりや能力をまざまざと見せつけられた。それと同時に、ガソリンへの依存や衣服など一部の生活用具の西洋化など、セバスティアンたちが住むケンクイム村よりも遥かにアマゾン熱帯雨林の「奥地」に位置するこの村もまた、決して「外部から隔絶された自律世界に住む先住民像」という俺も人類学も捨てきれない暴力的なロマンティシズムを満たすものではないことも見えつつあった。
街に出るにはカヌーを漕いで3日かかるこの地点までやってきても、彼らは全てのものを森から自給しているわけではない。もし、ロマンティシズムの完全な死を見届けるためにさらに次のステップを踏むならば、ヤスニ国立公園に住むと言われる未接触民族たちとの出会いを模索することに帰着するだろう。しかし、それには今までとは全く別種の手順を踏む必要性と、あらゆる面で次元の異なるリスクを伴う。俺の研究の主旨がそれでないことは、明らかだった。
俺の脳内で急激に崩壊し再構成されていく、アマゾン熱帯雨林を取り巻く認識や土台となる知的構造を感じながら、さらにディテールを知るためにオスカルに質問を投げかけてみる。「オスカル、この村にシャーマンはいるの? 村人たちは今もアヤワスカを飲んだりしているの?」と、聞いた。オスカルは答えた。「シャーマンは今、この村にはいない。何年か前までいたけど、その人は亡くなってしまったんだ。アヤワスカは、この村の人たちはもうほとんど飲んでいないよ。体調が悪くなったら、プーヨで買ってきた薬局とか病院の薬を使う。僕の叔父さんは薬草にそれなりに詳しいけど、病院の薬よりも薬草に頼る人はこの村にはいない」。なんとなく、そんな予感はしていた。オスカルの家には街の薬局で買ったであろう薬が大量にストックされていたし、今日一日を過ごす中で、アヤワスカやマイキュアといった薬草の重要性について村人たちから言葉を聞くことはなかった。これまで会ったシュアールの人々からは、こちらが話題を振らなくてもいつの間にか薬草から得られるヴィジョンの話を聞かされていることが多い。
また、この村にはキチュア族が元々使用してきた楽器を弾く人も存在しなかった。ギターを弾く人はいるようだったが、セバスティアンが吹いていた「ピンギュイ」という笛のような、森の素材を使い、世代を越えて受け継がれた手法によって彼らが自作する楽器を、失っていたのだ。
アマゾンの最奥にやってきて理解できたのは、都市からの距離と、いわゆる「先祖伝来の知識が残っている程度」に、比例関係は存在しないということだった。また、「自然がより手つかずの状態で残っているかどうか」と「自然から得られる糧を受け取る量や意思の程度」にも、比例関係は存在しなかった。この事実が突き付けるのは、「伝統的共同体」と呼ばれる地域に関する大衆的想像力に対するアンチテーゼだけではない。人類学もまた、無邪気にこの誤った比例関係を前提としている。少なくとも、この比例関係を明確に脱構築した上で、理論的にもスタイル的にも刷新した上で編み上げられた民族誌はほんのわずかしかなく、影響力も微々たるものだ。
最も重要なのは、この比例関係の成立不可能性は、我々に根源的な意味での行為主体性の再考を迫るということだ。端的に言えば、どんな環境で暮らしているにせよ、そこでどのように暮らすのかは、どんな属性の人間であれその人自身が決めるという主体の存在を、先住民に対しても認めなければならないということである。それはこれまでの、さらには現代の、先住民と呼ばれる人たちを扱う人類学の主流が決して認めてこなかった、言説的かつ修辞的なタブーである。また、これは近年の「人間的なものを超える人類学」なるものの総体が、暴力的に押し進めてきた先住民コミュニティの「再イデア化」の過程に、顕著な現象として表れている。
次の日の朝、目が覚めて瞼をゆっくりと開けると、あたりからこれまで聞いたことがない音が聞こえてきた。5時にまだならないくらいだろうか、部屋の中は薄っすらとした光に包まれている。「ホアホアホア」「キイキイキイ」「ギャウギャウギャウ」「カァッカァッカァ」あらゆる擬音語の可能性を試しても描写できない、凄まじい種類の猿の鳴き声が、森の全方位からこだましている。猿たちの鳴き声に反応して、鳥たちも歌声を奏でる。しかし、猿たちの早朝の気合いは、鳥たちを凌ぐ勢いで森の音響空間を支配する。アマゾンの森に広がる壮大なコンサートホールで、地球上最大のオーケストラによる音色が搔き鳴らされていた。
オスカルの家から外に出て、しばらくその音に身を浸す。まるでイングランドのフットボールスタジアムでゴールが決まったかのような体感的音圧だが、その「厚さ」は、単純な音量から来るものではない。数百メートルあるいは数キロ先にいる猿たちも含んだ無限遠の反響が、彼らの鳴き声を多層化することで身体に染み入るようなウェーブフォームのグラデーションを生み出しているのだ。猿たちの大合唱で目を覚ますことなど、アマゾンといえども爆発的な生物多様性が存在するここ以外ではあり得ないのではないか。実際、その後に訪ねたいかなるアマゾンの村でも、こんな体験はできなかった。
俺はここで大きな選択を迫られていた。科学の認識が生態系全体を摑むことができない、気が遠くなるような森と生命の深淵が存在するこのヤスニ国立公園の側で、「人間」が持ちうる身体知のキャパシティに対する俺のちっぽけな想像をはるかに超えるような生き方を体現している一方で、薬草やシャーマニズム、アヤワスカなどのヴィジョンによる変性意識を半ば忘却したオスカルたちの村にこのまま居着くのか。それとも、この村とは異なり道路によって到達することが可能で、原生林が減少傾向にあるが、独自の方法論で薬草とともに生き、変性意識によって得られるヴィジョンにこの上ない価値と真実を見出しているセバスティアンたちがいる村に戻るのか。
一つだけ確実なのは、どんな選択をするにせよ、その選択に必然性を持たせるために、この村を訪れたことは重要な意味を持つということだった。アマゾン熱帯雨林と一言で括られ、上空からは緑一色の「大自然」として単純化されかねない地理的範囲の中に、途轍もないスペクトラムと差異が広がっている事実を身をもって認識することができた。また、奥地へ行けば行くほど、より「純粋」でより「自給的」な、「近代性」から離れた生活を先住民たちが維持している、という単線的で独善的なロマンティシズムと完全に決別する必要があること、既存の支配的な知的言説による概念装置を用いて構成した生をめぐる対立軸に、十全な効力がないと認めざるを得ないことが理解できた。
猿の大合唱は、日が昇り、朝霧が晴れるにつれて落ち着いてきた。その日は漁などには行かず村で過ごし、希望者の人たち数人にアルファベットの英語での発音を教えた。「アー」ではなく「エィ」、「ベー」ではなく「ビィ」、「セー」ではなく「スィ」だという具合に。そして、挨拶はHelloと書き、「エジョ」ではなく「ハロー」と発音することを教えた。午後になり、日が緩やかに傾いていく。俺の心は固まった。この村にこのまま居続けることはできない。俺はセバスティアンがいるケンクイム村に戻り、あそこで1年間を過ごしたい。この村に来るために、JICAのヒロシや彼の同僚のマヌエルなど、様々な人たちの協力があった。オスカルをはじめ、村の人たちは俺のことを暖かく迎えてくれた。彼らに対して、罪悪感が芽生える。しかし、命を捨てるつもりで飛び込んだこのアマゾンの地で、その罪悪感に負けるわけにはいかなかった。俺の腹も、心も、頭も、肌も、一斉に囁くのが聞こえる。行け、セバスティアンの村に。なんとしてでも!
しかし、そもそも小型飛行機を手配して、20キロ以上のソフトスーツケースと、同じくらいの重さのバックパック、さらに撮影機材一式を詰め込んだカメラバッグを積み込んでたどり着いた場所だ。定期的に飛行機が飛んでいないこの村から、どうやって抜け出せばいいのだろうか。飛行機をまたチャーターするとなると多額の料金がかかるのは間違いなく、しかもネットや電波が届かないこの村から手配するのも難しそうだ。手配するためにはオスカルに俺の意向を伝えて協力してもらう必要があるが、彼は俺のことを許してくれるだろうか。小さな思考が脳内を飛び交うが、一筋の道に繋がるようで繋がらない。
その矢先だった。オスカルに呼び止められたのは。「アキミ、実は明日から僕はプーヨに行く。街に薬を買いに行きたくてね。あと、役所と話すこともあるんだ。だからしばらく僕はいないけど、僕の妻が食事は作るし、村のみんなが色々助けてくれるはずだから問題ない」。明日プーヨに戻るだと? なんてタイミングのいいチャンスなんだ。今話すしかない。「オスカル、実は話したいことがある。3日間この村にいて、確かに素晴らしい場所だと思う。ここの森は信じられないような恵みを持っているし、きっとたくさんのことを学べるに違いない。でも、まだこの村で1年間過ごす決心がつかないんだ。だから、なんとか君と一緒にプーヨに行くことはできないかな? どうしても一度プーヨに戻って考え直したいんだ」。心の中ではセバスティアンたちの村に向かうことを決めていたが、オスカルを悪い気にさせずにプーヨに舞い戻るために、こういう言い方をした。
オスカルは、少し目を見開いて驚いた素振りを見せたが、全く苛立った様子ではなく、あっさりと一緒にプーヨに向かうことを了承してくれた。「わかった。一緒に行こう。よく考えた上でまた来たくなったらそのときは連絡してくれ。あと、何か僕たちの助けになりそうなプロジェクトやNGOについて知ったりしたら、教えてほしい。それじゃ、明日は明け方にカヌーで出発するから、よろしくな」。最後の言葉を飲み込むのに、数秒がかかったかもしれない。ここからプーヨまでは、200キロくらいの距離がある。クラライ川の流れに逆らって上流に向かう上に、途中で泊まれる場所もおそらくない。川幅は太くも細くもなり、流れが激しくなったり障害物に出会うことも多いだろう。それに、オスカルのカヌーは小さく、屋根もない。天候によっても川の様子は急激に変化する。頻繁にスコールが降るが、撮影機材や衣類、紙のノートはどう守ればいいのか。いくつも疑問が湧いてきたが、それしか手段がないのなら、このチャンスを摑むしかない。オスカルによれば旅は3日くらいかかるらしいが、プーヨまで問題なくたどり着くことを疑ってはいなかった。彼が行けるというのなら、付いていくまでだ。
翌日、猿の大合唱に再び起こされると、前日にパッキングしておいた荷物をカヌーの方に引きずるように持って行く。「荷物が多いな」と、オスカルは笑った。1年間フィールドワークをするためと考えればこれでもかなり少ない方だと思ったが、彼らは確かにこんな量の荷物を持って旅をしない。オスカルに手伝ってもらいながら荷物をカヌーの真ん中の方に積み込むと、雨除けのためのブルーシートで包んでくれた。途中雨に見舞われる可能性は高いが、多少なら撮影機材なども耐えられるだろう。
この旅には、ラファエルと5歳くらいの彼の娘であるクララも同行するようだ。ラファエルは大柄で筋骨隆々とした男で、ニカっと歯を見せて笑う様子がチャーミングだ。クララは旅慣れた様子で、3日間のプーヨまでの旅について不満も不安もまるっきりなさそうな、むしろ楽しみが勝るような表情をしていて、落ち着き払ってちょこんと座っている。この落ち着きは、フィールドワーク中に出会った先住民の子供たちの共通点でもあった。
チチャがたっぷり入ったポリバケツと大鍋を積み、それぞれ小さなバックパックを一つだけ持ち込んでいた。おそらく、ライトや現金などが入っているのだろう。それだけの荷物で、プーヨを目指す。欧米や日本の基準で考えると、同様の状況下で数日間移動する場合、テント、ライフジャケット、非常食、折りたたみ式の椅子、バーベキューセットと火起こしのための着火剤、食器や洗剤など、あらゆる道具の山が「必要なもの」として思い起こされるのかもしれないが、彼らはその一切を持たずに旅をする。アマゾンで本格的なカヌー旅をしたことがない俺は、これがどのような経験になるのか想像しにくかったが、不思議と彼らに全幅の信頼を置いていた。それは、彼らの身体的な感覚や察知力、何よりも森や川の生態に関する知識が、現時点での俺の理解が全く及ばないような次元で研ぎ澄まされていることを少なくとも知っていたからだ。彼らの身体に刻まれた自己生成的知性は、砂や水のように絶えず形態を変え、ありとあらゆる状況に対応する。
まだ夜が明けないうちに、カヌーは出発した。ペケペケの音が森の静寂を搔き乱す。後ろでラファエルが船外機を操縦し、クララはその前にいる。俺はカヌーの中央に座っていて、先端側に座っているオスカルの背中を眺めている。同じような音と景色が続くままに、5分が経ち、10分が経ち、15分が経つ。揺れがあるため、本を読むことはできない。エンジン音の強さにより、音楽を聴くこともできない。そもそも、俺のiPhoneの電源はとっくに切れていた。完全なオフグリッドであるオスカルたちの村には、充電できる場所などどこにもなかったからだ。
猛禽類のようなペケペケの音だけが薄暗い森にこだまする。会話はない。エンジン音がうるさいのも理由の一つだが、そもそも会話が止まることを誰も問題だと思っていない。オスカルの背中をぼんやりと見つめながら、視界の隅で確かに流れている川を間接視野で捉えている。そのうち、目の焦点が曖昧になり、思考がとろけるような感覚になってきた。散漫になった脳内に、代わる代わる断片的想念が現れては消え、現れては消えていく。坐禅を組んでいるときと同じように、感覚が少しずつ拡張していく。俺は今、前を見ているのに見ていない。音を聞いているのに聞いていない。考えているのに考えていない。しかし、公園の芝生やヨガマットの上で坐禅を組んでいるときのように、背筋にすっと1本の気が吹き抜けるような感覚はない。纏わりつく濃厚な霧や匂い、川の緩やかで広大な流動やカヌーの揺れ、ポリタンクに入ったチチャのツンと鼻を突く発酵臭とテクスチャー、マチェーテに付着した土のザラリとした手触り。カヌーに拵えられた、真っ直ぐ整った姿勢で座ることができない板。これら全てが複合的に形成するアマゾン熱帯雨林特有の瞑想状態では、意識は混沌とし、飛び交う感情の襞の形は歪でありながら柔らかく、物質的である。
2時間くらい経っただろうか。カヌーは淡々と、大きく変わることはない環境の中を進んでいる。俺は目測だけで何種異なる木を数えることができるか試す遊びや、この状態で羊を本気で数えたら何匹まで増えるのかなど、時間を潰すためのいくつかの方法を試したが、永遠に続くかのようなこの時間をカバーしきるほど続けることはできなかった。結局、瞑想状態に戻るのが一番苦痛ではない時間の過ごし方だった。実のところ、音楽も読書も会話もない状態で何時間もカヌーの上で過ごすことが、苦痛ではなく、むしろ体感したことがない種類の精神的充実感すらもたらしていることに、自分でも驚いていた。
日が昇り、すっかり朝の光が森を照らす頃、ペケペケのエンジンが切られ、カヌーがゆっくりと川岸に向かった。どうやら、ここにある村に一度立ち寄るらしい。「さて、降りて飲むぞ」と、カヌーを木に縛り付けながらオスカルは言った。なるほど、3日間の長旅では、俺たちが持っているポリタンク一つ分のチチャだけでは空腹や喉の乾きを癒やすことはできない。だからこうして、途中で村々にカヌーを停め、チチャや食料をもらいながら旅を進めるのだ。村に入ると、オスカルやラファエルは何人かの村人たちと親しげな挨拶を交わす。彼らにはクラライ川沿いの村々に、叔父・叔母、甥・姪、従兄弟など、多くの親族がいる。どの村に停まっても、高確率で顔なじみの親族の誰かが住んでいるのだ。
とある家の中に通されると、土器に並々と注がれたチチャを女性から早速いただく。もちろん、ありがたく飲むしか俺に選択肢はない。土器を上に傾け、ゴク、ゴク、ゴク、ゴク、ゴク、と、5回ほど喉を鳴らす。200ミリリットルくらいは一気に飲んだだろうか。なかなかに発酵が進んだ、強めの旨いチチャだ。一息つくと、チチャをくれた女性は俺の目の前から一歩も動かず、座っている俺を上から見下ろしている。「さあ、飲んで」と女性は言う。「もちろん。まだまだ飲めるよ」と言うと、もう一度土器をクイッと傾ける。ギアが上がってきた今回は、一気に300ミリリットル近く飲んだだろうか。あれほど並々と注がれていたチチャは、半分以下くらいにまで減っていた。しかし、強めのチチャをこれほど短時間に一気に飲むと、酔いも回る。旅はまだ長いのだ。ひとまずこれくらいで止めておこう。「何してるんだい? 全部飲まないといけないでしょう?」目の前で俺を見下ろしている女性が言う。そうか。シュアール族たちがキチュア族について「彼らは注がれたチチャを飲み干すまで逃してくれない」と警告していたことは、本当だったのだ。外部との繫がりも多いオスカルは、彼らの流儀の特殊性や、外部の人間にとってそれが厳しい要求であることを知っていた。だから俺に対して、チチャを飲み干さなくてもいいと言ってくれていたのだ。だが、この女性は決して容赦してくれない。至近距離に立ち続けることで、俺が飲み干すようプレッシャーを掛けてくる。
こうなったら、なんとか切り抜けるしかない。もう一度土器を上に傾け、喉を何度も鳴らした。そして、チチャを飲み干すことができた。「ウヘイィィィ」と先住民の男性のように声を出しながら土器が空であることを示すと、女性は満足げな表情を浮かべ、無言で土器を回収し、それ以上俺に無理に飲ませようとはしなかった。朝からいきなり陥った中度の酩酊に戸惑いながらも周りに座る村人たちに視線を配り、感謝の言葉を述べていると、オスカルとラファエルが立ち上がり、「アキミ、行くぞ」と言う。見ると、彼らも土器一杯のチチャを飲み干したのだろう。俺以上に酔っているかもしれない顔色で、すでに目が据わりつつある。
クラライ川を上る旅は、こうして数時間ごとにオスカルたちの親族がいる村々にカヌーを停め、プラタノやキャッサバなどの軽食や、土器一杯のチチャをもらい、飲み干すことを繰り返しながら進んでいった。2つ目に訪ねた村では、前回と同じように並々と注がれたチチャを女性から差し出されたときに、「ありがとう。でも、実は前の村でも同じ量をもらっていて、もうすでに酔っているんだ。この量は飲み干せないかもしれない」と言い訳したが、女性は聞く耳を持たず、「そんなことは関係ない。あんたは飲み干さないといけない」と答えるだけだった。仕方なく、辛い身体にムチを打ちながらなんとか飲み干した。これほど酔ったのはいつぶりだろうか? 自分の身体の限界を越えて飲むことなど、学部生時代に羽目を外して以来、ほとんどなかったはずだ。なぜ俺はアマゾンの森に来てまで、人生史上屈指の酒量を摂取しているのだろうか。
2つ目の村を出るとき、横に目をやると、オスカルはすでに千鳥足になっていた。このままでは旅の途中で酔い潰れてしまう。船員たちの運命を案じた俺は、腹も満たされている今、これ以上村々に頻繁に寄る必要はないとオスカルに訴えた。オスカルは川岸に向かってフラフラと前かがみで歩きながら小声で言う。「いや、寄らないとダメだ。俺たちの家族だからな、挨拶するべきなんだ。大丈夫、まだまだ飲めるさ」。そこまでして村々に立ち寄らないといけないのか。もちろん、彼らにとって村の前を通るたびにそこに住む親族や友人たちに会いに行くことが、社会的均衡を維持・強化するために重要な意味を持つことは、人類学的観点から問題なく理解できる。しかし、今ここで無視できないのは、彼らのソーシャビリティ構築のプロセスを参与観察することで、俺はアルコールによって身を滅ぼす危機を迎えているという差し迫った事実だ。もしこのペースで土器一杯のチチャを必ず飲み干さなければならないなら、今日のうちに俺は酔い潰れて意識を飛ばしてしまうだろう。そんなとき、万が一事故が起きたらどうするのか。大人3人が酔い潰れた状態でカヌーが転覆したら、幼いクララはどうなるのか。様々な危険信号が頭をよぎる。
しかし、オスカルたちを止めることはできなかった。彼らは村を見つける度にカヌーを停め、訪ねる。その度にたっぷりとチチャを飲み干すことを、決して目の前から動かない女性たちに強いられるのだ。3つ目に訪れた村で、俺はついにチチャを飲み干すことができず、これ以上自分には無理だと女性に伝えた。すると、女性は俺が持っていた土器を受け取り、俺の頭の上で勢いよく土器をひっくり返した。薄黄色のチチャが、ドシャっと俺の頭や肩を叩き、床にまで飛び散った。「キチュア族の女性は、誰かがチチャを飲み干せないとき、その人の頭に残りのチチャを浴びせる」という説は、シュアール族の友人たちから何度も聞いたことがある。それはある種の誇張された冗談である可能性もあると思っていたが、どうやら真実のようだ。周りにいる他の村人たちは、チチャを頭から被った俺に対して大きい反応は示さなかった。時々起こることがただ今日も起こっただけのようだ。
チチャでドロドロの身体を引きずるようにして家の外に出ると、オスカルがプラタノの木の横で嘔吐していた。一杯目の時点でそれなりに酔っていたオスカルだ。この量のチチャを飲み続ければ、嘔吐してしまうのは目に見えていた。しばらく吐き続けたオスカルだが、一段落したのか身体を起こすと、俺の方に歩いてきた。すると、晴れやかにも見える顔で「これでまた飲める」と呟いた。オスカルにとって、腹や喉を満たすために適量を飲むことは、村々でチチャをもらいながらカヌーを進めることの目的ではない。彼にとっては、いかなる身体的犠牲を払ってでも、チチャを飲み干すことが最も重要なのだ。その観点からは、急激なアルコール摂取によって引き起こされる嘔吐も、より多くのチチャを飲み干す可能性を高めるための有効な身体的反応に過ぎない。
次に訪ねた村で家の中に入る前に、俺も嘔吐せざるを得なかった。このままでは、今後頭から繰り返し大量のチチャを浴びることになる。川で水浴びができるのはおそらく翌日だが、身体中をチチャで濡らした状態で眠るよりは、嘔吐をバイオリズムの中にうまく取り入れて事態を乗り越えていくことを選んだ。嘔吐は一度では済まなかった。嘔吐したあとにチチャを飲み干しても、次に訪れる村で再びチチャを飲み干すためには、腹の中身を吐き出すことが必要だった。オスカルもラファエルも俺も、極度の酩酊状態のまま、日が暮れるまでクラライ川を進んだ。
日没直後の薄い光が残る時間になった。ラファエルがエンジンを切り、また川岸にカヌーを停めるようだ。しかし、今度は川岸に村がある様子はない。そこには少し開けた砂の空間があるだけで、辺りは全く人の気配がない深い森である。「今夜はここで寝る。今から葉っぱを集めて寝床を作るから、少し待っててくれ。ここは前に未接触民族が現れて俺たちの仲間が殺された場所でね。でも大丈夫、もうこの辺りにはいないはずだ」。なるほど、俺たちはまだヤスニ国立公園の側にいて、ここに住む未接触民族たちは時々クラライ川を渡り彼らのテリトリーの「外部」と出会っているようだ。今まさに自分がいる川辺でキチュア族が彼らに殺されたと聞いても、不思議なことに俺に恐怖心は全く芽生えなかった。冷静に反芻できないほど酔っていた、というのも理由の一つかもしれないが、それ以上に、これまでアマゾンの森に滞在した過程で、自分の身体に対する例外主義的思考が塗り替わりつつあるのだろう。自分の身体性を遥かに超越した存在の浩蕩たる息吹に包まれるようなこの感覚のもとでは、許容度を越えた酒量によって繰り返す嘔吐も、突然遭遇した未接触民族に殺されることも、ただ単純にその瞬間起こるべきことであった以上の意味を持たないまま、森の生態系の渦に吸い込まれていくだけの、無限に発生する水泡のようなものに思えた。
オスカルとラファエルが、マチェーテを持って木々がある藪へ入っていく。しばらくして戻ってくると、彼らは硬い茎を持つ大きなヤシの葉などを担いでいた。それらを素早く手頃な角度で地面に突き刺し、重ね合わせると、即席の雨除けができた。そして、素早く焚き火を作り、持参していた大鍋で貰い物のキャッサバのスープと肉の燻製などを熱し始める。俺たちはテントも寝袋も持っておらず、ブランケットだけがあった。スープと肉を平らげて横になると、辺り一面にこだまする無数の虫たちの声が聞こえてきた。地上で最も生物多様性に富む森の中の、人里離れた川岸でこの合唱を聴いていると、歪なギザギザを持った渦巻きが流動的に形質変化しながらぐるぐると回っているような、不思議なイメージが脳内に湧いてくる。途轍もなく分厚い音のレイヤーが、折り重なることで丸みを帯びて回転しているように感じたのだ。
翌朝目が覚めると、酔いはなくなっていた。未接触民族に寝込みを襲われずに済んだようだ。少ない荷物をさっさと船に積み込むと、再び出発した。この日もまた、村々に立ち寄り、チチャをもらいながら進んでいく。しかし、昨日の酒量によって身体が少しは慣れたようで、朝のうちに嘔吐し始めなければならない状況ではなかった。また、親戚たちが多くいるエリアから遠ざかったのだろうか、カヌーを村に停める回数自体が昨日より少なかった。
昼食後の午後、日が傾き始める前に時間に、再び村にカヌーを停めた。家に案内されると、階段があり、2階建てのようだ。何やらガヤガヤと男たちが話している声が聞こえる。階段を上がると、壁の側面一杯に男たちが座り、宴を開いていた。何人かがタバコの葉を巻いて吸っていて、煙が立ち込めている。階段から見て左側の側面の中央に、ギターを持った男が座っている。俺に何かキチュア語で話しかけている。手招きするようなジェスチャーをしているので、どうやらお前も座れと言われているようだ。オスカルとラファエル、クララと一緒に、ギターを持った男と対面する逆側の壁に沿って座る。
すると、男が気勢を上げてギターを搔き鳴らし、歌い始めた。チューニングは「合っていない」が、この不協和音を含んだ音色自体が、絶妙に場を纏う異様なオーラと絡み合う。聴くとすぐにわかるキチュア語の歌特有の上がっては下がり、上がっては下がる音程と、日本語の歌謡曲ともどことなく共通する変調の少ない4拍子が、うねるような情感を生み出している。オスカルに耳打ちし、何についての歌なのかを聞くと、「自分の人生についての歌だ。家族や友達について歌っている」と言う。酔っていたこともありそれ以上深く聞き出すことができなかったが、反復されるギターフレーズに身を委ねる。
一曲を歌い終えると、男は俺の方を見てギターを差し出し、「次は、お前の番だ」とスペイン語で言った。予期せぬ展開だ。ギターを渡されると、しばらく俺はどうしたものかとまごついた。高校時代は軽音楽部でギターボーカルをやっていたが、海外を転々とする生活に吞まれるうちに、ギターを持って移動することを止めてしまい、長い間弾いていなかった。物珍しいよそ者に部屋に溢れる男たちの目線が一斉に注がれているこの状態で、上手くパフォーマンスができるだろうか。
俺は中学生時代に毎日のように弾いていて身体に染み付いているはずの、スピッツの「チェリー」を弾くことにした。この曲もたまにカラオケで歌うくらいで、弾き語りは長らくしていない。歌詞も全ては覚えていないかもしれない。しかし、後には引けない。コード進行を必死に思い出す。C、G、Am、F。C、G、Am、F。イントロのコード進行を確認した。ギターを渡してきた男は、まだ歌わないのかと言わんばかりの視線を俺に送っている。
「ジャーン」とギターを鳴らし、始めるぞと合図を送る。まだ男たちの会話が静まらないうちに、弾き始めた。アマゾン熱帯雨林の奥地に、日本語の歌が響く。男たちが高い集中力で耳を澄ませている。歌唱力にはそれなりの自信があった。コード進行を間違えたが、構わず歌い続けて押し切る。歌詞が飛んだ箇所もあった。そこには日本語とも言えない音を入れて誤魔化した。こんなに必死に歌ったことが今までにあっただろうか。男たちに「こいつはなかなかやるやつだ」となんとか印象付けたい。歌う言葉を持つやつだと認めてもらうことが、この場を乗り切る唯一の方法なのだと理解していた。
1番だけ歌い終えたところで、ギターを止めた。男たちはあっけに取られた様子で俺を見つめている。「一体、今何が起きたんだ?」とでも言わんばかりの、素直な衝撃を感じているようだ。それは、おそらく初めて聞く日本語の響きや、「チェリー」の独特の曲調にもよるだろう。彼らが日常的に聞く音楽は、キチュア語歌謡やクンビアが大部分を占める。レゲトンなどのラテン・アーバン・ミュージックも耳にはするが、ロック自体を聴いたことがないはずだ。「今の曲は何を言っているんだ?」とギター弾きの男が聞いてきた。「愛についての曲だ」と答えると、男たちはそれぞれに納得したような表情を見せた。
突然のライブリクエストをなんとか切り抜けると、次に待っているのはもちろんチチャだ。今回はなぜか男たちだけが部屋にいて、女性はチチャが注がれた土器を持ってくると、部屋の外に出ていった。つまり、飲み干さなくても頭からかけられることはない。うまく誤魔化しながらチビチビとチチャを飲んでいると、オスカルたちが出発する素振りを見せたので、土器を置いて部屋から出た。
その日も結局一度は嘔吐したが、昨日ほど大量のチチャを飲まなくて済んだので、ある程度意識が鮮明な状態で旅は進んだ。そして、夕暮れ時に最後の村で停泊した。今夜は川辺ではなく、この村で寝るようだ。「ここには俺の大事な親戚が何人も住んでるんだ。完全に信頼できるから、ゆっくり休もう。明日の朝にはプーヨに着くぞ」とオスカルは言った。
この村では、ちょうど村長が変わるタイミングだったようで、中心にある広めの茅葺き屋根の建物の中で10人くらいの村人たちが集まって宴を開いていた。蒸したキャッサバとゆで卵を夕食としていただいたあと、オスカルたちと宴に参加した。毎日これだけチチャを飲んでいて飽き飽きしていても不思議ではないが、屋根のある場所で寝れる安心感と、明日にはプーヨに着けるという高揚感からだろうか、チチャを飲む俺のモチベーションはなぜか高かった。村人たちも、俺の存在を訝しむ様子はなく、受け入れてくれているようだった。オスカルの隣に座り、近くにいる村人たちと会話をしながらチチャを飲む。
夜もかなり深くなり、周りの人々も俺も酩酊が進んできた。しかし、生気が湧き出し、ダウナーではなく、アッパーな方向に酔いが進んだ俺は、むしろ積極的に場の状況と関わろうとするモチベーションがいつになく高かった。そんなとき、建物の中心部で怒鳴り合う声が聞こえてきた。見ると、2人の男が摑み合いの喧嘩をしている。かなり激しい応酬だ。周りの人間が止めようとしているが、力が強く、お互いに一歩も譲らない。周りに聞くと、従兄弟同士で何かわだかまりがあるようだった。
酔いが回った俺は、立ち上がり喧嘩を止めに行こうとした。すると、オスカルがグイっと俺の腕を引っ張り、座っていた板に押し戻す。周りが騒然としている中、大声で俺の耳元に叫ぶ。「アキミ! お前は行かなくていい。お前が行ったら本当に危ない。ここにいるのが一番いいんだ!」恐怖心がなくなっていた俺は、「なんでだ? あの2人は喧嘩しているじゃないか。このままだと殴り合いになってしまうかもしれない。その前に止めないと!」「何を言ってるんだ! キチュアの男同士が本気で喧嘩したら、何が起こるかわからない。マチェーテも持ってるし銃だって持ってくる。殺し合うことだってあるんだ。お前が行ったら死ぬかも知れないぞ!」いつも温厚なオスカルが、このときばかりは本気で俺を止めようと絶対に引かない態度で説得している。
まさか、親類同士の摑み合いの喧嘩が殺し合いに発展する可能性を感じていなかった俺は、オスカルの言葉に驚いた。ここアマゾンの森では、死は常に日常の延長にある。それはいつでも、どんな些細なことがきっかけでも、物事の連鎖の末のふとした瞬間に起こり得ることなのだ。不慮の事故や、毒蛇やジャガー、電気魚といった動物からの攻撃や、明確な計画のもとに実行される悪意を伴った殺害だけではなく、飲みの席でのヒートアップがきっかけにもなる。国家による警察や司法が事実上存在しないこの地では、それを防ぐのも、それが起きたときに秩序を修復するのも、全てコミュニティの成員たちの責任となる。オスカルは、外部から来た俺にその責任の一部を負わせないよう、どんなリスクも取らせないように計らっていたのだ。
チチャ・ハイの状態のまま宴の会場を抜け、村の家の床で寝かせてもらい、無事に翌朝を迎えた。どうやら喧嘩は大事に至らず終わったようだ。日焼けで痛む身体に再びむち打ちながらボートに戻る。川が細くなった最後の急流をラファエルの手さばきでなんとか切り抜けると、南中に近づいた太陽が照りつける頃、ついにプーヨの外れにある川岸に到着した。ヤスニ国立公園に面したエクアドル最奥の森から、約200キロのプーヨまでのカヌー旅を、無傷で切り抜けたのだ。
肉体的限界はとっくに越え、気力だけで立っていた。だがそれ以上に、ヤスニで過ごした3日間とクラライ川を横断した3日間は、それ以前にアマゾンの森に対する解像度を着実に高めていた俺の体内に、1週間足らずで再び別次元の認識空間をこじ開けた。それは知的かつ身体的で、感性的な、不可分の直接経験として、俺の研究の方向性を決定づけ、参照点としての土台にもなるだろう。いまや、俺がどんな他のアマゾン内の別の土地を訪れても、この経験を抜きにして何かを思考することはあり得ない。
久しぶりにアスファルトの上に立っている感覚が、なんだかこの世のものではないように感じる。気を抜いていても足元がぐらつかないことに、もはや身体が慣れていないのだ。「アキミ、俺は今から友達のところに行って、薬を買う。君はどうするんだ?」とオスカルが聞く。「俺は街の方に行って、まず宿を探すよ」「そうか。じゃあ、また俺たちのためになりそうなプロジェクトがあったら連絡してくれよ。またな」オスカルとラファエルは俺と軽い握手を交わすと、クララと一緒に道路を歩いていく。俺の身体から立ち込める匂いも、服や身体にこびり付いたチチャと泥も、あたりを眺める視線も、もはや以前のものではなかった。何かが決定的に、俺の身体図式を変えてしまったのだ。軋む身体と日焼けで痛む肌を捻じるように荷物を引きずりながら、行きつけの宿を目指す。次の目的地がこれ以上に明確になったことはない。セバスティアンがいるケンクイム村に、残りのフィールドワークを捧げる準備が整った。
1. Bass MS, Finer M, Jenkins CN, Kreft H, Cisneros-Heredia DF, McCracken SF, Pitman NC, English PH, Swing K, Villa G, Di Fiore A, Voigt CC, Kunz TH. Global conservation significance of Ecuador's Yasuní National Park. PLoS One. 2010 Jan 19; 5(1): e8767, p. 5.