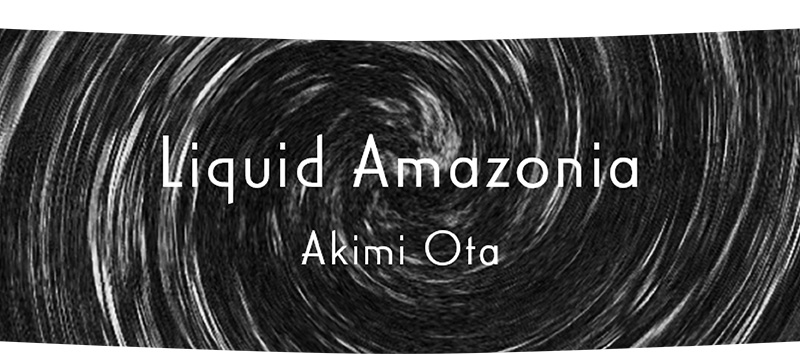「決めた。君の名前は今からナンキだ」。村の男たち数人がセバスティアンの家に集まっていた。特別な用事のために訪ねたわけではなさそうだったが、俺が今からこの村に住むことを知ると、セバスティアンの提案によりチチャを飲み交わしながら俺のシュアール名をあれこれ考えていた。かかった時間はものの数分だった。「ナンキ」はシュアール語で「槍」を意味する。まだ数単語しか理解できない俺でもすでに知っているほど、シュアールにとって欠かすことができない言葉だ。
「僕たちで今話しあった結果、君に合う名前は『ナンキ』だということになった。なぜか。君を見ていると、まるで槍のような身体をしている。細くて、長いだろう?」そう言うと、セバスティアンは周りの男たちに目配せし、皆クスクスと笑った。「だがな、よく聞けナンキ。この名前は、僕たちシュアールにとって最も重要な名前なんだ。槍は僕たちにとって敵を倒すための武器。この名前は、最強の戦士になることを願って子どもに付けられる。誰もが付けていい名前じゃないんだ。君は細い身体をしている。見た目は強そうではない。だけどこんなに遠いアマゾンまでたった1人でやってくる勇気を持っている。つまり、君はとても強いということだ。だから『ナンキ』という名前がふさわしい」。このときから、俺は「アキミ」ではなく、「ナンキ」になった。まるで生まれたてのシュアールの子どものように、村や森に漂う粒子の一粒一粒をスポンジのように吸収する日々が始まった。
ヤスニ国立公園からプーヨに戻ったあと、俺はすぐさまスリティアクに連絡し、セバスティアンとパストーラの住むケンクイム村で残りのフィールドワーク期間を過ごしたいという意思を伝えた。受け入れのお願いをするため、再び村まで同行してほしいとも。ケンクイム村に戻ってくると、ちょうどセバスティアンは小雨の中、森に行っている最中だった。焚き火に当たりながらしばらく帰りを待っていると、「トゥラシャ!」と後ろからセバスティアンの声がした。濡れたTシャツを脱いで煙にかざすと、「男は焚き火の煙を纏わないといけない」とセバスティアンは一言呟いた。
チンビ(1本の木から切り出した椅子)に座り、セバスティアンと膝を突き合わせると、改めて1年間この村に住みたいという自分の意向を彼に直接伝えた。「いいだろう」。セバスティアンは数秒の間を置いたあと、何かを飲み込んだように答えた。何か決定までのステップがあるかもしれないと思っていたが、思いの外すんなりと了承を得ることができたようだ。これまでも、この村に外部の人間が数ヶ月滞在したことは何度かあったが、1年間という長期滞在は初めての事例だという。
セバスティアンとパストーラの寝床の隣にスペースをもらい、蚊やコウモリを避けるため、スリティアクから借りたテントを張って寝泊まりすることになった。寝室は仕切りがなく、着替えの洋服や自作の槍数本、わずかな書類や印刷された記念写真などを除いて物もほとんど置かれていない。棚や箱など、収納家具は一つもなかった。彼らの家は当時屋根の張り替え作業中で、屋根に穴が空いており、さらに季節は雨季だった。天井がなく、屋根まで吹き抜けの構造のため、ほとんど常に2階の床は濡れた状態となる。雨が直接当たらない場所にスーツケースやバックパックを置くが、洗濯物は1週間経っても乾かず、毎日蚊やその他の虫に食われた傷が増えていく身体は治りづらい。
極度の湿気のためか、夜には必ずと言っていいほどテントの中にゴキブリがひそんでいる。ゴキブリは「得意」ではないが、生活するうちに慣れ、何とも思わなくなった。それに、アマゾンで出会うゴキブリたちには不思議と不潔感がない。都市では下水道や生ゴミ、食べ残しなど、ゴキブリが繁殖している環境に対する想像力が瞬時に動員されることが、この古の昆虫に対する潜在的忌避感を過剰に増幅させている。ここアマゾンの村では、水は土を伝って川に流れ、生ゴミや食べ残しは鶏や豚といった放し飼いの家畜や犬が貪るか、生活の邪魔にならない任意の場所に無造作に投げ捨てられるうちに土で分解される。トイレは存在しないため、村人たちは毎回異なるスポットを見つけ、茂みに隠れて野糞をする。つまり、一箇所に大量の糞尿が溜められるのではなく、ミクロレベルでの生分解が偏在的かつ迅速に行われている。あらゆるライフラインはオープンな状態であり、ゴキブリがどこか不潔な「暗部」で増殖しているという不気味さが存在しないのだ。また、ゴキブリは鶏たちの栄養豊富な餌であり、ときには人間の風邪を治すための薬を煮出すためにも使われる。ゴキブリはアマゾンの森の生態系の重要な一員として存在している。
早朝、まだ日が昇らない時間に、セバスティアンとスリティアクとともにワユサの儀式を行った。ワユサは同名の木から取れる葉っぱで、シュアールたちが胃の洗浄に使う。都市部ではお茶っ葉として使用されることもあるが、シュアールにはお茶を日常的に飲む習慣はなく、ワユサはあくまで身体を浄化するためのものだ。大きなココナッツをくり抜いて作られたお椀に、大量のワユサの葉を煮出したお湯を満杯になるまで注ぐ。それを2杯ほど飲んで、吐瀉することで、胃を洗浄するのだ。セバスティアンによれば、あらゆる病気のサインはまず胃の不調に表れる。それは魔術による攻撃を受けた場合に最初にダメージを感じる内臓器官でもある。だからこそ、頻繁にワユサの儀式を行うことで、胃の状態を保つことが重要なのだ。
「お茶をたくさん飲んで吐き出す」とは言うものの、最初は量を飲んだところで意図的に嘔吐できるものだろうかと疑問だった。「ナンキ、見てな。こうやって吐き出すんだ」。スリティアクがまず手本を見せてくれるというので、観察する。傾斜になっている地面の上の方に立ち、お椀を2杯一気に飲み干した。すると「ウゥッ、ウゥッ」と小さな声とともに上体が揺れるように動き出す。次の瞬間、「ウオェェェ」と勢いよくスリティアクの口から透明な液体がたっぷりと噴き出した。早朝のため、胃の中に固形物はなく、今飲んだワユサのお茶がそのまま吐き出されたようだ。液体は、傾斜の下の方に流れていく。
「これで私のお腹はきれいになった。さあ、ナンキもやってみな」。さっぱりとした表情のスリティアクが言う。確かに、飲み干してから吐くまでの流れが淀みない。スリティアクが立っていた地点から少しずらして位置に着くと、俺もお椀を2杯一気に飲み干した。すると、胃の中にギュッと詰まった苦みが充満し、急激な吐き気を催した。そのまま勢いよく嘔吐すると、ワユサのお茶がドバドバと地面を伝っていく。お茶と胃液と一緒に、腹の奥から不純物がえぐり取られるような感覚で、吐いたあと吐き気はすぐに消え、心地よいほのかな疲労感とともに妙にすっきりとした感覚を得た。
「嘔吐」は、欧米あるいは日本などの社会通念においては、身体の不調による危険信号として認識される。それは、能動的に求める身体の反応ではなく、また嘔吐したからといってそれが「浄化」と結びつけられるわけではない。しかし、シュアールにとって「嘔吐」はときに準備を伴い能動的に求められる身体現象であり、それは何よりもまず身体の浄化と結びついている。もしかしたら、キチュアのオスカルがクラライ川沿いの村々を訪ねて大量のチチャを飲みながら嘔吐を繰り返していたのも、彼にとってそれが身体に害を与えるものではなく、ある種の浄化を意味していたからでもあるのかもしれない。
シュアールの人々が繰り返し語るのは、「チチャは飲み物でもあり、食べ物でもあり、薬でもある」ということだ。「アパッチ(メスティーソ)たちは、チチャを飲んだあとお腹がゴロゴロすると、すぐに『バクテリアに殺される』と怯える。全くそんなことはない。チチャでお腹がゴロゴロするのは、チチャが持つエネルギーがお腹をきれいにしているからだ。それは恐れることじゃなく、むしろ身体にいいことなんだよ」とセバスティアンは言う。胃を「変性」させる苦みや違和感をあえて取り込むことで、ワユサやチチャに身体を洗浄させる。物質の流れの途上にある自らの身体は、常に「何も感じない」状態を目指すものではない。それは、諸々の物質との絶え間ない交渉の中で、揺れ動きながら維持される生命の経験装置なのだ。
物質=substanceを取り込み、あえて身体感覚を変性させ、体液とともに吐き出すことで浄化する行為は、他にもシュアールの生活の中で様々な場面に見られる。最も頻繁に見られるのは、森に自生しているタバコの葉を水に浸して出す液体を鼻から吸い込み、喉の手前で止め、再び鼻から吐き出す実践だ。ケンクイム村での定住を始めてから数日も経たない頃、まだ一緒にセバスティアンたちの家に滞在していたスリティアクが嬉々としてタバコの葉を村人からもらってきた。「セバスティアン、ナンキ! タバコを手に入れたよ!」興奮した様子のスリティアクを見て、てっきり乾燥させてから葉巻にして吸うものかと思っていた俺は、緑色の生葉を水に浸して液を絞り出し始めた彼女を見て不思議だった。
掌を少し閉じて中央に窪みを作り、茶色く濁ったタバコの葉の液を貯めると、鼻の穴をそこに当て、ジュルジュル、ジュルジュル、とゆっくり吸い込む。喉に入らないよう慎重に手前で止めると、鼻をつまんで思い切り鼻水と一緒に地面に向けて吐き出した。タバコの葉の強烈な刺激により、みるみる鼻水が噴き出してくる。どんなに風邪を引いていても、1回の鼻かみでは出ないような量の鼻水だ。
「フェェェェェイ」と唸るような声を出しながらスリティアクが顔を上げると、異常に辛いワサビを間違えて食べてしまったときのような、薄ら赤い表情をしている。「これはすごく身体に良い。鼻の中が全部洗われて、病気のもとも消えた。タバコが全て殺してくれるんだ」。スリティアクが言った。「それにね、こうやってタバコの液を吸うと、良い夢が見れるんだ。タバコはアヤワスカやマイキュアと同じように、ヴィジョンをくれる植物だから」。タバコの葉で鼻を洗うことと、それによる酩酊、そしてその日の夜に見るヴィジョンは、一繫がりのプロセスなのだ。
俺もタバコのエキスを掌で受け取り、鼻から吸い込んでみる。左右の鼻の穴を順番に水面に浸すのが、上手く吸い込むコツだ。タバコの生葉のツンとする豊かな香りが鼻腔を通る。慣れていないので少しだけ液が喉側に行ってしまったが、しばらく鼻の奥で止めてから、フンッ! と吐き出す。3回、4回、5回と、何度も大量の鼻水が出てくる。それが収まると、確かにほんのりクラっとするが、むしろ感覚が研ぎ澄まされたようにも感じた。そして、その夜に見た夢は確かに強烈だった。内容自体というよりは、夢の中で感じる「肌触り」に、普段よりも濃密なテクスチャーが加わったという感じだった。
タバコの葉は森に自生しているが、大抵は村人の誰かが「フィンカ」と呼ばれるそれぞれの世帯に割り当てられた森の区画内に持っている。セバスティアンはタバコの葉を持っていなかったが、同じ村に住むお兄さんのゴンサロは持っていた。このように、村の誰かから分けてもらうなどしてタバコの葉が手に入ったとき、人々も俺も、我先にと鼻からエキスを吸い込み、吐き出すのが村の日常だ。
数日をケンクイム村で過ごしたスリティアクがバーニョスに帰る前日の夜、寝床に着いて2人で話していた。「アマゾンは自由だ。都会と違う。都会は不自由だ」とスリティアクが言った。それまで聞いたことがない発想だった。高度資本主義社会では、人々は田舎の不自由を嘆き、自由を求めて都会に流れていく。それが自明のナラティヴであるかのように語られる。アマゾンが自由で、都会が不自由というのは、そのヘゲモニーに反している。そして、スリティアクが言う「自由」は、必ずしも金銭や法律、社会的ヒエラルキーの問題のみに依拠しているとは思えなかった。そこには何か、この世界を満たしている物質や諸々の生命、あるいは精霊たちとの深い交流への渇望が感じられる。
「ナンキ、私は他の人と違って、日本が中国と違うということをわかってる」とスリティアクは話題を切り出した。「日本には、盆栽があるだろ? 小さい器にすごい小さい木が植えられてるやつ。前にキトで盆栽のイベントを見たことがあって、そのときに感動したんだ。あれは日本の文化だよな?」アマゾンの先住民の中で、盆栽のことを知っている人はどれだけいるだろうか。改めて、スリティアクのアンテナの広さには驚かされる。
しかし、次にスリティアクが言ったことにはもっと驚かされた。「前に恋人にお願いしたことがあるんだ。プレゼントで盆栽がほしいって。盆栽をもらったら、その木を器から抜いて広い土地に植え替えて、どこまで伸び続けるか見てみたいって。盆栽に入った小さな木を見ると、『この木はどこまで成長してくれるんだろう』って、すごくワクワクするんだ。でもね、そう言ったら恋人は『なんてことを言うんだ! そんなことのためになんで大金を払って盆栽を買わないといけないんだ』って、怒った。彼には私が言ってることの意味がわからないんだ」。盆栽を鉢から解放し、広い土地に植えて成長を見届ける。そのポテンシャルを想像することで、喜びを得る。そんな発想に今まで出会ったことはなかった。「恋人は花束をくれようとする。でも私は大嫌いだ。切って集められた花なんて、死体と同じ。まるで自分が腕を切られたように感じる」。スリティアクは続ける。
キト在住の白人ビジネスマンであるスリティアクの恋人からすれば、作家がせっかく丁寧に手入れをした盆栽に対してそんなことをするのは言語道断なのだろう。だが、スリティアクが「ワクワクする」のも、今の俺には腑に落ちる。彼女はこの世界に息づく諸存在がそれぞれのあり方で生長し、拡張し、流動し、巡ること、その運動やエネルギーを全身で感じることこそに、生の充実を見出している。それは、異種間における互酬性と伝達可能性を基盤として生きている彼女にとっての「自由」の概念とも根底で接続する態度である。盆栽から土に移された木が、今まで感じていた窮屈さや生きづらさから解放され、広い世界で自らのポテンシャルを最大限に発揮しようと生命力を発露させるとき、スリティアクはその植物の意志を痛烈に感じるのだ。だからこそ、彼女は盆栽を見るとワクワクする。その木が持つ未知なる力に思いを馳せる。
「マイキュアを飲むと、虫や植物と話せるんだ。ナンキだってもうアマゾンに慣れてきたし、わかるだろ? 虫も植物も動物も、自分たちの考えがある。マイキュアを飲んでヴィジョンを得れば、彼らが何を思っているのか、何を感じているのか、わかるようになるんだ。アパッチたちはそんなことあり得ないって言うけど、私たちにとっては当たり前の真実だ。私は子供の頃にいたずらをして家を火事で燃やしちゃってね、怒り狂ったお父さんにマイキュアを飲まされたんだ。これで反省しろって。普通よりも早い年齢だったけど、そのおかげでたくさんヴィジョンを得たよ。それでね……」。スリティアクとの会話がとめどなく続き、やがて俺たちは眠りについた。
「これがサングレ・デ・ドラゴだ。とても良い薬で、色んな力がある。癌、糖尿病、下痢、咳風邪や喘息、何にでも効く。肌に塗っても、身体が良くなるんだ」。セバスティアンが言う。俺たちは家の横にあるセバスティアンの薬草園の端っこにある「ドラゴの木」の側に立っている。この木から出る樹液は赤く、血のように見えるため、「サングレ=血」と呼ぶのだ。「でもね、飲む量は考えないといけない。サングレ・デ・ドラゴはとても強力な薬だが、飲み過ぎると毒になる。女性だったら、不妊になってしまうんだ」。20メートル前後はある長い木の幹には、刃物で切り刻まれた無数の跡があった。古い傷と新しい傷が混ざり合うその木肌から、長い年月にわたり村人たちに頼られてきたこの木の過去が垣間見える。
ケンクイム村での生活は、予想していたよりも目まぐるしい。毎日様々なことが起きる。全ての出来事や見聞きすることが研究に繫がっているのはもちろんだが、興味があることや聞きたいこと、行きたい場所のみに常に触れられるわけではない。村には村のリズムが、セバスティアンとパストーラには彼らのリズムがある。それらに身を預けながら、波を乗りこなすように、砂に埋もれた美しい貝殻を拾い上げるように研究を進めていく必要がある。セバスティアンと薬草や樹液についての対話を重ねるのは、この漸進的で雑然とした過程の中にある貴重な瞬間の一つだ。
毎朝6時から7時くらいに、「ナンキー! 食べにおいで!」という離れの方から聞こえるパストーラの声で起きる生活が始まって、もう何週間も経つ。キャッサバやパパチーナ、プラタノなどチャクラから採れる作物を茹でたり蒸したりしたものと、「チチャ・ドゥルセ」と呼ばれる一晩だけ発酵させた少し甘みのある口嚙み酒をいただくことから、大抵の一日は始まる。起きたらまずやるのは、薪を探すこと。家を出て村の中心につながる小道を歩いていくと、途中の左側に倒れた木々が折り重なっている場所がある。そこで乾いている薪を見極め、なるべく大きな丸太を肩に担いで持ち帰る。薪をストックして保管するための収納はないため、前日に土砂降りの雨が降っていても毎朝のように薪を探しにいく。
晴れた日に大量の薪を集めておいて、雨に濡れない場所にストックすればいいのに、と思うだろうか。「非効率だ」と思うだろうか。だが、この毎日の薪探しは誰かが薪を独り占めしないための知恵でもあり、そもそも大量保管は彼らにとって必要のないことである。どんなに濡れていて使い物にならないように見える木々の山からも、彼らは「乾いている」薪を見つけることができるからだ。「ほら、触ってみな。これは乾いている木。そしてこっちは湿っている木だ。わかるか?」まだ村での生活を初歩から学んでいる時期に、セバスティアンに連れられて一緒に薪探しをしていると、彼は言った。並べられた2つの木の、木肌が剝がれた部分にそっと手を当ててみる。どちらもしっとりと湿っていて、どちらかが乾いていることなど見抜けない。前日には雨が降っていたのだから、どちらも濡れているのではないか。
「表面が濡れていても、中身まで濡れているとは限らない。木によるんだよ。木には湿りやすい木と乾きやすい木がある。まずは何の木なのか見ないといけない。どのくらい湿っているのかで匂いも触り心地も変わる。木がどれくらい硬いか、柔らかいか。それも違う。温かさも違う。触ったときに、奥の方までどうなっているか感じるんだ。集中して調べると、全ての木が違うのがわかる」。そう言うと、セバスティアンは「乾いている」方の丸太を担ぎ、持ち帰った。斧で砕き、マッチで火を焚くと、確かに炎が燃え上がった。村人たちのように百発百中で乾いた薪を感知できるわけではないが、森で過ごす時間が延びていくにつれ、確実に俺の判断の精度は上がってきていた。
セバスティアンは、口癖のように「集中する」という言葉を使う。「何か作業をするとき、何かを調べるとき、何かを考えるとき、いつも集中しないといけない。集中することで、良い仕事ができるし、前に進むことができる。強くなれる」。シュアール語では、「集中する」は「enentaimsatin」と言う。「Enentai」とは、「心」を意味し、「anent」と呼ばれるシュアールの人々がチャクラに種を植える際や戦争に向かう前に歌う種々の魔術歌1と語源を同じくする。この「enentaimsatin」という言葉は、セバスティアンたちとのフィールドワークの中で、自らの身体を通して物事の「真実」に到達するための彼らの一連の技術と態度を観察するための重要な語句となっていく。
ところで、ケンムイム村での定住開始後、俺は本格的にシュアール語を学び始めた。前述の通り、アマゾン熱帯雨林のどの民族について研究するのかを敢えて事前に決めていなかった俺は、エクアドル渡航前にシュアール語に触れていなかった。エクアドルで話されている先住民言語の中で、世界的に最も浸透し、国外で唯一体系的な教育が行われているのはインカ帝国の言語であるケチュア語だ。インカ文明の遺跡とされるマチュピチュや帝国の古都クスコが存在するペルーのみならず、インカ文明圏はその最盛期においては現代のエクアドル、ボリビア、コロンビア、チリなどにまで及んでいた。エクアドルの先住民について何か手がかりが摑めるかもしれないという想いで、俺はパリで博士課程に向けた研究計画を書きながら INALCO(国立東洋言語文化学院)で1年間だけケチュア語を学んだ。
しかし、ケチュア語とシュアール語は、語族からして全く異なり、互いにコミュニケーションが成立しない関係にある。また、シュアール語はヒバロ語族に属し、隣接するアチュアール語、ワンピス語、アワフン語、シビアル語などと語彙や文法の面で多くを共有するものの、言語学的に未知な部分が大きく、第二言語としての体系的教育は未だ確立されていない。単語集などはいくつか刊行されているものの、古いものが多く、しかも結果的には実際にシュアールの人々から教えてもらう内容とは多くの相違点があり使い物にならないことがあった。したがって、俺はスペイン語を仲介言語として主にセバスティアンから直接シュアール語を学ぶこととなった。
元々語学が得意で、すでに日本語を含め5言語を流暢に操っていた俺はスペイン語を間に挟めることもあり、比較的スムーズにシュアール語を習得できると予想していた。だが、俺の自信は見事に打ち砕かれることになる。第一に、スペイン語への根本的な翻訳不可能性により、説明ができない事項が数多く存在する。それ自体に驚きはない。しかし、一度意味を教えられたはずの語彙や、スペイン語との互換性を確認できたはずのフレーズについて、別の機会では全く異なる意味を説明されたり、初めて聞く対応文を新たに教えられることが頻繁に起きることで、シュアール語の知識が積み上がっていくイメージを描くのは困難を極め、雲を摑むような感覚だった。今までは、3ヶ月も過ごせばその土地で話されている言語で日常会話が十分できる状態に持っていくことができた。シュアール語は、そのケースから外れた初めての言語だと認めざるを得ない。
しかし、だからこそ俺は能力的かつ時間的限界の中で、可能な限りシュアール語を身に付ける努力をした。流暢に話すことができずとも、シュアール語特有の概念や言い回し、語彙、そしてリズムに触れ続け、何より求め続けることで、森のエロコジーと深く結びつきながら発達してきたこの言語とともに生きる彼らの、宇宙の内奥に迫りたかった。
その一方で、もう一つ心に留めておきたいのは、現代のシュアールたちは、スペイン語やそこから派生する一連の言説体系から深い影響を受けているという否定できない事実である。村の外との接触をほとんど持ってこなかった高齢者(特に女性)などを除き、今では大部分の人々はスペイン語を解し、話す。15歳以下に限ると、むしろシュアール語が話せない子供たちも驚くほど多い。
例えば、スペイン語で「自然」を意味する「naturaleza」には、シュアール語の直接的翻訳が存在しない。「野生の森」は「ikiam」、「川」は「entsa」と言うように、自分たちが住む環境内に存在する個別の自然的要素に言及することはできるが、それらを抽象化した「自然」という大きな概念を持たない。だが、先述したように、現代のシュアールたちは、スリティアクも、アルベルトも、セバスティアンも、声高に「自然=naturaleza」に対する愛を語ることを厭わない。また、「化学的な=químico」物と「自然な=natural」物を分け、後者に絶対的価値と優位性を見ている。つまり、「自然」という概念は、すでに彼らの世界観や価値観、あるいは行動指針を形作る一要素になっており、それを「彼ら独自の概念ではない」という理由で考慮から外すことはもはや妥当ではない。
それが最も差し迫った形で表れているのは、現代のシュアールや他の先住民族の人々が示す、スペイン語による法律言語への執着である。タクシーで意図せず行き着いてしまった先住民のリーダーたちによる秘密会議や、その後の機動隊による制圧、記者会見を見ても痛切に感じたのは、彼らが「環境=medio ambiente」、「持続可能な=sustentable」、「権利=derecho」、「搾取=explotación」など、先住民言語に直訳が存在しない語彙を用い、それらを反論の余地が生まれないように硬質なスペイン語文語体に落とし込むことで、自らの存在とその正当性を森の外部に突きつけようとする覚悟と技術だ。
確かに、歴史的にはその状況は彼らが望んだものではないかもしれない。しかし、彼らが切実に参入し流用しているスペイン語の概念を彼らの言説から捨象するのは、彼らの生身の現存在としての多面性や政治的意志、社会的現実に否応なく巣食う布置=dispositifとの折衝を通したある種の未来への希求を否定する点において、新たな言説的、認識論的暴力でしかない。
これをはっきりと主張できるのは、俺の第一言語である日本語自体が、西洋言語との邂逅によって現代語として大きく姿を変えた歴史を持つからである。ほかでもない「自然」という語句は、19世紀末にヨーロッパから輸入された「nature」を森鷗外が訳し、定着したものだ。今では「自然」と言うとき、日本語話者の脳内には抽象化された概念が浮かび、それは科学や政治、知的言論においても使用されている。もちろん、日本における自然観の特殊性について論じることは可能だ。しかし、「自然」という概念は本来の日本人のものではないという理由で、この概念への日本語話者の参入や理解可能性=intelligibilityを外部から阻むような言説は、西洋中心主義的暴力以外の何物でもない。
フィリップ・デスコラが『自然と文化を越えて』の中で「シゼンとは、人間の行動から独立した諸現象の圏域という発想を意味するのではない。なぜなら、日本の思想では、自然の意識的客体化、あるいはそれを取り巻く一切からの人間性の撤退はあり得ないからである2」と書くとき、我々は細心の注意を払わなければならない。シゼンという単語の意味を「nature」とは相容れないものとして捉えること、あるいは「西洋でnatureが持つ諸々の意味のたった一つの側面しか表現しない3」と断定することは、言語的マルチチュードを称揚することで世界を脱中心化しているように見える一方で、どっしりと中心に根を下ろした「西洋」の周縁にシゼンという概念をソフトタッチで配置し、そのヒエラルキーを結局のところ再度強化する言説に過ぎないからだ。
シュアール語は、大別すると膠着語的性質を持ち、日本語やトルコ語、モンゴル語、あるいはフィンランド語などのウラル語族、タミル語などドラヴィダ語族、そして多くのネイティヴ・アメリカン言語などと同様に、助詞や接辞が単語に連なることで文が構成されていく。例えば、「私の名前はナンキです」と言う場合、「私」を意味する「Wi」に「の」を意味する「nia」がくっつくことで「私の=Winia」ができる。また、「名前」を意味する「nar」に「は」を意味する「ka」が接続することで「名前は=narka」、「ナンキ」に「である」を意味する「ti」が繫がることで「Nanki ti」となる。すると「Winia narka Nanki ti」という、文法的に日本語と同じ構造の文が出来上がる。
手探りでシュアール語を学びながらまず驚いたのは、このように日本語と非常に近い語順と助詞・接辞の使用が一部見られることだった。「元気」を意味する「Penker」に「kai」を繫げることで「Penker kai?=元気かい?」の意味になることを知ったときは、「カイ」という疑問詞が日本語と全く同じだということに驚愕した。しかし、同時に大きな障壁ともなったのが、助詞・接辞が日本語と同様の機能を持つケースは一部のみであり、多くの接尾語類は日本語にそのまま置き換えられない意味を持っていたことだった。そして、様々なパターンに変化するこれらの語句のスペイン語や英語への変換は、日本語よりもさらに困難を極める。
言語学的ロジック自体を自ら紡ぎながら学ばなければならない状況に苦しみつつも、俺はもがきながら地べたを這うようにシュアール語を少しずつ学んでいき、最終的にはシュアール語とスペイン語をハイブリッドで使用しながらコミュニケーションを取るようになった。本書におけるシュアールの人々との会話は、何か特別な意味が込められているか、文脈上の説明が必要でない限り、シュアール語とスペイン語の会話を細かく区別しないで記載している。
「ここは二次林だ。なぜかわかるか? あの木を見ろ。あれはバルサという。それとあの木、あれはワルンボだ。あの2つの木は、他と比べて成長が早い。森を切り開いてチャクラを作ったりすると、その辺りの木は全て倒す。チャクラをしばらく使ったあと場所を変えると、すぐに大きくなって辺りを覆うのはあの2つの木だ。だからここのようにバルサとワルンボがたくさんある場所は、二次林なんだ」。森の中をセバスティアンと歩きながら、彼の言葉に耳を傾けていた。
セバスティアンは、原生林=selva primariaと二次林=selva secundariaを区別し、前者に最上の価値を置いている。「原生林というのは、先祖たちも含めて一度も切り開いたことがない森だ。もちろん、木の1本や2本を切って使ったり、植物や果物を取ったり、人が何かしたことはあるかもしれない。でもまっさらに切り開かれてチャクラとして使われたりしたことはない」。「原生林」という概念は、数世紀にわたって南米征服以前のアマゾン熱帯雨林を想像する際に与えられてきた「手つかずの自然」というイメージに反して、近年の考古学的発見を踏まえ再考されつつある4。しかし、セバスティアンをはじめ現地に住む先住民の人々にとっては日常的に使用される概念であり、彼らに正当性がないとも言えない。ティム・インゴルドが述べるように、環境の知覚とは「関与すること」の連続的な実践に埋め込まれる「感覚のエコロジー」であり、自然科学と文化的ロジックを分離した状態では捉えきれない諸相だからだ5。「原生林」とは、リトマス紙のように二分される色の片方なのではなく、スペクトラムとしての森の内部において、活動する主体によって身体化される経験なのである。
「僕のフィンカの中に、原生林がある。今からそこに行こう」。起伏の激しい森の中に一本だけ続く小道を、セバスティアンのあとに付いて進んでいく。マチェーテの使い方はもう覚えた。村人たちのようにあらゆるものをマチェーテ1本で捌けるようになるにはまだ時間がかかるが、森の中で藪を切り分けたり、求めるものをマチェーテで切り取ったり、薪を整えたり、生活に必要な最低限のことはできるようになった。
セバスティアンが足を止める。木の前に立って、しんみりとした様子で上を見上げている。「この木はサンディという。この樹液はとても、とても良い薬だ」。セバスティアンが語り始めた。何年か前のこと。セバスティアンは胃炎を患い、苦しんでいた。色々な薬草や樹液を試したが、どれも効かなかった。痛みに耐えきれず、こんなことなら手術を受けるしかないと、絶望の中でプーヨの病院に行った。待合室にいると、隣に座っていたキチュアの女性から話しかけられた。どうしたんだい? 胃炎があまりに酷くて手術を受けに来た、と答えた。すると「こんなに弱っているじゃないか。その身体じゃ手術は耐えられないよ。きっと死んでしまう。手術はやめて、サンディという木を探しなさい。あなたの村にもあるでしょう。その樹液は胃炎にとても効く。それを飲めばあなたの胃炎は治る」と彼女に言われた。
「サンディのことは、もちろん知っていた。だけど、それが薬になることは知らなかった。ケンクイムでは、僕たちはみんなサンディを見つけても平気で切り倒し、捨てていたんだ」とセバスティアンは回想する。しかし、その女性の声に従って村に戻り、このサンディのもとへやってきて樹液を手に入れると、1週間毎朝5時に飲み続けた。すると、みるみるうちに体調は回復し、胃炎が治ったという。
「それ以来、ケンクイムではこの木のことを『ドクトール・サンディ』(サンディ先生)と呼ぶ。僕はサンディに命を救ってもらったんだ」。セバスティアンはサンディにそっと抱きつくようにもたれかかると、シュアール語で語りかけ始めた。念仏を唱えるようなボソボソとした語り方ではなく、まるで久しぶりに会った友人に様子を聞くような、快活な身振りと声質だ。「今、サンディに感謝の気持ちを伝えた。あのとき僕を助けてくれてありがとう、とね。それに、今は妻のパストーラも病気でね。僕は分析した結果、彼女にもサンディが効くと思っている。今から、少し樹液をもらおう」。そう言うと、マチェーテでサンディに一つ切り傷を入れ、持っていた竹の筒を木肌に添えた。ジワジワと、真っ白な樹液が出てきた。真っ赤な樹液を持つサングレ・デ・ドラゴとは異なる色だ。一体パストーラの病気とは、どのようなものなのだろうか。
「樹液をもらうときは、こうして手で抱きしめるように触れて、感謝の気持ちを伝えないといけない。そうしないとサンディは治してくれないんだ」。竹の筒に樹液が溜まるのを待ちながら、セバスティアンは言った。セバスティアンにとって、植物から得る薬は、万人に同じ効果を機械的にもたらすものではない。木には木の気持ちがあり、個別の能力がある。それをうまく引き出すのは自分たちであり、そのために進めなければならないプロセスがある。セレーザ・ミラーが述べるように、植物への声掛けによるこのシャーマニックな異種間コミュニケーションは、植物が己の生命力を発露させ、生育し、「成る」ために必要なのである6。そして、それはサントス=グラネロが「信頼空間7」と呼ぶ、アマゾンにおいて親族ネットワーク外部の諸存在と共に創る結託関係の一つの表出でもある。
セバスティアンのフィンカへは、村の中心から歩いて1時間くらいかかる。急な斜面を登ろうとして、土に手をつきながら進んでいると、後ろを振り返ったセバスティアンが言う。「手は土につけない方がいい。蛇がいたら嚙まれるぞ」。確かに、セバスティアンや他の村人たちが森の中を進みながら土に手をつけているところを見たことがない。手をつかずに傾斜を登ろうとすると、下半身の強いバランス力に加えて、足の指先で土を握るように摑む必要がある。長靴を履いているし、もちろん実際に握るわけではない。しかし、意識下では土に足の指を食い込ませるように動かす。
傾斜の上に来ると、今度は下りがある。剝き出しの土だ。中継点として足を置けるような安定した箇所は見当たらない。行けなくはないが、道が細く、左側は崖になっているので踏み外して転がりでもすると危険だ。セバスティアンは先に滑るような軽快さで下に降りていた。上で躊躇っている俺を見ると、「こうやって降りてみろ。こうやって」と、半身の姿勢で足を土に対して斜めの角度で当てるような仕草をした。なるほど、スノーボードと同じように、地面に対して斜めに当てる角度を調節することで滑りやすさをコントロールすればいいのか。それまで俺は、指先に力を込め、踵を上手く使いながらも、下りの場面で足先を正面に向けて土に当てていた。セバスティアンが言うように、足を斜めにし、外側の面を土に当て、腰を少し落として膝に遊びの空間を作る。ゆっくり降りていくと、何事もなく下までたどり着くことができた。
改めて断っておくが、俺はアマゾン熱帯雨林に向かうまでの人生で、野生の自然環境で豊富な経験を積み重ねてきたわけではない。人によっては、上に述べた歩き方について「そんなこと、セバスティアンに言われなくてもわかる」と思うかもしれない。確かにそれには一理ある。しかし、ここで俺が注意を払いたいのは、セバスティアンをはじめとするシュアールの人々が、事物の性質の慎重な観察を積み重ねることで実証的かつ論理的な結論を導き出していると、彼らの言葉に従って何かを実践する際に必ずと言っていいほど感じられるということである。先住民をめぐる言説において未だに支配的なのは、一方に西洋的な理性主義の基にすでに弾き出された科学的事実があり、他方に「非理性的」だが「興味をそそる」先住民たちの実践がある、という暗黙の二項対立であり、両者の間にある「真実」の正当性をめぐる明確なヒエラルキーである。
この二項対立とヒエラルキーは、インゴルドを引用するまでもなく、おそらくこの宇宙が実際には必要としない諸カテゴリーを無意味に前提としている。その意味において、これらを乗り越えるための最適な手段は、単に両者の間のヒエラルキーを転覆することで西洋的理性を否定することではなく、そもそもその両者が純粋な固形物として存在しているという観念自体を脱構築することである。その上でさらに必要なのは、無数にありうべき思考の道筋や実践の作法の間に、緊張や差異を伴いながらも共にアクセス可能な領域、すなわち通約可能性=commensurabilityが存在するという視点を、厳密でありながら主観性の混在を恐れない経験主義的記述によって編み上げることだ。
何度も目の前に現れる傾斜面を越えては降り、俺はセバスティアンに必死に付いていく。しかし、以前も述べたように、この森の中では、進むのが困難なのは傾斜面だけではない。比較的フラットに見える道でも、そこにはあらゆる障害物があり、慣れないままでは視線を常に足元に向けながらでないと進むことができない。こちらに背中を向けているセバスティアンを見ると、彼は真っ直ぐ前に視線を向けながらハイスピードで前進している。一体、どうやってそんなことが可能なのだろうか。「森の中では、常に前を見ていないといけない。下ばかり見ていたら、横から何かが襲ってきても気付けない。上にツルがあったら絡まってしまう。そうだろ?」セバスティアンは言う。「それはわかる。でも足元を見ていないと枝や根っこに引っかかってすぐに転んじゃうよ。一体、どうすればいい?」と俺は聞いた。
そんなこと、考えたこともないぞ?という、頭に浮かんだ言葉がそのまま見えそうな表情をセバスティアンはした。数秒間考えたあと、彼は次のように答えた。「僕は一歩進むたびに、その後の道がどうなっているのかわかっているんだ。足を土につけると、そこには根っこがあったり枝があったりする。土が泥だったり、水溜まりがあったりする。柔らかさ、硬さ、深さ、色々違う。僕は目ではなくて、足で見ているんだ。アマゾンの森を歩くときに、まずわかっておかないといけないのは、目に頼るなということ。目では全部見ることはできない。歩くときには、つま先が一番大事な目だ。それがわかっていれば、夜もライトなしで森を歩ける。先祖たちはそうやって夜も裸足で森を歩いていたし、僕だって長靴は履いているけどライトなんか必要ない」。目でなく、つま先で見る。確かに、つま先が何かに当たったときに意識を集中させると、驚くほど多くの情報を瞬時に身体は得ている。枝にコツンと当たれば、その枝がどれくらいの大きさと長さで、どの方向に向かって伸びているのかわかる。枝分かれが激しいのであればつま先より上にも触れる部分があり、トゲがあればそれもわかる。
視覚至上主義が近代以後の世界のヘゲモニーを握って久しい。物事の状態を最も正確に把握できるのは視覚を通してである、という発想は、嗅覚や触覚、さらには小さな違和感から生まれる直観といった判断基準を疑わしいものとして社会から奪ってきた8。ここアマゾンの森では、「真実」を見極める際の視覚の特権性は相対的に弱まり、代わりに嗅覚や触覚といった感覚が重要度を増す。それは何よりも森の中で生きていくために不可欠な身体の多次元性であり、「歩く」という最も初歩的な動作にも必然的に埋め込まれている。
真っ直ぐ前を見据え、俺はつま先で得られる情報を頼りに次の一歩をどこに向けるかを瞬間的に決断しながら歩き始めた。盛り上がった大木の根っこにつま先が当たった。斜め右方向にある大木から伸びている。根っこの太さや傾斜の度合いについて、確かにつま先の感覚から見当が付くような感覚がある。恐る恐る、足元を一度も見ずに一歩を進める。根っこと根っこの間にある窪みに足が着地した。無事に前側の根っこを乗り越えたのだ。左足を前に運んだあと、次の根っこを右足で越えた。土を踏みしめると、水はけが悪い箇所で泥だった。ソールが数センチは沈む。だが、間接視野では左斜め前方に細長い倒木が縦に2本並んで横たわっているのが見える。そこを足場にすれば、泥に足を取られることなく進める。倒木に乗り、わずかに身体の角度を変えて足裏の広い面積が木を捉えるようにする。するとバランスを崩さずに倒木の上を伝いながら泥を回避できた。だが、その間にも視線は足元ではなく、前を向いている。泥を越えたすぐあとに、今度は膝上の高さまである倒木が道を塞いでいるからだ。歩くペースを一切落とさずに、倒木をまたぐ。つま先で感じる情報を頼りに、次の道筋を反射的に導き出し、身体を連動させていく。今まであまり使ってこなかった脳の部分がほんのりと熱を帯びているような、大人になって久しぶりにパズルで遊んだときに感じるような、心地よいフロウ・ステイトに入っていく。シャカシャカ、シャカシャカ。突然降り出すスコールに備えて毎日着ているゴアテックスのマウンテンパーカーが擦れる音が、鳥や虫たちの鳴き声に混じって森に響く。
球体的視野と複合的な身体感覚の動員によって次の進路の最適解を導き出すことに慣れ、森の中を立ち止まらずに進めるようになりつつあった。しかし、セバスティアンはそれ以上の速さで進んでいる。おそらく、これでも俺に合わせてスピードを落としてくれているし、時折立ち止まって俺を待ってくれることすらある。シュアールの人々の歩行を観察し、模倣することでわかるのは、彼らが最も効率的で、最も速い経路を求め、それを瞬時に割り出しているということだ。
サッカーではよく、走る速度やパスやシュートの速さ、あるいはフェイントの動きの機敏さなどとは別に、「プレースピード」が重視される。それは、22人のプレイヤーたちがフィールドに入り乱れるカオス的状況下において、次に行う最適な一手は何かを把握し、実行する速さである。足が遅くとも、身体のキレがなくとも、キック力が欠けていても、「プレースピード」によってゲームを支配することができる。その能力に長けた存在としての最たる例は、世界的には例えばシャビ・エルナンデス、日本人ならば遠藤保仁であろう。森の中のセバスティアンは、その意味で並外れて速く、合理的で効果的だった。
セバスティアンがピタッと立ち止まった。何やら横の茂みを見ている。足を踏み入れると、そこにある植物の実がなっている薄緑色の部分を切り取った。「見ろ、これはヤウンという。とても良い匂いがするんだ。僕たちは、祭りのときや別の村を訪ねるとき、この植物の匂いを身体につける。今、これを粉にして保存できる方法がないか、考えているところさ」。一部をすり潰したものの匂いを嗅がせてもらうと、ふんわりと甘く、それでいてしつこさのない爽やかな香りが鼻を通り抜けた。セバスティアンは、そこに生えていたヤウンを何本か摘むと、その場にあった葉にくるんでジーンズのポケットに入れた。
シュアールの人々が「速く、効率的な」経路を求めている、と述べるとき、「何のために?」と同時に問わなければ、我々はすぐに新自由主義的な速さへの渇望と、それに対抗するスロー・ムーヴメントが織り成す二項対立に絡め取られてしまうだろう。速く効率的であることは、企業的態度を個々人に対して刷り込む新自由主義的社会において度々「目的を限定する」ことを強いる。非目的論的行動は非効率性や遅さと同義であり、それはより生産的な生活を営むために避けなければならない。他方、スロー・ムーヴメントでは、それらこそがより豊かな心身の充実に繫がると主張される。速さと効率性を求めることは、一方からは正しく、他方からは間違っていることだとされ、それらに紐づく様々な価値の体系が、根こそぎこの一面的対立の犠牲となっている。
しかし、速さと効率性を求めるシュアールの人々にとって、森を歩くことの目的は一つではなく、身体のアンテナは常に全方位に開かれている。「原生林に一緒に行く」という大枠の目的の中で、最も速い経路を歩きながらも、茂みに隠れたヤウンの匂いに敏感に反応し、摘み取ったセバスティアンの行動から知覚できるのは、彼の目的は単に複数的なのではなく、目的そのものが森との多次元的関わりの過程で、創発的に現出するということだ。それらが分散することも、一繋がりになることも、実行されることもされないこともあり得るが、少なくとも言えるのは、彼にとって「速さと効率性を求めること」は、目的の可変性と矛盾するものではないということである。
インゴルドとヴァーガンストが述べるように、歩行とはそれ自体が知の方法である9。それは、ある種の社会的活動であり、同時に歩行の調整を通して紡がれる社会的関係は、人間や動物、その他の諸存在との分断を横から切り崩す10。インゴルドが別の場で主張するように、それは「すでに完結した諸存在のある地点から別の地点への時空間的移動」なのではなく、「環境の只中における実質的形成が織り成す運動11」であり、瞬間ごとの生成による絶え間ないプロセスなのだ。
「さあ、僕のフィンカに着いたぞ。もう少しだけ行けば、原生林がある」。セバスティアンが言った。時計は身に着けていなかったが、1時間と数十分くらいかかっただろう。もう森を歩くことには慣れていたが、一休みしたくなるくらいには疲れていた。辺りを見渡すと、オリートの木が一面に並んでいる。セバスティアンたちの家の近くにあるチャクラには主にキャッサバやパパチーナなどの芋類が植えられているが、こちらにはバナナ類が植えられているようだ。そこから少し進むと、チャクラでもなく、かといって荒々しく木々が生い茂る森でもない、曖昧な空間が現れた。倒木を見つけると、俺は休むためにマチェーテを地面に差し、木に座った。
俺を横目にセバスティアンはその空間の中心あたりの位置まで進み立ち止まると、目をつぶった。耳を澄ませているようだ。自分たちが歩行を止めると、アマゾンのサウンドスケープがたちまち空間を浸す。複数の異なる種の鳥たちが、それぞれの声で鳴いている。30メートル以上はありそうな長い木の上の方から、誰かを呼びかけるような透き通った鳥の声が響く。
セバスティアンが何をしているのか気になった俺は、倒木から腰を上げて彼のもとまで行った。俺に気づくと、「ナンキ、僕はここに立って鳥たちの声を聴くのが好きだ」と、セバスティアンは語り始めた。「実は僕は、昔この原生林を切り崩していた。村にやってくるディーラーたちに木材として木を売っていたんだ。子供たちが学校で必要なお金を稼ぐために。木を切り倒したあと、そこに草を植えて、牛を飼い始めた。他の村人たちのようにね。僕はたくさんの木を倒し、牛が生きやすいよう、森が元に戻らないように一生懸命草を手入れしていた。でも、ちょうどその頃、アルコールを1日中飲んで常に酔っ払っているようになった。自分でも飲みたくなかったのに、どうしても飲むことをやめられなくなったんだ。木材を売ると、1回で何百ドルか手に入る。もちろん子供たちのために使うけど、一部は自分がウアンボーヤまで出てトラゴ・デ・カーニャを飲んだりするために使った。本当のところは、何かがおかしいとわかっていた。パストーラは『子供たちのために頑張って働いて』といつも僕に言っていた。それに僕は従った。でも実際は、自分がとても悲しいということを知っていた。ある日、いつものように木を切って牛たちの世話をしにここに来ると、気づいたんだ。鳥たちの声が全く聞こえなくなっているということに。彼らが止まり、歌いに来ていた木を、僕が全て切り倒してしまったから。夜には来ていたイノシシや鹿や猿も、みんないなくなっていた。彼らが食べる木の実や果物がなる木も、なくなったから。そのとき、僕自身が自分の森を破壊していることにはっきりと気づいたんだ」。
一番下の息子が中等学校を卒業したあと、つまり約5年前、セバスティアンは木材を売ることも牛を飼うこともやめ、自分のフィンカにある残りの原生林の部分を傷つけまいと誓った。それ以来、彼は過去に木を切り倒していたこの地点に通うたびに、少しずつ鳥たちや他の野生動物が戻って来るのを注意深く観察している。
セバスティアンが目を閉じて鳥たちの声に耳を澄ませていた裏には、彼とこの森をめぐる痛苦の物語があった。この地点から真上にドローンを飛ばし、上空から眺めてみると、何のことはない一面の緑が広がっているはずだ。だが、人々と森の関係は、「そこに森がある」という前提からは捉えられない機微を持つ。また、このセバスティアンの物語からわかるのは、貨幣経済や国民教育が浸透しつつある現代のアマゾン熱帯雨林では、森自体が決して保証された存在ではないということ、それはいつでも諸力のもつれ合いによって、ときには先住民たち自身の手で破壊されうるということ、そしてたとえ一部であれ、森の消失は先住民の人々の生世界=lifeworldに身体感覚や物質性の次元で避けがたく影響をもたらすということだ。
エドゥアルド・コーンに対しての第一の批判はこの点から発する。コーンが「ルナにとっての挑戦は、富を集中させている森の諸形態にどのようにアクセスするかである。なぜなら、この常にすでにある領域には、動物たちは不変の豊富さで存在するからである12」と書くとき、彼はわずかたりとも森が消失し、動物たちが姿を消す可能性を考慮していない。これらの消失可能性は、現代のアマゾン熱帯雨林に住む諸民族や人々にとって向き合わざるを得ない問題であり、今や毎年のようにこの森で発生している人為的な大火災でなくとも、ミクロレベルでの変容が彼らの知覚や感覚世界に対して、また非人間的存在との関係性を築く上での緊張を生み出している。先住民の人々と森との関係は、様々な諸力や情況を包括的に踏まえながら、それらとの交渉と折衝を通じて生成されるものとして探究されない限り把握できないということを、俺は強く主張する。
「さあ、ここから原生林だ」。セバスティアンが言う。正直なところ、言われる前にわかっていた。ヤスニで森に足を踏み入れたときと同じように、空間の性質が変化したことは身体が感じているからだ。例えば、それは木漏れ日の形や角度、光がどのように自分の知覚に浸透してくるかだけでもわかる。いわゆる二次林よりも圧倒的に豊富な種の多様性を内包する原生林では、葉の形態や大きさ、幹や枝の伸び方、色味などが異なる種々が密集しているため、木漏れ日の形や差し込む光の角度は複雑になり、色はより柔らかく滲む。また、視覚的にもさらに不規則で凝集度の高いイメージが網膜に訴えかけてくる。
もう一つ書き記したいのは、風の吹き抜け方が二次林とは異なるように感じるという点だ。原生林に足を踏み入れると、風の流れがまるで意志を持っているかのように、まるで意識的に組み立てられた道を通ってきた知人に出会うかのように感じられるのだ。
二次林と原生林の違いは、前者が数十年単位の森林としての活動期間であるのに対し、後者は数千年、最低でも数百年かけて現在の姿になっている可能性が高いということだ。もちろん、その間に木々は息絶え、倒れ、分解され、種から再び芽吹く過程を繰り返している。しかし、俺というちっぽけな寿命しか持たない生命体の想像力が及ばない壮大な時間軸において、この木々たちはあらゆる動物や微生物、昆虫、他の植物たちとの共存と交渉を重ねながら一繫がりの流動的な建築実践を行っている。その空間に吹き抜ける風は、数十年程度では得られない説得力と必然性、あるいは多種間によるある種の合意の痕跡を醸し出すようになる。
あらゆる天候や雲の流れ、種の絶滅、ときには地球規模の気候変動期も乗り越えながら、原生林に吹く風は今この瞬間も、木々たちが時間をかけて自らの意志で築き上げた空間の隙間を通り抜け、俺の頰を撫でている。その感触を得ると、その意志を一度感じると、セバスティアンやスリティアクが「木や虫と話せる」と言っていたり、「ヴィジョンの中で風が先祖に変化して話しかけてきた」という話を聞くとき、単に人類学者として他者である彼らの発話を真剣に受け取るだけでなく、俺自身の実感としても彼らの主張に次第に同意せざるを得ないようになっていく。
「木や虫と話せる」という主張に対して欧米や日本、あるいは南米都市部のメスティーソの人々がバカバカしい、科学的に証明が不可能などと言って否定する際に、彼らはセバスティアンやスリティアクが前提とするものと同様の種の多様性や活動期間を持つ森の中で、木や虫が発するエネルギーや風の流れを感じることを想定していない。しかし、原生林という爆発的な多様性を持つ場で、木々たちが数千年にわたり自らデザインを手掛けた空間で時間を過ごすことで、森自身が強力な意図を持っていることを認識できる。そのとき、「木や虫と話せる」のは、戯言ではなくなる。コーンはその点において、次のような引用に代表されるように、人間以上の存在が持つ意志が森での生を駆動させる主体と不可分であることを示したことによって、間違いなく重要な仕事をした。
「もし思考が生きていて、生きているものが思考しているのなら、もしかすると生命世界は魔術的に蠢いている=enchantedのかもしれない。私が意味するのは、人間的なるものを超えた世界とは、元々無意味だったものを人間たちが意味があるように仕立てた世界ではないということだ。むしろ、意味とは―手段と目的の諸関係、労力、目的、テロス、意図、機能、そして意義深さ―生きた思考の世界において人間的なるものを超え、我々のあまりにも人間的な、それらを定義しコントロールしようとする試みでは汲み尽くされていないようなやり方で、浮上するものだ13」
コーンが述べるように、アマゾン熱帯雨林の原生林には、人間的なるものを超えた意図が確かに顕在している。それは、人間の言語による理解可能性や既存の科学体系が捉えられる範囲を超えている。森を理解しようとする「あまりにも人間的な」試みは、その枠組みの限界に収まる範囲以上のことを先住民の人々が知覚している可能性に直面すると、彼らを否定するか、「真剣に受け取る」という名の「聞くが聞かない」態度に終始してきた。本書における俺の認識論的挑戦は、人間的なるものを超えた生世界である森で確かに生活を営む先住民の人々について、彼らの主体性が森が孕む還元不可能な意図と切り離せない存在であることと、彼らの生を取り巻き規定する森という存在自体が、人間の意志によって瞬時に消失する可能性を同時に把握し記述すること、それらを保証なき生成として捉え、表象することである。それはある意味で、「人間的なるものを超えた」言説に、「あまりにも人間的な」次元を逆流的に注入すること、その結果として発生する、決してクリアカットになりえない混沌とした現実の諸相を言論空間に立ち上がらせることである。
それは、セバスティアンをはじめとするシュアールの人々に対して、「聞くが聞かない」態度を捨てること、ドストエフスキーやシャーロット・ブロンテ、桐野夏生が描く登場人物たちと同じように個人としての複雑性と矛盾を彼らが抱えていることを一切の妥協なく描き、自らにその現実を憑依させることを意味する。様々な点において、本書は「人類学ではない」という烙印を押される可能性が少なからずある。俺はその可能性を認識した上で、その枠に収まるよりも、言葉が持つあらゆる力を用いて実験することを選ぶ。この身が力尽きるまで。
なぜなら、俺が人類学を通して認識したいのは、アマゾン熱帯雨林で命をかけて時間を過ごしたのは、なぜ福島第一原発は爆発しなければならなかったのか、なぜあの土地に人間が住めなくなり、放射能に汚染された瓦礫や水が周辺諸国にまで影響を与えることが容認されているのか、なぜ主権国家であるはずの日本はアメリカ合衆国の承諾なく自分の意志で原発を止めることができないのか、これらの現象の根幹にある動力源は何なのかを知るため。そのパワーの獰猛な破壊力に立ち向かうために必要な、オルタナティヴな世界認識の可能性を探るため。そしてそのポテンシャル自体が直面している課題に対峙するためだ。
セバスティアンが「僕が森を壊したことで、鳥たちがいなくなってしまった」と回想するとき、その言葉は俺に自分自身の相似形として突き刺さってくる。「福島で発電された電気によって東京で育ったのは、俺だ」。地球の裏側で生まれた者同士なのに、俺たちは同じ問題に直面していた。自らが生きる土地との繫がりを命をかけて紡ぎ直さなければ、次世代は成立し得ない。その意識を共有していた。それは、どれだけ他の諸地域が崩壊しても自分の身だけは安全であることが無意識に刷り込まれているような人類学者たちには理解できず、する必要もないため、彼らはその危機感を自分ごととしては共有しないまま研究を遂行し、それが研究倫理的にも正しいという立場が、新たな論文が発表されるたびに確認・強化される。
俺たちは原生林の道なき道を進んでいた。めくるめく木々や蝶の群れに目をやる暇もなく、セバスティアンの背中を追いかける。以前の俺なら間違いなく付いていくことは不可能な道だ。彼がここに俺を連れてくるまでに数週間かけたのも頷ける。屋根を葺き替えるのに必要なプンプナやチャピといった葉も、村の近くとは違い豊富に見かける。家を建てる際の木材にもなり、セバスティアンは使わないものの屋根の葉にもなるクーントゥも、特徴であるタコ足のように広がり、吸盤のような突起を持つ根をよく見せる。
「見ろ」。昼間なのに夕方のように薄暗い鬱蒼とした地点で、セバスティアンが立ち止まった。そこには、上の方から長く伸びてきて俺たちの目の前でフラフープのような輪を描き、横方向にさらに伸びていく、手で摑んだら親指と人差し指の間に2センチくらいスペースができる太さのツルがあった。「これはとても良い薬だ。俺たちは今、チチャも持ってないだろ。そんなとき、このツルを見つければいい」。そういうと、セバスティアンはマチェーテでツルを真っ二つに切り、顔を上向きにして切り口を口元に持っていった。すると、そこから蛇口のように水が流れ出したのだ。一通り喉を潤し、俺にも分け与えてくれた。トロみがありつつ雑味のない水だった。「これはタンピルイシュネイクという植物だ。この水はとても美味しい。シュアールでは薬だとは思われてないけれど、僕は薬効があるんじゃないかと踏んでいて、今調べているところなんだ。なぜかというと、このタンピルイシュネイクには、いつも他の植物がくっついて寄生している。僕が今まで数えたのは4種類。つまり彼らはタンピルイシュネイクから栄養をもらって成長している。他の植物を養えるくらい、エネルギーを持っているということさ」。セバスティアンが持論を語った。
フィールドワークを通してセバスティアンが繰り返し語る、彼の薬草研究の根幹にある発想を、ここで初めて聞いた。それは、植物の持つ力を見極める際に、何よりもまず「その植物の生き様」を観察することで、それがどのような固有の能力を発揮することでこの世界を生き抜いているのか、あるいは他の種に対してどのような影響を与えているのかを注意深く調べるということだ。その態度を、セバスティアンは「科学的」と呼ぶ。「僕がやっている研究は、科学的だ。知らない植物に出会ったら、まずはよく形を観察する。自分がすでに知っている植物と似ていたら、もしかしたら似た力を持っているかもしれないな、と見当をつける。僕はここの森にあるほとんどの植物を知っているから、色々な植物と比べることができる。そして、毎日そこを訪れて、鳥や虫がその植物とどう関わっているかを見る。もし果物や花を付けていて、それを他の生き物たちが食べていたら、それは彼らにとって栄養になっているということ。つまり、人間にとっても栄養になるかもしれない。あとは、その植物が生きている環境もよく見ないといけない。例えば強い風が吹く場所なのにわざわざそこにいて、それでいて真っ直ぐ立っているとする。それはつまり、その植物が忍耐強いということ。その植物の葉が長く垂れ下がっていて髪の毛のようなら、それはもしかしたら髪の毛にとって良いものかもしれない。他の植物にくっついて生きている寄生植物は、生命力が高い。なぜなら彼らは場所を変えて生き抜く知恵があって、しかも根っこがないから他の植物よりも早いスピードで命を繫いでいる。それだけエネルギーが詰まっているということだ」。植物について語るセバスティアンの口ぶりは、まるで人間同士が相手の表情や体型、言葉遣い、歩き方、身振り手振り、声質、服装、住んでいる場所、職業、交友関係など、様々な観点から微細な情報を総合しコミュニケーションを取っているように多角的かつ共感的である。
「これは薬かもしれないな、といよいよ考えが深まってきたら、僕はほんの少しだけ、その植物を自分の口で味見してみる。もしそのあと30分くらい待ってみて身体の調子が悪くならなければ、それは薬だということ。これだけ観察して研究を重ねて、害がないということは、身体のどこかを治そうとしているということだ。そのときどこも悪くなければ、何に効くのかすぐにはわからない。だからそこからは自分の体調が少し悪いときに、その植物を色んなやり方で使ってみる。お湯で煮出して飲んだり、すり潰して身体に塗ったり、蒸気を身体に当ててみたり。すると、だんだんとどんなタイプの不調に効くのかわかってくる。そこまで来たら、最後にやらないといけないのは、植物を完全に信じ切るということ。植物も生きているんだ。僕たちが信じてやらないと、力を出してくれない。だから、これは間違いなく薬だと思ったら、その植物を信じ切って使う。すると本当に効くようになる」。
まず興味深いのは、セバスティアンは植物を「薬」か「毒」のどちらかに分けている、ということだ。デスコラが同じヒバロ語族のアチュアール族に関する研究で主張するように、アチュアール社会には様々な点において二元論が見られる。例えばそのうちの一つが「食べられる動物/食べられない動物」の二元論であり、前者は昼行性、後者は夜行性の動物だとされる14。だが、シュアール族あるいは他のヒバロ語族の民族に関する先行研究において、「薬」と「毒」の二元論の存在について論じられた形跡はない。先述したシュアールの「医食同源」の思想についても先行研究からは抜け落ちていたが、今までの研究では、シュアールの人々にとって薬が薬に「成る」過程にこそ繊細な思考が詰まっていることが見逃され、「どれが薬なのか」を単純に尋問するような研究ばかりが行われていたと想像せざるを得ない。彼らにとって「何が薬なのか」=「何が良き身体を醸成させるのか」は状況によって変わりうることであり、ときには「毒」とされるものを適量摂取することで「薬」として使用することもあれば、「薬」なはずのものの量を誤ることで「毒」になってしまうこともある。
ここで重要なのは、植物の効力の流動性と可変性を認識しているにも拘らず、植物の力を信じ切る態度に変わりはないこと。結果的に効くにせよ効かないにせよ、「効かないかもしれない」という疑いを持って薬草を使用することは、セバスティアンにとって、また多くのシュアールにとってあってはならないことなのだ。「ヴィジョンをたくさん得ないといけないのは、自分の未来に対して確信を持つため。ヴィジョンがあれば、植物のことも自分のことも信じることができる」。何一つ流動を止めることがない森の中で、瞬間を信じ切ることがどのように可能なのか、このときの自分にはまだ理解ができなかった。
酷い胃炎から自分を救ってくれたサンディの木に対して、セバスティアンは言葉で語りかけながら感謝の気持ちを伝えていた。そうしなければ、サンディは治してくれないという。研究を重ね、薬草が薬草に「成る」瞬間にも、それに信じる気持ちを伝えなければ、植物は真の力を発揮しない。植物の能力は、人間たちがそれに関与する在り方によって発露の度合いが変化するということがここでも観察できる。
川辺に着いた。セバスティアンがいつも自慢げに語る滝がある地点まで、もう少しだ。「僕のフィンカには滝がある。純粋で、全てを洗い流してくれる滝。僕はいつもフィンカに行くとここを訪れる」。シュアールに関する研究の先駆者であるラファエル・カルステンは、シュアールの人々が滝を精霊が行き交う場と見なしていると論じ、マイキュアやアヤワスカの儀式の前に必ず滝水を浴びると1935年の時点で記している15。また、その後に続くマイケル・ハーナー16やエルケ・マデルなど、多くの研究者たちがシュアールにとっての滝の重要性を繰り返し強調してきた。セバスティアンにとっても、確かに滝はなくてはならないものである。
丸みを帯びた石にギッシリと埋め尽くされた川の中を、足を持っていかれそうな流れに逆らって歩いていく。足と同じくらいのものから、その何倍かあるくらいの大きさの石が多く、石と石の間に足が引っかかって進みにくい。セバスティアンの言葉を思い出し、つま先に意識を集中させる。なんとか100メートルくらい進むと、そこには滝があった。高さは3メートルくらいで、そのまま飲めそうな清らかな水が激しく流れ落ちている。
何度も訪れている那智の滝をはじめ、日本に数多く存在する滝の名所を念頭に置くならば、この滝は通俗的な意味での「絶景」ではないかもしれない。それはひっそりと隠れ家のように流れ続ける、極めて個人的な滝だ。しかし、だからこそ地図では見つけられないこの場所にたどり着いたとき、自分のことを待ちわびてくれていた何か不思議な存在に出会ったような、柔らかな感情が心に充満するのを感じた。セバスティアンはヴィジョンを得る前に必ずここで滝に打たれ、心身を清めるという。また、甥っ子や姪っ子など村の子供たちにマイキュアやアヤワスカを与える前にも、ここに連れてくることがあるようだ。
セバスティアンは服を着たまま、滝の中に向かった。そして、激流がその筋肉質な身体を飲み込むと、くるりと俺の方に向き直って腕を左右に広げた。打ち付ける水の重さに耐える身体は、ブルブルと震動している。数分経っただろうか。体感的にはかなり長い時間、彼は滝に打たれていた。そして濡れた長い髪が顔を覆ったまま滝から出ると、「ホオオオオオウ」と裏声で雄叫びを上げた。「ナンキ、これがシュアールだ。僕たちは滝を愛し、滝から力をもらう。滝にはアルータムのパワーが満ちているから」。アルータムとは、森の中を行き交い、その生命力を司る超越的存在である。多次元的存在であるアルータムは、ヴィジョンの蓄積を通して人間が得られる具体的な力を意味すると同時に、ヴィジョンの中に現れる様々な精霊的存在のことも意味する。また、土の神であるヌンクイなど、シュアールが語り継ぐ神々は、アルータムの化身であるとされる17。アルータムはシュアールたちが住み着く森に偏在する生命力の源泉であり、同時に体現でもある。滝はその力が凝縮される場であり、水を浴びることで自分の状態を森に合わせて調律し、高めることができる。
シュアールにとって、アルータムの力を得るための最上の方法はマイキュアとアヤワスカによるヴィジョン経験を適切に積み重ねることだ。これら2つの薬草は、何よりもまず自分の人生における未来を見せてくれるという。また、ときには心身の苦悶を引き起こすそれらの薬草に打ち勝つことで、森に棲む精霊たち=アルータムの化身から力を獲得する。その力によって、シュアールの人々は前に進むための勇気と確信、そして明晰な思考を手に入れるのだ。「セバスティアン、俺は自分の未来がどうなっているのか、知りたい。シュアールの人たちと同じように、ヴィジョンを得て強くなりたい。俺もここにいる間にアヤワスカを飲めるかな?」意を決して聞いてみた。この時点では、シュアールにとって最も重要な薬草であるマイキュアを飲めるとも、飲みたいとも思っていなかった。飲むと3日間は効果が続き、目に見える現実の全てが変容するというマイキュアは、飲む人によっては後遺症が残ってしまうことや、意識が狂いすぎて崖や川に落ちてしまう可能性もあるとセバスティアン自身から聞かされていた。また、これまでシュアール以外の人間にマイキュアを飲ませたことは一度もなく、外の人間が飲んだという話を聞いたこともないと言っていた。だが、あくまでマイキュアと比べる場合だが、アヤワスカは比較的後遺症のリスクが小さく、効果が続く時間も3〜4時間くらいで短いと聞いていた。もちろん、シュアールにとって最も重要な薬草の一つであることに変わりはなく、外部の人間が簡単に飲ませてもらえるものではないことはわかっていた。しかし、極限の身体性とともに生きる彼らの宇宙に接近するためには、少なくともアヤワスカをこのフィールドワーク中に経験することは必須だと考えていた。
「いや、まだダメだ」。一瞬考えた末にセバスティアンが発した言葉に、俺は落胆した。同時に、当然だとも思った。「ナンキ、僕はまだ君がアヤワスカに耐えられると思えないんだ。前に比べれば随分歩けるようになったし、色んなことができるようになってきた。でも君はまだ森に慣れていない。その状態でアヤワスカを飲んだら、後遺症が出てしまうかもしれないし、良いヴィジョンを見ることができない。いいか。本当に良いヴィジョンを得るためには、アヤワスカから真に力をもらうためには、シュアールの1人にならないといけない。それは君の骨と血と肉が、変わらないといけないということだ」。「骨と血と肉……。つまり、この森に住み続けることで俺の身体が変わったら、俺もシュアールになるってこと?」「そうさ。僕たちはみな、骨と血と肉でできている。それはみんな同じこと。どんな国で生まれようとも、人間は平等だ。でも僕たちはなんでシュアールなのか。それはチチャを飲み、キャッサバやプラタノを食べ、ここの川で採れる魚や森の動物を食べているからだ。毎日森を歩き、強い身体と精神を持つからだ。それをやめてしまったら、僕たちはシュアールではなくなってしまう。親はシュアールだけど、もう森に生きるのをやめてシュアールではなくなった人間がたくさんいる。でもナンキ、もし君が僕たちと同じことを続けて、同じものを食べ、同じように歩けるようになったら、それは君もシュアールになるということだ。そうなったとき、アヤワスカも飲める」。
セバスティアンとの初めての原生林の探索を終え、滝に打たれた清々しい身体を携えた俺は村への帰途についた。全身の感覚を張り巡らせて森のディテールを吸収し、彼と交わす一つ一つの言葉から微細なニュアンスを汲み取った。自らの身体経験を介した思考に基づく極限の具体性を帯びたセバスティアンの言葉は、同時に機知に富み、意外性に溢れている。この意外性は、シュアールの生き方が俺にとって未知であることのみに起因するのではない。セバスティアンという人間が持つ特別な何かが、彼がシュアールであるという事実を越えて言葉や振る舞いに宿っているのだ。彼とパストーラの元でシュアールの子として生まれ変わった俺のフィールドワークは、まだ始まったばかりだ。
1. 「anent」についての詳しい記述は、例えば以下を参照。Mader, Elke. 1999. Metamorfosis del poder: Persona, mito y vision en la sociedad de Shuar y Achuar (Ecuador, Perú). Quito: Abya-Yala. Descola, Philippe. 1986. La nature domestique: symbolisme et práxis dans l’écologie des Achuar. Paris: Ed. De la Maison des sciences de l’homme.
2. Descola, Philippe (trans. Janet Lloyd). 2013. Beyond Nature and Culture. Chicago: The University of Chicago Press, p. 30.
4. Slater, Candace. 2001. Entangled Edens: Visions of the Amazon. Berkeley: University of California Press. p. 16.
5. Ingold, Tim. 2000. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge. p. 10.
6. Miller, Theresa L. 2019. Plant Kin: A Multispecies Ethnography in Indigenous Brazil. Austin: University of Texas Press. p. 186.
7. Santos-Granero, Fernando. 2007. “Of Fear and Friendship: Amazonian Sociality beyond Kinship and Affinity”. Journal of the Royal Anthropological Institute 13(1), pp. 1-18, p. 11.
8. 例えば以下を参照。Levin, Michael David(ed). 1993. Modernity and Hegemony of Vision. Berkeley: University of California Press.
9. Ingold, Tim. Vergunst, JL. 2008. Ways of Walking: Ethnography and Practice on Foot. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd. p. 5.
11. Ingold, Tim. 2000. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge. p. 144.
12. Kohn, Eduardo. 2013. How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. Berkeley: University of California Press. p. 183.
14. Descola, Philippe. 1986. La nature domestique: symbolisme et práxis dans l’écologie des Achuar. Paris: Ed. De la Maison des sciences de l’homme. p. 115.
15. 以下を参照。Karsten, Rafael. 1935. The Head Hunters of Western Amazonas: The Life and and Culture of the Jivaro Indians of Eastern Ecuador and Peru. Helsingfors: Societas Scientiarum Fennica.
16. 例えば以下を参照。Harner, Michael J. 1972. The Jívaro: People of the Sacred Waterfalls. Berkeley: University of California Press.
17. Mader, Elke. 1999. Metamorfosis del poder: Persona, mito y vision en la sociedad de Shuar y Achuar (Ecuador, Perú). Quito: Abya-Yala. p. 90.