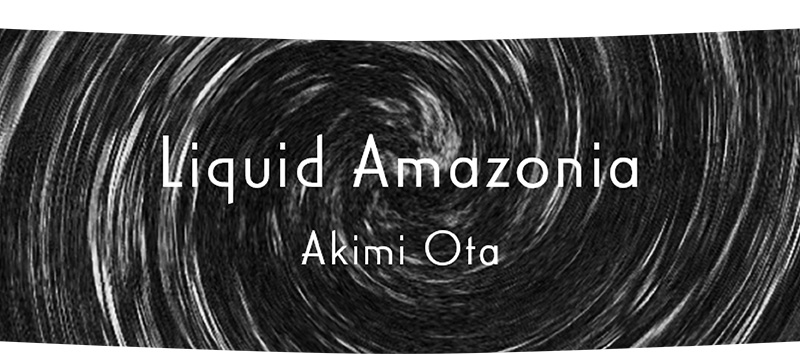「ちょっと今から村のみんなの家を回って、君がこれからここに住むことを伝えてくる。だから家で待っていてくれ」。ケンクイム村に住み始めてまだ何日かの頃。セバスティアンは、一度ならず二度、三度と早朝に村の家々を回ることがあった。俺が今後1年にわたってこの村に住むという計画について村に周知するためだ。統一された情報網が存在しないここでは、告知ひとつとってもそれが全体に浸透するには時間がかかる。間違った情報や誤解が広まらないように念には念を入れて丁寧に伝達することが肝要のようだ。
ナンキンツ村が中国系鉱物採掘企業によって破壊されて以来、シュアールにとって、「チーノ」(中国人)は最も警戒するべき存在である。そのことによって、俺はスリティアクと他のシュアールの村を回っていたときに頻繁に懐疑の目を向けられ、何度か訪問自体を断られることもあった。
ケンクイム村では例外的に訪問初日から村人たちが受け入れてくれているような雰囲気を感じ、それがシュアール全体から感じる反感にも拘らずこの村への滞在を望んだ理由でもあるが、なぜ受け入れられていたのかはハッキリとわからない。スリティアクによれば、この村は攻撃を受けたナンキンツ村から遠いため警戒心が高まっていないことが理由らしいが、俺が訪問を断られた中には必ずしもナンキンツ村に近くない共同体もあった。
窓口となった彼女やセバスティアンに対する信頼の厚さが大きな要因なのかも知れないが、結局のところ、村の構成員たちそれぞれの「チーノ」に対する見方がたまたま敵対的でなかったから、としか言いようがないのかもしれない。住民のうち成人の数が数百人、ときには数十人の場合もあるこれらの村々では、個々人の考え方や知識の在り方によって一つの村全体の方針や態度に劇的な差が生まれる。それでも念の為、最初の1〜2周間はセバスティアンやパストーラに密着するように生活を送り、怪しい行動を取っているとみなされないように細心の注意を払った。その甲斐もあり、少しずつ村全体で俺の存在が受け入れられてきたようだ。
セバスティアンは周知行脚から帰ってくると、サンディの木から採取した樹液と森で蜂の巣を仕留め採ってきた野生の蜂蜜を混ぜ合わせ、パストーラに与えた。以前セバスティアンが語っていたように、パストーラが抱えている慢性的な病気を治すためだ。コップの半分よりちょっと少ないくらいに注がれたその薬をゆっくりと時間を掛けて飲み終わると、彼女は「きっとこれで治る」と頷くように呟いた。パストーラの病気とは何なのか、俺はフィールドワーク中に何度も彼らに尋ねた。その度に彼らは様々な症状について語り、それを治すために病院に行って診断を受け、薬を処方されたことや、シャーマンに会いに行き治療の儀式を施してもらったことなどを説明するが、最後には「何の病気なのか確実ではない」という結論に返ってくる。
病院からは血小板が不足していることによる複合的な不調であると説明されたようだ。以前、パストーラは出血が止まらなくなり、ケンクイム村からはバスで8時間ほどかかる山岳地帯に位置するエクアドル第三の街クエンカで入院したことがあったという。「身体が全部痛くなることがあるの。全部、全部! 骨や筋肉がすごく痛い。太陽が強いときにチャクラで働いているとよくそうなるわ」とパストーラは語る。パストーラが入院している間、セバスティアンはクエンカで一緒に過ごし、たまたま病院で出会ったメスティーソ系の人から屋台での雑用の仕事をもらい、僅かな日銭を稼いで凌いだ。
別のときには、出血ではなく、全身の痛みによってものも食べられなくなったパストーラが3日ほどマカスの病院に入院していたことがある。マカスはケンクイム村からバスで約3時間のところにある人口2万人ほどの街で、この村があるモロナ=サンティアゴ州の州都だ。「病院の注射や薬のせいで、パストーラは入院中すっかり弱ってしまった」とセバスティアンは当時を思い出す。パストーラの様子を見たセバスティアンは彼女を連れて帰りたいと医者に直訴したが、医者はそれを認めなかった。激昂したセバスティアンは、「もしこれで妻が死んだら、お前を刑務所に入れるために訴えてやる!」と怒鳴り、泊まっていたマカスのホテルに帰った。ホテルで怒りを沈めながら、どうすればパストーラを治すことができるか、考え込んだ。しかし、方法がどうしてもわからなかった。
こうなれば、シャーマンに頼るしかない。そう思ったセバスティアンは、マカスの街中を回ってシャーマンを一人探し出した。治療費を聞いてみると、100ドルと言われた。「そんな金はとても払えなかった。ホテル代が7ドルで、もう2日泊まっていた。手元に残っていたのは50ドルもなかったんだ」。治療に必要な物はなんだ?とそのシャーマンに聞くと、「卵4つ、トラゴ・デ・カーニャ、タバコ2本」と答えた。「あと1つくらい何か言っていた気はするけど、思い出せない。とにかく、僕はそれを聞くと、じゃあ買ってくるよとシャーマンに言って、それきり彼のところには戻らなかった」。言われたものを買ったセバスティアンは、それらを持ってパストーラの病室に戻る。「父がやっていた治療を必死に思い出して、目を閉じて集中した。そのまま治療してみると、次の日にパストーラは元気になったんだ」。セバスティアンの父は、この地域で有名なシャーマンだったという。セバスティアン自身は若い頃シャーマンになることに興味がなく、このときも何も知識はなかった。しかし、子供の頃見ていた父の治療の朧気な記憶をたどり、実践することで、パストーラを治すことができた。そんなことができたのは、このときが初めてだった。
「僕にシャーマンになる力があると気付いたのは、そのときだった。シャーマンと名乗るためには、そのための修行を積まないといかない。僕は若い頃、その修業を怠った。興味がなかったんだ。でも、僕にはシャーマンとしての資質があると確信した。そのときから僕は薬草に目覚めた。パストーラを、人々を、治療するための知識を得ないといけないと強く思った。僕は今でもシャーマンではない。でも、クランデーロとして人々を治療することはできる」。
森がスペクトラムであるように、シャーマニズムもまた、スペクトラムである。セバスティアンは、社会的にも自己認識においても、シャーマンではない。しかし、「シャーマンであること」と「シャーマニズムに関与すること」は別の位相として存在する。事物の潜在能力を見出し、解放し、操作し、誘導することで、宇宙にひずみと繫がりを生み出し、求められる現象を発生させる力を行使するという点において、セバスティアンはシャーマニズムにリミナルな存在として参入を始めた。それは、名付けや肩書によってではなく、意識の覚醒と実践によって起き、その限りにおいて維持されることである。
セバスティアンは、一夫多妻制のもとで何人も妻を持ち、40人以上も子供がいた父にとって、最後に生まれた子供だった。以前、首狩りをしていると指摘されて俺が縁を切ったアルベルトと訪れたパローラ地区の近くの村で生まれ育ったセバスティアンは、父から特別の寵愛を受けた。それにより、父が亡くなる直前にあらゆる兄弟姉妹を差し置いて最も大きな土地をもらうことになった。まだ10代だったセバスティアンが戸惑う中、年上の兄弟姉妹たちは彼を妬み、様々な方法で彼を攻撃してくるようになった。争いに嫌気が差したセバスティアンは、父から受け継いだ土地を売り、ウアンボーヤ地区にあるケンクイム村に住んでいた20歳ほど年の離れた姉であるママイに助けを求め、この村に移り住んだという。
原生林の木々を切り倒して木材を売り、原っぱに変えて牧畜を行っていた飲んだくれのセバスティアンは、度重なる体調不良に悩まされる妻のパストーラを治すため、そして自ら破壊していた森への愛をその身に宿すため、森を守りながら薬草研究に勤しむ生活を始めた。それにより、スリティアクをはじめ、村人たちの尊敬を集め始めると、彼の知識に興味を持つ訪問者が森の外部からやってくるまでになった。その中には、ドイツやアメリカ、アルゼンチンなど、国外からの者も含まれる。彼の存在こそが、ケンクイム村を周辺にある他の村々から差別化し、ある種の敬意と羨望の眼差しを集めていた。
それでは、セバスティアンはケンクイム村のリーダーなのだろうか? 実はそうではない。ならば、ケンクイム村のリーダーは誰か。この村には村長や副村長、会計係など、行政的役職が存在し、それぞれが村人たちの投票で選ばれている。そして、ケンクイム村のリーダーは、パストーラである。
シュアールはおろか、アマゾンの先住民コミュニティにおいて、リーダーが女性である例はほとんど報告されていない。政治文化を抽象化して語る場合、確かにアマゾンにおいて女性リーダーが擁立されやすい土壌があるわけではない。様々な意味で、パストーラの存在はこの熱帯雨林におけるアノマリーである。だが、だからと言ってパストーラの事例が無視されていいわけではない。それどころか、彼女のリーダーシップについて考えることは、アマゾンにおけるジェンダー、そこに賭けられているもの、さらにその変容について探究するために必須である。
そもそも、パストーラは元々シュアールではなく、キチュアである。15歳のときに当時19歳だったセバスティアンとプーヨで出会い、その後結婚したことで、シュアールの村であるここケンクイムに移住した。まず、ここに一つの「逸脱」がある。シュアールは母方居住制であり、結婚した夫婦は妻のコミュニティに住むのが一般的だ。ところが、パストーラとセバスティアンの場合はこれに反し、女性が男性のコミュニティに居住している。「キチュアの村ではシュアールよりもチチャをたくさん飲む。私はそれが嫌だった。だからシュアールの村に住みたいと思った」。冗談とも本気ともつかぬ言い方でパストーラは表現した。何かの理由を聞くと、彼らはよく「え? それだけ?」とこちらが困惑するほどシンプルな答えを言うことがある。それは彼らとの信頼関係の度合いとは必ずしも直結しない。
「住み始めて最初の方は大変だった。シュアール語でみんなが何を言ってるのか、一つも聞き取れなかったから。でも住んでいるうちにだんだん話せるようになって、今はキチュア語よりもシュアール語の方が得意なの。親戚や兄弟に合うと、いつも最初はキチュア語を話すのに苦労する。自分でも、もう私はシュアールだと思ってる」。セバスティアンは俺に「骨と血と肉が変わったら、君もシュアールになる」と言ったが、パストーラにとってもまた、民族的アイデンティティは流動的であり、土地や生活環境の変化、経験の蓄積によって醸成されるものとして捉えているようだ。
ホーンボリとヒルが画期的書物『古代アマゾンにおけるエスニシティ』(2011年、未邦訳)の冒頭で述べるように、アマゾン熱帯雨林先住民のエスニシティや言語をめぐる研究は、明快な境界と遺伝的に異なる人口構成の存在を前提とする本質主義に常に基づいていた。それは領土、言語、アイデンティティ、生物学的側面を一斉に統合することに苦心した欧州における国民国家形成の歴史モデルに基づいた、西洋中心主義的エスニシティ観である1。
ジュリアン・スチュワードが編纂し、後のアマゾン熱帯雨林先住民研究の礎となった大著『南米インディアンに関するハンドブック』(1948年、未邦訳)は、これらの民族性をめぐるコンセプトを先住民たちに当てはめることで、先住民の諸グループが断片化された状態で否応なく森の狭い範囲に貼り付けられた存在として示した。後のアマゾン熱帯雨林先住民に関する研究に絶大な影響を与えることになるクロード・レヴィ=ストロースも同書に寄稿しており、後の著作からはスチュワードと少なくとも同様のエスニシティ観を共有しているのが見て取れる。レヴィ=ストロースの仕事を発展的に受け継いでいるヴィヴェイロス・デ・カストロや直弟子であるフィリップ・デスコラも、アマゾンにおける境界化された民族言語観に対して批判的な立場を提示した形跡は全くない。
だが、ホーンボリとヒルが示すように、近年の考古学的研究によれば、征服者上陸前の古代アマゾンは地理的、言語的、遺伝的な側面、そしてアイデンティティの変容において、それまで考えられていたよりもはるかに流動的だったことが明らかになっている。経済的専門性や流通経路、戦争、政治的同盟、人口動態など、変わり続ける条件下で、アマゾンの先住民たちはヨーロッパ人の存在なくして絶え間ない変容の過程を生きていたのである2。スチュワードが礎を築き、レヴィ=ストロースが歴史的無意識と円環性を特徴とする「冷たい社会」と呼んで以来、今日まで世界中の人々の想像力を支配し、限定してきたアマゾン熱帯雨林先住民たちに投影される「変化に乏しい社会」という視座とは、決別しなければならない。
確かに、「骨と血と肉」を持つ限りにおいて、どこで生まれた人間であれ違いはないというセバスティアンの言葉は、パストーラからはもちろん、ケンクイム村の他の住民たちや、シュアール以外の先住民の人々からもフィールドワーク中に頻繁に耳にした。彼らにとって、「シュアールであるかそうでないか」は、シュアールの土地に住み、シュアールと共に時間を過ごし、同じものを飲み食いし、同じ森の光を浴び、川に浸かり、動植物と関わり合うことで不断に耕されるものであり、所与のものではない。パストーラは確かにキチュアだったが、今はシュアールなのであり、そこに比喩的な意味は込められていないのだ。アパレシーダ・ヴィラサが「不安定な身体3」と呼んだように、彼らにとって、アイデンティティとは身体の絶えざる物質的構築の途上で浮かび上がるものであり、諸存在との日々の互酬的な愛情やケアの交換が心身の記憶として蓄積されて初めて成り立つ。アマゾンの先住民世界は、支配的言説とは異なり、流動と変容を前提としている。それは限定された民族共同体内部における親類関係の維持や非人間的存在との関係構築の過程においてだけでなく、彼らの生きた身体がどこであれこの世界に存在する限り有効な前提なのだと、定式化され直さなれければならない。
セバスティアンとパストーラが2人とも俺と一緒にいるときは、セバスティアンが会話のイニシアチブを握り、パストーラが口を挟むことは少ない。これは個人の性格の問題ではなく、やはりシュアールにおける「家の主」としての男性性をセバスティアンが内面化しているからだ。アマゾン熱帯雨林に特に男性人類学者として滞在する場合、ジェンダー化されたコミュニケーションの様態に対して無自覚に向き合っていると、明らかに男性との会話に経験が偏ってしまう。アマゾン熱帯雨林の先住民に関する研究で、主に男性が担う領域であるシャーマニズムや狩猟についてのものが議論の中心を占め、あたかもそれらこそが最も重要なテーマであるかのように語られているのも、研究者たち自身によるこのジェンダー化された経験が最大の理由である。
これは、女性人類学者にとっても無関係なことではない。第一に、女性であっても、先行研究の大部分を担う欧米出身の白人や南米都市部の白人・メスティーソ系の研究者たちは、アマゾン先住民コミュニティ内部におけるジェンダー化された関係性から相対的に自由な立場に置かれ、男性のリーダーなどとも豊富な対話の機会を得られることが多い。とある民族の「エートス」について説明できる存在が男性であるとされている場合、女性研究者であってもそのような知識や周囲からの敬意を集める男性に誘導されやすいことに違いはない。
無論、特に1990年代以降そのようなジェンダー化された関係性について自覚的かつ批判的な女性研究者が多く現れていることも忘れるべきではない。ジョアンナ・オーヴェリングやローラ・リヴァル、アンヌ=クリスティン・タイラー、ローラ・グラハム、アパレシーダ・ヴィラサ、セシリア・マッカラム、ベス・コンクリン、ルイサ・ベラウンデ。これらの名前はアマゾン熱帯雨林先住民に携わる現代の一部の代表的な女性研究者であるが、彼女らのうち一人としてシャーマニズムや狩猟に研究の主眼を置いていないのは、偶然ではない。
第二に、先行研究の引用と検討によって発達する学術的実践において、過去の男性研究者たちが築いてきたエピステモロジーから逸脱することが女性研究者たちにとって難しいということが挙げられる。シャーマニズムや狩猟に最も高い価値を置いている男性研究者たちが権威を得ている現状の中で、それ自体が「ムラ社会」である学術の場において彼らに真っ向から対抗することや、彼らを優先的な参照点として扱うことを控え独自路線を歩むことは、言説をめぐるパワーポリティクスの関係から決して簡単なことではない。
これらのジェンダー化された構造や経験のプロセスについて、俺は薬草やヴィジョン、シュアールの何たるかについてのセバスティアンや他の男性の村人との対話を懸命に吸収しながらも、敏感に感じ取っていた。パストーラにはパストーラの語るべきことがあり、彼女の思想があるはずだ。それを聞きたい。しかし、セバスティアンも一緒にいる場合、目に見えてパストーラの口数は減ってしまう。つまり、パストーラに心置きなく話してもらうためには、彼女と俺が2人で過ごす時間を意識的に作り出さなければならない。
ケンクイム村でのフィールドワーク開始から数週間後、俺は機を見てパストーラと2人で活動する時間を増やした。最も簡単なのは、料理を手伝うこと。朝食を食べたあと、セバスティアンが他の家を訪ねたり森で何かを採集したりする間、「シュアールの料理についても知りたい」という理由で俺は彼に付いていかず、パストーラと一緒に家に残ることがあった。一緒にチャクラに行き、キャッサバやパパチーナを掘り出し、カゴに入れて持ち帰る。火を焚き、収穫したものの皮を剝き、大鍋で茹でる。火が通るのを待つ間、俺たちは2人で向き合いながら、ポツポツと他愛のない会話をする。
ケンクイム村の人口は約200人。半分以上は子供だ。ヨーロッパや日本の都市部では、赤子の泣き声や子供たちの叫び声、彼らが立てる雑音などは、日常から排除され、彼ら専用のエンクレーヴに閉じ込められている。そこからはみ出て彼らが外部に「侵入」するとき、その所業は大人たちの円滑な経済活動や精神の集中を攪乱してしまう「バグ」や「ノイズ」となる。翻ってアマゾンの村では、それらはバグでもノイズでもなく、生活の中心の只中にある。多くの男性たちが家から遠い森で作業をし、比較的距離が近い家とチャクラを女性たちが行き来する午前中から昼下がりの間は、赤ん坊たちの泣き声や小さい子供たちの遊ぶ声がサウンドスケープのメインパートだ。親が2人とも出払っている場合は、1歳や2歳の乳幼児を6歳〜8歳くらいの姉や兄が見守っている光景も当たり前である。
パストーラが約20年前に見た夢について語りだしたのは、そんな赤子たちの泣き声が村にこだまする時間だった。「ナンキ、セバスティアンと結婚したばかりの頃、私はチャクラで働くだけだった」。焚き火に当たる大鍋のグツグツいう音の中で、彼女は村のリーダーになるまでの長いプロセスをゆっくりと明らかにしていく。
「キャッサバやパパチーナ、カモーテを育てて、チチャを作って。セバスティアンが言うことにいつも従っていた。昔はそういうものだったの。結婚したら、男が言うことに従うものだった。これをしろ、あれをしろって。私たちはただそれをやり続けるだけだった。昔の男たちはときに凶暴だった。だから私たちは従ったの。一番下の娘のムラヌアが生まれた頃は、私たちはフィンカの中に住んでいて、全てを持っていた。鶏もチャクラも、全部ね。欠けているものなんか何もなかった。ナランヒージャも育てていた。そんなとき、セバスティアンが夢についての本を持ってきたの。彼は刑務所に入れられていたお兄さんに会いに行くためにアンバト(山岳地帯の街)に行った帰りに買ってきた。『パストーラ、こんな本を買ってきたよ』って言って、私にくれたの。ページを色々めくると、色んな絵が書いてあった。ある日座って考えるうちに、思い立って、読むことにした。私が寝ているときに見る夢に何か結果が表れるんじゃないかと思ってね。読み進めると、身体が全部大蛇に変わった人間が出てきた。その箇所を読むのが大好きで、昼間に横になって読んでいたわ。そしたらその時期、ある夜の夢で大蛇が出てきて、私を攻撃してきた。とても大きな川沿いを歩いているとき、突然襲ってきた。大蛇は人間を食べるから、私のことも食べようとしてきたの。でも夢の中で私はそいつを殺そうと戦った。もし大蛇を殺せないなら、そんなの私じゃない。だから私は自分に言い聞かせた。『殺す。絶対に殺す!』って。夢の本を読んでいたから、きっと何か結果が出ると思った。大蛇は巻き付いて締め付けてきた。私は嚙みついて反撃した。マチェーテも振り回して必死に戦って、支配した。ようやく大蛇を倒した。次の日起きて本をめくると、そこには『夢で大蛇を殺したら、将来あなたはコミュニティのリーダーになる』って書いてあった。そのあとも、眠れば毎日のように大蛇は夢の中で私を追いかけてきた。そのたびに戦って、殺し続けたわ。大蛇は一度も私を上回ったことはない。いつも、いつも、最後は私が殺した。そしてこの本にはその意味が書いてあった。『一体いつ、私はリーダーになるんだろう? それに、どうやって?』セバスティアンに聞いた。『わからない』と彼は言った。『君がどうやってなれるっていうんだい?』でも私はそのときセバスティアンに言ったの。『いつか必ず、私は村のリーダーになる』って。そして、その夢は本当だった。私はその夢をいつも心に留めていた。いつも、いつも。そして、夢を見て数年後、2000年のことだった。村で集会を開いていた。みんながどう考えていたかはわからない。でも私はゴミみたいだった。何も知らなくて無知だった。女性たちの中には今もチャクラでの作業とかチチャ作りしか知らない、家事しかできない人たちがいる。私もその一人だった。セバスティアンが言ったことをただ守っていた。でも2000年の集会で、みんなが私を村長の候補に選んだの。『パストーラ叔母さんも候補に入れていいかもしれない』と言われた。候補は10人いた。村長、副村長、会計係、秘書、色んな役職があった。秘書の人が候補者の名前を書いて、それぞれに誰が相応しいかみんなに聞いていった。するとみんな、『パストーラ』、『パストーラ』、『パストーラ』、『パストーラ』って。そして私が村長に選ばれたの。『なんで私が?』って思ったけど、自分の思考と精神の中では、こうなることは知っていた。いつかリーダーになるって知っていた。『やっぱり本当だった』ってそのとき思った。ボードには『村長パストーラ』ってはっきり書いてあったわ。それ以来、私はこの村のリーダーとしてやってきた。長い間働いてきた。本当に長い間。そうするうちに、前にはなかった知識が自分の中に入ってきて、私の精神を変えた。前みたいな私じゃなく、完全に変わったの。ナマキム川の村のリーダーたちが集まる集会に行ったり、シュアール連合の会議に行ったり、他にも色んな集会に行った。そこで他のリーダーたちがどうやって話しているか、耳を澄ませた。そうして、彼らの言葉が私の頭の中に入って、彼らを見ながら一生懸命記憶して、経験を積んで、また積んで、それがまた私の精神に入っていった。こうして私はリーダーになっていったの。最初は集会で人前で話すのが恥ずかしかった。初めてだったからどうすればいいかわからなかった。『ケンクイム村の村長に前で話してもらおう』って言われるのが嫌で、隠れていた。まずは他の人の話を聴きながら、2年間働いた。1年後には、もう他の人たちから知識を得て、恥ずかしさはなくなっていた。思考が完全に変わったの。集会では自分の言葉で話せるようになった。学びながら、自分の考えが変わっていく。セバスティアンは色々とアドバイスをくれた。私が村長になったとき、『パストーラ、なんてことだ!君が見ていた夢は本当だったんだ。君が言っていたことは、真実だったんだ』って言っていた。『そうよ。今から私がリーダーになる。誰もが私のことを知るようになるのよ』って私は答えた。たくさんの人たちと友達になる。夢ではそうだった。友達がたくさんできるっていう夢も見ていたの。今、私は色んな人たちと友達になった。たくさんの人が私のことを知っている。州議会でも、役所でも、他の機関でも、私のことを知っている。ちゃんと扱ってくれるし、話してくれる。アイデアをくれたり、彼らの経験について話してくれたり。そしてまた、私は物事を知ることができる。だから私は女性たちにアドバイスをするわ。私たちもコミュニティのリーダーにならないといけないって。女性だってリーダーになる力がある。男たちは私たちから色んなものを奪ってきた。でも私たちだって……私たちも人間でしょ。それに女の方が男よりもたくさんの経験をしてるのよ。私たちは母として、子供たちを育てるために何年も捧げてきた。女たちにとって、それはものすごく大変な仕事なの。私たちにはたくさんの責務があるの。男たちはそうじゃない。まだ子供が小さかったとき、私は息子や娘をみんな背中に背負いながら作業をした。チャンキンを額で背負って、その上に彼らを背負うの。ものすごく多くを捧げたの。でもナンキ、今この瞬間、私にはもう小さな子供はいない。だから調子はいいわ。私は色々な場所に行く。あなたが知っているように。私はよく村の外に出るけど、それでもセバスティアンと一緒にいるし、お互いに理解があるわ」
上の言葉を、パストーラは溢れ出すように俺に語った。唐突に始まったまるで神話のようなパストーラの叙事詩的語りに、俺は完全に引き込まれ、彼女が内に秘める覚悟と強靭な意志から計り知れない衝撃を受けていた。
パストーラの語りは、「夢」あるいは「ヴィジョン」がシュアール世界において流れ着き、侵入し、誰かにとっての確信となり、具現化する過程が水のように形を変えながら、彷徨える光源のごとく現実に憑依する圧倒的な力を示していた。パストーラの「夢」は、アヤワスカやマイキュアによるヴィジョン経験ではなく、夜眠るときに見たものである。夢の中で繰り返し現れた「大蛇に襲われ、殺す」というモチーフに対して、パストーラは偶然にもその時期セバスティアンが山岳地帯の街アンバトで買ってきた本に書いてあった内容に基づいて解釈をした。その解釈はそのまま彼女の「ヴィジョン」となり、数年の時を経て実現したのだ。村の中心にある「エスパシオ・クビエルト」の建設を実現したのも、道路と村を繫いでいるナマキム川に掛かる橋を建てたのも、全てリーダーとしてのパストーラの仕事である。
つまり、ここには2つの無視できない要素がある。シュアールにとって、自らの未来を確信に導く(そもそも、パストーラはシュアールとして生まれたわけではない!)「ヴィジョン」は、覚醒作用をもたらす薬草を介さずとも眠るときに見る夢を通して得ることが可能であるということ。また、その夢を「ヴィジョン」として血肉化する過程で必要とされるのは、コード化された一定の解釈ではなく、そこから強い確信を能動的に抽出できる限りにおいて、どんな由来の解釈でもあり得るということだ。パストーラの語りの他にも、他の村人たちやセバスティアンからは、睡眠時に見る夢も「ヴィジョン」=「kara」(シュアール語)であり、現実の一部であり、未来に起こることの何らかの示唆を含んでいるという主張が絶えず聞こえてくる。
アマゾン熱帯雨林先住民がヴィジョンを得る過程と睡眠時の夢の関係については、研究者たちの間で議論が続いている。例えば、ロビン・ライトはブラジルの北西アマゾンに住むバニワの人々に関する研究の中で、あるシャーマンが重病を患っている時期に見た睡眠中の夢の中で「死者の魂の家」を訪れ、その際に「まだこの世を去るべきではない」とお告げを受けたことで修行を始めたという語りを記している4。カーラ・スタングは、同じくブラジルの熱帯雨林に居住するメイナクの人々の魂が夢を見ている間に肉体を離れて旅をし、新たな経験を積んで還ってくること、その夢自体が彼らにとって肉体を更新する物質的経験であると主張する5。デスコラは、シュアールと言語的かつ文化的に非常に近いアチュアールの人々にとって、睡眠中の夢におけるアルータムの化身との出会いは個人的な力を蓄積する重要な機会であり、強い戦士のことをときに「眠り方を知る者」という意味の「カヌラウル」と呼ぶと述べる6。
このように、アマゾン熱帯雨林先住民の多くにとって、睡眠中の夢は単なる幻でも偶然の情景でもなく、それ自体がマテリアルな現実の一部であり、起床時の生を推進する強力なドライバーであることは、確かにこれまで論じられてきた。しかし、ここで俺が目を向けたいのは、とある民族に内在する解釈コードや彼ら固有の思考の存在を自明視するあまり、夢がいかに柔軟性や矛盾を伴いつつ主体の生を変革するか、民族的固有性なるものがいかにあっさりと溶解し、越境されうるかを見過ごしている点である。
実際、パストーラが言うように、大蛇を殺した夢を見たあとに本を読んで自分がリーダーになると信じ、実現した彼女に対して、最初は疑っていたセバスティアンはあっさりと「君が言ったことは本当だった」と認めている。疑っていた理由も、「君の夢はアヤワスカやマイキュアを通してのものではない」からだとか、「その本に書いてあることはシュアールの考え方ではない」からなどではなく、単に当時のパストーラの状態を見るに、彼女がリーダーになるという未来があまりにも彼の想像を超えていたからであろう。その後、セバスティアンに当時について尋ねても、彼が何らかのシュアール固有の思考システムを念頭に置いた上で、パストーラの夢についての主張がそこから逸脱していると感じていた様子はなかった。そもそも、「夢の本」をアンバトから買ってきたのは彼自身であり、それはそこに書いてある内容が自分たちにとっても意味があるものだとその時点で判断したからこそではないか。
マイキュアとアヤワスカによって得られるヴィジョンの重要性を事あるごとに強調し、これらの薬草に最上の価値を置いていると言って憚らないセバスティアン、そしてパストーラが、それらとは異なる経路をたどって得たヴィジョンの価値を僅かたりとも低く見ることがないという状況に、俺は当初戸惑った。マイキュアとアヤワスカで得るヴィジョンの価値を頂点に置いた場合、その手順を踏んでいないヴィジョンは真のヴィジョンと呼べず、前者よりも価値が下がるはずだと捉えることしか、その瞬間俺が持ち合わせていたロジックではできなかった。
しかし、「真実であって真実ではない」、「重要であって重要ではない」、「絶対であって絶対ではない」、「必然であって必然ではない」という矛盾の間を行き来すること、あるいはそれらを矛盾と認識しないこと、それでいてあらゆる言葉や行為に確信を込め続ける態度は、この森で生きていくうちに確かに俺の身体を浸し、意識を組み替えていく。
パストーラの語りから受けた衝撃は、もう一つある。それは、女性としてアマゾンの森で生きる上で彼女が抱えてきた忸怩たる想いと、現在のリーダーシップをめぐるジェンダー的構造が変わるべきであるという透徹した思考である。「アマゾンの女性たちもリーダーになるべきだ。なぜなら、私たちの方が男たちよりも多くの経験を積んでいるから」。決して西洋的フェミニズムに触れてきたわけではないパストーラが自らの経験と思考を根拠に森の片隅でこのような意識を内発させていることは、ジェンダーをめぐる支配的見方を大きく揺るがす。
端的に言えば、それは「非西洋社会の女性たちを目覚めさせるために、ジェンダー理論を教えなければならない」というある種の白人救世主的態度と、「彼ら固有のジェンダー観を保持させるべきである」という、あたかも現地の女性たちは現状に納得しており、それに影響を与えないことが世界の多様性を守ることなのだという不干渉の態度による無意味な二項対立である。そのどちらに与せずとも、パストーラをはじめ先住民の女性たちは、日々自らの置かれたジェンダー的環境と対峙し、思考し、行動している。彼女たちは、常に能動的変容の過程にいるのである。最も重要なのは、容易くかき消されがちな不定形の萌芽としてそこにある彼女らの声を、思考を、スポイトで液体を汲み取るように聞くこと、それがある種の言説的一貫性を攪拌することを歓迎し、歪な細い糸を切らさずに紡ぐことだ。
「彼女らもまた、変容している」という主張をわざわざ繰り返ししなければならないのは、アマゾン熱帯雨林先住民に関する人類学では、いまだに「◯◯族の女性は主に◯◯をして過ごし、男性は◯◯をする」など、あたかも研究対象のコミュニティ内部に安定したジェンダー的均衡が存在するかのように記述することが多いからだ。確かに、男女の分業は強い傾向として存在するし、それを無いものとして扱うべきではない。だが、それを透明な主語の基に硬直的に描くかどうかは別の問題である。おそらく、人類学者たちは想定した枠組みからはみ出る例外にもフィールドワーク中に出会っているはずだが、それは研究成果のアウトプットからは度々漏れ、触れられることがない。また、それらの例外がフレームワーク自体に歪みを生むものかもしれないという意識は弱い。
いや、むしろ、フレームワークを壊す可能性があるからこそ、捨象しなければならないという方が正しいかもしれない。なぜなら、フレームワークは権力をもたらすからだ。人類学が維持し続けるこの硬直した言説的態度は、我々が遠くの他者を想像する際の認識論的土台を築き、国際NGOや政府機関に援用されることで、結果的に周縁に生きる諸民族が体感している微細な現実の襞やミクロな語りを犠牲にし、読者たちに目眩ましをしている。このような言説の流通を攪乱し、現実の回廊に新たな毛細血管を開くためには、「フレームワークの樹立による権力の奪い合い」という人類学が抱える男性主義的欲望そのものを批判的に乗り越え、記述という行為に今までとは異なる命を吹き込まなければならない。そうでなければ、パストーラの語りをすくい取ることは決してできない。
「エミリー、元気? 例の村で一箇所だけ少しネットが通じるところに来てる(笑)仕事の面接結果はどうだった? 良い結果が出るのを願ってるよ。とにかく、こっちは無事に生きてる。また連絡する! 愛してる」。辺りがみるみる薄暗くなる中、森での作業後の疲労感を感じつつも高速で親指を動かしてなんとかエミリーにフランス語で短いメッセージを打った。こちらが夕方17時半頃だとすると、フランスは午前11時半頃。電話が繫がるかもしれないと思ってかけてみたが、彼女は出ない。これで3回連続で電話が繫がらなかったことになる。しかも、1週間前に送ったメッセージにはまだ返事が来ていない。不安が頭をよぎる。彼女の身に何かあったのだろうか? それでも、俺が無事であることは伝えておいた方がいいし、村の中とはいえ、夜になる前にこの地点に寄れるタイミングは意外と見つけるのが難しく、毎日必ず来られるわけではない。伝えられるときに伝えておかないと、後悔する。森が漆黒の闇に包まれる直前の僅かな光を頼りに、忍ばせていたエミリーが写っているポラロイド写真を眺める。何十秒も見てその顔を目に焼き付け、彼女が今どう過ごしているか、想像し、愛の念を送る。
ケンクイム村には、電波もネットも届かない。プリペイド式SIMカードを買ってエクアドルの電話番号は手に入れていたし、都市部では3Gも使えたが、ここではそれらが遮断される。唯一、村の中心から原生林の方へ向かう途中に登る傾斜の途中に、一箇所だけ電波とネットがギリギリ届くスポットがある。幅80センチくらいのゴツっとした岩が目印だ。その岩の目の前に立つと、半径1メートルくらいの範囲内のみで、iPhoneの右上に「E」と表示される。低速のネットが繫がっていることを意味するマークだ。YouTubeはおろか、情報を検索したりSNSを見ることは全くできないが、WhatsAppのメッセージを送ることはできる。ただし、画像や動画の送受信は一切できない。家族にもエミリーにも、俺がどんな環境に住んでいるのかを言葉以外でなかなかシェアできないまま、何週間も経っていた。メッセージを送るにしても、限られた時間では長い文章は打てない。
電気に関して言えば、ケンクイム村には一部電気が通っていた。村の真ん中に位置し、子供たちがサッカーやバレーボールに興じたり、村のミーティングや祭りが開かれる「エスパシオ・クビエルト」の天井には照明が取り付けられている。また、多くはないが世帯によっては電気を引いているところもあり、電球やコンセントを1つや2つ持つ家もあった。セバスティアンの姉ガブリエラと夫であるフランシスコの家がその一つだ。彼らの家は村の中心に近く、ナマキム川の川辺に位置するセバスティアンとパストーラの家からは徒歩5分くらいの距離がある。フランシスコは60歳を超えていて、腹回りの肉付きの良さから村人たちに「ゴルド」=(スペイン語で「太っちょ」の意)という愛称で呼ばれていた。また、彼は村の最年長者の一人であり、シュアールの歌や神話、その他の知恵に詳しかったこともあり、セバスティアンは俺やパストーラを連れてよく彼の家を訪ねた。セバスティアンの長男であるダルウィンは、フランシスコの娘と、従兄妹同士で結婚しているという繫がりもある。
俺は時々、iPhoneの充電をそこでさせてもらうことがあった。古い機種だったので1日中電源を入れているとその日の終わりを待たず切れてしまうが、なるべく機内モードに設定してバッテリーの減りを抑えつつ、フランシスコの家などで充電の機会を得ることで、俺は傾斜の岩の近くでWhatsAppメッセージを送受信できるチャンスに備えていた。
だが、iPhoneの充電をさせてもらうだけでも、そこにはいくつかの課題が伴う。1つ目は、充電中のiPhoneを守ることである。どういうことか。電気が引かれ、コンセントを持っているフランシスコの家は、村の他の家と同じように自前で建てた木造のものだ。床は板を敷き詰めた高床式で、板同士の間には隙間がある。また、誰かが部屋を歩く動作などで、床は時折激しく震動する。つまり、ケーブルに差したiPhoneが、俺たちが家を訪ねている間に床下に落ちるなど、アクシデントに見舞われない保証はどこにもない。スマートフォンを充電する想定で取り付けられていないコンセントは、家の入口を入ってすぐ右の柱の下部にあり、iPhoneは床にさらされる状態となる。
そこにさらに加わるのが、子供たちや犬の存在である。フランシスコとガブリエラには何人も子供がいるが、彼らはすでに全員大人になっている。しかし、アマゾン熱帯雨林の多くの先住民の村と同様に、彼らの家には常に甥っ子や姪っ子、孫、従兄弟の家族など、ほとんどが血縁・親類関係で繫がっている他の村人家族の頻繁な出入りがある。犬も状況は近い。飼い主は各世帯に分かれているが、この村の犬たちは人間から独立した生活を営むかのように森中を駆け回っており、気付かれれば追い出されるものの他の家の犬たちが何らかのタイミングで一時的に別の家に紛れ込むことは日常茶飯事である。1歳から5歳くらいまでの幼児が床に隙間の多い小ぶりな木造の家を走り回り、あらゆる目についた物を触って遊んでいる中、どこかからやってきた犬たちが徘徊している光景を想像してほしい。そのとき床に置いてある充電中のiPhoneは、果たして無事でいられるだろうか?
2つ目の困難は、フランシスコたちの家を訪ねる際に、チチャを飲まずに、あるいは差し出された軽食をいただかずに出入りすることが実質的にできないということだ。シュアールの村々では、兄弟姉妹、親、子供を含め、どんなに近しい客人がやってきたとしても、箇条書き的に要件のみを済ませて訪問を終わらせることは注意深く避けられる。どんなに丁寧な挨拶やお礼の言葉で挟んでも、この過程を飛ばすことはできない。チチャを介した物質的かつ感情的な交歓によって社会的関係をその都度紡ぎ出すことが、あらゆる要件に優先されると言っても過言ではないからだ。その導線を破る行為は、村での自らの社会的存在を危うくする。言うなれば、30分間だけコンセントを借りるにも、その過程でどんな言動を選択するかには微視的なレベルでの政治性が賭けられており、単に「お礼の言葉を言う」のとは質の異なる非言語的プロセスが「信頼空間」を編み上げるための設計図に書き込まれているのである。
もちろん、俺の滞在開始直後に「エスパシオ・クビエルト」の照明が故障し、それきりフィールドワーク終了まで復旧しなかったように、せっかく引かれている電気や取り付けられたコンセントが機能しない可能性も常にある。これらの困難を考慮するとき、「ケンクイム村に電気はあったのか?」という問いに答えるのは難しい。「電気はあった」と答えるときに人々が覚えるある種の安心感は、実際の現地の状況や俺の経験を反映していないからだ。電気へのアクセスという単純に聞こえる目的自体が、シュアールの村の隅々にまで張り巡らされた関係性の網目の中に、あるいは容赦なく降りかかる森や天候の激しい変異の連続に、不可避的に条件付けられているのである。
iPhoneは機会を見つけて充電することができたが、撮影用に持ち込んでいたカメラのバッテリー充電にはより時間がかかり、ダメージが生じたときのリスクが大きすぎたため、村でコンセントを借りて充電することはできなかった。対応策として、闇雲な撮影を控えてバッテリーを消費しないように心掛けつつ、充電が切れたときはタイミングを見てマカスに一泊し、ホテルで充電するようにした。おおよそ、月に1回くらいそのためにバスで片道約3時間をかけてマカスに通っていた。家族とビデオ通話をして近況を報告できるのも、そのときだった。
マカスで泊まる行きつけの宿は、あえて自分で調べず、パストーラとセバスティアンにどこに泊まるべきか聞いた。マカスというメスティーソが作った街を、彼らの視点で捉えたかったというのが一つの理由だ。また、彼らから教えてもらった宿に泊まることで、「あらゆることを彼らに教えてもらっている」という信頼と、「彼らと同じ金銭感覚を共有し、彼らが通う場所に対して違和感を抱いていない」というメッセージを行動によって伝えるためだ。彼らにとって、外国人である俺が村の外部の街で泊まるということは、それだけでそのための資金があることを明示する。パストーラをマカスの病院で看病していたときに「7ドルのホテルに2泊して、手元に50ドルもない」状態だったセバスティアンのエピソードを聞いても、彼らにとって金銭で何かを行うことは、橋を渡って世界の向こう側に行くのと同じことなのだ。
彼らに教えてもらった一泊10ドルの安宿の部屋でバッテリーを充電しながら、撮影した写真や映像を落ち着いて整理する。高い頻度で床が水浸しになる屋根が張替え中の家では、冷静に作業ができないからだ。それでなくとも、村では身体を使う様々なアクティビティによって手が汚れていることも多い上、村人や子供たちの出入りも激しいため、嫌でも注目を集めてしまうMacBookやハードディスクをスーツケースから出すのはなるべく控えたい。
「彼らと同じ感覚を共有する」ことを徹底して自らに課しつつも、マカスに滞在するときに唯一自分に対して許したのが、レストランでホワイトソースを和えた海老入りのスパゲッティを食べることだ。たまに訪れるマカスではいつも市場や食堂でアマゾンで採れた淡水魚を使った3〜5ドルくらいのスープなどを食べるセバスティアンやパストーラが、10ドルを超える価格のこのスパゲッティを食べることはまずあり得ない。価格の問題だけではなく、彼らはアマゾン料理以外の食べ物に対してほとんど食欲が湧かないのだ。非日本人の多くが忌避する納豆を俺は愛してやまず、できることなら毎日食べたいことと、その構図は似ている。彼らは、消去法でキャッサバやプラタノ、パパチーナを食べ続けているのではない。彼らはそれらを、愛してやまないから食べている。だが、俺はアマゾンの森で採れるそれらの糧を主体とする毎日の食事に満足しながらも、いや満足していると自分に暗示をかけながらも、数ヶ月で自分の食欲の性質を完全に塗り替えることはできなかった。これもまた、否定しがたいフィールドワークの真実だ。
「ホオオオオウ!」「フイ、フイ、フイ!」セバスティアンやオズバルド、アントニオなど、村人たちが様々に雄叫びを上げながら自分たちを鼓舞し、ぬかるんだ森を力強い足取りで進んでいく。雨季の真っ只中、久しぶりに晴れ間が覗いた森で、柔らかな朝日が木々の間から差し込む。消えかかっている朝霧が、光を粒上に霧散させ、テラテラと肌に染み込ませる。鳥たちの陽気な声の掛け合いが響き渡る。
今日はセバスティアンとパストーラの家の屋根の張り替えに必要な、ヤシの葉を集めるためのミンガの日だ。「ミンガ」とは、村のメンバーの誰かが主催して村人たちを集め、自分の生活に関わる大仕事を丸一日かけて手伝ってもらう共同作業を意味する。多くの人手を一つの世帯のために動員するミンガは、別の機会では他の村人のために力を割くことで互酬的に労働を循環させる機能を持ち、アマゾン熱帯雨林における贈与経済の肝をなす。ケチュア語に由来するこの言葉は、シュアール語では動詞で表現され、「ミンガを開く」ことを「イピャマムー」=「ipiamamu」と言う。通常、活動をしたい前日に呼びたい村人たちの家々を周り、参加者を集める。主催者はできる限り上等の昼食と、発酵が進んだ強いチチャを用意する義務を負い、参加者たちのモチベーションを高めようとする。
俺がケンクイム村に住み込みを始めて以降、屋根の張替え作業に関わるミンガは何度も開催され、完成するまでに数ヶ月を要した。大きく分けて、行程は2つ。まず、「プンプナ」と「チャピ」という2種類のヤシ科植物の葉っぱを、森のあらゆる場所から大量に集め、しばらく置いて乾燥させること。次に、乾燥したプンプナとチャピの葉を折ることでパーツを量産し、家で実際に屋根葺きを行うこと。第1段階と第2段階に分かれた制作ではなく、集めた葉っぱがある程度乾燥したら屋根葺きを一部行い、また葉っぱを集め……というように、何度かのサイクルを繰り返しながら行われた。俺はほぼ全てのミンガに実際に活動を行いながら参加した。絵に描いたような「参与観察」である。
世帯ごとに土地の配分が行われているケンクイム村では、セバスティアンの領地からだけでは必要な量の葉っぱを得ることはできない。そのため、セバスティアンは領地内にそれらの種の葉っぱを持つあらゆる村人たちに尋ね、葉っぱを採っても良いという了解を得て回った。また、その日の翌日にミンガの開催を計画している場合は、ミンガに参加してもらえないか聞いていた。セバスティアンと村人たちの全ての会話の現場に立ち会っていたわけではないが、彼らの発言を聞く限り断られるケースはほとんどなかったと言える。むしろ、村人たちは高いモチベーションで地道かつ過酷な屋根葺き作業に取り組んでいた。
それには、セバスティアン個人が村人たちから得ている人望だけではない理由がある。実はセバスティアンとパストーラの家の屋根は、ケンクイム村に唯一残る、葉っぱで葺かれたものなのだ。他の家々の屋根は全て、アルミ製の板を組み合わせて拵えられていた。ミンガに参加していた村人たちが口々に強調するのは、「セバスティアンはシュアールの屋根の葺き方を今も守り続けている、それをサポートしたい」という意志である。セバスティアンはよくこう言っていた。「葉っぱで作られた屋根は、気持ちがいい。雨が降っても音がうるさくないし、太陽が強くても家の中は涼しくなる。それに、古くなったら森に捨てれば土に還る。森にとって一番いいんだ。アルミ製の屋根は化学的で、自然じゃない。シュアールとして僕は、葉っぱで屋根を張らないといけない」。屋根が無事完成したら、彼はこの家を村人に開放し、アヤワスカの儀式を行うための神聖な場所にしたい、とも話していた。覚醒植物によるイニシエーションを行うために特別に用意される小屋のことを、彼らは「アヤムテイ」=ayámtaiと呼ぶ。エルケ・マデルの先行研究によれば、その小屋は家の外部になければならない7。しかし、ケンクイム村では、セバスティアンとパストーラの家が、他の村人たちにとってのアヤムテイとなる。それは、現代のアマゾン熱帯雨林で彼らが置かれたある種の窮状と、それに対する懸命な応答を端的に示してもいる。
マイケル・ハーナーが1963年にカリフォルニア州立大学バークレー校に提出した博士論文内で論じているように、シュアールたちは少なくとも20世紀以降、石器の使用をやめて鉄製のマチェーテや斧、鉄砲などの工業製品を森の外部から継続的に獲得してきた歴史があり、それらのテクノロジーはシュアール社会に絶大な影響を及ぼしてきた8。ハーナーは、本来食料などの生産性を高めるための道具として需要があった鉄製道具は、現地の人々によると実際には生産性を高めることには貢献せず、むしろ低下させたと主張する。なぜなら、導入以前は木を切り倒さずに実だけを収穫していたのが、木自体を切り倒す収穫法が主流になってしまったからである。
また、金銭的富と特権を示すそれらの鉄製道具は、次世代の若者たちにとってその獲得自体が目的化する対象となり、より効率的に生存を支えるための道具という存在意義から離れ、チャクラを開墾する意欲などを失わせてしまったと、ハーナーは論じる。例えば、それまで使用されていた毒矢などに比べて狩猟を圧倒的に容易にした鉄砲は、皮肉なことに食料としては見做されず、毛皮や羽が取引の対象となるジャガーやオオハシの乱獲を引き起こした。その目的は、特権の象徴である鉄器のさらなる獲得である。このように、フェティッシュ化された鉄器は、その本来の使用価値を離れ、さらなる鉄器の蓄積のための道具と化した9。
これを踏まえてアルミ製の屋根にもう一度目を向けると、それは確かに道具ではない。また、それを所有することが特権の誇示にことさら役立つわけでもない。しかし、葉っぱで屋根を葺くという手間のかかる行程を金銭によって一気に省略し、効率化する工業製品である。それは導入当初、シュアールをはじめアマゾン熱帯雨林の先住民たちにとって自分たちを面倒な作業から解放する物として歓迎されたはずであり、今現在に至るまで、少しずつ普及の範囲を広げ続けている。
しかし、村の全ての家がアルミ製の屋根に切り替わりつつある地点に立ったところで、村人たちは自分たちが何か決定的なものを手放そうとしている、ということに気付きつつあるのかもしれない。もしアルミ製の屋根が葉っぱの屋根よりもあらゆる点で優れていて、後者はもはや必要ないという確信があるなら、次は自分のミンガに参加してくれること以外に大きな見返りも無いに等しいセバスティアンのミンガの誘いに喜んで応じるかは疑わしい。なぜ葉っぱの屋根が優れているかを力説するセバスティアンの言葉からは、長きにわたって自分たちの変わりゆく姿を見つめながら、「良く生きる」=buen vivirとは何かを再帰的に、身体感覚全体によって反芻した跡が感じられる。雨の音も、通り抜ける風の涼しさも、葉っぱが腐り土に還っていく光景も、いまや所与のものではなく、能動的に選び取らない限り、手元から離れていってしまうものなのだ。
先述したように、現代のアマゾン熱帯雨林先住民について論じる際に「自然」と「文化」の二項対立を脱構築することをひたすら目指す理論的態度は、現地の住民たちの実践や主張に丁寧に耳を傾ける限り、その問題意識の重要性を部分的に引き受けた上で、ベクトルの向きを再考する必要が大いにある。アルミ製の屋根に侵食されるケンクイム村の中で徹底して葉っぱで屋根を葺くことにこだわったセバスティアンの意志と、それに他の村人たちが高いモチベーションとともに協力する姿、またそれに対する彼らの理由付けを聞いても、それは明らかだ。彼らにとって、それら2種類の屋根は、「どっちも結局自然」なのでもなく、「どっちでも良い」のでもなく、「その境目はない」のでもない。逆に、その違いは途轍もなく大きい。そして、どちらを選ぶのか、あるいは選ぶことを肯定するのかは、屋根を一つ獲得するまでのプロセス全体、つまりそこに賭けられる時間や情動、身体感覚、あるいは金銭、そして人間および非人間的諸存在との関係性の揺れ動きを通して、彼らにとっての世界そのものを物質的かつ知覚的に形作ることに繫がっている。屋根の作り方の選択は、「自然」とどのように関わるのか、そこに彼らが見出す意味とは何かを炙り出し、異なる諸力がせめぎ合うアリーナにほかならない。
ここで注意しなければならないのは、一見矛盾するようではあるが上に書いたことは決して「全てが自然物で構成されることを理想とする」立場を彼らの態度に見出すものではないということだ。例えば、セバスティアンは決して、マチェーテを捨てて石器だけで生きようとはしておらず、ゴム製の長靴を捨てて裸足だけで森を歩こうとしているわけでもない。俺が強調したいのはむしろ、ピエール・ルモニエが編書『技術的選択』(1993年、未邦訳)の導入で述べるように、物質世界に対する人々の行動を規定する精神的過程は、より広い社会的文脈や象徴システムに埋め込まれたものであるということ、技術をめぐる社会的表象は、物質やエネルギーの領域を越えた思考の混淆物でもあるということだ10。彼らにとって何をどのように使用するかの選択は、常に再発明されることであり、重要なのはそこに込められた価値の諸相を見落とさないことである。その点において、「自然」は学び捨てるべき概念ではなく、むしろ言説化の過程を通して価値や基準のボーダーを歪に紡ぎ出す、ほつれた網の目のような役割を担っている。
セバスティアンはときどき、葉っぱを運ばせるための馬を借りたりするとき、通常は考えられない大金を要求されることがあると愚痴をこぼすことがあった。それは間違いなく、外国人である俺の存在が原因である。俺以外も含め、外部からの訪問者と繫がりを持つセバスティアンは、ときに村人たちから金持ちに違いないと嫉妬されていたのだ。実際のところ、セバスティアンから金銭を要求されたことは一度もなかった。彼は所持金が全くなくとも、森から得られる糧さえあれば何も問題はないと真に思っていたからだ。後述するように、俺の滞在中の金銭を巡る難しい舵取りは、パストーラや他の村人たちとの間で行われることになる。
先ほど俺はミンガを「贈与経済」と呼んだ。贈与経済とは狭義では金銭を介さない経済の在り方の一つである。しかし、現実には現代のアマゾン熱帯雨林の村々では、一部金銭のやり取りが発生するミンガも増えている。「日当」という形態など、明らかな賃労働を外注することはいまだにご法度と言えるが、「馬を借りる」や「大量の葉っぱをもらう」、「足りない分のチチャを補う」、「昼食で提供したい肉をもらう」など、ミンガの開催に伴い個別に必要となる要素を確保するために、村人同士の裁量で金銭を要求するなど、支払いを提示することは珍しいことではない。それでもミンガが贈与経済の一形態であると言えるのは、「一日をミンガへの参加に充てること」自体には値段が付いていないからだ。ミンガを賃労働として捉えていない限りにおいて、つまり「誰かのミンガに参加したこと」が「次は自分がミンガを開催できる」ことに繫がること、「参加してくれた人のミンガに、次は自分が参加しなければならない」というある種の契の心情が強力に発生する点において、ミンガは揺れ動きつつも贈与経済であり続けている。
森を何十分か歩き、今日の作業スポットに到着した。村の最年長者の一人であるフアンの領地だ。参加者は10人くらいだろうか。雨季のスコールに備え、枝と葉っぱを広く張り巡らせ、夥しい数の寄生植物でモジャモジャになっている木の下に、荷物を置く。一息つく間もなく、到着したらまずチチャを皆で回し飲みする。主催者の妻であるパストーラが、用意したチチャを一つのお椀に注ぎ、それを全員で回し飲みしていく。一人ずつ飲み干すことはなく、それぞれが飲みたい分だけ飲めばよい。何人かが飲むと、パストーラがもう一度お椀を受け取り、チチャを並々と注ぎ、手でお椀の縁を一回転するようになぞってキャッサバのかすなどを拭き取ってから再び村人に手渡す。このサイクルを二度、三度、あるいは四度と繰り返す。
チチャを飲んでいる時間は、他愛のない村人同士の会話が隙間なく満たす。「この前あいつが森に行ったとき、猿を見つけたのに、躓いて転んで捕まえられなかったらしいぞ」だとか「この前お腹が痛かったときに使った薬草は全く効かなかった、あれは酷いもんだ」、「夢でこんなことを見たから、きっと今日はこんなことが起きるに違いない」など、事実とも作り話とも判別が難しいエピソードが次々と繰り出され、一人が話し終わる前に別の誰かが突っ込み、文脈が異なる別の話題を差し込んでいく。まるで相手の話を遮断しているかのように聞こえるが、お互いにとってそれが当たり前のようだ。森を探索している間に起きたこと、動植物とのおかしなエピソード、以前見た夢などに加え、性的な暗喩が幾重にも折り重なりながら語られる。例えば、この日は次のような会話がゴンサロとカロリーナの間で交わされた。
「子供が木を揺らしすぎたせいで、鳥が木から落ちてケガしちゃったの」
「それなら、その鳥に蜜蝋を塗ればいい。すぐに回復するさ」
「私の蜜蝋はもう古すぎるよ」
「大丈夫だ、蜜蝋は熟せば熟すほどいいんだ」
この会話が交わされていたとき、2人の間でも周りの村人たちからも、それが何かの暗喩であるという突っ込みが挟まれることはなかった。また、明らかにそれが暗喩であり、会話が指している本当の内容は別のことであるということが明示されるような爆笑やそれに準ずる反応もなく、一つの笑い話として淡々と会話は続き、自然と別の話題に切り替わった。
しかし、たまたま動画として撮影してあったこの会話部分をある日スリティアクに見せると、彼女は転げ回って爆笑した。「ナンキ! なんて会話を撮ってるんだ!」嬉々としてスリティアクが語るに、この会話には明白に性的な意味が込められており、それは誰も笑っていなくても全員が気付いていることだという。「シュアールの会話はそういうもの。私たちは常にセックスの話をしている。ハッキリ冗談にするとか、全員で笑うとか、そういうものじゃない。普通に会話しているように見えてもどこかに意味が込められていて、それはみんなわかってるんだ」。それは、文に「表と裏の意味がある」こととは異なる、特異な言語の指向性を表しているように思える。個別に抜き出して羅列できる実体を持つのではなく、一つの文それ自体が還元不可能な多方向性を持ち、「解釈の固形化」そのものを霧散させるような力を持つように思えた。文脈や内容が徐々に積み上がっていくというよりは乱反射しているかのように、モンドリアンの「コンポジション」というよりはむしろポロックの「コンヴァージェンス」のような、激しく交錯する意味と情動の流れがそこには感じられる。そして、この「モノとしての摑めなさ」は、彼らの森に対する態度に、通奏低音として響いている。
チチャで皆が酔い切る前に、セバスティアンが声をかけ、「さあ、仕事をするぞ」と雰囲気を作る。全員がサッと切り替えて機敏に移動するわけではないが、石などで研ぎ上げたマチェーテを手に、男たちは何組かに分かれて葉っぱがあるスポットに向かう。俺はセバスティアンがいるそのうちの一組に自分のマチェーテを持って付いていった。
「皆が酔い切る前に」と書いたのは、今回よりは小規模な屋根葺きのためのミンガで、作業前にチチャを飲みすぎて参加者の仕事のやる気がなくなってしまい、ほとんど葉っぱを集められなかったことがそれ以前にあったからだ。ここには、チチャという物質がシュアールによって、単なるアルコール入りの栄養補給物をはるかに超えた存在である理由について考える糸口が隠されている。
ここで、ミンガの場におけるチチャを「微生物の力を利用して、女性が男性の労働力を最大限に発揮させるための装置」だと解釈してみる。すでに触れたように、チチャは女性たちが茹でたキャッサバを主な材料として使用し、そこにカモーテ(スイートポテトの一種)を少量加え、嚙んで柔らかくしつつ自らの唾液を含ませ、鍋に吐き戻すことで唾液が持つアミラーゼの力を利用して分解・発酵させる口嚙み酒である。ミンガの場で求められるチチャは、一晩だけ発酵させた甘みのある「チチャ・ドゥルセ」ではいけない。それは、強く発酵した状態で力仕事を行う男たちを酔わせ、覚醒させ、ある種の集団的変性意識に持ち込むことが求められる。ミンガに参加する男たちが口を揃えて言うのは、「俺たちは強いチチャを飲めば飲むほど仕事のやる気が出る」ということ、ミンガのときはそれが絶対に必要だということだ。
しかし、一方で何度か観察したのは、強いチチャを飲むことが自己目的化してしまい、男たちがひたすら酔っ払っていき、作業が進まないまま一日が終わってしまうという現象である。それは、家を建てるためや新しいチャクラを開墾するためなど、家庭生活にとって死活問題となるミンガが不発に終わることを意味し、女性たちにとっても歓迎すべきことではない。その意味で、女性たちが心血を注いで磨く技術の一つは、「男たちの仕事へのやる気を高めつつ、酔うことが自己目的化しない程度の強さのチチャをいかにして作るか」であるとも言える。それは、アナ・ツィンが述べる「気づく術11」、すなわち非人間的存在の時間と意図に自らをチューニングし、触角を伸ばし、点と点を合わせる技術にほかならない。
チチャの発酵が強く進んで飲み応えがある状態になるのは、天候や気温にもよるがだいたい2日から3日弱寝かせたときだ。ミンガの日程は、チチャの発酵が翌日にピークに達するタイミングを見計らって決められる。その手前でもその一日あとでも基本的にミンガは開催されず、人が集まらなかったり雨があまりに酷い場合などは、最低でも2〜3日間を空けるか、他の世帯がたまたま飲み頃のチチャを大量に持っている場合はそれをもらう、あるいは買い取るなどして用意することになる。フィリップ・エリクソンが述べるように、アマゾンにおける催事には、口嚙み酒を基準とした厳格な計画が不可欠なのだ12。
実は、チチャは毎回真新しい材料から作られるのではなく、前回のチチャの残りを少量取り置きし、混ぜることで、いわば「チチャ菌」を飼い慣らしている。前回作ったチチャが腐敗してしまい、捨てざるを得なくなった場合、別の世帯からチチャの残留物をもらってこなければならない。その手間をなるべく省くため、チチャ作りのサイクルは前回分が腐る前のタイミングを基準として繰り返される。日常生活において他の村人などの訪問者に必ずチチャを与えなければならないということ、さらにそこにミンガ開催の日程調整が組み込まれること、それぞれの場面のために適切なチチャの発酵度合いが存在し、シュアールの人々にとってそれを飲み交わすことが社会生活の源泉であり根幹をなすということを考慮するとき、次のような発想の転換がありえる:すなわち、この熱帯雨林における生の鼓動を司っているのは、人間というよりもむしろチチャであり、発酵をもたらす微生物なのだ。チチャの作り手である女性たちは、チチャを介して微生物の能力を引き出す媒介者であり、男性たちが斧を振り下ろす力を発揮させて社会生活を循環させる複雑かつ繊細な技術を日々研ぎ澄ませているのだとも言える。
プンプナが生い茂っているスポットで、付いてきたグループの男たちとチチャを飲みながらひたすら葉っぱを茎の根元から切っていく。その後、茎を短く切り落とし、葉を茎の付け根から10センチくらいのところまで半分に割いて何枚か重ねて置く。葉の数が溜まってきたら、細めの木の枝を4本集め、点を結ぶと真四角になるように垂直に地面に差す。その四角の中に収まるよう葉っぱを2列に分けて重ね合わせ、左右を強く折り返す。そのとき、地面に差した枝を葉っぱが飛び出さないための支えとして使う。折りたたまれた葉っぱの束を、予め近くに生えている別の植物の茎部分を剝がして表皮だけにしたものを紐として、強く締めて結ぶ。
独特な葉っぱの束ね方を不思議に思って観察していると、セバスティアンは「これがシュアールのやり方だ」と誇らしげに言った。一緒に作業している村人たちもこのやり方を共有しているようで、「その部分を折り曲げろ」「もう少し多く葉っぱを重ねられる」「締め方が緩いぞ」など、口々に細かいコツをアドバイスし合いながら葉っぱをまとめていた。一つの作業にも、彼らにとって押さえなければならないポイントがいくつもあり、それらが満たされていることが、良い仕事ができている証となる。チチャをかっ喰らうことで酔いが回りながらも、ディテールに対する彼らの感性は鈍るどころかより鋭くなっているように感じられた。酒に酔いながら力仕事をした経験がそれまで全くなかった俺も、活気と笑いに溢れた彼らの会話に混じりながら作業することで、どんどん力が漲ってくる。もう何度も葉っぱを集めるミンガに参加しているが、チチャが量や質の面で足りていないときは、仕事が捗りにくい。何百何千という葉っぱを収穫する地道な作業は、チチャが活性化させるリズムによって、愉快になり、交歓深度を高める。
観察もほどほどに、俺も葉っぱを折りたたむ作業に参加してみる。決して複雑な動きではないため、何度か繰り返すうちに彼らと遜色ない出来の束を作れるようになった。それを見るとセバスティアンは「この男は物覚えがいい。もうシュアールと同じ仕事ができるようになった」と、嬉しそうに周りの男たちに声をかけていた。
束になった葉っぱをみんなで担いで、作業スポットの近くにまとめて置きに行く途中のこと。突然、行く手に凶暴そうな蜂が数匹現れた。正確な種はわからないが、スズメバチと非常に良く似た姿をしている。すぐ近くの木の幹に大きな巣があり、サイズが大きいものからまだ小さいものまで、無数の蜂たちが飛び交っていた。大きな蜂に刺されたら看過できないダメージを受けることは、どうやら皆の共通理解のようで、ブンブン音を立てて飛び回っている蜂を刺激しないように慎重に巣の横を通り抜けた。
その後、束ねたプンプナの葉を地面に下ろすと、フランシスコの息子であるダニエルが言った。「蜂を殺すぞ」。その言葉に俺は面食らった。相手にするのは攻撃性が高い蜂で、失敗すれば集団に刺されて大変なことになる。うまく避けながら作業をすれば、蜂だって遠くまで追いかけて刺すわけではない。わざわざ殺しに行く必要があるだろうか! だが、周りを見渡すと、居合わせた男たちは誰も異議を持たないようだ。むしろ、積極的に蜂を殺すことを望んでいるように見える。
ダニエルは、近場の落ち葉を物色すると、雨季には珍しいその日の日照りで十分に乾いた葉の束を一摑みして、「うん、これが殺すのにいい葉だ」と言った。持っていたマッチで手摑みのままの落ち葉の束に火を点けると、スタスタと蜂の巣の方に向かい、暗殺者のように滑らかな動作で蜂の巣に燃える落ち葉を突っ込んだ。パニックに陥った蜂たちの一部は巣の外に出て飛び回るものの、不思議にもダニエルを攻撃しに掛かる様子ではなく、むしろ不意を突かれて為すすべがないかのようだった。
無言でじっくりと、手の中の落ち葉の束の位置を少しずつ変えながらダニエルは蜂の巣を燃やし続けた。その時間は1分くらいだろうか。巣の半分以上が燃え、中に残っていた多くの蜂は死ぬか弱りきっている。木の幹から巣を剝がすと、ダニエルは皆に向けて「蜂、食べるか?」と勧めた。そうか、巣を燃やしたのは蜂を食べるためだったのか。焼けた巣を見せてもらうと、弱った成虫に混じって多くの生きた幼虫がひしめいていた。ダニエルはそれらを摘みだすと、何匹か口に入れて見せた。「美味しいぞ。身体にもすごくいい。疲れが吹っ飛ぶさ」。蜂を食べた経験はそれまでなかったが、恐る恐る1センチくらいの幼虫を生きたまま食べてみると、プリプリとした食感と口の中に蕩ける中身がたまらなく美味しい。これは何匹でも食べられそうだ。
セバスティアンにも蜂を勧めようとして彼の方に向かうと、妙に距離を取っていた。「セバスティアン、蜂食べない?」「ああ、蜂か。本当は、蜂はシャーマンしか食べてはいけないものなんだ。でもまあ、もらっておくよ」。そう言うとセバスティアンは何匹かの幼虫を口に含んだ。彼は時々、呟くようにいつも守っているわけではない食のルールについて教えてくれる。例えば、川で採れるワンチャという魚は、子供が食べるのはよくないとされている。殺すときにブルブルと震えるその魚を食べてしまうと、男の子は戦争を、女の子は出産を恐れる大人になってしまうと言われている。
ダニエルが危険を顧みず蜂の巣を襲おうとしたのは、蜂を食べるためという目的があったからだということが後に理解できた。しかし、危険な野生動物や虫に出会うとき、逃げたり避けるのではなく、必ずと言っていいほどリスクを取ってでも殺そうとするのは、フィールドワーク中の彼らの行動を観察していて興味深い点の一つだった。森の深くでジャガーと出会った話をするとき、「いかにうまく逃げたか」を語る人は皆無に等しく、多くの話は「いかに仕留めたか」あるいは「いかに惜しくも取り逃がしたか」についてである。アナコンダ、あるいはシュアール語でパンキ=pankiと呼ばれる大蛇も、食用ではないにも拘らず、出会ったら必ず捕らえるか殺そうとする。ジャガーはその牙や毛皮、アナコンダは骨や皮が工芸品に使用されるため、その価値は確かに高い。だが、ケンクイム村もそうであるが、アマゾン熱帯雨林では売買するルートがすぐ手に届くところにあるわけではない。大抵の場合、それらは仕留めた人間の手元にしばらく残り、結局売らずに終わることも多い。
ヴィヴェイロス・デ・カストロが「狩猟イデオロギー」と呼んだ、彼の主要理論である「パースペクティヴィズム」の支柱をなす構成要素の現前が、シュアールたちのこのような態度に垣間見えているとも確かに言える。それが「生態学的必要性ではなく、象徴的重要性の問題13」であることも、間違いない。だが、シュアールたちにとっての獲物を狩ることの高い価値を認めつつ、より重要かもしれない要素として俺が彼らの態度に見出すのは、「前に進む」ことの至上の価値である。彼らにとっては、「リスクがある状況に対して、逃げずに前に進み、戦う」ことが、「獲物を狩ること」に先行する価値であるように思えるのだ。そして、それはヴィジョン経験と切っても切り離せない関係にあり、彼らにとって自らの未来を能動的に創出するために必要な態度である。
パストーラが襲ってきた大蛇を殺す夢を見てリーダーになるというヴィジョンを得たというナラティヴは、俺がフィールドワーク中に記録した「前に進む」ことの重要性を示す最たる事例の一つである。だが、シュアールあるいは隣り合う民族が持つある種の「前進思考」について論じるのは俺が初めてではない。アンヌ=クリスティン・タイラーは、自身の研究対象であるアチュアールを含むヒバロ系の人々が、「強化された個人」と「前進的スタンス」を特徴とし、自分たちのことを持続的アイデンティティを基盤にした「社会」というよりは「それぞれが模範的な人生行程を形成することに励む個々人の集合体14」と捉えていると主張する。彼女はそれを白人性との歴史的交渉という視点から分析しているが、その点については後に少しずつ触れていくとしよう。ひとまず今確認したいのは、避ければ葉っぱを集める作業は問題なく遂行できる状況にありながら敢えてリスクを取って蜂の巣を襲ったダニエルの行動は、単に食料を得ること、あるいは獲物を狩りたいという欲求以上に、「生きること」に対する彼らの思考の結晶化でもあるということだ。
朝7時頃から作業を開始し、地道に葉っぱの束を量産してもう4〜5時間は経っただろう。昼食の時間だ。「ホオオオオウ」という雄叫びをセバスティアンがあげると、離れた場所で作業をしている他のグループのメンバーたちの名前を呼んで昼飯を食べることを告げる。焚き火の煙が立ち上がり、食欲をそそる匂いが香る草むらの方へ向かう。パストーラとカロリーナが作った鶏肉とコンキリエのスープがこの日のごちそうだ。その場で拵えた3本の丸太で火を焚き、大鍋を上に載せている。
鶏肉は家で放し飼いをしているクリオージョと呼ばれる種類のもので、森に棲む虫や餌として時々与えられるトウモロコシを主に食べて育つ。狩猟肉の減少によって現在では多くの村で一般化しており、猪や鹿、アグーチ、猿、野鳥などの狩猟肉に次ぐごちそうである。また、コンキリエなどのパスタ類は街で買えるもので、村内では高級品かつ貴重な食材のため、ミンガのような重要な機会で主に振る舞われる。すっかり村の感覚に染まりきった俺も、毎日はありつけない食材を使ったスープを見て心躍った。周りの村人たちも、ミンガに相応しいごちそうを前に嬉々とした表情だ。パストーラがそれぞれの人に対して「適切な」肉の量を配分し、一皿一皿配膳していく。鶏肉の部位、大きさ、パスタやスープの量は、その人物とセバスティアンやパストーラの関係や、世話になっている度合いなどに応じて、あからさまではない形で繊細に配分される。その判断を下すのは、主催者側の妻であるパストーラの役目だ。
「はい、ナンキ。これがあなたの分」。パストーラに渡された器には、高いとは決して言えない俺のミンガへの貢献度を考えれば、十分すぎる量の鶏肉が入っていた。感謝の気持ちがこみ上げる。心地よい身体の疲労と空腹を感じながら、すでに貪るように食べている他の村人たちに混じって食事を開始する。シュアールの世界には、食べ始めの挨拶は存在しない。食料を手にした者から、好きな場所で好きな姿勢で好きなペースで食べる。早速、約一週間ぶりにありつけた鶏肉にかぶりつく。
「よく煮込まれた柔らかい肉」ではない。アマゾン熱帯雨林の村で食べるクリオージョの鶏肉は、多くの場合硬い。だが、それが信じられないくらい美味いのだ。「鶏肉は硬いほうが良い」と、シュアールの人々は言う。「硬いのは、強い筋肉で森を駆け回ったから。そういう鶏肉の方がパワーがあるんだ。街で売っている籠に押し込められた鶏は、パワーがないから柔らかい。でも、僕たちはそういう鶏肉を美味しいとは思わない」と、セバスティアンは頻繁に語っていた。また、彼らは鶏肉を殺すとき、首を切り落とさずに締めて窒息させる。それは、敢えて血を抜かないことで鶏が持つエネルギーを逃さず得るためだという。焚き火の煙と木々が放つ豊満な匂いに包まれながら、つい今朝まで森を駆け回っていたクリオージョの硬く弾力性のある筋肉を嚙みちぎり、咀嚼する。その肉からは、鶏の生を通して染み込んだ森の香りが舌の上で確かに感じられた。その違いを実感できるくらい、俺の身体も森に馴染んできたということかもしれない。
夢中になってスープをすすっていると、カロリーナが横の方で何やら別の作業をしている。見ると、パイナップルを細かく切っては汁を絞り、チチャに混ぜている。その後、果肉もチチャに投入し、全体を攪拌する。この「チチャ・デ・ピーニャ」は、男たちのやる気をさらに高めるために女性たちが作る、いわばチチャの拡張形態である。パイナップルは一部の村人たちが育てていて、とても人気がある。その価値は高く、収穫期になるとパイナップルを持っている村人は他の家を回り、1個1ドルで売ることもある。バナナ類とは比較にならず、パパイヤなどと比べても貴重度は上がり、決して珍しいものではないがいつもありつけるわけではない。カロリーナは今、そんな果物を惜しげもなくチチャに大量投下しているのだ。俺も含め、皆のボルテージは一気に上がった。連日の土砂降りが続く雨季にあって、久しぶりに高く昇った太陽の下でひと仕事のあとに強烈に発酵したパイナップル入りチチャを並々と飲む快感は、何物にも代えがたい。
俺たちは昼飯のあとも必死に働き、せっせとプンプナの葉を集めた。いくら集めても屋根の完成には足りないような気の遠くなる作業だったが、少し頑張ればチチャ・デ・ピーニャにまたありつけるという期待感が、皆の背中を押した。チチャを喉に流し込み、他愛のない笑い話を交換しながら、日が傾いていく森の光と影を背に、マチェーテを振り続けた。
1. Hornborg, Alf, and Jonathan D. Hill (eds), 2011. Ethnicity in Ancient Amazonia: Reconstructing Past Identities from Archaeology, Linguistics, and Ethnohistory. Boulder: University Press of Colorado. p. 1.
3. Vilaça, Aparecida. 2005. “Chrinically Unstable Bodies: Reflections on Amazonian Corporalities.” The Journal of the Royal Anthropological Institute 11(3), 445-464.
4. Wright, Robin M. 2013. Mysteries of the Jaguar Shamans of the Northwest Amazon. Lincoln: University of Nebraska Press. p.36.
5. Stang, Carla. 2009. A Walk to the River in Amazonia: Ordinary Reality for the Mehinaku Indians. New York: Berghahn Books. p.50.
6. Descola, Philippe. 1996. The Spears of Twilight: Life and Death in the Amazon Jungle. NewYork: The New Press. p.305.
8. Harner, Michael J. 1963. Machetes, Shotguns, and Society: An Inquiry into the Social Impact of Technological Change among the Jívaro Indians. PhD Thesis, Berkeley: University of California. p.171.
10. Lemonnier, Pierre. 1993. “Introduction” In Pierre Lemonnier (ed). Technological Choices: Transformation in Material Cultures since the Neolithic. London: Routledge. p.3.
11. 以下を参照。Tsing, Anna L. 2015. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.
12. Erikson, Philippe. 2004. La pirogue ivre: Bières traditionnells en Amazonie. Saint-Nicolas-de-Port: Musée Français de la Brasserie. p.6.
13. Viveiros de Castro, Eduardo. 1998. “Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism.” The Journal of the Royal Anthropological Institute 4(3), 469-488. p.472.
14. Taylor, Anne-Christine. 2014. “Healing Translations: Moving between Worlds in Achuar Shamanism.” HAU: Journal of Ethnographic Theory 4(2), 95-118, p.107.