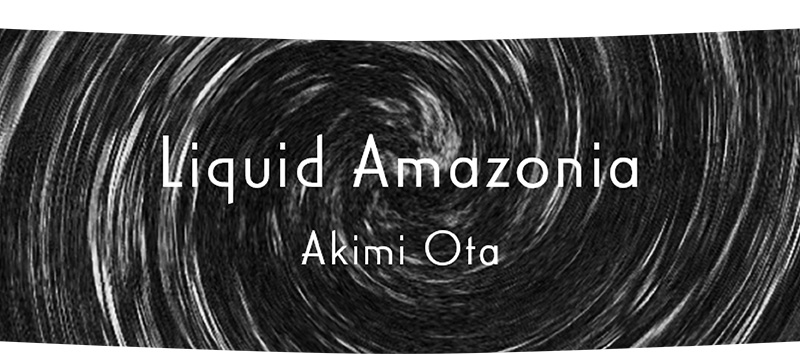青みがかった水面の奥に、夕方前の光が斜めに真っ直ぐ差し込んでいる。俺たちはナマキム川沿いの細道をしばらく歩くと見つかる紆曲にある、ひときわ水深が深そうな淵を覗き込んでいた。南国の海のような透き通った色ではなく、森の堆積物がたっぷりと含まれた、濁りを持つ黒に近い青緑色だ。奥がどうなっているのかは見透せない。セバスティアンと俺が準備できていることを確認すると、ダニエルの養子である11歳のアントニオは「ディナミタ」(スペイン語で「ダイナマイト」の意)と呼ばれる小型爆発物に無言で点火した。そして、事前に川に投げ入れておいた、残飯や集めた虫などをまとめた餌の塊のあたりに狙いを定め、ディナミタを放った。
「ボフン!」という鈍い音とともに、半径1メートルくらいの範囲の水面が一瞬跳ね上がり、波紋が広がる。餌に集まっていた魚たちが衝撃で気絶し、お腹を上に向けて浮かんでくる。「バモス!」アントニオが叫んだ。俺も水着とゴーグルを装着し、臨戦態勢だ。しかし、横を見るとセバスティアンが気の乗らない顔で川に飛び込むのを躊躇している。みんなで漁をしたいからというのでウアンボーヤで買ったディナミタを手にここまで来て、今になって彼に何が起きたというのか。
以前のある夜、家の焚き火で温まりながら寝る前の会話をしていたときのこと。セバスティアンは、森に棲む様々な存在について自分が抱く畏怖について語っていた。その日は特に、水辺に棲むものたちのことを話していた。「いいかナンキ。僕たちは強い。特にヴィジョンを得ると、何にも怖さを感じなくなる。いつまでも失われない勇気を持てるからだ。だけどね、強さというのは何も考えずにどこにでも行くことではない。何かをする前には、いつも集中して、そこに何があるか見透さないといけない。例えば川に行くとき。子供たちは何も考えずにただ川に飛び込んで遊んでいるだろう? でも川には恐ろしいものがいくつか棲んでいる。先祖たちも彼らに対していつも恐れを抱いていた。僕も恐れを抱いているし、はしゃいでいるだけの子供たちには、時々それについて教えてやらないといけないんだ」。
セバスティアンによれば、川の淵にはツンキという女が棲んでいる。ツンキはシュアールの一人だが、身体がとても大きく、「まるでグリンゴ1のよう」な薄い目や髪の色をしていて、強大な力を持っている。ツンキは川底にいることもあるし、ケンクイム村の場合は淵の横にある小さな洞窟の中にも潜んでいることがあるという。
「ツンキに会ってしまったら、どうなる?」と単刀直入に聞いてみた。「わからない。ツンキ次第だ。だけど、軽々しく会うものじゃない」とセバスティアンは答えた。ツンキの力は、彼女の近くで覚醒植物、特にマイキュアを飲むことで受け取ることができるため、セバスティアンは村の子供たちの何人かに、彼女が棲む淵の近くでマイキュアを与えたことがある。確かに、マデルによれば、ツンキはシャーマニックな力の源泉を持つ精霊であり、川辺に棲む存在だとされる2。セバスティアンの語り方では、超自然的存在というよりはまるでシュアールの一人の女のようであったが、いずれにしてもツンキは、その力によって彼らに良いことも悪いことももたらしうる両義的存在であり、彼女に恐れを抱きつつも、避けることができない川との交流を通してアルータムを受け取ることが重要なのだ。
俺は横にいたセバスティアンが川に飛び込まないのを見て一瞬戸惑ったが、このままでは川の流れによってせっかくディナミタで気絶させた魚たちを捕り逃がしてしまうことになる。ここは俺が先陣を切って飛び込むしかない。意を決して川に入っていくと真ん中の方までクロールで泳いでいき、浮かんでいる魚を一尾ずつ手で摑み、エラに親指を食い込ませて殺してから段差のある岸に向けて投げていく。ぬめり気のある魚の身体を手で素早く摑むにはコツがいるが、何度か漁に参加するうちに慣れてきていた。アントニオも俺に続いて川に入った。バシャバシャと犬かきのような泳ぎで進むと、ゴーグルもなしに潜り、水中に漂う魚たちを捕らえていく。シュアールの人々は、基本的にクロールや平泳ぎといった型を持たず、速いスピードで泳ぐのは得意ではない。俺は決して飛び抜けて泳ぎが速いわけではないが、水中での移動に不自由を感じず、何より川よりも遥かに深く広い海での経験もあるため、水に慣れている。魚を摑むテンポはもしかしたら彼らと同等、あるいは上かもしれない。
ディナミタの音を聞きつけた他の子供たちや大人たちも、次々に水しぶきを上げて漁に加わり、川の中はさながらお祭り騒ぎである。水の中に潜ると、子供たちの足や胴体が視界に入る。ディナミタは一個20ドル以上するため、村人たちが手軽に買えるものではない。誰かがたまたま持っていて使うときは、分け前を他の村人たちが取ることも暗黙の了解である。それは、決して「横から利益をかすめ取る」態度ではない。多くの場合、ディナミタ漁に飛び入り参加する人たちは、その所有者を助けるかのように摑んだ魚を所有者の籠の近くに投げていく。自分のために取っておくのは摑んだ分の一部に留まる。その感覚は繊細で、高度なメタ・コミュニケーションを通して妥協点が探られる。
川底が急激に深くなっている地点にも、何尾かの魚が漂っていた。そのうちの一尾は他の魚よりもやや大きかった。俺の中のセンサーが「あれは捕り逃してはいけない」と反応する。一瞬川面から顔を出して素早く息を吸うと、垂直に近い角度で水中に潜った。脚で水を蹴りながら、ひと搔き、ふた搔きと、腕を回してグングンとその魚に近づいていく。だが、魚はゆっくりと、奥が青黒くなっていく見えない川底の深遠に吸い込まれていく。もう少しで摑めるかもしれないと、必死に水を搔くが、僅かに手が届かない。すると、ある地点を過ぎたあたりで微かに水の流れが変わる兆候を察知したような気がしたと思うと、急に慄然とする感覚が身体を貫いた。「これ以上は行ってはいけない」と悟った。ここから先は、自分が立ち入って良い世界ではない。何か得体の知れない力が無慈悲に自分を引き込み、二度と元の世界に戻れなくするという予感が働いた。
自らの身体を水中に浸す際に生じる海と川の大きな違いの一つは、前者は泳ぐ者が暫定的な拠点とする岸に向かって身体を押し戻す波の反復運動との相克を生むのに対し、後者は身体をその拠点から永続的により遠くへ引き離す水流運動であるということだ。無論、海にも様々な海流が存在し、泳ぐ者を想定とは異なる地点に流す力がある。だが、俺はこのときほど自分が川を泳いでいること、その流れに身を任せることが取り返しのつかない帰結をもたらすかもしれないことを意識した瞬間はなかった。そのとき、俺の脳内では川底に潜んでいる巨大なアナコンダと、滑らかに包み込むようなアルータムの力を授けつつも、生と死の境界の向こう側にぬめりと連れて行ってしまうツンキのイメージが明滅していた。身体をくねらせながら水流に乗って移動するアナコンダのイメージがとらえどころのない畏怖の念を呼び起こすのは、アナコンダが決して俺を岸へ押し戻すことがなく、永遠に終わらない川の流れに誘い込むからだ。やがて、俺はアナコンダに喰われ、その身を捩る反復運動によって細長い体内を貫く腸の中を通り抜け、命の螺旋としてツンキが棲む世界を訪ねることになるのだろう。
その日、漁を通して俺は村人たちのちょっとしたヒーローになった。ツンキが待つ世界の入口から身を翻した俺は、追っていた大きめな魚を諦め、水面を目指した。その途中で小さな魚を二尾捕まえ、手柄に付け加えたのだ。それがなくとも、この日は村人たちよりも得意な泳ぎによって、多くの魚を捕らえた。また、彼らがあまり向かわなかった川の深淵の方にも敢えて向かうことで、勇気を示すことができたようだ。無論、その勇気は単に深いところまで到達したことによるのではなく、ツンキが待ち構えているかもしれない場所まで潜ったことによる。「セバスティアンは怖がって川に入れなかったのに、ナンキは入った!」魚でいっぱいになった鍋を囲みながら村人たちは口々に冗談めかした笑い声をあげた。「あそこはツンキが潜んでいるところだ。それに、アナコンダも底の方にいるかもしれないだろ?」意外にもからかわれることを苦にしないセバスティアンは、漁の途中まで川に飛び込めなかったことについてはにかみながら弁明していた。やはり、彼はツンキとアナコンダを恐れていたのだ。
アナコンダは、確かに川底に潜んでいることがあると言われ、その巨大な身体に飲み込まれることを人々は心のどこかで恐れている。また、アナコンダに対する恐れはツンキと無関係ではない。単に危険な動物としてだけではなく、それはツンキが持つ強大な霊的力の比喩として、あるいはその具体化として捉えられるからだ3。俺自身、セバスティアンから聞く様々な話の蓄積によって、川への畏れの感情が芽生えつつあった。しかし、だからこそ、それをものともしないかのように振る舞うことで彼らの信頼をさらに勝ち取ることができるかもしれないという直感が瞬間的に働いた。万が一、そこでアナコンダに喰われてもそれはそれでいいと腹を括った。その小さな賭けに、俺はどうやら勝てたようだ。フィールドワークを進めるためには、傍観者であってはいけない。それはプライドを捨てて賭けに勝ち続け、ときに負け、それでも諦めずに立ち上がり進む、長大な七転八起のプロセスにほかならない。
家で待っていたパストーラは、大漁の魚を見て嬉しそうな表情を浮かべた。「マイトを作るわ」。そう言うと、家の裏に豊富に生えている「ティン」という横幅もありつつ縦にスラッと伸びている葉っぱを何枚か刈り取り、持ってきた。「マイト」とは、魚や肉をティンあるいは他の香りの良い葉っぱに包んで焚き火の熱で蒸す料理で、「アヤンパコ」や「パタラシュカ」(主にペルー)など、アマゾン熱帯雨林の広い地域で様々な名前で呼ばれる。シュアール語の呼び名は、「ユンクルナ」=yunkurunaだ。この日は、「ウープ」(実際にはウとエの中間的発音)という種の、栽培されず森に自生している山菜的な葉っぱと、漁で獲れた魚を使って調理していた。
食べる魚と食べない魚を仕分けすることはなく、獲れた魚は全て食べる。また、魚は日本のように下処理はせず、内蔵を取り出さないまま葉っぱに包み、二つ折りにすると、どこにでも生えている細い蔓を使って綴じ目を結ぶ。20〜30分火の側に置いて待ってからマイトを開くと、勢いよく湯気が飛び出すと同時に、途轍もない旨味の絡まり合いがすぐさま鼻を刺激する。ふっくらと柔らかくも適度な汁気を帯びた魚は、熱々で手に取るのも一苦労だが、息でちょっと冷ましてから口に放る。淡水魚の透き通るような外連味のない味に混じり、川の雑味を含んだ内蔵の味が滑り込んでくる。そこにウープの芳醇な香りが加わることで、味は唯一無二の領域に向かう。マイトは、俺がアマゾン熱帯雨林で食べた食事の中で、間違いなく1、2を争う大好物だ。おそらく、それは村人たちの多くにとっても同じだろう。マイトさえあれば、どんなに手の込んだ料理も必要ない。マイトこそが、漁に向かう俺たちのやる気を支える。
俺の横で、パストーラも恍惚の表情を浮かべながらマイトをほうばっていた。そして、食べ終わる頃になってもう一度彼女の方を見ると、葉っぱを広げ、貼り付いた魚の旨味を味わい尽くすかのように、舌を大きく出して縦横無尽に舐め回し、吸い付いていた。西洋や日本の社会通念に照らし合わせると、大の大人がしているのはなかなか見られない光景だ。しかし、パストーラの舐め方はとても堂々としていて、いそいそと隠れながら行っているわけではない。
「マイトの中で、一番美味しいのはこの部分なの。ティンの葉っぱに染み込んだこの魚の汁を吸うのが一番好き」。パストーラが俺に視線を向けて言った。「吸う」という食の行為は、確かにシュアールの人々とともに暮らす中で「嚙む」ことと同じか、場合によってはそれ以上の重要性を持っているように見える。例えば、「魚のどの部位が一番好きか」と人々に聞いて回ると、最も頻繁に返ってくる答えは「頭」である。スリティアクも、セバスティアンも、パストーラも、彼らの子どもたちや他の村人たちも、口を揃えて魚の頭の美味しさについて強調する。そして、しばしば固い骨に囲われている川魚たちの頭を味わうために取られる動作は、「吸い付く」ことだ。シュアールの人々が大人数で魚を食べている現場に居合わせるとき、聞き耳を立ててみるとそれがよくわかる。場を支配しているのは、「チュ……チュチュ……チュ……」という吸い付く音。日本の蕎麦屋で鳴り響くズルズルと豪快に麺をすする音に西洋からの訪問客がしばしば衝撃を受けるのと同じように、シュアールの村に生きる中で驚かされるのは、吸うという動作がいかに食の中心を占めているかである。
また、「吸う」という動作の重要性から見受けられるのは、彼らが「腹を満たす」ことと同じかそれ以上に、「味を感じる」ことを食事に対して求めているということである。確かに、パリやロンドン、東京などで享受できるような古今東西の食のバラエティはアマゾンの森には存在しない。だが、アクセスできる品目数は、彼らが感受している味の種類の数と一致するわけではない。実際には、彼らは一つの品目から微細な味の多次元性を認識し、引き出し、知覚しているのだ。
「パストーラが言うように、葉っぱに付いた魚の味を吸うのは美味しい」。同じように葉っぱを舐め始めたセバスティアンが言う。「しかしね、マイトの葉っぱを舐めたり魚の骨をしゃぶるのは、大人だけがやっていいことで、子どもには本来禁止されているんだ」。彼によると、子どもがこの最も美味しい部分を舐めたり吸ったりして味わうことを覚えてしまうと、軟弱に育ってしまうのだという。ワンチャという殺される瞬間にブルブル震える魚を子どもが食べてはいけないように、魚の旨味を最後まで舐め尽くすこともまた、いくつかのイニシエーションを経て「大人」と認められなければ許されない。しかし、実際にはこのように至る所に張り巡らされた食の禁忌は、厳格な戒律のようなものではなく、ヒエラルキーに支配されたルールでもなく、曖昧さと隙間を多分に含む。それらは頭の片隅にあるが、目に見えない粒子が凝集と離散を繰り返すかのように、状況とともに瞬間的に現れ、また溶解しうる。
とはいえ、現在はあまり行われなくなったものの、言いつけを守らない子供に対しては様々なバリエーションの罰が与えられる。例えば、子供が何か物を取ってくる言いつけを守らなかった場合は、唐辛子を火にかけ、子供の顔を布で包み、呼吸が苦しくなるまでその煙を吸わせるという罰がある。女の子がチチャ作りの手伝いを3回言いつけてもしないときは、「ナラ」というトゲを持つ植物を積み上げ、裸にしてその上に座らせるか、アリの巣に両手を突っ込ませる。若者や成人に対しては、例えば誰かが祭りの場で女性を殴ったり誰かと喧嘩した場合、強い唐辛子を二つに裂き、その人の両目に塗りつける。すると、大抵は酔っ払っているその人物は、這いつくばって泣きながら家に帰るという。若者、成人に対するこの罰は、今でも時々行われるそうだ。
夜がまた深くなり、漆黒の闇に近づく。焚き火だけが俺たちの顔をゆらりと照らしている。セバスティアンは舐めていたティンの葉を家の中から裏に向けて投げ捨てると、焚き火の側に戻ってきた。そして、「ハァァァァァァ」と低い小さな声を細く伸ばす。なんでこんな声を立てるんだろう、と不思議に思っていると、「そろそろイウィアが出てくる時間だな」とセバスティアンは言った。「イウィア」という名前はそのとき初めて聞いた。「さっき、川の深いところにはツンキが棲んでいるという話をしたよな。それで思い出したんだが、もう一つ気をつけないといけないものがあってね。それがイウィアだ。イウィアはツンキとは違って森の中に棲んでいる。森には葉っぱが粘着質で身体にくっついてくるものがあるんだが、夜に森を歩いていると時々気付かずにその葉っぱに絡め取られてしまうことがある。それはイウィアが仕掛ける罠で、捕らえられた人間は喰われてしまうのさ」。さっき聞いたツンキの話では、ツンキは決して喜んで会いに行くような存在ではないが、同時にヴィジョンを通して彼らに霊的な力、つまりアルータムを授けてくれる存在でもあった。どうやら、イウィアの場合はそうではなく、彼の目的は人間を喰うことだけのようだ。
イウィアもまた、ツンキと同じように他のシュアールよりも大きく、まるで白人のような目と髪を持つという。しかし、ツンキはシュアールの女だが、イウィアはシュアールではなく、どこからやってきたのか得体の知れないものである。「この森だけじゃない。サンガイやパブロ・セクストに行くと、遠くからさっき僕が出していたような『ハァァァァァァ』という静かな声が聞こえてくる。それはイウィアが出す声で、僕たちを誘っているんだ。誰かが助けを求めてるのか? なんて思って応えたら絶対にだめだ。すぐにイウィアが来て喰われるぞ。イウィアからは一度見つかると決して逃げられない」。真っ暗闇の中でセバスティアンの話を聞きながら、腹がギュンと緊張するのがわかった。恐ろしい。そんな存在がこの森のどこかを徘徊し、俺たちを狙っているのか。
「大丈夫さ。意志を強く持って、間違ったやり方で森に入らなければ、イウィアはやって来ない。今夜も良い夢を見ないといけないからな、イウィアの話はもうやめて、一つ僕がマイキュアを飲んで見たヴィジョンを教えてやろう」。セバスティアンは不敵な笑みを浮かべた。焚き火の光が薄暗いのでよくわからなかったが、彼は今日も知らぬ間にチチャをたくさん飲んで少し酔っているのかもしれない。
「ナンキ、前も言ったように、シュアールの男はマイキュアを12回飲まないといけない。それ以上でも以下でもいけない。12回飲むことで、真の強さを手に入れることができ、『ワイミャクー』(「ヴィジョンを得た者」の意味)に近づくことができる。僕はその12回を乗り越えた。マイキュアを飲むのは簡単なことじゃない。マイキュアは飲むとすぐに僕たちを捕らえ、見える世界の全てを変えてしまう。それが3日続くんだ。その間、僕たちはヴィジョンを見続け、無事に過ごさなければならない。弱い人間だと、マイキュアの力に負けて川に落ちたり森で転んだりして危険にさらされ、悪い夢を見る。僕は長い時間をかけて、毎回たった一人で森に籠もり、誰の助けも借りず、何度もヴィジョンを見て、自分がこれからどうなっていくのか、学び、考えてきた。君がここにいる間、僕のヴィジョンについて少しずつ教えていくことになるだろう」。
セバスティアンはいつも、原生林である自分のフィンカの奥深く、あるいはフィンカを抜けたさらに遠くの地点でマイキュアを飲む。ある夜、マイキュアを飲むとたちまち意識が支配され、全身の感覚がなくなっていった。上裸のまま森に佇んでいると、男と女の二人組がどこからともなくやってきて、セバスティアンの肩を片方ずつ担ぎ、空を飛んでどこかへ連れて行かれた。途中で下を見ると、キラキラした光が無数に灯っている。気づくと、いつの間にかディスコのドアの目の前に立っていた。しかし、そのときセバスティアンは「僕は絶対にディスコには入らない」と心に決めた。彼らの誘いに乗らず、扉を決して開けなかった。無事マイキュアの覚醒作用から目が覚めたセバスティアンは、その後友人からディスコに誘われたことが何度かあったが、ヴィジョンの中でディスコに入らなかったことを思い出し、誘いを断ったという。
別のヴィジョンでは、セバスティアンが森の中を彷徨っていると突然人が来て、「警察が君を捕まえに来るぞ!」と警告してきた。「こんな森の奥まで?」と意味がわからなかったセバスティアンは、ひとまず警察から逃れるために家に戻ろうとした。なんとか家に戻ると、そこには死んだはずの父がいた。父は深刻な顔で「何をしている! ここに警察が来るぞ。森へ戻れ!」と、今度は家に警察が来るから森に戻れと言ってきた。必死に森へまた戻ると、なんと最初に人が警告したように森の中で本当に警察の大群が現れた。また身体を翻し、セバスティアンは家に戻った。そこにはパストーラがいたが、「パストーラ、警察が来る! 逃げるんだ!」と訴えると、彼女はセバスティアンを見て怖がり、逃げ出してしまった4。迫りくる大勢の警察に対して腹を括ると、セバスティアンは槍で立ち向かい、皆殺しにした。その1年後、ケンクイム村近くでメスティーソの人間が勝手に占拠していたシュアールの領地を取り返すために皆で強硬手段に出たとき、70人の警官がやってきた。そこにいたシュアールはセバスティアンを含め6人だけだったが、「シュアールは恐れを抱かない」と警官たちに訴え、銃を構えて応戦しようとした。すると、重装備の警官たちは帰っていった。
初めてセバスティアンが俺に彼が見たヴィジョンを語ったこの夜、彼から聞いたストーリーは上の2つだった。3日間続くと言われているマイキュアによる覚醒状態を、具体的かつ簡潔なストーリーとして解釈していること、そして現れるモチーフや起きる出来事が、例えば精霊や先祖との深遠な出会いなどではなく、ディスコや警察など、都市的かつ俗世的であることに強い印象を受けた。アマゾン熱帯雨林に関する民族誌を読んでいて「ディスコに行くヴィジョン」についての記述などに当たったことはない。どれもこれも、精霊との対話や戦士になる話など、森の外部に由来する要素は徹底して排除された夢やヴィジョンについての語りばかりだ。
他の民族誌が、「理想化された先住民の定型」に当てはまらないナラティヴを記録から排除しているのか、それとも彼らと協働する現地の人々が本当にそのような語りしかしていないのか、詳細の真偽はわからない。しかし、セバスティアンが語るヴィジョンが上のようなものだったことは事実であり、またその後セバスティアン以外の人々から聞き取りしたときも、彼らのヴィジョンでは学校や都市、酒場などが、森の動物たちや精霊、先祖との邂逅というモチーフに混じって度々現れることを確認している。
また、もう一つ興味深いのは、マイキュア、そしてアヤワスカによるヴィジョン経験は、植物の力を借りて「お告げを受け取る」という受動的体験ではないということである。ヴィジョンの只中で自らの意志に確信を抱き、コントロールできない意識をそれでも懸命に操縦することで体験を能動的に創出することが重要であり、その「現実」を携えて非覚醒状態に戻ることで、得たヴィジョンを未来において具現化する力を得ることができる。それはむしろ植物と意志や生命力の強度を試し合う対話であり、対決なのだ。「ポジティヴな気持ちで、かつ自分の未来に対する疑問があるとき」がこれらの薬草を飲む最適なタイミングだとは言われているが、そこに「良いヴィジョン」を見られる保証はない。それは、生死を賭けて強大な力を持つ植物と向き合い、打ち克つことで自ら摑み取らなければならないものだ。
この時期、セバスティアンはしきりに「アヤワスカを飲みたい」と言っていた。曰く、以前アヤワスカを飲んだときに見たヴィジョンが、自分が死ぬことを示唆する内容だったからだそうだ。そのヴィジョン内では、セバスティアンの周りを死んだ先祖たちが取り囲んでいて、死臭が立ち込めていた。まるで彼らが自分をそちらの世界へ招き入れようとしているかのようだった。それについて兄のゴンサロに最近相談したところ、「もう一度アヤワスカを飲んで違うヴィジョンを得て、それを追い払うべきだ」と言われ、アヤワスカの断片を分け与えてもらった。「僕は今、アヤワスカを自分では持っていなくてね。何度か挿し木をしようとして色々な場所に意識を集中させて植えてみたんだが、どこに植えても育ってくれないんだ。きっと僕の手が良くないんだろう。だからゴンサロからすぐに調理できるアヤワスカをもらったんだ」。植物が力強く育ってくれるかどうかは、植える人の手が持つエネルギーに左右されると、セバスティアンは考えていた。彼が植えると、マイキュアは力強く育つが、アヤワスカはなかなか育ってくれない。
植物には、それ自身のエネルギーに加え、それを植えた手の主のエネルギーが宿っていると、セバスティアンは語る。それは、どちらも無限ではない。セバスティアンの酷い胃炎を治してくれたサンディは、毎日のように樹液を摂取していたとき、一度枯れかけるほど力が弱まってしまったことがあった。「なぜ死ぬんだ、サンディ? 君は僕をこんなにも早く治してくれるような強い力を持っているはずだ」と、その姿を見たセバスティアンは、サンディの樹皮に手を置きながら強く念じた。すると、そこからサンディは葉を青々とさせ、なんとか復活を遂げたという。
「植物は、誰かを治したら力が弱まる。サンディは僕のことを治してくれたが、それは命を削ること。僕もマイキュアを誰かに対して用意し、儀式を通して与えるとき、自分の寿命が縮むような感覚になる。誰かに力を与えるということは、与える側の命を分けることなのさ」。シュアールの人々は、科学名では同一とされるマイキュアの中に、用途によって使い分けられる様々な種類を独自に見いだしている。例えばそれは、シャーマンがヴィジョンを見るために使われる「ウウィシン・マイキュア」や、骨折の治療のために使われる「ウクンチ・マイキュア」などに分かれ、セバスティアン自身は6種類のマイキュアを持っている。だが、用途による分類以前にまず存在するのが、川辺に自生している「ウンツァニャ・マイキュア」と、「人が植えたマイキュア」の区別である。マイキュアの儀式の際には、野生のマイキュアと誰かが育てたマイキュアの2種類を混ぜて液体を作り、それぞれが持つパワーの相乗効果を引き出すことでより強烈なヴィジョン経験を授けることができ、そのどちらが欠けていても不完全である。つまり、マイキュアには必ずそれを植え、育てた個人の想念とエネルギーが宿っているのだ。マイキュアを与えることが、与える側の人間の命を削る理由は、マイキュアを植えた手の主の生命力がそこに濃縮されているからに他ならない。
「ともかく、僕が見たヴィジョンはたくさんある。少しずつ伝えていくよ」。セバスティアンはいつものように言いながら微笑みを浮かべると、いつものように言った。「カナルタ」。シュアール語で「おやすみ」という意味だ。焚き火に当たりながら寝る前に語り合い、この言葉を交わして床につく。この毎日の繰り返しが、身体に浸透しつつあった。「カナルタ」には、もう一つの意味がある。「夢を見なさい」、あるいは「ヴィジョンを見なさい」という意味だ。シュアール語では、これら全ての意味が切り離されずに一つの語句の中に同居している。寝ることはすなわち、夢を見ること。夢を見ることは、すなわちヴィジョンを得ること。マイキュアやアヤワスカを飲まずとも、俺たちには毎晩、ヴィジョンが蓄積されているのだ。
「おーい! ナンキー!」翌朝、家でパストーラとセバスティアンと一緒にチチャを飲んでいると村人の一人の声が聞こえた。視線を向けると、何かを脇に抱えてこちらに向かって歩いてきている。それは黒い毛の色をした、生まれて数日ばかりの可愛らしい雌の仔犬だった。「うちの犬がたくさん子供を産んでね。これ以上犬がいても困るから村のみんなにあげてるんだ。もらってくれないか?」その仔犬の親である雌犬は、村の中でも指折りのハンターとして有名だった。その雌犬は全身が白かったので、この黒毛の仔犬の母親だとは思わなかった。「あの犬が産んだのか? そりゃ、すごく良いハンターに育つこと間違いなしじゃないか」。セバスティアンが興味ありげに応えた。パストーラが控えめな表情で俺に目を向け、反応を伺っている。「ナンキ、この仔犬をどうしようか?」なぜ俺に決定を委ねているのか不思議だったが、彼らなりの気遣いなのだと思う。犬を飼ったことが一度もなかった俺は、単純に犬に興味があったことに加え、シュアールの世界において犬の生がどのように成り立っているのかを間近で観察できる絶好の機会だと思い、快諾した。毛の色にちなみ、日本語でその仔犬を「クロ」と名付けた。
「クールゥー! クールゥー!」なぜか「クロ」という発音が難しいらしく、「ル」に寄せがちな呼び方で、パストーラとセバスティアンは仔犬に声を掛ける。「ナンキが犬を飼い始めた。彼の言葉で『ネグロ』(=黒)という意味で、クロという名前らしい」というエピソードは、しばらく村人たちのお気に入りの話題となり、家々を訪ねるたびに同じ話の流れが繰り返された。初日は不安そうな顔つきをしていたが、数日後にはクロは徐々に俺たちの家に慣れてきた。キャッサバやプラタノなどの残飯を潰したものを、空になった缶詰に入れて差し出す。恐る恐る口を付けると、空腹だったのか、貪るように食べ始めた。数週間も経つと、身体はみるみる成長し、家の外を走り回るようになる。顔つきが少し険しく、何かを企んでいるかのような思慮深さを感じさせるようになっていった。セバスティアンは森に入るとき、必ずクロを一緒に連れて行くことにしていた。「小さいときから森に連れて行くことで、強いハンターに育つんだ。アパッチたちがやるように『可愛い可愛い』と言って安全な家にずっと置いていたら、こいつは何も学ばない。身体は弱く、獲物を追いかける気力もないまま成長してしまう。僕たちは『可愛い』なんて思わない。犬も自立して、僕たちを助けないといけないからな」。
まだクロが生まれて数週間足らず、やっと少し森の険しい道に慣れてきた頃、セバスティアンと俺は彼女を連れて原生林の滝に向かった。踏み越えねばならない大きな石や段差、泥水に浸された道、沼の上を通るために渡らなければならない細い木。クロは初めて直面する数々の困難に懸命に立ち向かう。セバスティアンも俺も、基本的にクロに構うことなく早足で先に進む。「クゥーン、クゥーン、クゥーン」クロのか細い鳴き声が後ろから聞こえる。道を塞いでいる倒木を飛び越えられないようだ。クロを摑んで登らせると、俺たちは再び歩みを進めた。「置いていくなよ!」と必死に訴えかけるような仔犬特有の高音の声が、辺りを包む虫の合唱に混じる。
流れの強い川に差し掛かった。慣れてきたとはいえ、踏み込む角度を正しく選択しなければ身体を持っていかれるくらいに圧力がある。「クロはどうする?」と聞くと、セバスティアンは「歩かせよう。川の中も進めるようにならないとな」と答えた。クロを俺の手前で歩かせながら、水中で足を運ぶ。仔犬はずぶ濡れになりながらも、なんとか踏ん張りながら進んでいく。しかし、水深がわずかに深くなった一瞬で、川がクロの身体をさらった。前足を石に掛けようと伸ばすが、流れの強さに耐えきれない。「キューン! キューン!」徐々に遠ざかっていくクロの悲鳴が、川の轟音を押しのけて耳に響く。「クロ!」咄嗟に叫ぶと、俺は重い足を渾身の力で持ち上げながらザブンザブンと川を下流に向かって進む。目を数メートル先にやると、傾斜がかかっていて川の流れが急になっている。岩の群れの位置を考えても、危険すぎてそこから先はたとえセバスティアンでも立ち入るのは難しいだろう。それまでにクロを摑まなければ、助からない。
間一髪のところで追い付き、クロの前足を摑んだ。引き上げると、水に濡れた小さな身体はブルブル震えている。突然訪れた命の危機に呆然としているようだ。そのまま肩に抱え、セバスティアンが待つ地点まで歩く。クロを歩かせるというセバスティアンの選択はある意味で裏目に出た。正直、俺はクロにとってまだこの川の中を歩くのは難しいと予想がついていた。それでも歩かせたのは、ここでの俺の第一の目的は「セバスティアンが仔犬をどのように育てようとしているのか」を、あらゆるプロセスを包括した状態で観察することだったからだ。
確かに、クロはまだ発達途上の身体では乗り越えるのが難しい試練を課され、川を上手く渡ることができなかった。しかし、セバスティアンは命を救われたクロを見て「助かってよかった、僕の判断が間違っていたよ」などとは言わない。ただクロがまだここにいるという事実を認識すると、まるで何事もなかったかのように歩行を再開した。おそらく、彼にとってクロがここで死ぬことはなんら問題ではない。むしろ、森を歩く自分に付いて来られないような犬は必要としていないのだ。確かに、村で一目置かれる犬は皆、障害物を軽やかに越えながら途轍もないスピードで森を進む。すでに凄まじい歩行能力を持つシュアールの人々が、獲物を仕留めるために武器として使用する存在である。ハンターの犬たちは、イノシシや鹿、アグーチ、アルマジロなどを追い詰め、攻撃して弱らせ、ときには自力で狩りを完結させてしまう。飼い主を守るために、勝ち目が薄いジャガーにも立ち向かう。そんな犬たちにも、クロのように森を歩くこともままならない仔犬の時期がある。セバスティアンの犬に対する態度は、このような視座から捉えれば説得力があるとも言える。
ある夜には、セバスティアンが水浴びをしている最中、家の横の薬草が植えてある場所の奥の方から物音がした。すると、どこから嗅ぎつけてきたのか、村で一番と言われる狩猟犬が村の中心の方から風のように現れ、草陰に飛び込んだ。なんと、潜んでいた狐がセバスティアンとパストーラが飼育する鶏を襲おうとしているところだったのだ。狐に咬み付きながらその犬が吠えると、声を聞きつけたセバスティアンは何が起きているのか勘が働いていたのか、濡れた髪のままマチェーテを持って駆けつけた。狐を確認すると、マチェーテで腹を切り裂き内蔵を搔き出し、最後には首を切り落として殺した。
「こいつはとにかくしぶとくて、どんな怪我を負っていても死なないんだ。殺すには首を切り落とさないといけない」、返り血に染まったセバスティアンが言った。狡猾に鶏を襲う狐は、イギリスでは時々見かけると幸運な気持ちになったが、ここアマゾンの森では出現すると容赦なく殺される存在だった。腹を裂かれ首を切り落とされた狐の姿にも衝撃を受けたが、それ以上に不可解だったのが、狐を追い詰めたこの犬がなぜ遠いところ、おそらく数百メートル離れたような地点から颯爽と現れたのかである。しかも、セバスティアンはそれを当然のように受け取り、すでに予定されていたコラボレーションであるかのように振る舞っている。
その狩猟犬は、真っ黒な毛を持っていた。「この犬は、クロの父親なんだ。母親は真っ白だけどね」とセバスティアンは言った。そうか、あの真っ白な雌犬からクロが生まれた理由は、この黒い雄犬だったのだ。つまり、クロは村における最強の狩猟犬二匹の間に生まれたということ。セバスティアンが厳しい態度で育てようとしているのも、頷ける。
腰を低くかがめ、マチェーテを地面と並行に近い角度で左右に振り回し、草を刈る。この日のミンガに集まった参加者が皆横並びになり、木々が茂っている森の方向に向けて草を刈りながら進んでいく。この動作は俺にとって負担が大きく、遅れを取っていたため、集まった男たちから「ナンキの仕事が遅すぎる」として笑われていた。20代後半になって自分たちのように身体が動かせない大人を見ることがとにかく珍しく、可笑しいのだろう。この日はサウルという村人のチャクラ作りを手伝うミンガで、セバスティアンと俺も参加していた。30分毎、あるいはそれ以上の頻度でチチャを回し飲みし、集団的に酔いを進めながらリズムよく草を刈り取っていく。時間が進むにつれて疲れが溜まってくると、口々に「ホゥゥゥゥゥゥ」と裏声で雄叫びをあげながら互いを鼓舞する。ポリタンクに大量に仕込まれていたチチャは、みるみるうちに減ってきた。
「残りのチチャはこれだけか。頑張れるのはもう少しだけだな」と、セバスティアンが一息つきながら漏らす。まるで自分とチチャが一心同体であるかのように、自分のエネルギーの残量がチチャのストックの量に比例するかのように、少なくなったチチャを見て気力が奪われているようだ。森で働くとき、シュアールの男たちは強いチチャによって酔い、覚醒することで、普段以上のパワーを発揮する。「酔っていても働ける」のではなく、「働くためには酔わないといけない」のだと、シュアールの人々は口々に語る。酩酊のレベルをコントロールする技術も重要だが、セバスティアンによれば、チチャを飲む上で重要なのは「強いか弱いか」だけではない。何よりも重要なのは、「それが自分にエネルギーを与えてくれるかどうか」なのだ。
「何日も発酵させた強いチチャを飲めば、確かにすぐに酔う。だけど、それで働くパワーが出てくるかどうかは別の話なんだ。一番大事なのは、作る女性が本当に集中してそのチチャを作ったかどうかだ。火加減も重要だけど、何より意識を研ぎ澄ませてすり潰したか。集中してキャッサバを嚙んだか。それによってチチャは美味しくなったり、不味くなったりする。僕たちの力は、本気で集中して作られた強いチチャを飲むことで、最も発揮される」。つまり、数値化や可視化ができる技術だけではなく、調理作業に込められた意識や感情の状態が味に決定的な影響を与え、それがミンガの浮沈に繫がるということだ。「だから僕は、パストーラが作るチチャを一滴も無駄にすることはない。彼女がいつも意識を集中させてチチャを作っているのを知っているし、味でそれを感じるから」。確かに、セバスティアンはいつも、チチャを最後の一滴まで惜しむように飲む。それは彼がチチャ自体を愛しているのと同時に、パストーラが作るチチャを愛しているからだ。
昼になり、少し長めに休憩を取っているときのこと。ミンガの主催者であるサウルが、細い木の幹のようなものの皮を薄く削り取り、それを手で握ったりして汁を染み出させた。そして、付いてきていた自分の犬を呼ぶと、木の皮の束をその鼻に思い切り擦り付けた。「キャウン!」強い刺激からか、不意を突かれた驚きからか、ビクっと身体が跳び上がった犬は咄嗟にサウルから距離を取ると、フン!フン!と鼻を鳴らしながら小走りで辺りを徘徊する。一体、何をしたのだろうかと不思議に思っていると、「こうすると、犬が獲物を嗅ぎつける力が上がるんだ」とサウルが言った。セバスティアンを含めても村に3人ほどしかいない、数少ない長髪の男の1人であるサウルは、薬草に詳しく、「シュアールの生き方」を真に実践しているとセバスティアンも認める存在だった。
「そう。今彼が犬にあげたのはツェクタルという植物で、鼻の中をきれいにしたり、風邪や喉の問題にもよく効くんだ。犬に与えると、感覚が良くなって狩りが上手くなる」。セバスティアンも会話に加わってきた。「犬にも薬草を与えるの?」と聞くと、2人は「もちろん」と口を揃えた。「犬もヴィジョンを見るからね。ヴィジョンを見た犬は強い。どうやって獲物を仕留めるか、犬も考える。勝てるかどうかわからない獲物に、それでも勇気を出して挑む。良いハンターになるためには、犬にもヴィジョンが必要なんだ」。エドゥアルド・コーンによる論考「犬はどのように夢を見るのか」によれば、彼が観察したキチュアのコミュニティでは犬に「ツィタ」という覚醒植物を与えることで「犬に備わっている人間的振る舞いのエートス」を強化しようとする5。そこに見られるのは、人間と犬が同様の精神的成長プロセスをたどるというアマゾン熱帯雨林先住民コミュニティにおけるある種の認識である。人間が薬草によってヴィジョンを得ることでより深い知識や勇気、世界に対する鋭い感覚を得るように、犬もまたその力によって狩りの感覚を研ぎ澄まし、良い振る舞いを身に付けていく。
「パンキ・ハアスタ!」「ヤワ・ハアスタ!」この日のミンガも終盤に差し掛かり、日が傾いてきた。シュアールのミンガでは、参加者たちは主催者が「ありがとう」=Yumin sajmeと言うまで作業を終えることはできない。主催者でもないセバスティアンがシュアール語で「アナコンダであれ!」「ジャガーであれ!」と、皆に呼び掛け、鼓舞している。上の二つに加え、彼は「クハンチャム・ハアスタ!」とも叫んでいた。「クハンチャム」とはシュアール語で「狐」。つまり、「狐であれ!」という意味だ。鶏を襲う存在として目の敵にし、見つければ徹底的に斬り殺すことに微塵の躊躇もないに拘らず、「狐になる」という。疲れを知らず、じっくりと獲物を見極め、手負いの状況でも諦めずに生き抜こうとする。その狐の姿を、セバスティアンは殺めながらも自分たちに重ね合わせていた。シュアールの人々の歌や掛け声には、森に棲む種々の動物たちが入れ替わり立ち替わり登場する。「力」=kakaramの文脈で最もよく触れられるのは、間違いなくジャガーとアナコンダである。この2種の動物は、生態も持っている能力も大きく異なるが、アマゾンにおいて最も恐れられ、同時に敬意を払われる存在である。
全く別の意味で、シュアールたちが愛し、求めてやまない存在がいる。それはオオハシだ。スペイン語では「トゥカン」=tucán、シュアール語では「ツカンガ」=tsukankaと呼ばれるこの鳥は、「アマゾンで最も上品で美しい鳥」だと言われる。「オオハシ」とは科の総称で、実際には40種以上に分かれるが、最も典型的なのは主に黒と白の毛に身体を覆われ、バナナが伸びるように艶やかな流線型でオレンジ色の嘴を持つ種である。お尻に一部だけ毛が赤い箇所があるのもその種の大きな特徴であり、民族のリーダーが重要な場面で使用する羽冠には、オオハシの羽がふんだんに使用されることも多い。オオハシは、アマゾンを力ではなく、上品さと気高さの面で象徴する唯一無二の動物なのだ。
広大な森に覆われているはずのケンクイム村では、もう何年もオオハシを見た者はいないという。二次林を含めた森の面積を考えれば、餌がないわけではないはずだ。だが、オオハシは人に見つかることがない森の奥深くに身を隠すように、この地から消えてしまった。その最大の理由は、この鳥の羽毛を剝ぎ取ることを目的とした乱獲と、牧畜による森の草地化である。リーダーたちが纏う羽冠は、誰でも身に着けられるものではなく、生産量も多くはない。しかし、観光客向けのアクセサリーなど、森の外部に向けて作られる商品にオオハシの羽が大量に使用されてしまっている。また、森を分断し巣を作ったり身を隠したりするための生息域を縮小させてしまう草地の拡大は、餌の絶対量の有無以上にオオハシたちの飛行エリアを限定する。アマゾンの環世界は、内部で絶えず蠢くミクロレベルの変異によって、終わりなき再構成の過程にある。地続きの森にお互いが生存しながらも、オオハシの環世界はケンクイム村をはじめシュアールの環世界との接地点を失いつつある。「最も上品で美しい鳥」を自分たちが住む森で見ることができないという事実は、シュアールの人々の世界認識に無視できない影響を、まるで障子にできた小さな穴が少しずつ広がっていくように与えている。
オオハシだけでなく、野生動物全体がシュアールの森から姿を消している。エクアドルに限らず、アマゾン熱帯雨林全体でモザイクのように広がる人為的な森林破壊によって、絶滅の危機に追い込まれる多くの動物が存在するのは確かだ。しかし、生息数などの数値を通してでは先住民たちとの距離を把握することができないのは、人を恐れて森の深くに逃げ込んでいる動物たちである。ケンクイム村の人々は、よく「狩りをするためには何日も森に籠もらないといけない」と言うが、この言葉を歴史性の考慮を抜きにして鵜呑みにしてしまうと、彼らの生がどのような変容に直面しているのか理解できない。
ナタリア・ブイトロンが先行資料を引きながら強調するのは、シュアールたちが現在のように「セントロ」と呼ばれる村々を形成し、集住し始めたのは20世紀後半に入ってからに過ぎないという事実だ。それ以前、シュアールは分散して川沿いに居住し、獲物や魚が捕れる量に応じて6〜10年ほどのサイクルで住居を移動させる遊牧生活をしていた6。それが変化したのは、1950年代にキリスト教宣教師たちが国家からシュアールの住むアマゾン内部に土地を提供され、宣教のための拠点作りを本格化させてからである。
アメリカ合衆国で発足した福音宣教連合(GMU)が1903年にモロナ=サンティアゴ州都マカスに初の拠点を作って以降、国家の協力のもとで徐々にアマゾン内部の移住者を増やしたキリスト教諸団体は、彼らが諸悪の根源とみなすシャーマニズムを抹消し、「貧しい」シュアールたちに「経済発展」をもたらすために尽力した。その大きな柱の一つが、農業や畜産を中心とした定住生活の推進である。
1950年代後半に施行された一連の植民法により、アスアイ地域庁(CREA)と土地所有権・農業庁(IERAC)の斡旋によって主にアンデスの高山地域からアマゾンへの移民流入が進められた。新法は、農民が自ら耕した土地への所有権を得ること、そして土地が持つ「社会的機能」―すなわち、土地の生産力によって個人のみならず、共同体や国家に利益をもたらすこと―というコンセプトを打ち出した。その法によれば、狩猟や採集は土地所有権を得るに値する生産活動とはみなされず、所有する土地の3分の2を農地として使用しなければならないと定めていた。このままでは流入し続ける植民者たちに次々と森の土地所有権を奪われることになる。その帰結として、シュアールたちは植民者たちの生活様式を模倣することを強いられていく。伝統的な焼畑農業ではその広大な土地の3分の2を使用することが不可能だったシュアールたちにとって、唯一残された手段は牧畜の導入による定住だった7。シュアールの間で牧畜が一般的な活動として今日広まっているのは、そのためだ。牧畜をやめ、原生林を農地として使用することも拒むセバスティアンが直面しているのは、「シャーマニズムの駆逐」と「先住民の国家経済への吸収」を目的として、国家とキリスト教という巨大な権力機構がシュアールたちに押し付けてきた抑圧の歴史そのものである。これまでずっと、「シュアールがシュアールであるために」、彼はたった1人で戦ってきたのだ。
だとすれば、牧畜と木材売却によって動物たちの気配を一度は森から失ったセバスティアンの悲哀は、そのままシュアールと彼らを取り巻く権力関係の凝縮でもある。それぞれの住居が広い間隔で点在し、牧畜も営んでいなかった1950年代以前のシュアールたちは、家の前を流れる川から大量の魚を得、数歩森に入ればめくるめく野生動物たちに出会い、音の出ない吹き矢で猟をしていた。しばらく時間が経ち、獲物の数が減れば再び家族で森を移動し、適した場所を見つけては家を建て、チャクラを切り拓いた。それを繰り返すことで、森は再生し、動物や魚は生息数を回復させ、不規則な異種間の出会いを維持することで生態系は循環していた。これは推測ではなく、ケンクイム村の最年長者でセバスティアンの姉であるママイをはじめ、多くの村人たちやその他の場所で出会ったシュアールの人々が証言することである。「昔はこのナマキム川で漁をしたら、大きな魚が食べ切れないくらいたくさん獲れたものよ。今はすっかり変わっちゃったわ」、とママイは言う。それを聞いてパストーラは、「あんたたちが私たちの分まで獲っちゃったのね」と冗談めかして笑う。その会話を聞きながら、俺はたった20年ほどしか年の離れていない彼女たちが生きる歴史の物質性を、多重露光で凝視せざるを得なかった。
パストーラが頻繁に嘆くのは、「時間がない」ということだ。乗降客たちが1分を争い改札口に突進していく都心の通勤ラッシュに揉まれる高校時代を過ごした俺にとって、最初は彼女の嘆きを正面から受け止めることは難しかった。毎日森の糧を得て、食べて、寝る。森での生活なら、これだけで満たされるじゃないか。なんとか彼女の知覚に肉迫しようと努めながらも、どこかにそう高を括ってしまう感覚が残っていた。だが、村に長期滞在することで俺自身に確実に染み込んできたのは、この森の深くにおいてですら、偏在する国家的、政治的、経済的諸力、つまりミシェル・フーコーが言う「生権力」から逃れることはできないという深部感覚である。むしろ、要素が削ぎ落とされているからこそ、その影響をより如実に、明確に、直接的に感じる。
もちろん、パストーラは村のリーダーであり、自身の生存の外部にいくつもの義務が存在する。だが、それは「時間がない」最大の理由ではない。では、最大の理由は何か? パストーラによれば、それは教育である。ある日の昼下がり、パストーラと昼食後の消えかけた焚き火を眺めながら会話していたときのこと。彼女はこの森における「時間感覚」の変容について語った。「昔は何も気にせず、狩りをして漁をして、よく食べて生きていればそれでよかった。森に籠もりたければ何日でも籠もれた。でも今は子供たちを学校に送るためにお金が必要で、前のように何日も狩りに出かける時間はないの。その代わりに鶏を育てて時間をかけずに肉を食べられるようにしたいわ」。リアリストである彼女は、今の状況の中で最も物事がうまく運ぶ方法を選ぶことに躊躇はない。彼女にとって、子供たちができる限り教育を受け、「準備ができている何者か」=alguien preparadoになってほしいという現在の希望に、曇りはない。
沈黙が続く。鶏の声と焚き火がパチパチと鳴る音が辺りを満たす。「私のお父さんはね、すごく足が速かったの。裸足で犬と同じスピードで森を走ることができたの」。パストーラが再び語り出した。「イノシシとかジャガーとか、動物は何でも狩っていたわ。一日に何頭も捕れることもあった。その日には持ち帰れないから、イノシシはその場で肉をスモークにして置いておいて、ジャガーなら皮を剝ぐ。次の日に私のお兄さんや村人たちを連れて行って、一緒に担いで運ぶの。お父さんは優秀な狩人だった。昔は動物も魚もたくさんいて、何頭も捕れる日があっても今みたいに驚かなかった。よく夢を見るの。一番小さかった子供の頃に住んでいた、カネロスの近くにある『ヤタピ』というところ。全く手つかずの森だった。思い出すと、いつも泣きそうになる」。話し終わるパストーラの目には、すでに涙が浮かび、声は震えていた。
俺がケンクイム村に滞在していた当時、パストーラとセバスティアンの5人の子供たちは全員村の外で生活していたが、2人がまだ教育を受けていた。看護師になるために専門学校へ通っていた最年長の長男ダルウィンと、中等学校(日本では高校にあたる)の最終年度を迎えていた最年少の次女ムラヌアである。最も金銭的負担がのしかかる時期は過ぎたかもしれない。しかし、村に住みながら5人の子供たち全員を森の外にある中等学校を修了するまで養うことに、想像を絶する労苦があったことは理解するに容易い。セバスティアンはそのために森を伐採して木材を売り、プラタノを育てて街に売りに出かけ、メスティーソたちの牛の世話をして日銭を稼ぎながらも、精神的負荷からアルコールで身を持ち崩しかけた。
「アマゾンの全ての子供たちのために学校教育を!」と西洋や日本で声高に唱える人がいたら、反対よりは賛成の声の方が圧倒的に多く集まるだろう。「未開発地域に教育をもたらす」ことは、国連やEUをはじめ、多くの国際機関が高貴な使命の一つとして目指していることだ。だが、そもそも学校教育とはある集団を共通のカリキュラムによって包括的に染め上げるイデオロギー的手段である。それは、「私たち」という想像上のアイデンティティに組み込まれるグループの全体にとって、何が最上の価値を持つ知識であり、規範なのかを、一律に決定する。日本では夏目漱石を、フランスではギュスタヴ・フローベールを、イギリスではジェーン・オースティンを教える。アメリカ合衆国では広島・長崎への原爆投下を正しいこととして教え、日本では間違ったこととして教える。それらの知識や規範を他より抜きん出て身に付けた者たちが「エリート」と呼ばれ(ただし、日本のエリートは核兵器を間違ったこととして主張はできないが)、それぞれの国家の「トップ」とされる高等教育機関に集結することで、イデオロギーとヒエラルキーは再生産される。
無論、上に挙げた国々の内部でも、学校教育による弊害について議論の蓄積はあり、オルタナティヴ・スクールなど、既存の画一的教育に対するカウンターが実践されている例もある。だが、先に述べたような視座を基にアマゾン熱帯雨林に「一般国民教育」の網の目を張り巡らせることの意味をもう一度考えてみると、それがいかに壊滅的結果をもたらしうるかが見えてくる。
他の国々と同様に、エクアドルにおいても「エリート校」とされる高等教育機関は首都キトや最大都市グアヤキルに集中している。そこに集うのは、多くの場合既得権益の恩恵を受けた、アマゾン熱帯雨林の諸文化に微塵の興味もなく、知識も持たない子息たちである。「大都市のエリート校を卒業する」ことが教育の成功の指標とされるとき、アマゾン熱帯雨林の先住民コミュニティは、その成功可能性が最も低い圧倒的マイナスとされる位置からのスタートを強いられる。
だが、森の動植物についての知識を、研ぎ澄まされた身体感覚を用いた観察を通して練り上げ、覚醒植物によって得たヴィジョンと共に生きる、セバスティアンが理想とするようなシュアールの生き方にとって、エクアドル国家が画一的に提供する国民教育から得るものは限りなく少ない。その教育の中に、自分たちの姿がないのだ。狩猟や漁のやり方、薬草の見分け方、作り方。自分たちの祖先が語り継いできた神話。家の建て方。木の切り倒し方。チャクラの切り拓き方。キャッサバやプラタノの育て方。チチャの作り方。リーダーとはどうあるべきか。森で力強く生き抜くために必要な態度とは何か。これら全ての生活実践を学ぶことが教育そのものであり、座学とそれ以外の分離も存在しない彼らの生世界において、彼らが生きる森についての知識を何一つ授けないまま、ただ教室の中で身体を椅子に貼り付けられる学校教育は、森の子供たちの時間を奪うもの以外の何物でもない。
確かに、エクアドルは「エドゥカシオン・ビリングエ」=Educación bilingüeという二言語教育を導入し、シュアールを含む先住民コミュニティがそれぞれ持つ独自言語による初等教育を行う余地を与えている。だが、それにも拘らず目を逸らすことができない事実は、新しい世代になるにつれ、子供たちはシュアール語を話さなくなり、スペイン語の比重が目に見えて大きくなっているということだ。俺の滞在当時、すでに15歳以下の子供たちのほとんどはスペイン語の方が得意だった。それからさらに時間が経っている今、シュアール語を話す子供たちの割合は確実により減っている。シュアールの親たちは悟っているのだ。二言語教育が所詮は偽善であることを。その先には、大都市のメスティーソや白人たちと同一線上の競争にさらされ、敗れる未来しかないことを。
パストーラが時間感覚の変容について語った日の数日後。彼女は再び体調を崩し、部屋で寝込んでいた。容体を心配しつつも、俺はセバスティアンと夜の焚き火に当たりながら話していた。ふと思い当たり、パストーラと交わした学校教育についての会話のことをセバスティアンに尋ねてみる。彼がそのことについてどう思っているのか、興味があった。すると、それまでいつものようにこの日飲んだチチャがもたらす心地良い酩酊に浸りながら上機嫌で会話していたセバスティアンの表情が、急変した。「教育が全てを破壊したんだ」。セバスティアンが呟いた言葉の意味を、最初は摑みきれなかった。もう一度、念を押すように彼は言った。「教育が、僕たちの生活を全て破壊したんだ」。今度は文の意味を確認できた俺は、驚いた。普段、薬草の知識やヴィジョンについて、あるいはどのように生きるかという、どちらかといえば内省的な関心が強いセバスティアンが、国の制度についてこれほど瞬時に断定することはなかった。薄暗い橙色の光の中で彼の目を見ると、血走ったような怒りを伴う強い視線を感じる。
「子供の教育が義務化されてから、学校に通わせないと親は逮捕されるようになった。そのせいでお金が必要になって、街に働きに行ったり森を破壊して木材を売らないといけなくなって、前みたいな生活はできなくなった。義務教育が僕たち先住民の生活を全て破壊したんだ」。セバスティアンは語気を強めた。数日前に彼がいない場でパストーラが言っていたのと同じことを言っている。エクアドルでは、ホームスクーリングの実施に厳しい条件が設定されており、学校が自宅から通えない距離にある、子供が病弱である、親が教育スキルを持つことなどを証明する必要があり、セバスティアンの家族にとってそれは不可能なことだった。
建物の中で、パーティが行われている。誰かの卒業式のようだ。中央にいる若者が、スーツを着てネクタイを締め、祝福されている。その隣に、若者の父親らしき人物の喜んでいる姿がある。そこには教師たちもいた。様々な体格で、何人かは背が高く、背が低い者も、太っている者もいた。女性の教師もいた。皆が拍手をしてその若者を称えていた。15年前に、セバスティアンは森の奥深くでマイキュアを飲み、3日間彷徨い、もがきながらこのヴィジョンを得た。それ以来、彼は誰にもそのことを伝えないまま、自分の心の中に真実を閉まっておいた。マイキュアを通して見たヴィジョンは、それが具現化するまで誰にも話してはいけない。来る日も来る日も、セバスティアンは街へ日雇い労働をしに出かけ、プラタノとパパチーナを売り、1日に10ドルを稼いだ。
長男のダルウィンが専門学校の卒業式を迎えたとき、初めて息子に自分が見たヴィジョンを伝えた。そして、そのときのために貯めていた560ドルを使って牛を一頭丸ごと買い、皆で食べた。ヴィジョンを得たあと、ただその未来を待っているだけでは、ヴィジョンを生きることはできない。それを実現させるためのプランニングと行動、そして信じ切る意志が必要だ。「ヴィジョンは必ず実現する」とセバスティアンは言う。ヴィジョンとは、マイキュアが与える「宿題」、つまり何か課題を達成しなければ成果を得ることができない契約関係ではない。ヴィジョンは必ず実現する。それは薬草の力によって、それがもたらすある種の臨死的体験によって、望もうが望むまいが自らの身体に刻印され、その存在様態を根底から作り直すものだからである。
「義務教育が自分たちの生活全てを破壊した」と血走った目で断言するセバスティアンはまた、自らが信ずる薬草の力によって、息子がまさにその教育システムの中で成長し、看護師の専門学校を卒業するヴィジョンを得、その実現を真に望んでいた。夢を媒介にして彼が生きているこの乗り越えがたい二重意識―W・E・B・デュボイスが「二重の人生、二重の思考、二重の責務8」と呼んだもの―は、現代のアマゾン熱帯雨林における先住民世界を深く貫き、自己像を脱臼させ、生活の端々に不可視の破片を散乱させている。
セバスティアンとキリスト教の関係もまた、この村の中で異質である。彼は村の中でほぼ唯一、能動的にキリスト教から自己破門した人間なのだ。彼以外の村人たちは、「あなたの宗教はなんですか?」と聞かれれば「キリスト教」と疑問なく答えるだろう。福音派によるシュアールの村々における宣教活動は、20世紀を通して森の隅々まで浸透し、彼らの大半を入信させることに成功した。確かに、宣教師たちが目指す「シャーマニズムという蒙昧からの先住民の解放」はいまだに達成されていない。また、「神」をシュアールにとっての森を司る生命力の源泉である「アルータム」として言い換えることもあるなど、この地でのキリスト教の存在様態は、避けがたく重層的である。しかし、冠婚葬祭や祭日、礼拝などを通し、生活の様々な場面でキリスト教の様式が導入されているのは無視できない現実である。
「2002年頃だったかな。宣教師たちが何人か僕の家に来たんだ。『モンテ・シナイ』という名前のグループだった」。セバスティアンがある日語り始めた。「マサ」という摩り下ろしたプラタノを茹でたスープを啜っているときだった。このスープは、現在では日常的に飲まれるが、元々は戦士が戦いの前に食するものだった。敵を殺す前に肉や魚を絶ち、霊感を高める彼らにとって、植物性の「マサ」は最も重要なエネルギー源だったのだ。俺たちの横では少し身体が大きくなったクロがまだあどけない声で鳴きながら鶏を追いかけている。
セバスティアンが続ける。「その宣教師たちは、『神』について説明し始めた。なるほど、と思いながら聞いていたよ。すると、聞いているうちに強引にキリスト教徒になることになってしまった。仕方ない、試してみるかと思って、彼らが正しいとすることをしばらくやってみたんだ」。福音派に入信すると、セバスティアンがまずやめることを求められたのは強い酒を飲むことである。当時、トラゴ・デ・カーニャなど度数の高い蒸留酒を好んでいたセバスティアンは、翌日からそれらを飲むことを止めた。さらに、宣教師たちは酔っ払いに囲まれることや、祭りに行って踊ったりすることも禁じたため、それまで参加していた催しに参加しなくなるか、参加しても酒を飲まずに控えめに振る舞うことが多くなった。
「神に服従するようになってから、僕の人生はつまらなくなった」。セバスティアンは端的に言う。「それと、他の信徒たちが実は意地悪だということに気付いてきた。例えば、聖書には『困っている人がいたら助けなさい』と書いてあるけど、実際にはそういう状況になっても宣教師は人を助けない。他にも、『噓をついてはいけない』と書いてあるのに、彼らは嘘をつく。そういう場面をたくさん見て、信頼できなくなった」。入信以来、みるみる生気を失っていくセバスティアンを見て、パストーラはキリスト教をやめるように言い始めた。彼自身も辛くなり、約1年後、宣教師たちに自己破門を申し出た。宣教師たちはなんとか踏みとどまるように説得し、その後もしつこく戻るように求めてきたが、「一度やめたものに戻りたくはない」と後ろを振り返ることはなかった。何より、セバスティアンは神の矛盾に気づき、信心を失ったのだ。この「キリスト教に入ってみたが、やめた」というセバスティアンの経験は、留まるところを知らない宣教活動と、植民地主義との決定的結びつきによって世界の景色を以前とは全く異なるものに変えたこの宗教を、一方向的な侵食運動としてではなく、ある種の可逆性として捉える契機を生み出す。
別の日には、セバスティアンはキリスト教についてもう一つ興味深いことを述べていた。それは、「キリスト教徒になった村人たちは、もはや自然を僕と同じ見方では見ない」という証言だ。「キリスト教徒になると、『勤勉に働きなさい』と言われるようになる。村人たちは一生懸命、チャクラを切り拓き、売るための作物をたくさん育てようとする。草地を増やしてより多くの牛を育てようとする。僕からすれば、彼らは森をお金の源泉としてしか見ないようになっている。キリスト教徒になると、宣教師たちからそう教えられるんだ」。俺は滞在中、ケンクイム村を行き来していたセバスティアンも顔なじみのスウェーデン出身の宣教師と一度顔を合わせたことはあるが、長く会話する機会はなかったため、宣教活動についての証言はセバスティアンやパストーラ、村人たちを通してのものが多い。それ自体が圧倒的多様性を持つキリスト教の中で、この村に通う宣教師たちがどのような言葉を掛けながら布教活動を行っているのかについての俺の直接的な観察経験は少ない。だが、マックス・ヴェーバーの名著『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』以来、禁欲と清貧によって時間の無駄を省き、勤勉に働くことで富の蓄積を目指すプロテスタンティズムの倫理体系については様々な議論が行われている。福音派とは、数多あるプロテスタンティズムの一宗派であるが、森を「富の源泉」とみなし、より多くの金銭を得るための資源として活用するように説くことは、プロテスタンティズムの姿勢としてある種の一貫性の顕在であるとも言える。セバスティアンは、森に対するこの姿勢が自分とは相容れないと喝破し、自己破門に至った。それは、森に住む誰もができることではない。
アマゾン熱帯雨林におけるキリスト教についての論考は、決して少なくはない9。西洋や南米出身の研究者たちは、自身もほとんどがキリスト教の出自を持ち、森に住む先住民たちとの接触を図る際にも宣教師たちの協力を得ることが多い。キリスト教の宣教活動や、入信の過程やその後の変容についての第一次資料は、むしろ俺よりも豊富に持っている可能性が高いだろう。だが、上記の諸事情ゆえに、彼らはキリスト教から完全に距離を取ることができない。認識論的には距離を取っているように見えても、自らが生まれた瞬間から浸されているその神学的世界観の外部に身を置くことは困難である。従って、アマゾン熱帯雨林におけるキリスト教についての研究はあっても、「森におけるキリスト教そのものの是非」を問う研究は皆無に等しい。
ならば、白人でもメスティーソでもキリスト教の家系出身でもなく、先住民の人々との接触に際して宣教師たちの協力を得てもいない人類学者として圧倒的少数派である俺が、問わなければならない。シュアールをはじめ先住民の人々を「貧しい集団」と断定し、シャーマニズムを邪教として駆逐し、彼らを貧困から救うために「森を切り拓き、勤勉に働いてお金を稼げ」と説くキリスト教が、まさに森を過剰に破壊する原動力となり、彼らを動植物との緊密な交感と諸実践から引き剝がすことで、劣等意識の下に置き続ける装置となっていたとしたら? 学校教育と同様に、崇高な目的のもとに正当化されるか、あるいは「様々な面がある」両義的存在として検討されるキリスト教は、「文明化の使命」=mission civilisatriceの名の下に遂行された植民地主義支配の現在進行形の姿として、最大の批判的意志とともに問われるべきものではないのか? キリスト教を、「すでにそこにあるもの」として、所与のものとして受け入れることは、「植民地」を「海外領」と言い換えることで当たり前のものとして受け入れることと同じではないのか? 「アマゾンにおけるキリスト教の在り方」について知的思索を行う前に、セバスティアンがキリスト教を「やめた」意味を、正面から受け止めるべきだ。
「元気そうでよかった。もっとゲッソリしてるかと思ったから」。俺はマカスの行きつけの宿で、心もとないWi-Fiを使ってエミリーと途切れ途切れのビデオ通話をしていた。「俺は元気だよ。まだ家の屋根が完成しないから雨が漏れるのが大変だけど、もうすぐ終わると思うしね」「え、何それ! 屋根を葉っぱで作ってるの? それが完成しないから屋根に穴が空いたまま生活してるの? すごいところにいるね」。そうか、森での生活が自分にとっての標準になってしまったので当たり前のことのように話しているが、パリにいるエミリーが聞いたらまずそこから驚くのか。俺が話す一文一文に、彼女を驚かせる要素がいくつもあるせいでなかなか会話が進まない。寝ているテントの中に毎回ゴキブリがいることは伝えないように気を付けよう。マカスに来るのは1ヶ月ぶりだが、エミリーとお互いの顔を見ながら話すのは2ヶ月ぶりくらいかもしれない。通話の前にすでにクリームパスタを食べておいた。
「報告があるの。例の日本大使館のPRの仕事、受かったの!」「ええ、本当に? すごい、おめでとう!」物凄い倍率だったはずのその仕事を、エミリーが見事に射止めたことが素直に嬉しかった。「そうなの。最初は書類審査で、最後に面接があるんだけど、私面接で本当にめちゃくちゃなことばっかり言っちゃって。でもとにかく面接官の人はずっと爆笑しっぱなしだったから気に入ってくれたらいけると思ったんだけど、やっぱりいけたわ」。エミリーは緊張しやすいところがあるが、縮こまってしまうのではなく逆に饒舌になりすぎるタイプで、面接や人前で話すときなど、パブリックな場面で重苦しい空気を破壊する才能を持っていた。日本大使館という硬い組織にそれがどう受け取られるかわからなかったが、どうやらプラスの方向に働いたようだ。エミリーはすでに仕事を開始していて、SNSアカウントの運用やイベント開催のための関係作りなどに取り組んでいるらしい。「最初に色々やり方は説明されたんだけど、もうほとんど自分のやり方で作り変えちゃった。正直、グラフィックとかについて疎い人多いじゃない。見せ方とかにセンスないっていうかさ。だから自分で1からやり方考える方がいいと思って。怒られそうだなって思ったら、『ガイジンだから、それわかんない〜』って言えば、日本人の人ってけっこう好き勝手やらせてくれるから、わざとわかってないふりとかして」。雨季の豪雨がいまだ頻繁に降り注ぐ鬱蒼とした森から、灰色の空とクリーム色の建物が支配する冬のパリに脳内のイメージが引き戻される。とはいえ、月に一度マカスに一泊するだけでは森の外部に戻って来られないほどに、俺の頭も足腰も、耳もリズムも味覚も肌感覚も、シュアールの生世界の一部になっていた。
「アキミがいないことは、やっぱり辛い。それを忘れるために仕事してるって面も多分ある。何もしなかったら苦しすぎるから」。俺の不在が、エミリーの生活にぽっかりと穴を空けていることに、変わりはなかった。仕事がない日は、友人とカンフーを習ったり、兄が関わるクラブイベントの手伝いをしたり、サンマルタン運河沿いにあるお気に入りのイラン系ティーハウスで俺がプレゼントとしてあげた『ジェーン・エア』のフランス語訳を読んでいるらしい。「『ジェーン・エア』、すごく面白いよ。女性として考えさせられることがたくさんある。今の私にぴったりの本。プレゼントしてくれてありがとう」。セルビアの田舎からパリに移民としてやって来て、結婚後は専業主婦として3人の子供を育てるために必死に生きてきた母親の存在は、3人のうちの唯一の女性であるエミリーにとって、自由で洒脱で媚びない「パリっ子」としての生き方に、一方で乗り越えがたい重しを吊る存在でもあった。娘を自由に育てたい母親の意思に揺れはない一方で、兄をはじめ親戚たちはルーツであるセルビアへの傾倒を強めていく。エミリーは、そのような家庭環境の中で女性である自分に対する保守的な視線を感じていた。『ジェーン・エア』を勧めたのは、エミリーが直面している課題の大元が描かれていると思ったからだ。
エミリーとはフィールドワーク中の通話で、一度些細なことがきっかけで口論になってしまったことがあったが、仲直りしていた。その後、ケンクイム村の電波が届く丘から時々メッセージを交換していたが、徐々に彼女からの返信が滞ることが多くなっていた。彼女にとっては、ほとんど連絡がつかない状態の俺について考えを巡らせること自体を避けることで、自分を守るために必要だったのかもしれない。だが、俺からすれば、毎日必死にフィールドワークを行いながらも、彼女を忘れていないことを伝えるために疲れた身体を引きずり、丘を登ってメッセージを届けていた。エミリーが写る1枚のポラロイド写真を暗くなる前に何分も眺めながら、森の片隅で彼女に想いを馳せていた。出発前にあれほど強固に感じていた、絶対に崩れることはないと確信できた俺たちの結びつきに、ほんの僅かずつではあるが、綻びめいたものが生まれつつあるのだろうか。「じゃあ、そろそろ寝るから切るね。エクアドルに行けるかわかったら、言うね。森の動物はなんでも食べるって言ってたけど、猿だけは可哀想に感じるから食べないで。愛してる。ジュ・テーム。おやすみ」。エミリーは、俺が森で猿を食べるかもしれない可能性を知ると、どうもそのことに違和感を持っているようだった。
雲一つない晴れ空に、トンカチで釘を打つ音が間断なくこだまする。セバスティアンとパストーラの家の屋根の張替え作業を行う、最後のミンガの日だ。川が穏やかに流れる音に耳を澄ませ、土を踏みしめる感触を味わいながら薄青い朝の空に視線を向ける。ケンクイム村での滞在を始めてからというもの、俺は2ヶ月以上にわたって穴が空いた屋根の下で暮らしていた。テントや荷物を雨が漏れない箇所に置けば問題ないと、最初は思っていた。だが、雨季のスコールに頻繁に見舞われるこの時期、部屋の中は常に猛烈な湿気に包まれることになる。イギリスの中でも雨が多い地域として知られるマンチェスターでも、湿気は生活上の悩みの種だ。だが、ここアマゾン熱帯雨林において屋根に穴が空いた状態で雨季を過ごすのは、イングランド北部よりも何倍も何十倍も厳しかった。
洗濯物は、部屋で干していても永遠に乾くことはない。1週間干しても2週間干しても、状態はほとんど変わらない。服を乾かすには、日によって訪れる一瞬の晴れ間に、家と村の中心の間を流れる小川に架かる橋の手すりのちょうど太陽の光が当たるところに干すしかない。そのタイミングを逃さなければ、20分ほどでしっかり乾く。ただ、日中はセバスティアンと森を歩いていたり、パストーラとチャクラに行っていたり、漁をしたりミンガに参加していたり、子供たちに英語を教えていたり、何かと外出していることが多かったので、太陽が出ているタイミングを逃すことも多かった。
洗濯物が湿っているだけなら、正直大したことはない。そのまま着たって生活はできる。だが、湿っている服をなるべく着たくない理由が俺にはあった。極度の湿度の中で生活することがもたらす俺にとっての最大の脅威は、皮膚に感染した得体の知れない細菌が活気づくことである。ケンクイム村での生活を始めて数週間も経たない頃から、鼠径部に強烈な痒みが出てきた。何日かすると、そこが赤く腫れ、魚の鱗のようにボロボロと皮膚が細かく剝け落ちるようになり、範囲が鼠径部から内腿へと広がっていった。川や泥水に服を着たまま入ったあと、すぐに洗い流したり十全に乾かさなかった、いや乾かせなかったことが頻出したことで、何らかの細菌が俺の肌に寄生してしまったようだ。完全に乾いた下着や服を身に着けると、幾分か痒みや痛みが和らいだ。だが、洗濯物がなかなか乾かないときは、湿ったままの服を着ざるを得ず、すると俺の肌を蝕む細菌はさらに勢力を増大させた。そんな慢性的な皮膚の異常に、俺はただただ耐えるしかなかった。
もちろん、ゴキブリや蚊などの虫も、湿気が大好物だ。毎晩のようにテントの中に潜んでいるゴキブリを追い出すことにはもう慣れていたし、蚊に喰われる頻度も量も、森の外部とは桁違いであるものの、徐々に俺の血肉がシュアールに染まっていくに従って、確かに減少していた。だが、屋根が完成し、部屋が乾いた状態が維持されることでこれらの虫の出現率が少しでも減るなら、それに越したことはない。ゴキブリや蚊を抜きにしても、俺にとって部屋に虫が溢れるのは不都合だった。ここアマゾン熱帯雨林では、ラップトップやカメラなどの電子機器の内部に、小さな虫たちが次々と侵入してくる。撮影しようとしてファインダーやモニターを覗くと、ぼやけた黒い斑点が見えることが度々あった。しかもその斑点が動くのだ。その度にレンズを外してクリーニングをしたり、あの手この手で虫を搔き出す手間に追われた。ラップトップに虫が混入すると、キーボードを照らすバックライトに影が見えたり、死骸がカスとなり裏に溜まったりした。
そもそも、極度の湿気はそれだけで電子機器の故障リスクを高める。さらに虫の混入が重なることで、このフィールドワーク中にラップトップは二度の故障に見舞われた。2012年製の旧式MacBookだったこともあり、エクアドルにも修理できる技術者がいたのが不幸中の幸いだった。ソニー製のカムコーダーとペンタックス製の一眼レフは、どちらも驚異的な耐久性により、この森の過酷な環境においても一度も故障することなく生き抜いたことは言及しておくべきだろう。
このように、アマゾン熱帯雨林に生きるということは、都市生活に馴れた自身の肉体や電子機器が全く想定していない苛烈な自然環境に身を置くということであり、それは「ジャガーに喰われる」などというだいそれた話の前に、微生物や虫によってこの森のどこにいても文字通り肉体を喰われ続ける経験から始まる。この森では、俺たちの身体は常に死線の上にある。なぜなら、屍として腐敗することを待たずとも、すでにありとあらゆる生命体が俺たちの肉体を喰うことから逃れることができないからだ。むしろ、この肉体は、常に腐敗し続けている。アマゾン熱帯雨林は、その事実を無慈悲に知覚可能にするに過ぎない。
セバスティアンをはじめミンガに参加している村人たちは、予め横向きに釘打ちしておいた竹の板とチャピの葉の間に、中央に切れ目を入れたプンプナの葉を茎から差し込み、折り曲げる。その作業を一枚ずつ、一段ずつ、続けていく。一枚一枚の葉っぱ全てが、何度も開催したミンガを通して皆が刈り取ったものだ。ミンガがなくとも、セバスティアンと俺は度々2人で森に入り、追加で葉っぱを集め、束を背中に担いだ。
外では、子供たちがチャピの葉を織り込んでいる。扇形に近い葉の形を持ち、茎が細いプンプナと異なり、太く長い茎と鳥の羽のような形のチャピは、補強材として屋根の裏側に取り付けられる。「このやり方はシュアールがいつもやってきたもので、この村なら子供もみんな知っているんだ。例えばプンプナの代わりにクーントゥとか違う種類の葉っぱを使うこともあるけど、プンプナの方が長持ちする。だから僕はプンプナとチャピの組み合わせが一番良いと思っている」とセバスティアンは言う。「シュアールのやり方」は確かに存在する。しかし、それは常に同じではない。パリで料理するときですら、オリーブオイルの代替としてサンフラワーオイルを使うこともある。環境が目まぐるしく移り変わるアマゾンで、物事が常にレシピ通りだと誰が言えるのだ。
それだけではない。ときに、「シュアール本来のやり方」そのものを、更新することもある。セバスティアンとパストーラの家の柱は、レム、イヒュ、カヤネムという3種類の木から出来ている。しかし、シュアールの先祖たちは伝統的にイヒュを家作りのための最適な木材と考えてきたため、レムとカヤネムを使うことはなかった。イヒュはシュアールにとっての最強の武器である槍にも使われる素材である。「石のように硬い」という意味のカヤネムは、メスティーソたちがアマゾンへの侵食を加速させると、価値の高い木材として大量に取引されたという。シュアールの人々にとっては、自分たちが使わない木が高値で売れたため、皆喜んで伐採していた。セバスティアン自身が、90年代から2000年代にかけて、カヤネムをディーラーに売っていたという。「あるとき、切ったばかりのカヤネムを見ながら思ったんだ。そもそもなぜ、先祖たちはカヤネムを不要な木とみなしてきたんだろうってね。この木はとんでもなく硬い。確かに切るのは大変だし重さもある。だけどこれを家の柱に使ったら長持ちするんじゃないか?」彼はシュアールの間で共有されていた常識に反して、不要とされていた木に価値を見出し、自分の家に使い始めた。「もう一つ、先祖が使ってこなかったのがこのレムという木だ。硬さはカヤネムやイヒュほどじゃないが、十分家の柱として耐える強さがあると、観察していて思った。なにより、この表面を見てくれ。とても美しいだろう?」セバスティアンが横目を俺の方にやった。確かに、レムの木は幹に水脈の跡が残っているかのようなへこみがあり、それが美しく波打つように縦に続いていた。初めてこの家に入ったときからその特異な形には気付いていたが、元々シュアールが使っていなかったこの木を彼が敢えて柱に使っていたことは知らなかった。
結果論として無事に家が建っているものの、元々民族の間で不要とされてきた木を柱に使うことは、場合によっては家族全体の命にも関わる大きなリスクを取ることでもある。観察と思索を重ね、「集中する」=enentaimsatinことで事物の性質を見極め、常識を超えて用途を見出すセバスティアンの態度は、薬草に対するものと同じだった。また、新たな使用方法を生み出す際には、実用性の他にも美しさが大きく作用し、二つの要素は分かち難く融解している。生きるか死ぬかの瀬戸際で使用される槍ですら、「黒く光るイヒュの木の美しさ」は、敵を刺し殺す実用性から乖離しては存在できないのだ。
屋根の張替え作業の休憩中にセバスティアンと言葉を交わしながら、俺はレヴィ=ストロースが語っていたことを思い出さざるを得なかった。ブリコラージュ。元々フランス語で「ありあわせの道具と素材で作業する」という意味で使われる単語を哲学的に転用し、『野生の思考』の中で展開された、後世に決定的影響を与え続ける概念である。レヴィ=ストロースによれば、神話的思考とは「知的なブリコラージュ」であり、それは構造化された集合体を、他の集合体を用いてではなく、残滓と瓦礫によって組み立て直すことである10。それは、すでに構造化された代替可能な何かを元々あったものと置き換えるのではなく、元々構造の外側にあったものを構造化の過程に組み込むことを意味する。その結果として、ブリコラージュは「輝き、予測不能な11」状況を作り出す。何より、ブリコラージュは一つの詩学=poésieとして、とある課題が常に複数の解決策を内包する芸術のフィールドと同様に、何かを達成することや遂行すること以上に「限定された可能であるもの」の中から行為者が選択し構築した事物を通して、その者の生の性質をありありと語るのだ12。
シュアールの人々の生世界には、アマゾン熱帯雨林でレヴィ=ストロースが閃光として受け取り、言語化した「ブリコラージュ」の思考と実践が剝き出しの姿で確かに生き続けている。シャーマンだった父からシャーマニズムに関する知識を全く受け継ぐことができなかったと悔やんでいるセバスティアンは、それでも自ら新たに知識を組み立てることができた。彼は、パラダイムを創出しているのである。「植物に詳しい人でも、なんでも知ってるわけじゃない。知らないことなんてたくさんあるんだ。だから僕たちはいつも新しい知識がほしい。昔のシャーマンたちは、民族の境界を越えて自分たちの秘密の知識を交換していた。僕も彼らのように、シュアールだろうがそうでなかろうが、知らない植物の知識を教えてくれる人がいたらそれを試し、自分のものにするだけさ」。
ひとたび移動すれば異なる植生や動物の姿が立ち上がる多様性を持つアマゾンの森では、その広大な領域全てに関する知識を体系化することは不可能であり、それぞれの環境下で知識が現れては消え、現れては消えていく。しかし、誰かが近くから植物を持ち帰り、自分の土地に植えることで新たな種が根付くように、知識は無限に生成変化を繰り返す。知識の継承の核にあるのは、内容そのものではなく、自ら知識を練り上げる技術であり、その意味で、セバスティアンは間違いなくそれを受け継いでいる。その力を持つからこそ、生まれ育った村から離れても、与えられた環境の中で自ら知識を組み上げることができる。あるいは、それを彼に継承したのは父ではないかもしれない。そこにこそ、植物を介した集合知の蓄積としてのヴィジョン経験の必然的な役割があるのかもしれない。
今日のミンガも終盤に入り、いよいよ屋根の完成が近づいている。村人たちはどこかで拾った鉄の棒を定規として使い、折れかけていた梁を補強するための木を切りに行った。電源ケーブルの残骸をロープとして使い、屋根の先端の方で作業している者たちに向けて釘や工具を下から送る。「ヤワ・ハアスタ! ヤワ・ハアスタ!」今日のセバスティアンの掛け声は、ひたすら「ジャガー、ジャガー、ジャガー」だ。とにかく、今は強さとパワーだけが必要ということだ。葉っぱを織り込むときの擦れる音が家中を支配する。日が傾いていく。セバスティアンが10ドルをはたいて村の女性から買い取ったバケツ一杯の古くなりかけたチチャを各々が作業を止めながら補給する。いつものような陽気な冗談の掛け合いはなく、飛び交うのは作業上の指示の声のみ。「ここまで来たら、絶対に今日終わらせる」と、その場の誰もが思っていた。
屋根の先端で何本かの竹を組んで葉っぱがずれないように固定する作業を、身軽なダニエルとペドロが行う。一部にかかっていた雲が消え、斜陽が彼らを薄いオレンジ色に染めた。ハシゴのない屋根の上から、まずダニエルが葉っぱを摑みながらゆっくりと降りていく。ペドロがはるかに身軽な動きで、すとんと地面に足を着いた。終わった。2ヶ月間、雨季の雨に行く手を阻まれながらもミンガを開催し、村人たちの協力を得ながら、ケンクイム村に残る唯一の葉っぱでできた屋根が、無事張り替えられたのだ。
2階に足を踏み入れると、床はすでに乾いていた。これまでは、たとえ雨が降らない日が何日か続いても床は常に湿っていた。細菌に喰われ続ける鼠径部の肌の苦しみが、少しは改善してくれるかもしれない。
ミンガに参加した村人たちのほぼ全員が、2階に集まっていた。途轍もない充実感に満たされている。俺たちと同じように呼吸を続ける葉っぱの束が、上方から優しく皆を包みこんでいる。セバスティアンは、感謝を伝えるため、自分が依って立つ場所とはどこかを宣言するため、歌を歌い始めた。会話がパタリと止まり、耳を澄ませる。
僕は独りここに立つ
ただ独り立っている
マイキュアを摘むために
こうして今 マイキュアを摘んでいる
父が夢を見たように 僕もまた夢を見た
父と同じように 僕もヴィジョンを得た
続いて、セバスティアンのピンギュイの音色が鳴り響いた。俺の骨と血と肉も、ヴィジョンを得たい、森に棲む精霊たちと対話したいと、もはや疼きが抑えきれなくなっているのを感じていた。
4. 後日、このときパストーラは現実世界でマイキュアによって覚醒したセバスティアンを見て逃げたと語っている。
5. Kohn, Eduardo. 2007. “How dogs dream: Amazonian natures and the politics of transspecies engagement.” American Ethnologist 34 (1), 3-24. p. 9.
6. Buitrón Arias, Natalia. 2016. The Attraction of Unity: Power, Knowledge, and Community among the Shuar of Ecuadorian Amazonia. PhD Thesis, London: London School of Economics. p. 56.
8. Du Bois, W.E.B. 2015 (1903). The Soul of Black Folk. New Haven: Yale University Press. p. 152.
9. 全てを挙げるのは不可能であるが、例えば下記諸研究は、キリスト教とアマゾン熱帯雨林先住民の関係性について論じる主要な文献である。
Vilaça, Aparecida. 2016. Praying and Preying: Christianity in Indigenous Amazonia. Berkeley:University of California Press.
Vilaça, Aparecida, and Robin M. Wright, eds. 2009. Native Christians: Modes and Effects of Christianity among Indigenous Peoples of the Americas. London: Routledge.
Wright, Robin (ed). 1999. Transformando os Deuses. Os Múltiplos Sentidos da Conversão entre os Povos Indígenas no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp.
Wright, Robin (ed). 2004. Transformando os Deuses v. II. Igrejas Evangélicas, Pentecostais e Neo-Pentecostais entre os Povos Indígenas no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp.
10. Lévi-Strauss, Claude. 1962. La Pensée Sauvage. Paris: Plon, p. 32.