本を書くことで、ひとつ旅を終えたような気分だった。ようやく一息つけると思っていた。それなのに、全然終わっていなかった。本を出すことで、本に書いたことの続きが展開してくような、そんな出来事が次々と起こった。思いもよらないことだった――。
* * *
山の獣の肉を、猟師からもらって食べる。猟師と山に入り、殺した獣の肉を持ち帰る。そんな暮らしを十数年してきた。大きな脚を台所で解体しながら、肉の匂いを嗅ぎながら、どんな料理にしようかと考え、家族が集まる食卓に出す。山と台所を行き来する中で、当たり前に思えていたことが少しずつちがって感じられるようになり、“いま” を取っておきたくなった。消えゆく風景を写真に撮るみたいに書いたのが『山と獣と肉と皮』だった。
人間の住む世界で “悪いこと” とされていることが、山では当たり前の風景としてあった。 “暴力” と “殺す” こと。
でもそれは、決して人間だけのおこないではなく、ほかの野生動物たちもそうして生きている。だから、山で見る人間のそうした行為は、間違っているとも思わない、という妙な感覚があった。(P.1)

これは同書「はじめに」からの抜粋。人工物あふれる人間界から離れ、山に入ると、その異世界っぷりに圧倒された。樹々と落ち葉と土、流れる水と風、鳥と獣と小さな生き物たちの世界。おのずと、幼いころに読んだ昔話や神話の世界が思い浮かんだ。そうしたものに元来 “暴力”と “殺す” ことが含まれていたことにも、あらためて気づかされた。
猟師と山に入るようになって、それは当然のことだったのだと思い知った。現代を生きる私たちは、殺した肉しか食べられない。人間は死肉を食す鳥類ともちがうし、腐肉にたかる蛆(うじ)ともちがう。そこには必ず、人間が “殺して肉にする” という行為がある。それは野生肉だけでなく、家畜であっても同じこと。

『山と獣と肉と皮』の出版後、いくつかのメディアから本を露出させられないと言われてしまった。原因は表紙カバー写真だった。肋骨が露わになった猪の写真が、問題視されてしまう。
そもそも書籍自体がメディア。書籍づくりも終盤に差し掛かったころ、装丁家・関根信一さんによるラフがあがってきた。めちゃくちゃカッコいい。胸が高鳴った。電話で話す編集者の声も高揚気味で、「絶妙な線を衝いてる」と出来栄えを讃えていた。それが、翌日になると急に声のトーンが変わった。ステイホームのコロナ禍。大学生と中学生のお子さんに見せると、「うわっ」と目を逸らされてしまったとのこと。一年間の連載で私の感覚に近づいていたところ、気兼ねのない家族の素直な反応に、はたと目が覚めた気がしたのだろう。「とりあえず編集部に意見を聞いてみる」とのこと。
表紙ラフに使われた2枚の写真は、私にとって本命の2枚だった。肋骨が露わになった猪と、解体中の猪。いずれも、もう獣ではないが、まだ肉でもない、その間にある “肉になっていく風景”。私が見てきたものとして象徴的だった。
出版社では営業部だけでなく編集部内でも圧倒的な反対だったという。グロすぎる、平積みしてもらえない、と。このままでは出せない。じゃあどうならいいのか、どこまでならいいのか、血がダメなのか、いや赤いだけでもうダメなのか——。明確な線引きがない。だからといって、猪シチューの写真に差し替えるなんてゼッタイ御免。時間もない。デザインを一から変えることも困難な状況で、どう決着をつけるのか。編集者はさぞかし胃を痛めただろう。
結局、折衷案としてオビを高くして写真を半分隠すことになった。写真はチラ見せだが、オビを取れば全部見える仕掛けだ。まるでエロ本のよう。けれど、その見え隠れする感じが本の内容に合っている気もした。隠されることで生じる存在感がある。これで解決したと思っていた。

プロモーションを考えていたら、長崎市立図書館での刊行記念講演が決まった。ポスターの画像を準備したり、図書館側も「これから告知に力を入れます」と張り切って言ってくれた。ありがたい。本を書いたからには、たくさんの人に読んでもらいたい。
そんな矢先、イベント担当者から電話がかかってきた。
「いつも通りに地元テレビでイベント告知しようとしたら、今回に限って『表紙は放映できません。本のことは口頭だけで伝えてください』と言われちゃったんです」とのこと。翌日、私が直接やりとりしていた他局からも同様の連絡が入った。嫌な予感がしてきて、もうひとつ別局とも交渉中だったので、恐るおそるメールで尋ねてみた。「他局では表紙を出せないと言ってますが、そちらはどうですか?」すると、「プロデューサーは消極的。多くの人が不愉快に感じたり大きな衝撃を感じる映像については敏感にならざるを得ない」と返ってきた。
立て続けの出来事だっただけに、さすがにショックだった。“穢(けが)れ” についても触れた本だけれど、今はこの本自体が穢れ扱いされているみたい。黙殺され、排除されて、消えていくのか――。
肋骨が露わになった猪の写真は、確かに一見残酷に見えるだろう。ただ、説明を加えると、この写真はよりおいしくするための工夫として、寒く乾燥する真冬に干された猪の体。そのことは本に書いており、読む人がこの写真の由来を知って、読み終わるときには表紙が違って見えるんじゃないかと想像していた。けれど、本を知って手に取ってもらわなければ、それも叶わない。
世の中では “命の尊さ” “命をいただく” など命のキャッチフレーズがあふれ、大人から子どもまでもがそうした言葉を使う。でも、その言葉のリアルである “動物の死” と “肉” が接続する写真はこんなにも忌避されてしまう。なんだか、命が言葉だけでできているみたい。肉体は命そのものなのに。
山で獣たちが死んでいくところを見ながら繰り返し思ったのは、“命はこの肉体だけに宿っているんだ” ということだった。
猛々しくいなないていた猪が心臓を突かれ、一瞬で声を失い、ドサリと倒れたとき、肉体は目の前にあるのに、あの怒りに駆られた猪の精神のようなものはどこかへいってしまった。(P.223)

一方で、各紙の新聞書評は力強いものが多く、ずいぶん心救われた。受け取り方はさまざまで、少しずつSNSなどで紹介してくださる方も出てきた。よかった。大丈夫、まだ埋もれない。自分を励ます。
そんな年の暮れ、びっくりするようなことがあった。俵万智さんから「事後報告でごめんなさい」という言葉と一緒に、雑誌「短歌」の見開きページが送られてきたのだ。俵さんの担当のそのページには十首の歌が並んでおり、目で追っていくと……ん!? なんと、それは俵さんの体験として歌われた『山と獣と肉と皮』になっており、併記されているエッセイで絶賛してくださっていた。後日ツイッターでも告知され、たくさんの人に知ってもらうきっかけになった。
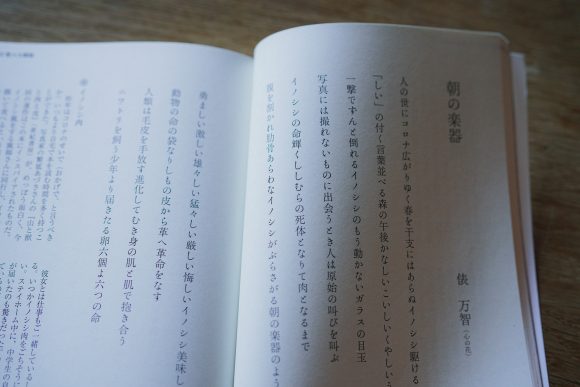
なんだか、せめぎ合っているように思えてきた。この本を見えないようにするチカラと、見えるようにするチカラ、両方があるみたいな。ただそれは、見ないようにする人と、見ようとする人という単純なものでもない気がした。というのは、「本屋で見かけて気になったけど買えなかった」とか「読みたいとは思っているけれど、まだ勇気が出ない」というコメントを見かけるからだ。見たいという気持ちと、見たくない気持ちが、一人ひとりの人の中で同時にわきあがっている印象。
そもそも、私はなぜこの写真にこだわったのだろう。
考えてみるに、おそらく、山で “見た” という体験が、私にとってとてつもなく大きかったからではないだろうか。殺して肉にする風景。それは、言葉を尽くしても、言葉には置き換えられない気がしていた。だから、そうした写真を本の表紙に掲げることは、当然のようにも思っていた。
ただ、山に通い、見慣れていくことで、その風景は私の中で変化していた。抱く印象が、ちがってきていた。だからこそ、私はこの写真を見た他の人の反応を、客観性をもって考えることができなかったのだろう。編集者も連載時から伴走してくれていたから、同様の変化が起きていたのかもしれない。周囲の編集者から「本気でこれでいいと思ってんの?」と訝しがられたという。

確かに私(と編集者)は、見誤ったのかもしれない。ただ、このことが、図らずも見たくないものを見ずに済むよう整備された社会の中で、気づきにくいことがあることを示しているように思う。それは、文脈や背景を知れば、その風景はちがって見えてくる可能性がある、ということ。“それは本当に見たくないものなのだろうか?” と疑いを抱き、みずからに問い直してみたいという気持ちが、今を生きる人の中にあるのではないだろうか。
* * *
はじめは異世界のように感じていた山の世界も、いつしか人間界とひとつづきと思えるようになった。遠く離れた場所も、はるか昔のことも、いまの私につながっている。私が見たひとつづきの世界を、また書いていこうと思う。
(第2回・了)
本連載は隔週更新でお届けいたします。
次回:2023年1月13日(金)掲載予定

