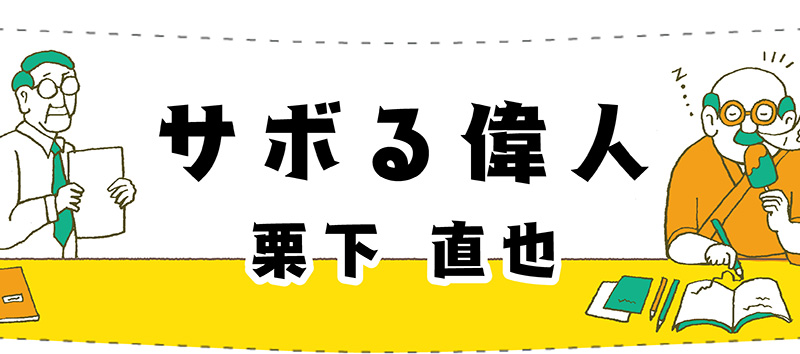関東地方では、平日夕方のNHKで「首都圏ネットワーク」という情報番組が流れている。地域限定のニュースで構成されているのだが、番組内に「STOP詐欺被害!私はだまされない」というミニコーナーがある。詐欺の手口を紹介するコーナーで、詐欺に狙われやすい高齢者の防犯意識を喚起する狙いだろう。
当初はボケーっとTVを眺めていて「ああ、詐欺増えているからね」と特に気にも留めていなかったのだが、同じ時間に繰り返し流れていると恐ろしいことに気づいてしまった。「毎日、新しい事例を取り上げるくらい詐欺って種類があるのかよ」と被害者には申し訳ないが感心してしまったのだ。
「助けて詐欺」「架空請求詐欺」「交際あっせん名目の詐欺」「還付金詐欺」「金融商品詐欺」など、次から次へと新手が登場する。また騙し役も複数の人物が入れ替わり立ち替わり登場する「劇場型」が主流で、ストーリーも精緻化されている。
例えば、実在の大手企業の名前を使って「老人ホームの債権」への投資を持ちかけ、お金をだまし取ったり、「世界一細い注射針を開発した」という架空の会社の未公開株を売りつけたり、シェールガス採掘事業への投資を装ったりと、その創造力には驚かされる。詐欺のバリエーションの豊富さと巧妙さに舌を巻く。
だが、そんな詐欺事案を毎日見ていると、ふと思う。「こんなに頭を使うなら、まともに働けばいいのではないか」。詐欺師たちは捕まると「楽して稼ぎたかった」と供述しているが、全然楽そうにみえない。昔の「俺だよ俺」詐欺なんて可愛いもので、詐欺師たちはターゲットをリサーチし、台本を練り上げ、必要な人材を確保し、ビジネスモデルを構築している。PDCAを高速で回し、警察の取り締まりの手から逃れるため、手口を日々アップデートするのに余念がない。もう、やっていることは実業家と変わらない。詐欺という「仕事」に全力投球してしまっているのだ。世の中、そう簡単に楽して稼がせてはくれないのだ。
だが、歴史を振り返ると、詐欺のような振る舞いを続けながら「楽して稼ぐ」ことに成功した人物もいる。現代の詐欺師たちがせいぜい数千万円をだまし取るのに四苦八苦している中、その男は国家そのものを使って「サボる」システムを構築した。ヨシフ・スターリンだ。彼は数百万人、数千万人を殺し、その財産を奪い、国民全員を休みなく働かせながら、自分は昼まで寝て、夜は飲み会でべろべろ。究極のサボリストだった。
スターリンといえば歴史に残る、誰もが知る政治家だろう。といっても、近年は、ヒトラー、毛沢東と並び三大悪人とも三大狂人ともいわれるなどネガティブな側面で語られることがほとんどかもしれないが。彼らはとにかく人を殺した。毛沢東が4000万人、スターリンが2000万人、ヒトラーは数百万人といわれているが、諸説あり、正直よくわからない。
特にスターリンは数値の把握が難しい。お付きの者が昨日までは元気そうだったのに、次の日にはいないなんてことが珍しくなかったからだ。「いない」といっても、休暇でもなければ、人事異動があったわけでもない。執務室や宴席などで毒を盛ったウォッカを勧められ、そのままあの世行きだ。「消された」のだ。「警戒して飲まなければいい」と思うかもしれないが、スターリンは殺す気がなくても、酒を人に勧めるのが大好きな厄介なタイプだった。「飲まなければいい」といっても、相手は誰も逆らえない独裁者だ。勧められたら、飲みたくなくても飲まざるを得ない。飲んでも地獄、飲まなくても地獄。スターリンが怖いのは「まさか私は殺されないでしょ」という人も殺している。愛人すら何人も殺している。
ウオッカであの世に行ければまだましだ。本当に気に入らなければ銃殺されてしまうのだが、「気に入らない」と憤る水準も常人離れしている。スターリンは西洋の映画が大好きだったが、英語はわからない。そこで、映画専用の通訳者を雇っていたが、気まぐれで「訳が悪い」と銃殺してしまう。おまけに、後任者も再び「訳が悪い」と立て続けに殺してしまったというから、映画を訳すのも命がけだったのだ。
歴史上の人物のみならず、あなたの周りでも権力を握ったり、出世の階段を上ったりすることで、態度がデカく、横柄になる人はいるだろう。「昔はあんな人ではなかったのに……」なんて言葉はよく聞くが、スターリンの場合は全く異なる。「人はやっぱり変わらない」のだ。
スターリンは1879年、ジョージア(グルジア)のゴリという町の靴屋の子に生まれる。バリバリの労働者階級の出身だ。
「ロシア正教の神学校で勉学に励むのもつかのま、革命に目覚めてしまった」というのが通説だが、ただただ怠惰だけだった可能性が高い。入学当初は成績優秀だったが、年を追うごとに多くの科目への興味を失い、成績が下がり始め、3年生で成績が低下、4年生では追試が必要になった。
学力だけでなく、問題行動も絶えなかった。神学校なのに、無神論者を宣言し、授業中におしゃべり、食事に遅刻、修道士に帽子を取らないとやりたい放題。1898年10月から1899年1月の間に独房監禁5回、厳重注意2回という処分を受けている。そして1899年4月に退学になる。スターリンは後にこの経緯を「革命活動のため追放された」と語っているが、実際は理由不明で試験に現れなかったことによる除籍だった。つまり、単純にサボって退学になったのである。
生涯唯一の「正規雇用」――それも究極のサボり職
スターリンの生涯でほぼ唯一の正規雇用が、1899年12月から1901年3月までのチフリス天文台での気象観測員の仕事だった。月給20ルーブルの夜勤で、ほとんど仕事がなく、勤務中に読書ができるという理想的な「サボれる職」だった。しかし、そんな仕事ですら、1901年初頭に警察の逮捕から逃れるために辞めてしまい、その後は革命まで一度も正規の仕事に就かなかった。
とはいえ、働かなかったら金がない。金がなかったらどうするか。あるところから持ってくればいい。スターリンは仲間とともに、銀行強盗、馬車襲撃、地元企業からの保護料の恐喝、富裕層の子供の誘拐による身代金稼ぎ、武器の密輸とあらゆる悪事に手を染めた。「不法にお金を貯めこんでいる資本家を懲らしめる」「革命のための資金調達」という大義名分はあったが、どうポジティブに解釈しても非合法であり、実態は凶悪な犯罪集団そのものであった。
例えば銀行強盗では銀行の護送馬車が広場に入ると、四方から爆弾を投げつけた。もうちょっと考えろよといいたくなるが、結果、約40人が死亡、50人が負傷する。テロリストだ。約4億円を強奪する。
スターリンはこの事件の首謀者とされ、後年、「戦闘に参加し、負傷した」と得意げに語っているが、これを裏付ける記録はない。襲撃当日にスターリンが何をしていたかはよくわかっておらず、特に何もせずに家でボーっとしていたとの指摘すらある。自分は何もせずに同士に血を流させる。サボり過ぎだ。これでは憎むべき資本家と変わらない。実際、レーニンは資本家から金を奪う行為は否定しなかったが、スターリンが売春宿を経営した際に、娼婦にほとんど金を払わず、ピンハネしていたので「そんな資本家みたいなことするな」と怒っている。それにしても、銀行泥棒や売春宿経営の経歴を持つ指導者は有史以来、他にいないのではないだろうか。
もちろん、こんなやりたい放題が続くわけがない。
捕まって、刑務所に送られる。スターリンは1903年から1917年まで断続的に流刑されている。脱獄して娑婆に戻っても、悪いことしかしないのでまた流される。この繰り返しだ。仲間と共同生活を送ったこともあるが、うまくいかない。家事を分担しようと決めても、狩猟や釣りなど好きなことしかしない。皿洗いの時間になると忽然と姿を消す。当然、周囲から嫌われる。子どもか!と突っ込みたくなるが、これが後の独裁者の実像だ。
レーニンもスターリンの能力は買っていたが、「こいつちょっとヤバいかも」と思い始める。レーニンの後継者にはトロツキーやジノヴィエフなど6人の名が挙がっていた。レーニンは6番目の男であったスターリンを党書記長から外すように遺言したものの、時すでに遅し。第6の男によって他の5人は次々に殺されていった。
権力掌握——国家規模の「楽して稼ぐ」システム
権力を握ったスターリンは国家をつかって「サボり」始める。ズルさもこれまでとは次元が違ってくる。自分が楽して稼ぐためには手段を選ばなくなる。
例えば、「クラーク」(富農)の定義を恣意的に拡大する。「隣人より牛が2頭多い」「土地が5–6エーカー多い」だけで富農認定し、100万世帯、500万人から財産を没収した。1932年に制定された「落穂拾い法」では、飢えた農民が畑から落ち穂を拾うことさえ死刑とした。
大粛清(1930年代後半)では、経済を改善する代わりに成功者を殺して財産を奪う「楽して稼ぐ」究極の方法を実践した。約75万人を処刑し、その財産を没収した。もはやなんでもありだ。「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」なんて狂歌がかわいく見える。グーラク(強制収容所)には1400万人が送られ、160万人が死亡した。モスクワ・ヴォルガ運河やシベリア横断鉄道は、この「無料労働力」によって建設された。
五カ年計画では石炭生産111%増、鉄200%増、電力335%増という不可能な目標を設定し、達成できない者を「破壊工作者」として処刑、またはグーラク送りにした。炭鉱夫アレクセイ・スタハノフが6時間で102トン(通常の14倍)採掘したという明らかに誇張された「記録」をプロパガンダに利用し、労働者により過酷な労働を強いた。
さらに驚くべきは、1929年から1940年までの11年間、ソ連では週末が廃止されていた。「ネプレルィフカ」(連続労働週)と呼ばれるこの制度で、労働者は休みなく働かされた。怖すぎる。もう、スターリン万歳、スターリン万歳と声が枯れるまで叫ぶしかない。
「質素な指導者」の実態
「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」という共産主義の理想を掲げながら、スターリンの「必要」は桁違いだった。複数の豪華なダーチャ(別荘)を所有し、クンツェヴォ・ダーチャには数百人のNKVD特別部隊が警備についていた。最高級ワインを楽しみ、オーダーメイドの衣服を身にまとった。娘スヴェトラーナの証言によれば、スターリンは給料には一切手を付けなかった。なぜなら欲しいものは全て国家が提供したからだ。
スターリンは午前3–4時に就寝、10–11時、時には正午に起床する夜型人間だった。そして、この異常な生活リズムにソ連政府全体を強制的に適応させた。党中央委員会、人民委員会議、国家委員会、主要な国家機関は深夜まで働いた。
夜10時から朝4–5時まで続く夕食会で重要な政策が決まった。ユーゴスラビアの政治家ミロヴァン・ジラスは「そのような夕食は通常6時間以上続いた。実際、ソビエト政策の重要な部分がこれらの夕食で形作られた」と証言している。こう書くと重要な「会食」のようなイメージを抱くかもしれないが、実際は飲み会だ。それも常軌を逸した。スターリンに飲まされまくるのが嫌でトイレに行くついでに戻ってこない者もいれば、泥酔して発砲する者もいた。仕事はサボるのに飲み会は全力だ。迷惑すぎる。
最高の皮肉「働かざる者食うべからず」
スターリンはレーニンが使った有名な言葉「働かざる者食うべからず」を頻繁に引用しながら、自身は神学校を試験サボりで退学し、生涯でまともに働いたのは気象台の数ヶ月のみ、犯罪収入と支援者の寄付で生活し、権力掌握後は国家の富を私物化した。労働者に連続労働週を強制しながら、自分は年数ヶ月の休暇を取っていた。好かれる要素が皆無だ。
ソ連の地下ジョークがスターリンの本質を鋭く風刺している。
「溺れかけたスターリンを農民が助けた。お礼は何がいいかと聞かれた農民は叫んだ。『何もいりません! ただ、私があなたを助けたことを誰にも言わないでください!』」
グルジアの銀行強盗から世界最大の泥棒へと「出世」したスターリン。個人的な強盗を「集団化」と呼び、殺人を「階級闘争」と呼び、個人的贅沢を「人民への奉仕」と呼ぶことで、史上最も大掛かりな「サボり」を実現した。令和の詐欺師たちが必死に劇場型の芝居を打ち、頭をフル回転させて数千万円をだまし取る一方で、スターリンは昼まで寝て、夜は飲み会をしながら、国家そのものを私物化した。彼の最大の偉業は「サボり」も巨大な規模になると、イデオロギーに見せかけられると教えてくれたことかもしれない。
働くことを説きながら働かず、平等を説きながら贅沢に暮らし、犠牲を説きながら他人を犠牲にして生きた。まさに「サボる偉人」の極致——史上最も矛盾に満ちた、そして最も成功したサボリストだろう。
「サボりたい」「楽して生きたい」——誰もが一度は抱く素朴な願望も、権力という増幅装置を通すと、かくも恐ろしい結果を生むのだ。だから、私たちがボーッとテレビを見ながら「働きたくないなあ」とつぶやいても、それは決して悪いことではない。私を含む多くの人は、幸いにも独裁者になる気力も野望もないのだから。
今回の教え:みんながサボれる社会を目指そう。
バナーデザイン:藤田 泰実(SABOTENS)