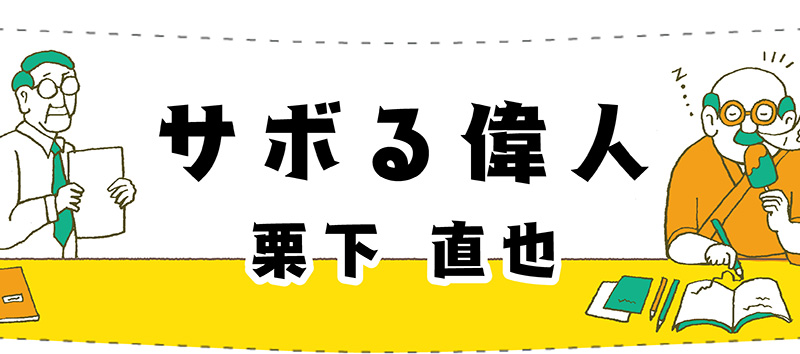小学生の頃、好きな四字熟語を聞かれると「四面楚歌」と答えていた。今思うと好きな四字熟語なんて聞かれる機会はほとんどないと思うのだが、とにかく四面楚歌と答えていた記憶だけはある。いったい誰に聞かれていたのだろうか、親か教師か、麗しきご学友か。全く思い出せないのだが、とにもかくにも四面楚歌が好きだったのだ。
周りが全て敵で、囲んでいる項羽の故郷である楚の国の歌をみんなで歌う。故郷の者まで敵陣にいってしまうなんてと項羽は絶望する。「なんとも悲しいではないか」とロマンチストだった少年は心惹かれたのだ。
ただ大きくなるにつれて、よく考えれば、いや、たいして考えなくてもわかるのだが「同郷の人まで敵側につくなんて、項羽、人望なさすぎじゃないの?」という気もしてきた。「別にそんなに悲しい話ではない」と思えてきた上に、年を重ねるうちに、生を授けられた以上、何とかして巨額の富を手に入れるべきだとマッチョな思想も芽生え始めてくる。敵に囲まれるくらいなら、お金に囲まれたいという現実的な欲望が頭をもたげてきたのだ。「おまえは資本主義の権化か」と糾弾されそうだが、生まれたときから資本主義にどっぷりつかり、小林多喜二なんて教科書でしか知らない世代にしてみれば、欲しがるのである、勝たなくても。そんな頃惹かれ始めた四字熟語が「一攫千金」である。どうやら俺は野球選手にもなれないし、ミリオンセラーの歌手にもなれない。でも、富は得たい。頑張らないでたらふく食べたい。四面楚歌から一攫千金へ。「一攫千金を狙って四面楚歌になるだけ」とのさささきも聞こえてきそうだが、余計なお世話である。これは私のような現代の凡人だけでなく、世界を変えた偉人も同じなのである。
アイザック・ニュートンといえば誰もが知る偉大な科学者だ。彼の登場によって人間が世界をどう見るかが大きく変わった。
ニュートンの何が革命的だったか。最大の功績は世の中の変わらない「ルール」を発見した点にある。そのルールは私たちが今、「法則」と呼ぶものだ。自然を観察し法則を探し出し、その法則を使って、自然現象をさらに調べ、新たな「法則」を見つけ出す。この連続する行為こそ「科学」なのである。
ニュートンが発見した法則の中で有名なのが運動の法則と万有引力の法則だ。運動の法則は慣性の法則が最も知られているだろう。走っている電車の中でジャンプしても、同じ場所に着地する。「電車は時速何十キロで走っているのに、なんで後ろに飛ばされないの?」と子どもの頃に疑問に思った人は多いはずだ。これはまさに「慣性の法則」が働いているからだ。「物は今の状態を続けたがる」のだ。
電車の中でジャンプする場合、あなたは電車と一緒に前に進んでいる。ジャンプしても、体は「前に進み続けよう」とするため、電車と同じ速さで前に進みながら上下に動く。結果として、同じ場所に着地することになる。物に新しい力を加えなければ、その物は今やっていることをそのまま続けようとするのである。
もうひとつが万有引力の法則だ。その名の通り、この法則は世界にあるすべてのものが、互いに引っ張り合っていることを教えてくれる。りんごが木から落ちるのも、月が地球の周りを回っているのも、実はあなたと隣にいる人の間にも、目に見えない引っ張り合う力が働いている。ただし人間同士の場合は、その力があまりにも小さすぎて全く感じることができないだけなのだ。
その力は距離が2倍、3倍と離れると、4分の1、9分の1に減少する。つまり、少し離れただけでも引力は急激に弱くなる。これはむっちゃ重要で、この性質があるから私たちは普段、地球以外の天体の引力をほとんど感じないのである。
ちなみに、「ニュートンはりんごが落ちるのを見て引力を発見した」という逸話があるが、あれは後世の作り話だ。「リンゴが落ちるのを見て引力に気づくなんて、ニュートンってすごい」といいたいのだろうが、ニュートンどころか17世紀の人間を馬鹿にし過ぎだ。古代から人間は物が落ちることを知っていたし、その理由についてもなんとなく理解していた。アリストテレスの時代から「重いものは下に落ちる」という考えは存在していた。
ニュートンが凄いのは、みんながなんとなく知っていた「物が落ちる現象」を、正確な数字と数式で表現したところにある。引力がどのくらいの強さで働くのか、距離によってどう変化するのかを、計算できる形にしたのである。この法則の発見によって、りんごが落ちることと月が地球を回ることが、実は同じ仕組みで説明できることを証明したのだ。
いずれにせよ、これらの法則があるから、私たちは目にする全ての運動について、説明でき、予測できる。建物の窓からモノを落としたときに何秒で地面に到着するか、野球でボールがどんな軌道を描いて飛ぶか、車がカーブでどのくらいの速度なら安全に曲がれるかも予測でき、計算できる。ロケットが宇宙に行き、地球に帰ってこられるのもニュートンのおかげなのだ。そう、ニュートンはマジで凄いのだ。人類史上最高の科学者との呼び声も高い。
「そんな立派な人ならば、一攫千金とは程遠いのでは」と突っ込みが聞こえてきそうだが、ところがどっこい、後半生、ニュートンは変な動きが目立つようになる。
そのひとつが錬金術だ。ざっくりいえば、鉄や銅を金にしちゃおうという行為であり、現代の感覚からすると「えっ、金をつくれちゃう? オカルトか何かですか」と怪しさしかない。
どのくらいどっぷりハマっていたかを物語るエピソードがある。20世紀初頭に経済学者のケインズはニュートンの遺稿が詰まったトランクをオークションで落札した。ケインズにとってニュートンは母国イギリスの誇りであり、母校ケンブリッジ大学の大先輩でもある。その遺稿の散逸を防ごうと男気を見せたのだが、トランクの中身はケインズの予想と大きく違っていた。遺稿の大半を占めていたのは、運動の法則でも万有引力の法則でもなく、怪しげな錬金術に関する文書だったのだ。ケインズはニュートンを「最初の科学者というより、最後の魔術師だ」と評しているが。
「えっ、魔術師? ニュートンって現代の科学の基礎を築いたんじゃないの」と困惑されるかもしれない。
確かにそうなのだが、現代的科学の価値観が確立され始めた時期ということは、前時代の価値観が残っていた時期とも重なる。中世の神秘的、魔術的な自然観をまだ引きずっており、ニュートンは神学者や錬金術師としての顔も持っていた。
とはいえ、すでにこの頃、錬金術は公には禁じられていた。古代から研究が続けられてきたが、どうにもうまくいかないことがわかってきた上、「鉄や銅を金に変えられれば大儲けできまっせ。一口乗りませんか」と怪しい詐欺が横行していたからだ。こうした背景もあり、「錬金術はちょっと怪しいよね」となっていたのだ。それでもニュートンはケンブリッジ大学に秘密の研究室を設け、古文書を読み解きながら、ひそかに実験を繰り返していた。鉛などの金属をるつぼに入れて高温で溶かし、液体状になった金属同士を混ぜ合わせる。さらに硫酸や硝酸といった強い酸と反応させ、発生した有毒な蒸気を直接かいだり、できあがった物質を実際に舌で味見したりしていたのである。
金ができる前に体がおかしくなってしまいそうだが、実際、体に悪かった。後にニュートンの遺髪を分析したところ、通常の40倍以上の水銀が含まれていたことがわかっている。それでもニュートンは84歳まで生きたから、丈夫な人は丈夫なのだ。「酒をガバガバ飲んで、たばこをぷかぷか吸っても長生きする人はする」とよくいうが、水銀をなめなめしても84歳まで生きる人がいるのだから、健康に過剰に気にしても意味がない気がしてくる。
ニュートンを擁護すると、時代が合理も非合理も未分化な状態の中で、彼にとってはあらゆるものが研究対象だったともいえる。錬金術の研究も、単に金を得るためではなく、物の本質は何かを突き詰める一環だった——と、言えなくもないのだが、ニュートンは錬金術だけでなく、株式投資にもどっぷりハマっていたと聞いたらどうだろうか。「やっぱり、錬金術で儲けたかったんじゃないの」という気もしてくる。
ニュートンは科学者であり、錬金術師でもあったが、英国王立造幣局長官として金融分野でも活躍した人物でもあった。英国の貨幣制度を銀本位制から金本位制に移行させ、貨幣鋳造のための正確な重量や測定基準を制定し、偽造犯を厳しく処罰したなどの功績もある。「偽造犯を罰しながら自分は錬金術にはまるってどうなんだよ」と突っ込みたくなるが、金融制度の発展に寄与した人であることは間違いない。
投資にも長けていて、堅実な投資スタイルで蓄財していた。株式や国債などに分散された投資ポートフォリオは、1720年の年初時点でおよそ3万2000ポンド(現在の価値で約6億5000万円)に相当したという。
そんな堅実な投資家だったニュートンを狂わせたのが南海泡沫事件だ。
1711年、イギリス政府は戦費調達のために南海会社を設立する。同社は国債を引き受ける代わりに南米との貿易独占権を与えられた。ニュートンは南海会社の設立から1年にも満たない1712年6月には株式の購入を始めていたが、当初は問題がなかった。多くの投資先のひとつでしかなかった。
だが、その8年後、株価が急騰する。政府の過度な保護や高配当の約束、巧妙な宣伝などいくつもの要素が絡み合い、南海泡沫事件が起きる。
株価は1720年3月のおよそ200から同年6~7月には1000近くに急騰した。ニュートンはこの上昇局面の1720年4月から5月にかけて(株価が350前後)、保有株の大部分を売却し、約2万ポンド(現在の価値で約400万ドル)の利益を確定させた。
かなり儲かったのだから、これでよしとするべきなのだろうが、天才ニュートンとしてみればその後も株価が上昇し続けたことが我慢ならなかったのだろう。株価は5月下旬には一時800まで急上昇していた。そこで何を考えたのか6月に売却時の2倍(株価700)で2万6000ポンドを投じて買い戻す。さらに8月にも(株価が750のとき)追加投資して、実質的に全財産を南海会社株に集中させ、一攫千金を狙ったのだ。堅実な投資家だったニュートンの姿はそこになく、単なる博奕野郎へと変貌してしまったのだ。このとき、ニュートン、77歳。強欲すぎるだろ。悲しいかな株価はニュートンのオールインを待っていたかのように急落し、200くらいまで落ち込む。
結果として、ニュートンは少なくとも総資産の3分の1以上を消失したことになったという。
マーケットが動いてるときは変な動きはするなというが、実際、仮にニュートンが1712年前半から、株価が乱高下を繰り返した後に安定する1723年まで南海会社株を保有し続ける投資戦略(バイ・アンド・ホールド)を続けていれば、トータルリターンはおよそ116%に達したはずだという。配当を無視しても年率約6.5%で運用したことになり、当時の長期国債の利回りが4~5%だったことを考えるとリターンは上々だったわけだ。
もちろん、それは結果論に過ぎない。むしいろ、南海泡沫事件は天才までパニックにさせるほど異常な出来事だったのだ。商人も農民も文化人も国会議員の大半も国王の家族も飛びついた。万有引力を発見した天才科学者も、「上昇したものは必ず下落する」という金融の法則からは逃れられなかった。ちなみに、「バブル経済」などに使われるバブルはこの事件に由来している。
ニュートンはこの投機の大失敗から「天体の動きなら計算できるが、群衆の狂気は計算できない」という有名な言葉を残したとされているが、これは後年の創作とされる。そもそも「いやいや、おまえも狂わされたのになにいってんねん」と突っ込まれることを天才ニュートンが予期しないわけがない。
果たして、天才ニュートンが一攫千金を狙ってもうまくいかなかったのならば、我々凡人は諦めるべきなのだろうか。
ニュートンが錬金術や投資に手を出したのは、すでに偉大な業績を上げた後のことだ。万有引力の法則を発見し、科学の基礎を築いてもなお、彼は一攫千金の夢を捨てられなかった。つまり、人間は成功しても、安定していても、どこかで劇的な逆転や大勝負を渇望する生き物なのかもしれない。それならば、現状に行き詰まりを感じる凡人が一攫千金を夢見るのは、むしろ自然ではないか。
四面楚歌で一攫千金の大勝負に出る。それはバカな行為に映るかもしれないが、人間らしい行為でもあることを偉大な科学者は教えてくれる。
今回の教え:一寸先はだいたい闇
[参考文献]
「金融の「万有引力」、ニュートンに手痛い教訓」ウォール・ストリート・ジャーナル日本版2017年11月9日
バナーデザイン:藤田 泰実(SABOTENS)