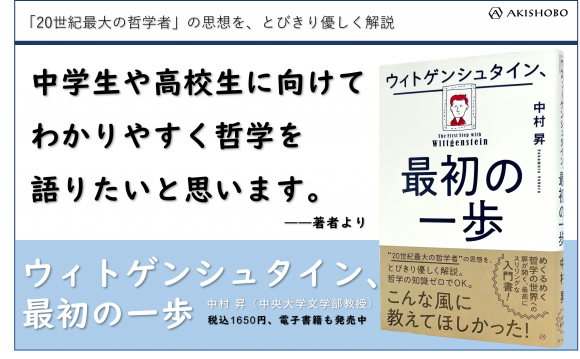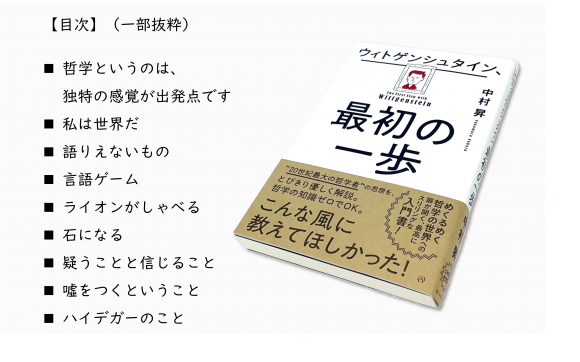「20世紀最大の哲学者」は
哲学の専門的な教育を受けたことがない〝素人〟だった!?
偉大な哲学者として名高い
ルートウィッヒ・ウィトゲンシュタイン(1889 - 1951)は
実は〝哲学を何も知らない〟私たちに最も近い哲学者でもあります。
そんなウィトゲンシュタインの思想をとびきり優しく解説!
哲学にチャレンジしたい人々に向けた、いまだかつてない《哲学入門書》
——この一冊から〈哲学の最初の一歩〉を踏み出そう!
私は世界だ
〈私〉というのは、とてもやっかいなものです。朝起きても〈私〉、一日中ずっと〈私〉、そして夜意識を失うまで、とことん〈私〉。ここからは、逃れようがない。たしかに、〈私〉以外の人は、たくさんいます。これは、誰でも(といっても、この「誰でも」は、〈私〉の推測ですが)わかります。ただ、〈私〉以外のたくさんの人は、この〈私〉からしか見えません。〈私〉以外の人たちに、〈私〉は、なることはできません。だって、この世界に〈私〉は、一人だけだからです。このことは、よくよく考えると、とても恐ろしいことです。
どういうところが恐ろしいかというと、他の人間、他の動物、さまざまな無限の可能性がある(ように〈私〉からは見える)のに、それらの可能性を〈私〉が試すことはできないということです。時代も地域も人種も生まれる家庭も、自分では決められない(この世界は、〈私〉だけなのに、何も決められない)。そして、いったん〈私〉になると、それ以外の可能性は、すべて消えてしまう。他人(やほかの動植鉱物)が、
どんな気持ちで生きているのか、自分とは異なるジェンダーである女性(男性)でいるとは、どのようなことなのか、ほんの少しも経験できない。可能性は、無数にあるのに、それにまったく関与せずに一生を〈私〉で終えるのです。とてつもない世界です。何とむなしいことでしょう。
もちろん父親、母親がいなければ、そもそも私も生まれてこなかったと、頭ではわかっています。〈私〉だけと言いながら、その〈私〉は、〈私〉が〈私〉の源から自己分裂して生まれてきたものではない、ということは、いくら〈私〉でも、わかっています。たしかに両親がいて、〈私〉は、生まれてきたのかもしれません。おそらくそうでしょう。みんなそう言っていますから。ただ、それは、後から身につけた知識にすぎない。誰かに教わっただけです。
わたしたちは、はっと気づいたときには、かならず〈私〉というとても狭い部屋に閉じこめられています。そこから、その同じ〈ワンルームマンション〉にずっと住みつづけます。不思議なことに、〈私〉は、このワンルーム以外に行くことはできないのです。引っ越しても引っ越しても引っ越しても、同じ部屋にいつづけるのです。その部屋から、外を眺めるだけ。悪夢です。つまり、原理的に「引っ越しはできない」のです、どんなにがんばっても。
他人から聞いたり、親がとった写真を見たりして、たしかに〈私〉には、肉体として誕生した瞬間があったというのは、何となくわかります。それ以前は、無だったのでしょうか(これもよくわかりません)。でも、ものごころつくと、「私は、私の世界である」(『論理哲学論考』5・63)という状態になっています。つまり、〈私〉という枠組みがあって、そのなかですべての出来事は起こっているのです、いつのまにか。それが、何もかもの始まりだったのです(始まりは、いつでも決して確認できません)。〈私=世界〉の誕生だったと、こと(世界の始まり)が起こった後に言えるだけでしょう。
決して離れることはできない、この〈私〉という枠組みのなかで、最初から最期まで(まだ、最期を迎えていないので、おそらくそうだと思うだけなのですが)すべては、進行していきます。これは、なんだか、とっても息苦しいことです。何ならうんざりすると言ってもいいでしょう。作家・埴谷雄高の言う「自同律の不快」とは、意味が違うかもしれませんが、この事態も、「自同律の不快」と言いたくなります。「私が私であること(A=A)のうんざり感」なので。
ウィトゲンシュタインが言うように、「主体〔私〕は、世界の一部ではない。そうではなく世界の境界」(『論理哲学論考』5・632)なのです。世界をつくりあげているのは、〈私〉という領域なのです。世界そのものが、〈私〉だから、この〈私〉の外側には、なにもない。無世界と言っていいでしょう。
たしかにこのマンションの部屋(〈私〉)は、他の人間から、「人間」と呼ばれています。名前も、身体ももっているからです。〈私〉も知識として、もちろん、それはわかっています。その部屋から外を眺めると、その〈私〉と同じような人たちが、〈私=世界〉のなかで動きまわっているというわけです。たくさん、見えます。〈私〉のなかで、「人間」と呼ばれるものたちがうごめいています。それと同じものとして、〈私〉の身体はうごめいています。ただ、その場合であっても、〈私〉そのもの(世界の中心)は、じっとしています。動きません。不動の中心です。だから、〈私〉は「人間」ではありません。
〈私〉のからだに注意を向けて、一日ぐらい植物になったり、一時間だけでも鉛筆になったりしたいと思ったとしましょう。でも、そんなことは起こりません。さっきも言ったように、引っ越しはできないのですから。でも、万が一そういう楽しいこと(人間から、植物や鉛筆への引っ越し)が起こったとしても、〈私〉は、同じだと思います。残念ながら、この枠組み(境界)は、そのままだと思います。なぜなら、マン
ションの名前が変わった(人間⇒タンポポ)だけで、そのマンションの部屋は、まったく変わりばえはしないでしょう。相変わらず〈私〉というあり方をしていると思います。やはり、〈私〉は動きません。
でももしかしたら、〈私〉自体が変化することはないのでしょうか? なにか、べつのものに突然変わったりはしないのでしょうか。ただ、いくら考えても、〈私〉以外になるということが、どういうことなのか、〈私〉にはさっぱりわかりません。ほんの少しも想像できません。やはり、一番想像可能なのは、植物になっても、鉛筆になっても、数字になっても、〈私〉は〈私〉なのではないかというものです。〈私〉が、なくなるとはどうしても思えません。〈私〉であるということが、そのまま「存在すること」になっているからでしょうか。これは、私たちの根源的なあり方にかかわることだと思います。つまり、同時に二重の存在にはなれないということです。ちょっと難しいですかね。
ウィトゲンシュタインは、つぎのようにも言います。
ここでわかるのだが、独我論を徹底すると、純粋な実在論と一致する。独我論の「私」は縮んで、延長のない点となる。そして残るのは、「私」のためにコーディネートされた実在である。
(『論理哲学論考』5・64 )
「独我論」とは、この世界に存在しているのは〈私〉だけ、という考え方です。そういう「独我論」を突きつめると、〈私〉以外のものは何も存在していないことになります。つまり、〈私=世界〉だけになります。ようするに、ここにあるのは、一つの実在(本当に存在しているもの)だけなのです。たしかに、〈私〉が枠組みなのであれば、ただ一つの〈私〉は、消えてしまうでしょう。映画館に映画を見にいって、映画そのものにのめりこんでいるとき、〈私〉はなくなって、映画のストー
リーだけが映しだされているようなものです。〈私〉は世界から消え、出来事だけがたんたんと起きていく。これをウィトゲンシュタインは、「純粋な実在論」と言います。
たしかに、世界に〈私〉一人しかいない(「独我論」)のならば、その〈私〉は、存在そのものと同じことになってしまうでしょう。しかしもし、私たちがこのようなあり方をしていることになると、これは、もうとんでもなく壮絶な孤独ということになります。誰一人として、自分と同じ存在は、この世界にはいないことになるからです。
自分のワンルームマンションに他人を招待することはできないし、他人のマンションに遊びに行くこともできません。そもそもそのワンルームマンションが、世界の外枠なのですから、そこからわれわれは一歩も動けないのです。とても息苦しい状態だと言えるでしょう。
———————————————————————————————————————
中村 昇(なかむら・のぼる)
1958年長崎県佐世保市生まれ。中央大学文学部教授。小林秀雄に導かれて、高校のときにベルクソンにであう。大学・大学院時代は、ウィトゲンシュタイン、ホワイトヘッドに傾倒。
好きな作家は、ドストエフスキー、内田百閒など。趣味は、将棋(ただし最近は、もっぱら「観る将」)と落語(というより「志ん朝」)。
著書に、『いかにしてわたしは哲学にのめりこんだのか』(春秋社)、『小林秀雄とウィトゲンシュタイン』(春風社)、『ホワイトヘッドの哲学』(講談社選書メチエ)、『ウィトゲンシュタイン ネクタイをしない哲学者』(白水社)、『ベルクソン=時間と空間の哲学』(講談社選書メチエ)、『ウィトゲンシュタイン『哲学探究』入門』(教育評論社)、『落語―哲学』(亜紀書房)、『西田幾多郎の哲学=絶対無の場所とは何か』(講談社選書メチエ)『続・ウィトゲンシュタイン『哲学探究』入門』(教育評論社)など。
ルートウィッヒ・ウィトゲンシュタイン
(Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889 - 1951)
1889年、ウィーンの世界三大鉄鋼王の家に、末子として生まれる。最初は、物理学を目指すも、マンチェスター大学でプロペラの設計に携わり、やがて数学基礎論に関心が移る。ケンブリッジ大学のラッセルのもとで、記号論理学を学ぶ。
第一次世界大戦ではオーストリア軍に志願し、激戦地で戦い生き延びる。この間も書き続けた『論理哲学論考』を1922年に出版、哲学界に衝撃を与える。この本は、(ドイツ語の辞書を除けば)生前刊行された唯一の著作である。
40歳でケンブリッジ大学に戻り、『論理哲学論考』で博士号を取得。50歳で教授となり、58歳で職を辞す。1951年、前立腺がんのために死去。最期の言葉は「素晴らしい人生だったと、みんなに伝えてくれ」だった。
死の2年後の1953年、遺稿がまとめられ出版される。これが哲学史に名高い『哲学探究』である。
———————————————————————————————————————
《『ウィトゲンシュタイン、最初の一歩』試し読み》
▶はじめに
▶哲学というのは、独特の感覚が出発点です
▶あとがき
ウィトゲンシュタイン、最初の一歩
中村 昇 税込1650円
【目次】
■ はじめに
1.哲学というのは、独特の感覚が出発点です
2.私は世界だ
3.論理
4.物理法則など
5.倫理とは何か
6.絶対的なもの
7.絶対的なものと言葉
8.死
9.語りえないもの
10.言語ゲーム
11.家族のような類似
12.言葉の意味
13.私だけの言葉
14.文法による間違い
15.本物の持続
16.ライオンがしゃべる
17.魂に対する態度
18.意志
19.石になる
20.かぶと虫の箱
21.痛みとその振舞
22.確かなもの
23.疑うことと信じること
24.人類は月に行ったことがない
25.ふたつの「論理」
26.宗教とウィトゲンシュタイン
27.顔
28.噓をつくということ
29.デリダとウィトゲンシュタイン
30.ハイデガーのこと
31.フロイトの弟子
■ あとがき